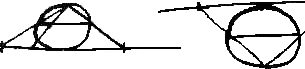原註
1
ブラッドリー氏の必然性と可能性の定義は、この用法と一致しない。氏の必然性の理論については後に考察するが、しかしそれ以外の場合ついては、可能的命題は、その反対が必然的命題でない命題であると定義できるものとする。
2
『感覚器官の心理学および生理学雑誌』XXI, p.202.
3
『論理学』p.183.
4
ただし、当該の命題を導く前提が真でない限り、その当該命題を必然的命題と呼ばない方がよいと見なすべきなら、話は別であるが。
5
『マインド』 n.s.Vol.IX. No.35, pp.289-304.
6
同一律、矛盾律、排中律は、やろうと思えば「論理法則」に含められるかもしれない。しかし、私たちが「法則」およびその帰結ということで意味することは多少なりとも恣意的であり、ゆえに私は、いわゆる「思考法則」は一切含まないようにするのが簡便だと思う。これらを入れたいと思うなら、その根拠は、よぼよぼになるまで仕えてくれた召使を解雇するのは忍びないという感情からしかありえない。
7
これは、ソクラテスが現れる命題が真である場合も含むことを意図している。
8
例えば、『ロンドン数学協会年報』第28巻の5番目の論文「同値な言明の計算」pp.156-7 を参照。
訳註
[1]
ラッセルが「神の実在についてのア・プリオリな知識の源泉」と呼んでいるのは、いわゆる「神の存在論的証明」のことです。
[2]
この箇所を読むときは、ラッセルが命題(タイプ)と文(トークン)を区別すること、一つの命題は必ず真偽のどちらかに決まると考えていること(2値原理)、という二つの前提を念頭に置くと理解の助けになります。
例えば、「雨が降っている」は、どのような時刻に発話しようとも文としては同一ですが、その表現する命題は異なる、ということです。いわば、こういう文は発話文脈に依存するような「隠れ時制」と「隠れ場所指定」を持つ命題を表現しているだけで、時制を明文化した命題に変換すれば、「2006年4月1日の午後20分、東京では雨が降っている」のようになります。この命題なら、これをいつ考えたかによらず真偽が定まります。「真かもしれないし、偽かもしれない」などという曖昧な命題は、ラッセルの哲学体系には現れません。
換言すると、ラッセルはこういう時刻と場所の指定が無い文を、文脈を入力として命題を出力する関数と考えているのです。
[3]
引用の箇所は、『ヴェロナの二紳士』第5場。この場合、「縁組みがまとまる」が命題 p に当たります。犬が何と言っても縁組みがまとまるということは、犬がどんな命題を言っても p が真になるということです。
シェイクスピアの翻訳は『シェイクスピア全集 I巻』(筑摩書房、1967) p.125 によりました。
[4]
この定義は解釈の難しいところです。私は、ラッセルがここで与えている必然性と可能性の定義は、様相論理に属するものというよりは、モデル論の先駆であるように思います。必然性と可能性が「議論領域に相対的に決まる」という彼の定義は、「議論領域と述語のペアに相対的に決まる」という一般化まであと一歩の地点です。そうすれば、結局のところラッセルの必然性とは「あるモデルのもとで恒真」と同じことです。
しかし、この定義を様相論理の先駆と見る少数派の研究者もいます。次を参照。Jan Dejnožka, "
Russell on Modality"(2003)
[5]
クロムウェルは1658年没、王政復古は1660年です。