序文
親愛なるラッセルへ
2年前になるでしょうか、私はあなたに手稿を一つお渡しすると約束しました。今日お送りするのは、その手稿ではありません。私はまだその手稿に手をとられていて、一部分ですら出版することがあるかどうかも分からない状況です。しかし2年前、私はケンブリッジ大学で講義を行い、それを生徒に書き取らせました。彼らが家に持ち帰れるようにするためです。それなら頭には残らなくてもノートには残ります。私はそのノートをコピーしました。幾つかのミスプリントと間違いを修正していたところ、あるいはあなたがこのコピーをお気に召すのではないかと思いつき、一部お送りしようと思いました。読んでいただくよう強制するつもりはありません。ですが、もしあなたが他にすることもなく、そしてもし読んでいただくことで何かしらの楽しみを得ていただけたなら、私は非常に嬉しく思います。(もっとも、多くの論点がヒントを示されるだけになっているので、理解は非常に困難と思われます。もともと講義に参加していた人間に向けてのみ書かれたものですから。)先ほども言いましたが、読んでいただかなくても全くかまわないのです。
本文
語の意味(meaning)とは何か?
この問いに取り組むにあたって、まず初めに、語の意味を説明するとは何か、語の意味を説明するとはどのようなことであるかを問いたい。
このような問いの立てかたは、ちょうど、「私たちはどのようにして長さを測るか?」という質問が「長さとは何か?」という問いに答えるのに役に立つのと同じ仕方で、役に立つ。
「長さとは何か?」「意味とは何か?」「1とは何か?」・・・こうした問いは、人間の精神に痙攣を起こさせる。このような問いに対し、何かを指し示す(point to)ことで答えることはできないと、私たちは感じる。だがそれでもなお、何かを指し示さなければならない気がするからだ。(私たちは、哲学の混乱の大きな源の一つに直面している。名詞に対しては、何かそれに対応するものを探さなければいけないと感じてしまう、というやつだ。)
最初に「語の意味を説明するとはどのようなことか?」と問うことには二つの利点がある。 一つは、「意味とは何か」という問いを、ある程度、地に下ろせることである。というのも、「意味」の意味を理解するためには、また「意味の説明」の意味も理解している必要があるからだ。簡単に言うと以下のようになる。「意味を説明するとはどのようなことか問うてみようじゃないか。なぜなら、その説明がすなわち意味であろうから」。
二つめは、「意味を説明する」という表現の文法を調べることは、「意味」という語の文法について君に何かを教えるだろうし、「意味」と呼べそうな対象(object)をきょろきょろと探したくなる誘惑から、君を解放してくれることだ。
「語の意味の説明」と一般的に言われるものは、非常に大雑把に言うと、言葉による定義(verbal definition)と、指さしによる直示定義(ostensive definition)の二つに分類される。後に分かることだが、この分類はあくまで大雑把で仮のものである(この点を是非おさえておいて欲しい)。言葉による定義は、別の言葉で言い換えただけだから、ある意味では一歩も前進していない。一方、直示定義の方は、意味について学ぶうえでもっと現実的な一歩を踏み出せるように思われる。
だが、すぐに直面する困難は、私たちの言語の多くの語に対して直示定義ができないように思われることである。たとえば、「1」とか「数」とか「ではない」とか。
ここで問題:直示定義自体も理解することが必要ではないのか? 直示定義が誤解されることは起りえないのだろうか?[1]
もし [直示]定義による説明が語の意味であるとすれば、その語を以前に聞いたことがあるかないかは、間違いなく本質的ではありえない。なぜなら、語に意味を与えるのは直示定義の仕事だから。例をとって説明しよう。鉛筆を指さしながら「これはタブだ」と言ったとする(「これはタブだ」と言う代わりに、「これはタブと呼ばれる」と言うこともできただろう。
こんなことをわざわざ言うのは、語の直示定義が、既に定義されたものについて何かを述べるという [誤った] 考えを今後一切排除するためである。「これは赤い」という、あるものが「赤い」という属性を持つことを言う文と、「これは『赤』と呼ばれる」という直示定義との間の混乱を避けるためである)。さて、「これはタブだ」という直示定義は、様々に解釈されうる。まともな英語を使って、いくつかそういう解釈を挙げてみよう。すると、この直示定義は以下のように解釈することができる。
「これは鉛筆だ」
「これは丸い」
「これは木だ」
「これは1だ」
「これは固い」 ・・・などなど
こういう風に言うと、「これらの解釈は他の語-言語の存在を暗黙に前提しているではないか」という反論があるかもしれない。しかしこの反論が有意味なのは、「解釈」という言葉を「他の単語への変換」という意味で用いる場合に限る。――この点をもっと明確にするため、少しヒントを出そう。こう自問してみるといい。誰かがこの直示定義をある方法で解釈したとき、我々がその解釈を正しいと認める基準はなんだろうか、と。例えば、私があるイギリス人に「これはドイツ人が『Buch』と呼ぶものだ」という直示定義を与えたとする。すると、大概の場合、「本」という単語がそのイギリス人の頭の中に浮かぶだろう。「彼は『Buch』を『本』に解釈したのだ」と、私たちは考える。しかし、彼がまだ見たことのないものを指差して「これはバンジョーだ」と私たちが言った場合は、事情が異なる。「ギター」という単語が彼の頭に浮かぶかもしれない、あるいは単語は浮かばないが、似たような楽器の像が浮かぶかもしれない。また全く何も浮かばないかもしれない。そこで私が彼に「ここにあるものの中からバンジョーを選べ」という命令を与えたとする。もし彼が、私たちがバンジョーと呼ぶ楽器を選べば、「彼は『バンジョー』という単語を正しく解釈した」と私たちは言うだろう。もし彼が他の楽器を選んだなら――「彼は『バンジョー』を『弦楽器』と解釈したのだ」と言うだろう。
私たちは「彼は『バンジョー』という単語にあれやこれやの解釈を与えた」と言う。しかしこの場合、私たちは、その選択するという行為とは別に、解釈するという[心的]行為があると想定しがちである。
私たちの直面している問題は、また次のようにも表現できる。
もし私が誰かに「あそこの草地から赤い花を取って来い」と命令したとする。私はただ「赤い花という」一語を与えただけなのに、一体、彼はどのようにしてもって来るべき花を知ることができるのか?
人が真っ先に思いつく答えはこうだろう。彼は心の中に赤の像を抱いて赤い花を探しにいき、その像と色々な花を比べてみる、というものだ。確かにそういう探し方もある。だが、私たちが使う像は、何も心的なものである必要はないという点が重要だ。実際、以下の探し方でもいいはずだ。色の名前と色見本の対応表を持ち、「~を取って来い」という命令を聞いたら、対応表の「赤」という見出しから色見本のところまで指でたどる。その後に花のところまで行き、色見本と同じ色をしている花を探すのである。もちろん、これが唯一の方法ではないし、普通の方法でもない。普通は、探しに行き、周りを見回し、何かと見比べたりせずに花を摘む。命令に従うという行為の過程がこうしたものであることを見るために、「赤い斑点を想像せよ」という命令について考えてみてほしい。この場合ならよもや君も、命令に従う前に、想像せよと言われた色との比較に使う色のパターンを想像する必要がある、などという考えに駆られたりはしないだろう [赤色を想像した時点で君は命令を果たしたことになるのだから] 。
さて君はこう尋ねるかもしれない。「私たちは命令に従う前に命令の言葉を解釈しているのではないか?」と。場合によっては、命令に従う前に、解釈と呼ばれるような何かを君は行なっているかもしれない。だが行なわない場合もあろう。
言語の働きと結びついたある特定の心的過程があるように見える。そしてその過程を通してのみ言語は機能しうるとういわけだ。私がここで言っているのは、理解と意味付けの過程のことである。私たちの言語の諸記号は、こうした過程がなければ死んでしまうように思われる。それどころか、心的過程を生じさせることだけが、記号の役割であり、私たちが真に関心を向けるべきはこの過程であるような気さえする。だから、名前とその名前が付けられたものとの関係を尋ねられると、その関係は心理学的なものだと答えたくなってしまうのだ。そしてそう答えるとき、君が考えている関係は、 [名前と物の] 連想関係なのである。――言語の機能は二つの部分から成ると考えたくなる誘惑がある。非有機的部分(記号の操作)と有機的部分(記号を理解し、記号に意味を与え、記号を解釈し、記号で思考する)だ。後者の行為は、非常に奇妙な媒体の中で行なわれるように思われる。心(mind)というやつである。心の仕組みや性質――私たちはそれをよく理解していないのだが――は、物質的な仕組みの中では起こりえないことも [心の中では] 引き起こすことができる。例えば思考(実に強力な心的過程だ)は、現実に一致することも一致しないこともできる。私は、ここにいない人物のことを考えられる。彼が遥か彼方にいようと死んでいようと、私は彼のことを想像し、彼について述べることで彼を「意味する」こともできる。「絶対に起こりもしないことを願うことができるとは、願望とは何と奇妙な作用であることか」と思う人もいるかもしれない。
思考する過程のこのオカルト的外見を、少なくとも部分的には回避する方法がある[2]。それは、この過程における全ての想像の作用を、具体的なものを見るという行為に置き換えることだ。つまりこうだ。少なくともあるケースにおいて、私が「赤」という語を聞いて理解する場合は、赤の像が私の心眼の前になくてはならないように思われるかもしれない。しかし、赤い斑点を想像するかわりに、本物の赤い紙片を見てはならない理由があるだろうか? 両者の違いといえば、後者の方が視覚的像がより鮮明であるにすぎない。色の名前と色見本との対応表を常にポケットに入れて持ち歩いている男を想像せよ。君は、「そんな対応表をいつも持ち歩くのは面倒くさい。対応表の代わりに私たちがいつも使っているのが連想の仕組みなのだ」と言うかもしれない。だがこの意見は的外れだ。のみならず、大抵の場合には正しくもない。なぜなら、たとえば、君が「プロシャン・ブルー」という君が知らない色を塗ってくれと頼まれたら、対応表を使って、「プロシャン・ブルー」という語から色見本まで指でたどらなくてはならないだろう。
私たちの目的のためには、心像を思い浮かべる全過程を、具体的なものを見たり、色を塗ったり、像を作ったりする過程によって置き換えて全くかまわない。同様に、心の中でしゃべる過程を、声に出したり書いたりする過程によって置き換えてよい。
フレーゲは形式主義者の数学観を「くだらないものである記号と、重要なものである意味とを混同している」といってからかった[3]。確かに人は、数学が紙切れの上のダッシュ記号を扱う学問にすぎないなどと認めたくはあるまい。フレーゲの考えはこう言い表すこともできる。「数学の諸命題 [=定理] は、もしそれらがダッシュ記号の組み合わせに過ぎないとするなら、生命を失っており全くつまらないものだ。しかし、それらがある種の生命をもっていることは明らかである。意義(sense)や思想(thought)がなければ、命題はとるにたらない死骸である。そしてさらに、非有機的な記号を命題にいくつ付け加えたところで、命題に生命を吹き込むことはできないことも明らかと思われる。従って、導き出せる結論は、死んだ記号を生きた命題にするために必要なのは、ただの記号とは質的に違う非物質的な何かなのである」。
しかし、もし記号に生命を与えるものを名づけろと言われれば、それは記号の使用(use)であると言わねばならない。
もし記号の意味(端的に言って、それが記号について重要なものだ)が、記号を見たり聞いたりしたときに心の中に作られる像だとすれば、その考えが間違いであることを示すために、まずは先に述べた方法――心像を、絵や像といった外世界のものを見ることによって置き換えること――を採用してみよう。すると、書かれた記号だけでは、その記号は死んでいるのに、それに描かれた像が付け加わることで、記号に生命が宿ることなどありうるだろうか? [明らかにそんなことはありえない。] 心像を描像によって置き換え、その結果、オカルト的性格が消えれば、たちどころに、心像が文に生命を与えていたように思われたのは実は勘違いだったことが分かる(実際、君が必要としていたのは、心的過程のこのオカルト的性格だったのである)。
私たちが犯しやすい過ちは、こう言い表せる。私たちは記号の使用を探しているのだが、あたかもそれを記号と一緒に並んでいるかのように探してしまうのだ、と(この過ちの理由の一つは、繰り返しになるが、「名詞に対応するもの」を探してしまうことだ)。
記号(文)はその意義(significance)を記号の体系、すなわち記号が属する言語から得ている。一言で言えば、文を理解するということは言語を理解することである。
言語の体系の一部として、文は生命を持つ。しかし人は、文に生命を与えるのはオカルト的世界の何かであり、それが文につきまとっているのだと想像しがちである。しかし文につきまとっているものが何にせよ、それは私たちにとってはただ、別の記号であるだけだ。
一見すると、思考にその特異な性格を与えるものは一連の心的状態であるように思われる。そして思考について理解するうえで奇妙にも困難にも思われるのは、それが心という媒体の中で起こる過程であり、心の中でしか起こりえない過程である点だ。この心的過程と非常によく類似している現象が、たとえば、アメーバ細胞の原形質である。アメーバのある種の行動、手を伸ばして食物を取ったり、細胞分裂した二つの細胞が同じような動きを見せたりするのをみて、私たちは、「こんな動きをするとは、原形質とは何と奇妙な性質を持っているのだろう」と言ったりする。さらに、私たちは、「どのような物理的な仕組みも、このように振舞うことはない。アメーバの仕組みは [他の物理的な仕組みとは] 全く異なる種類のものに違いない」と言うだろう。「心がこんな振る舞いをできるためには、心の仕組みは実に変わったものに違いない」と言うのも、これと全く同じなのである。しかしここで、私たちは二つの間違いを犯している。というのも、思想や思考について私たちに奇妙な印象を与えたものは、私たちがまだ(因果関係を)説明できない奇妙な結果をもたらすわけではないからである。言い換えれば、私たちの問題は、科学的なものではなく、問題のようにみえた混乱なのである。
心理学的探究の結果、心の活動を説明してくれるような心モデルを作ってみたとする。しかし、このモデルは、エーテルの力学的モデルが(そういうことが可能ならば)電気学の一部であるのと同じように、心理学の一部にとどまるだろう(ついでだが、そのようなモデルは常に理論の記号表現の一部であり、その利点は、一見して理解しやすく記憶に残ることである。だがモデルは、ある意味において、純然たる理論に化粧をほどこす。裸の理論は文と方程式である。この点は、後にもっと詳細に検討しなければならない)。
観察される心の活動を説明するためには、心モデルは非常に複雑で入り組んだものにならざるを得ないと思うかもしれない。この理由においてなら、確かに心モデルを奇妙な媒体と呼ぶことはかまわない。しかし心のこの側面は私たちの興味をひかない。心モデルがもたらす問題は心理学の問題であり、その解決方法は自然科学の方法である。
さて、私たちが関心を持つべきことが、心モデルの因果関係ではないとすれば、心の活動は私たちの前に開け広げに横たわっているのだ。そして私たちが思考の本性について思い悩んでいるとき、媒体の本性についての困惑だと勘違いしていたのは、実は言語の誤用によって引き起こされる困惑だったのである。この種の間違いは哲学では繰り返し起きている。時間が奇妙なものに思われるとき、その本性について困惑する場合などが、その例だ。「ここには何か隠されたものがある。外側からは見えるが、しかし中を覗き見ることはできない何かが」と考えたくなる誘惑は非常に強い。だが、そんなものはありはしない。私たちが知りたいのは時間についての新事実ではい。私たちが関心のある全事実は目の前に横たわっているのだ。実のところ、私たちを混乱させているのは「時間」という名詞の誤った使われ方である。時間という語の文法を調べてみればいい。そうすれば、人類が時間の神を思いついたことは、否定や選言の神を思いつくのと同じぐらい驚くべきことだと感じるだろう。
だから、思考を「心の活動」と呼ぶのはミスリーディングである。思考とは、本質的には記号を操作する働きだと言えるだろう。この働きは、書いて考えるときは手によって行なわれるし、しゃべって考えるときは口と喉頭によって行なわれる。だが記号や像を想像することによって考えるとき、思考する主体はいないのではないか。この場合、もし君が「それは心が考えているのだ」と言うなら、私としては、君がメタファー(書くときに手が主体であると言うことと、心が主体であると言うことでは、意味が異なる)を使っているという事実に気付いてもらうよう注意を促すだけだ。
思考が起こっている場所についてもう一度述べるなら、私たちには、「思考は私たちが書くのに使う紙や、しゃべる口で起こる」と言う権利がある。もし頭や脳が思考の場所だと言うのなら、それは「思考の場所」という表現を別の意味で使っているのだ。 [そのことを説明するために] 思考の場所が頭だと呼ぶことの理由を調べてみよう。この表現の形式を批判したり適切ではないことを示すのが目的ではない。私たちがしなければならないことは、その表現の作用、文法を理解することである。たとえば、「私たちは口で考える」や「私たちは紙の上の鉛筆で考える」などの表現の文法と、「私たちは頭で考える」という表現の文法がどのような関係にあるかを見てほしい。
思想の浮かぶ場所は頭であると言いたくなる主な理由は、おそらく以下のようなものだろう。「思考」や「思想」という語が、「書く」、「話す」など(身体的な)活動を指す他の語と並んであるために、「思考」という語に相当する活動――それは身体的動作とは似て非なるものであるが――を探そうとすることである。日常言語の語が、一見して他の語と似た文法を持っている場合、私たちはそれらに似た解釈を与えたくなるのだ。私たちは、いたるところでこの類比を使おうとする。例えば、「思想は文とは違う。なぜなら、英語とフランス語では、文を全く別の単語で表す。にもかかわらず、それらの文は同一の思想を表現できる」と言ったりする。そして文はどこかに存在しているのだから、思想のための場所も見つけようとするのである。(色々なチェスセットのキングのための場所はあるのだから、それに対して、チェスのルールが取り扱う王の居場所まで探そうとするようなものだ。) あるいはまた、「思想はなにものかである。なぜなら、それはなにものでもない、ということはないからだ」などと言う。これらの発言に対する答えは、せいぜい、「『思想』という語はその使用を持っており、それは『文』という語の使用とは全く異なる種類のものである」というだけである。
さて、以上のことは、思想の浮かぶ場所を云々することは無意義であるということだろうか。そうではない。「思想の浮かぶ場所」という句は、私たちがそれに意味を与えれば、きちんと意味を持つ。私たちが「思想が頭に浮かぶ」という場合、この句を冷静に理解したときの意味は何だろうか? 私の考えでは、ある生理学的過程が思想に対応しているということであり、もしその対応の仕方が分かるなら、観察によって思想を見つけることができるということである。しかし、どのような意味において、生理学的過程が思想に対応すると言えるだろうか? また、どのような意味において、脳の観察によって思想を得ることができると言えるだろうか?
私たちは、その思想と生理学的過程の対応は実験によって確認済みだと考えているようだ。本当に実験で対応を確認できるか調べるため大雑把にだが、被験者が思考している最中に脳の中を調べるという実験を想像してみよう。すると君は、「この実験はうまくいかない。なぜなら、実験者は被験者の思想を、被験者が何らかの形で表現することを通して語られたものとして、間接的にしか捉えることができないのだから」と反論するかもしれない。だが、この困難は取り除くことができる。一人の人間が被験者と実験者を兼任して、自分の脳を鏡か何かで見ればよいのだ(この実験の描写は大雑把なものだが、それによって議論の正当性が損なわれることはない)。
さて、ここで君に質問がある。この被験者兼実験者氏が観察しているのは、一つのものだろうか、それとも二つのものだろうか(「彼は一つのものを内側と外側の両方から観察している」という答えはなしだ。この答えは困難を解決しないからだ。内側と外側の問題は、後に取り上げる)。彼は、二つの現象の相互関係を観察しているのだ。そのうちの片方を、彼は思想と呼ぶだろう。それは一連の像や有機的な感覚、あるいはまた、書いたり喋ったりするときに感じるさまざまな視覚的・触覚的・筋感覚的経験によって形成されている。――もう一方の経験は、彼の脳が働いているさまを見ることである。この両方の経験を「思想の表現」と呼ぶことは正しいだろう。だが、混乱を避けるために、「思想そのものはどこにあるのか?」という質問は、無意味なものとして斥けたほうがよい。それでもなお「思想が頭に浮かぶ」という表現を使う場合、思想が頭に浮かぶという仮説を正当化するような経験を描写することによって(つまり、私たちが「頭の中の思想を観察する」と言いたくなる経験を描写することによって)、私たちはこの表現に意味を与えたに過ぎない。
簡単に忘れてしまいがちだが、「場所」という語は非常に多くの異なった意味で用いられるし、物についての言明も、様々な種類がある。だから、一般的な用法に従って「この文は物の場所を指定している」と言える場合は、特定のケースに限られる。それゆえ、視覚的な場所について、ある人が「その場所は私たちの頭の中にある」と言ったなら、私は、彼が文法を誤解したためにこのような言い方をしたくなったのだと考える。
私は「視界の中で、木の像が塔の像の右隣にある」とか「木の像が視界の中央にある」とか言うことはできる。だがそれと同じ調子で「視界はどこにあるのか?」と聞きたくなってしまうのだ。もし「どこ」という語が、先の例で木の像が指定された場所と同じ意味での場所を問うものであれば、私は、君はまだこの質問に意味を与えていないということを注意したい。つまり、君は文法的比喩を詳しく解明しないまま、その比喩を使って質問してしまったのだ。
「視界の場所は脳の中にある」という考えが文法の誤解から生まれると言うとき、私は、場所に対するそういう言明に意味を与えられないと言おうとしているわけではない。そうした言明によって描写するべき経験は、簡単に想像できる。たとえば、私たちがこの部屋の中を見回している間に、探針を脳に突き刺したと想像してみればいい。そして、探針の先端が脳のある特定の部位へ到達すると、私たちの視界の一部が消失することがわかったとする。このやり方なら、脳の部位と視界の一部との対応関係を知ることができるだろうし、この意味において「視界は脳のどこそこの部位に位置する」と言うこともできるだろう。それから再び「本はどこに見えるか」と君に質問すれば、(さっきと同じように)「鉛筆の右」や「私の視界の左半分」という答え方の他に、「私の左目の3インチ奥」という答え方もありうるだろう。
だがここで、「断言してもいいが、私は視覚像を鼻柱の2インチ奥に感じるんだ」という人間がいたらどうであろう。――彼にどう返せばいいだろうか。「彼は嘘つきだ」とか「そのような感覚はありえない」と言うべきだろうか? だが、もし彼が「君はこの世にありうる感覚を全て知っているとでも言うのかい? 『視覚像が鼻柱の2インチ奥にある』という感覚がありえないと、なぜ言い切れるのか?」と言い返してきたら、どうすればよいだろう。
他の例を出そう。もし占い師が杖を手に持って「5フィート地下に水源を感じる」とか「5フィート地下に金と銅の混合物が埋まっているのを感じる」と言ったとしたらどうだろうか。私たちの疑惑に対して彼はこう答える。「あなたは物を見ればその長さを測ることができますね。それならなぜ、私が [見ることとは] 異なる方法によって長さを測ることができることを疑うのですか?」
しかし、そうした測定の観念について理解すれば、占い師の発言や「鼻柱の奥に視界を感じる」と言った男の発言に私たちが感じた疑惑の性質が明らかになるだろう。
ここに「この鉛筆の長さは5インチだ」という文と「この鉛筆の長さは5インチであると感じる」という二つの文がある。私たちは、前者の文法と後者の文法の関係を明らかにしなければならない。「私の手に、水が3フィート地下にあると感じる」という文に対しては、私たちは、「それは何を意味しているのか分からない」と答えたくなるだろう。しかし占い師はこう言う。「あなたはそれが何を意味するか確かに知っているはずだ。あなたは『3フィート地下』という句の意味も『私は感じる』という句の意味も知っているではないか!」 しかし、私は彼にこう答えねばならない。「私は、語がある文脈において何を意味するかは理解している。だから、『3フィート地下』という句を、たとえば、『測量によって水が3フィート下を流れていることが示された』とか『3フィート地面を掘り進めば水に突き当たるだろう』とか『見たところ、水の深さは3フィートだ』などの文との関係のなかで理解している。しかし、『私の手に、3フィート地下に水を感じる』という表現の使用は、まだ未知のものだから私に説明してもらわないといけない」と。
私たちは占い師にこう尋ねることができるだろう。「あなたはどうやって『3フィート』という語の意味を習得したのか? きっと、その長さを見せられたり、実際に測ってみたりしたのだろう。だがそれなら、君は水が5フィート下にあるという感覚、その感覚を手に感じると語ることまで習ったというのか。もしそうでないとしたら、一体君は「3フィート」という語と手の感覚とをなぜつなげたのだろうか。」 仮に、私たちは目測で長さを測った経験はあるが、指を当てて測定した経験がないと想定しよう。すると、指を当ててインチ単位で長さを測ることは、どのようにして可能だろうか? つまり、インチ単位で測定した経験をどのように解釈するのだろう? 私の質問はこういうことだ。「指を当てて測ったときの触覚の感覚と、ものさしを使って目測した経験との間にはどのようなつながりがあるのだろうか」と。このつながりを知れば、「ある物が6インチの長さだと感じる」という文も理解できるだろう。占い師が「私は手の感覚と地中の水の深さの結び付け方を習ったことはない。しかし手にある種の緊張が起こったとき、『3フィート』という言葉が私の心の中に浮かぶのだ」と言ったとしよう。すると私たちの答えはこうだ。「その言葉で、君は『3フィートの深さを感じる』という言葉で君が意味することについての非の打ち所のない説明をしてくれた。手に3フィート地下に水を感じるという君の発言は、今君が与えてくれた説明以上のことも、それ以下のことも意味しない。もし経験的に、君の心に浮かぶ『nフィート』という数字と実際の水の深さが一致するなら、君の経験は、水の深さを測る目的のために実に有用だろう。」 ――だがそのためには、「私は水の深さをnフィートだと感じる」という文の意味が説明されなければならない。なぜなら「nフィート」という語が通常の意味において(つまり通常の文脈において)使われている場合は、この文の意味は分かっていないからだ。――私たちは、「視界を鼻柱の2インチ奥に感じる」と言う人間を嘘つきだとか、そいつの言っていることは無意味だと言おうとしているのではない。そうではなく、私たちはそのような句の意味を理解していないと言いたいのだ。そうした句は、確かに、馴染み深い単語を組み合わせて作られている。だがその組み合わせ方を、私たちはまだ理解していない。だから、この句の文法を説明してもらわないと、私たちは句の意味を理解できないのだ。
占い師の返答を調べることが重要な理由は、占い師がやったように「Pという文が真実であると感じる(または信じる)」と表明しただけで、Pに対して意味を与えたと勘違いしてしまう場合が多いからである。(ハーディ教授が「ゴールドバッハの予想は命題である。なぜなら私はそれが正しいと信じることができるから」と言った件については、後に検討しよう[4]。)1 既に見たように、「3フィート」という言葉の通常の意味を説明されただけでは、私たちはまだ「水を3フィート地下に感じる云々」という句の意味を理解できない。つまり、占い師が「私は手に特定の感覚を感じる度に水を掘り当てて、この方法によって自分が感じる感覚と水の深さを結びつけた。こうして、私は水の深さを推測することを習得した」と言ったならば、私たちは、 [彼の発言の意味を理解するうで] 困難を感じる必要などなかっただろうに。そこで、測定という行為と測定を習得することとの関係を検討しなければならない。この検討が重要な理由は、言葉を使うことと言葉の意味を習得することの間の関係にも適用できることにある。あるいは、もっと一般的に言うと、この検討は、与えられたルールとその適用との間にありうる様々な可能な関係を示すことができるのだ。
例として、目測で長さを測る過程を考えてみよう。重要なのは、「目測で測る」と私たちが一言で表す過程は、実は非常に多くの異なった種類の過程であるということだ。
たとえば以下のような例を考えてみよ――
- 誰かが「この建物の高さをどうやって測る?」と聞く。私は「これは4階建てで、1階が約15フィートぐらいだ。だから約60フィートだ」と答える。
- 別の場合:「この距離だと、1ヤードがどのぐらいに見えるか見当がつく。だからあれは約4ヤードだ。間違いない」
- さらに:「背の高い男なら、あそこまで届くはずだ。だからおよそ6フィートだ。」
- はたまた:「分からないな。ただ1ヤードに見える。」
さっき、占い師が深さの測定の仕方を習得したということを教えてくれれば、私たちは彼の答えに戸惑う必要はなかったということを見た。測定の仕方を習得することは、大雑把にいうと、測定という行為に対する異なる二つの関係において見られる。一つは測定という現象の原因として、もう一つは、私たちが測定するときに使う規則(表やチャートなど)を与えるものとして。
私が誰かに黄色の布きれを指差して「黄色」と発音することを繰り返して、彼に「黄色」という語の用法を教えるとしよう。その後ある機会に、「このバッグの中から黄色のボールを選べ」という命令を与えて、彼が習得したことを実際に適用させてみる。彼が私の命令に従ったときに起きたことは何だろうか? 私に言わせれば、多分こうだ。彼は私の言葉を聞き、バッグから黄色のボールを取り出した、と。だが君は、「それだけが全てではあるまい」と考えたくなる。「彼は命令を理解したとき何か黄色のものを想像し、それから像に従ってボールを選んだ」というたぐいのことを言い出すかもしれない。想像という過程が不要であることは、彼に「黄色の布きれを想像せよ」という命令を与えることもできたということを思い出してもらえば分かるだろう。それでもまだ君は、「彼は最初に黄色を想像し、命令をただ理解し、それから最初に想像した黄色と比べるためにもう一度黄色の布切れを想像する」などと言うつもりだろうか? (注意しておくが、それが不可能だと言うわけではない。ただ、こういう風に示せば、それが不必要だということが君にもはっきり分かってもらえると思ったのだ。ところで、これは哲学の方法をよく例示している。)
もしある種の直示定義(語の使い方の規則)によって「黄色」という語の意味を教えられたとすると、この教育は二通りの異なる見方ができる。
-
教育は訓練であるという見方。この訓練を受けることで、私たちは「黄色」という語と黄色の像や黄色の物を結びつけるようになる。従って、私が「このバッグの中から黄色のボールを選べ」という命令を与えたとき、「黄色」という語は黄色の像や、黄色のボールを見たときの認知の感覚を命令を受けた人物に喚起するだろう。この場合、教育による訓練は心理的な仕組みを作り上げたとも言える。もっともこれも、せいぜい仮説かメタファーに過ぎないが。教育は、電球とスイッチの間に電気回路を組み込むことに例えられるだろう。結線が切れたり故障したりすることは、語の意味や説明を忘れることに相当する(「語の意味を忘れる」という句の意味については、さらに議論しなければならない2)。
認知の感覚やその他色々なものの連想を引き起こす限りで、教育は、理解したり命令に従ったりといった現象の原因である。しかし、これらの結果を引き起こすために [語と像や物との結合を作り出す] 教育の過程が必要であるというのは、一つの仮説でしかない。 この意味において、言語を教わったことのない人間でも、理解や服従といった全ての過程を実行するのも、ありえないことではない(今の時点ではひどく逆説的に聞こえるだろうが)。
-
教育は私たちに、理解や服従の過程に含まれている規則を与えるという見方(ただし、ここでいう「含まれている」とは、この規則の表現が過程の一部をなしているという意味である)。
ここで私たちは、「規則に合致する過程」と「規則を(上記の意味で)含む過程」を区別しなければならない。
ひとつ例を出そう。誰かが私に、自然数を二乗することを教えようとして、次の数列を書き並べたとする。
1 2 3 4,
そして私に「この数字を二乗しなさい」という(この場合でもやはり、私は自分の心の中で起こる過程を全て紙に計算を書き出すことで置き換えよう)。そこで、上の数列の下に私はこう書く。
1 4 9 16.
私が書いた数列は、二乗の一般的規則と合致している。しかし、この数列はまた他の色々な規則と合致することも明らかである。そしてそれらの規則のうち、どれか一つが他の規則よりもよりよく合致しているということはない。さっき私が言った「ルールがある過程に含まれている」という意味では、この過程にはどんな規則も含まれていない。答えを得るために、私が1×1, 2×2, 3×3, 4×4を計算したとしても(ここでも、計算を実際に書き出す)、その答えはやはり無数の規則と合致する。逆に、答えを得るために、いわゆる「二乗の規則」というものを、例えば代数的に、書きつけたとする。この場合は、他の規則が含まれていないという意味で、この「二乗の規則」は [答えの数列に] 含まれている。
Bのケースの典型的な例は、命令や規則を理解し、従うなどの過程で私たちが実際に使う表が、教育によって与えられる場合である。私たちがチェスを教わる場合、規則を教えられるだろう。それから私たちがチェスをすると、チェスをするという行為の中に教えられた規則が含まれる必要は無い。しかし含まれる場合もあるだろう。例えばこういう場合を想像して欲しい。今、チェスのルールが表の形で表現されている。ある列にはチェスの駒の形が縦に書かれ、もう一つの列に、それと並行してそれぞれの駒の「自由度」(許される動き)を示す図が書かれている。さて、チェスをプレイするなら、指で表をなぞって駒の形から駒の可能な動きの図へと辿り、それから実際に駒を一つ動かすことになる。
私たちの一連の行為(理解し、従い、また長さを測ったり等)に対する仮説的前史としての教育は、私たちの考察の対象外である。私たちに教えられ、その結果、適用される規則が私たちの関心を惹くのは、それが適用の中に含まれている場合に限る。規則は、私たちが関心を持つ限りでは、遠隔作用はしないのである。
私が紙片を指差して誰かに「この色を『赤』と呼ぶ」と言ったとしよう。それから私は彼に「では、ここを赤色に塗ってくれ」と命令する。その後、私は彼にこう訊ねる。「命令を実行するにおいて、なぜ君はこの色を塗ったのか」と。彼の答えはこうだろう。「この色(と言いながら私が彼に見せた色見本を指差す)は赤と呼ばれた。だから、見てのとおり、色見本の色を塗ったのだ」。彼はここで、なぜ命令をそのような仕方で実行したのかの理由を私に与えたのである。ある人が自分のしたことに対する理由を与えるということは、その行為に至る道を示すことを意味する。道を示すと言うことは、(1)ある場合には、そこに至るまでに自分が進んだ道を述べることであり、(2)また別の場合には、そこに至るまでの道、それも、[一般的に] 受け入れられている規則と合致する道を述べることである。だから、「なぜ君は私の命令を果たすとき、まさにこの色を塗ったのか?」と聞かれたら、彼は、自分がこの特定の色合いへ至るまでに実際に辿った道を述べるだろう。これは、彼が「赤」という語を聞いて、色を塗るときに色見本を写し取った場合でも同様である。これに対して、彼は「自動的に」、あるいは記憶を頼りに色を塗った可能性もある。しかしこの場合でも、 なぜその色を塗ったのか、理由を聞かれれば、やはり色見本を指差して、自分が塗った色と色見本は同じ色だ、と言うだろう。後者のケースにおいては、彼が与えた理由は(2)のタイプである。すなわち、後からの正当化である。
さて、事前の教育なくしては命令を理解することも、それに従うこともできないと考える人がいたら、その人は教育を、人間が行なったことに対する理由を与えるものだと見なしていることになる。ちょうど人が歩く道を与えるように、である。だが、もし命令が理解され従われるならば、それに従うための理由がなくてはならない。そして実際、その理由の連鎖は無限後退に陥るという考えがある。この無限後退は、次の例と似ている。「君が今どこにいようと、どこか別の場所からそこに辿り着いたに違いない。その前にいた場所にも、別の場所から辿り着いたに違いない。そしてこの連鎖は無限に遡る」(これに対し、「君がどこにいようと、10ヤード離れた場所からそこに来ることができた。さらにその場所にも、別の10ヤード離れた場所から来ることができた。以下無限に続く」と君が言ったとすれば、これはステップを無限回行なうことの可能性を強調したことになるだろう[5]。従って、理由の連鎖は無限に続くという考えは、以下に述べる混乱と似た混乱から生じるのである。その混乱はこういうものだ。「ある長さの線分は、無限個の部分から構成されている。なぜなら線分は無限に分割できるから。つまり、分割のステップには終わりが無い」)。
もし反対に、現実には理由の連鎖に始まりがあるということを認識すれば、命令に従うことに理由がない場合があるという考えに、君が反発を覚えることはもうないだろう。しかしこの点について、また別の混乱が起こる。それは理由と原因を混同することである。人をこの混乱へと導くのは、「なぜ」という語の曖昧な用法である。だから、理由の連鎖が終わりに到達してもなお「なぜ」と尋ねられたとき、人は理由の代わりに原因を答えてしまいがちになる。例えばもし、「私が赤色を塗ってくれと頼んだとき、なぜ君はまさにこの色を塗ったのか?」と私が尋ねれば、「この色の見本を見せられたとき、同時に『赤』という語を聞かされた。だから、『赤』という語を耳にすると必ずこの色が心の中に浮かぶのだ」という答えが返ってくる。このとき、君は自分の行動に対する理由ではなく、原因を答えたのだ。
「私の行動があれやこれやの原因を持つ」という命題は、一つの仮説である。この仮説は、大雑把に言って、私たちが行為の原因と呼ぶ特定の条件に恒常的に続いて起こることを一致して示す経験を豊富に持っていれば、十分に基礎付けられる。一方、ある特定の言明をしたり、特定のやり方で行動することに対する理由を知るためには、 [行為に対する理由があれやこれやであるということを] 一致して示す経験は一つも必要ない。「理由」と「原因」の文法の間の違いは、「動機」と「原因」の文法の間の違いと実によく似ている。原因については、こう言うことができる。「理由を知ることはできない。できるのはただ、それを推測することだけだ」。反対に動機についてはしばしばこう言われる。「確実に、私はなぜそれをしたか知っていなければならない」。「私たちは理由を推測できるだけだが、動機は知っている」という言明は、文法的な言明であることが後に分かるだろう。「できる」は論理的可能性を意味しているのである。
原因と動機を求める「なぜ」という語の二重の使い方が、私たちは動機を推測するだけでなく、知ることができるという考えと一緒になって、動機は私たちが直接気付く原因、いわば「内側から見た」原因、あるいは経験された原因であるという混乱を引き起こす。――理由を与えることは、どのようにして特定の結果に至ったのか、その計算を与えるようなものである。
ここで「思考の本質は記号の操作にある」という言明に戻ろう。私の論点は、「思考は心の活動である」という言い方はミスリーディングであろう、ということだった。「思考はどのような種類の活動か?」という問いは、「思考はどこで起こるか?」という問いに似ている。この問いに対して私たちは、紙の上で、頭の中で、心の中で、などと答えることができる。だが、これらの答えは、思考が起こるまさにその場所を与えるものではない。こういう場所の特定の仕方は、どれも正しい。しかし、それらの言語形式が似ているからといって、それらの哲学的文法まで似ているという間違った考えを持ってはならない。例を挙げると、「思考の本当の場所は頭の中だ」と言うような場合である。同じことは、思考を一つの活動として捉える考えにも当てはまる。それぞれの文の文法を理解している限り、という条件つきで「思考はものを書く手の活動だ」とか「喉頭の活動だ」、「頭の活動だ」、あるいはまた「心の活動だ」と言うことは正しい。さらに、非常に重要なことは、言語表現の文法を誤解することで、なぜそれらの表現のうちの特定の一つが思考の本当の場所を与えていると考えるようになるのかを認識することである。
「思考は手の活動である」と言うことは反論を招くだろう。人は「思考は『私的な経験』の一部である」と言いたいのだ。思考は物質的なものではなく、私的な意識における出来事である、と。この反論は「機械は考えることができるか?」という問いの中に表現される。この論点は後で論じるとして、今は、「機械は歯痛を持つことができるか?」という類似の問いを君に投げかけよう。君はきっと「機械は歯痛を持つことはできない」と答えたいだろう。私としてはただ、君が使った「できる」という語の使用に注意を向けさせ、こう尋ねるだけである。「君が『機械は歯痛を持つことはできない』と言うことで」、私たちの過去の全ての経験に基づいて、機械は歯痛を持つことはできないということを意味しているのか?」と。実際は、君が言うこところの不可能性は論理的なものである。問題は「思考(あるいは歯痛)と、思考したり歯痛を持つ主体との間にはどういう関係があるのか?」ということである。これに関しては、今はこれ以上のことは言わない。
「思考は本質的に記号の操作である」と言うとき、君が持つ第一の疑問は「記号とは何か」ということだろう。――この問いに対して私は、どんな種類の一般的な答えも与えようとは思わない。代わりに、私たちが「記号を操作する」と言うときの特定の事例をよく見るよう提案したい。語を操作する簡単な例を見てみよう。まず、私が誰かに「八百屋へ行ってリンゴを六つ買ってきてくれ」と命令する。彼がこの命令を果たす仕方を記述すると、以下のようになる。「六つのリンゴ」と書かれている紙片が、八百屋に渡される。八百屋は「リンゴ」という語と色々な棚のラベルと比較する。そして一致するラベルを発見し、1から紙片に書かれている数まで数える。一つ数える度に、果物を棚から取り出しバッグへ入れる。――これが語を使用することの一事例である。私は今後、繰り返し君の注意を私が言語ゲームと呼ぶものに向けるだろう。言語ゲームとは、私たちが非常に複雑な日常言語の記号を使う仕方を単純化したものである。これは、子供が言葉を使い始める頃の言語の形式をしている。だから、言語ゲームの研究は言語の原初的形式、あるいは原初的言語の研究である。私たちが、例えば真偽の問題、つまり命題と現実の一致・不一致の問題や、あるいは言明・想定・疑問などの性質の問題を研究したいと思うなら、言語の原初的形式を見ることから大きな利点を得られる。なぜなら、言語ゲームにおいては、思考の表現が、思考の複雑な過程の混乱した背景を伴うことなく現れるからである。言語のこういう単純な形式を見れば、言語の日常的用法を覆っているように見える心理的な霧は消えうせる。私たちが見るのは [言語を使った] 活動であり、それに対する [言語を使った] 反応である。それらは明瞭で透明である。一方、こうした単純な過程においても、この言語形式は複雑な日常言語の形式と断絶しているわけではない。原始的な形式から始めてそれに新しい形式を付加していくことで、段階的に複雑な形式を作り上げることが可能である。
この線に沿った探究の仕方を採ることを妨げるのは、私たちの一般性への渇望である。
一般性への渇望は、特定の哲学的混乱と結びついた幾つかの傾向が合わさった結果である。その傾向というのは、例えば以下に挙げるようなものだ。
-
一般名辞に普通包摂される全ての実体に共通する何かを探そうとする傾向。――私たちは、全てのゲームには共通する何かがあるに違いないと考えがちである。言い換えれば、その共通の性質は、様々なゲームを「ゲーム」という一般名辞で包摂して呼ぶことを正当化する、というものである。[そうではなく] 諸ゲームは一つの家族を形成しているのであり、各々は家族的類似性(family likeness)を持っているだけである。何人かは同じ鼻を持ち、別の何人かは同じ眉毛を持ち、またさらに別の何人かは同じ歩き方をする、というように。これらの類似性は重なり合っているのだ。特定の個体が共通に持つ性質としての一般概念という観念は、言語の構造に関するもう一つ別の、原始的で極めて単純な観念と結びついている。それは、性質は、その性質を持つものの構成要素である、という考えと比較可能である。例えば、アルコールはビールやワインの構成要素であるのと同じように、美という性質は全ての美しい物の構成要素である、と。この考えに従えば、私たちは [純粋な美を構成要素に持つ] 美しい物によって不純にされていない、純粋な美を得ることが可能になる。
-
日常的な表現形式に根ざす傾向として、「『葉』などの一般名辞の意味を習った人間は、個々の葉の像ではなく、葉のある種の一般的像を所有するようになったのだ」と考える傾向を挙げられる。彼が「葉」という語の意味を習うときは、様々な種類の葉を見せられるのだが、その過程は「彼の中に」いわゆる一種の一般的像という観念を生み出すための手段に過ぎないわけだ。彼は、[見せられた] 全ての葉に共通するものを見てとる。そしてこの「全ての葉に共通する性質」というものは、私たちが彼に「それらの葉に共通する特徴や性質を教えてくれ」と言ったとき、そのような特徴や性質を答えられる、という意味であれば、真である。しかし私たちは、葉の一般的観念は何か視覚像――だが、それは [見たことのある葉だけでなく] あらゆる全ての葉に共通のものを含んでいる――ようなものだと考える傾向がある(ゴールトン[6]の合成写真)。繰り返すが、この傾向は、語の意味は一つの像、あるいは語と関係する一つのものであるという観念と結びついている。(おおまかに言うと、私たちは全ての語を固有名であるかのように見て、名前の担い手と名前の意味を混同しているのだ[7]。)
-
再度述べるが、「葉」や「植物」等の一般的観念を獲得するときに起こることについて私たちが持っている考えは、仮説的な心的機構の意味での心的状態と意識の状態(例:歯痛)との混同と結びついている。
-
一般性への私たちの渇望には、もう一つ別の源泉がある。それは、私たちが科学的方法を先入観として持っていることである。私が科学的方法と呼ぶのは、自然現象の説明を可能な限り少ない基本的な自然法則へ還元する方法であり、数学では、様々な主題の扱いを一つの一般化を使って統一する方法である。哲学者はいつも科学的方法を目の前に見せられているので、問いに答えるとき、科学的方法を使う誘惑に抗しがたい魅力を感じているのである。この傾向が形而上学の真の源泉であり、哲学者を完全な闇へ導くものである。ここで私は言いたいのだが、何かを何かに還元したり、説明したりすることは、絶対に私たちの仕事ではありえない。哲学は真に「純粋に記述的」なのである(「感覚与件は存在するか?」という問いについて考えてほしい[8]。そして、この問いを決定する方法は何か、と自問してほしい。内観だろうか?)。
論理学における、より一般的なものと、より特殊なものへの態度は、「種類」という語の使用法と結びついている。この語も混乱を招きがちである。私たちは数の種類、命題の種類、証明の種類、さらにはリンゴの種類、紙の種類などについて語る。ある意味で、種類を定義づけるのは、甘さや固さといった諸性質である。だがもう一つの意味では、文法的構造が種類を決める。もし果樹栽培の専門書の中に言及されていないリンゴの種類があれば、その本は不完全だと言われよう。この場合、完全性の基準は自然の中にある。これに対して、チェスとよく似ているがもっと単純な、ポーンを使わないゲームがあったとしたらどうだろう。そのゲームを不完全と言うべきだろうか? あるいは、ある仕方でチェスを含み、さらに付加的な要素を持っているゲームを、チェスより完全だと言うべきだろうか? 論理学において、より一般性が劣るケースを軽んじる態度は、それが不完全であるという考えを源泉とする。だが現実には、何かより一般的なものに対する特殊なものとして基数の算術をみなすことは、 [性質による分類と文法的構造による分類の] 混同である。基数の算術には何ら不完全なところはないし、有限な基数の算術も不完全ではない(リンゴの種類が異なれば味が異なるというような微妙な違いは、論理形式同士の間には存在しないのだ)。
もし私たちが、例えば「望む」「考える」「理解する」「意味する」などの語の文法を研究するなら、望んだり考えたりする様々なケースを記述することで満足するだろう。もし誰かが「だがこれは、いわゆる『望む』という全ての場合を記述していない」と言ったとしたら、私たちは「確かに全てのケースを尽くしてはいない。だが君は望むならいくらでも複雑なケースを構成していけるじゃないか」と答えよう。そして結局のところ、「望む」という場合の全てを特徴付ける性質のクラスを確定的に決めることはできないのだ(少なくとも、「望む」という語が普通の意味で使われている限り)。逆に、君がもし「望む」という語を定義したいなら、つまり、「望む」という語とそれ以外の語との間に明確な境界を引きたいなら、好きなように境界を引くことができる。だが、その境界が現実の使用法と完全に一致することは絶対にないだろう。現実の使用法は明確な境界を持っていないからである[9]。
一般名辞の意味について明確にするためには、それが実地に適用される全ての場合に共通の要素を見つけなければならないという考えが哲学的探求の足かせになっていた。とういのも、それでは何の結論にも辿り着かないし、[語の使用の] 具体的なケースを [語の意味の探求にとっては] 無関係なものとして哲学者から捨てさせたからである。本当は、語を使用する具体的なケースだけが一般名辞の意味を理解する助けになるものだったのに。ソクラテスは「知識とは何か?」という問いを発したとき、知識という語を使用する諸ケースを列挙する答え方を、仮の答えとしてすら認めなかった3。仮に私が算術とはどのようなものかを知りたいと思うなら、有限基数の算術の場合を探求することで満足するべきである。その理由は以下の2点である。
(a)有限基数の算術から出発して、もっと複雑な全ての場合へ辿り着けるから。
(b)有限基数の算術は不完全ではない、つまり、他の算術によって埋められるような隙間がないから。
Aという人が、BがAの部屋に来ることを4時から4時半の間に期待する場合、 [Aには] 何が起きるだろうか?「何事かを4時から4時半の間に期待する」という句は、ある意味において確かに、一定期間中続く一つの心的な過程や状態ではなく、多くの様々な心的な活動や状態を指すこともできる。例えば私が、Bがお茶に来ることを期待する場合、以下のようなことが起こりうるだろう。まず4時になると、私は日記を見て、今日の日付に「B」という名前を見つける。そこで私は二人分のお茶を用意する。「Bは煙草を吸うんだっけ?」とちょっと考えて、煙草もテーブルに置く。4時半が近づいてくると、イライラし始める。Bが部屋に入ってくるときの様子を想像してみる。こうした全てが、「4時から4時半の間にBが来るのを期待する」という句で表される過程である。さらに、この句で表される過程には数限りないヴァリエーションがあるのだ。「誰かがお茶に来るのを期待する」という句で表現される、互いに異なる過程が共通に持つ特徴は何か、と訊かれれば、たくさんの特徴が重なり合っているだけで、全ての過程が共有するただ一つの特徴などない、というのが答えだ。これらの過程は一つの家族を成しており、各過程が持つ家族的類似性は明確には定義ないものである。
もし「期待」という語をある特定の感情を意味するために使えば、それは上述の場合とは全く異なる使用法である。「願望」や「期待」などの語をこういう用法は、誰でもすぐに思いつくことである。この用法と上述の用法との間には、明らかな関係が存在する。前者の意味で、誰かを期待する場合、先に述べた [心的] 活動の一部または全てが、ある特別な感覚、緊張感を伴うことは間違いない。だから、その緊張感の経験を意味して「期待」という語を使うことも、自然な成り行きである。
さてここで疑問が生じる。この感覚は、以下のどちらの呼び方で呼ぶべきなのか。
(1)「期待の感覚」
(2)「Bが来るという期待」
もし(1)であるなら、「君がある期待の状態にある」ということは、「君がこれこれのことが起こるのを期待する状態にある」ということを、完全には記述していないことを認めざるをえまい [従って(1)の呼び方は間違いだ]。反対に、(2)の場合、よくある軽率な間違いだが、「Bが来ることを期待する」という句の使用の説明として「Bが来ることを期待する」という感覚が用いられる。[さらに悪いことに] こういう説明が与えられると君は、自分が確固たる基礎の上にいるとさえ考えかねない。なぜなら、それ以上のいかなる疑問も、「Bが来るという期待の感覚は定義できない」と言うことで片付けられるからだ。
さて、ある特定の感覚を「Bが来るという期待」という句で呼ぶことには何の反論もない。それどころか、こういう表現を使うことには、よい実際的な理由もある。ただ、一つだけ注意することがある。それは、「Bが来るという期待」という句の意味をこのように [特定の感覚であるとして] 説明した場合、「B」を他の名前で置き換えて得られる句の意味までは [特定の感覚によって] 説明されていないということである。このことから、「Bが来るという期待」という句は「xが来るという期待」という[命題]関数の出力値ではないという意見が出るかもしれない。この意見を理解するためにさっきの例と「私はxを食べる」という関数の例を比較してみよう。私たちは、「椅子を食べる」という表現の意味を特に教えられなくても、「私は椅子を食べる」という命題を理解する。先のケースで「私はBを期待する」という表現の中で名前「B」が演じていた役割は、「ブライトの病気」という表現における名前「ブライト」と比較できる4。[医師ブライトが発見した] ある特殊な病気を意味するときのこの語の文法を、ブライト氏が罹っている病気を意味するときの「ブライトの病気」という表現の文法と比べてみよ。私なら、両者の [意味の] 違いをこう特徴付ける。つまり、最初のケースでは「ブライト」は「ブライトの病気」という複合名の中の索引であるが、二番目のケースでは、「ブライト」は「xの病気」という[命題]関数の変項(argument)である。索引は何物かを指し示すと言えるだろうし、そのような指示は実に多様な方法で正当化できるとも言えよう。従って、ある感覚を「Bが来るという期待」と呼ぶことは、その感覚に複合名を与えることであり、「B」は、この感覚に続いていつもやって来る人物の名前を指すと考えることができる。
再度繰り返すが、私たちは「Bが来るということの期待」という句を名前としてではなく、ある感覚の特徴として使うこともある。例えばBが実際に来ることによって解消されるような感覚を、「B」が来るという期待」と言って説明したりする。こういう使い方をするなら、確かに、私たちは自分の期待が [現実に] 果たされるまで期待していたものを知らない、と言うことは当たっている(ラッセルはそう考えている)。しかしこれが「期待する」という語の普通の使い方だとか、まして唯一の使い方だなどは誰も信じまい。もし私が誰かに「君は誰を期待しているのか?」と尋ね、答えを聞いた後でさらに「君は、その人以外の人物が来ることを期待しているのではない、という確信があるか?」と訊いたなら、大抵の場合、この問いは馬鹿げていると思われるだろう。答えはきっと「もちろん。私が誰を期待しているかを私が知っているのは当然だ」というものだろう。
「願望」という語にラッセルが与えた意味を、「願望」は、その語の使用者にとっては、ある種の飢餓を意味しているという特徴づけができる。――[しかし、]ある特定の物を食べることで特定の飢餓の感覚が解消されるというのは、一つの仮説である。「願望」という語をラッセルのように使うなら、「私はリンゴを望んだ。だが、梨を食べることで満足した」という文は意味をなさない5。しかし、私たちは「願望」という語をラッセルとは別の使い方をすることもある。この意味で、願望の緊張は、その願望が果たされることがなくても解消されるし、逆に、緊張が解消されることなく願望が果たされることもある。この意味で、私は自分の願望が果たされることなく満足することもありうるのだ。
すると、今問題にしている、ラッセルと私たちとの間の [「願望」という語の意味に関する] 違いは、自分の望むものを知っている場合と知らない場合の違いに帰着するだけだ、と言いたくなる人がいるかもしれない。確かに「私は希求を感じるが、何を希求しているか分からない」とか「私は恐怖を感じるが、何が怖いのか分からない」、あるいは「私は恐怖を感じる。だがとりわけ何も怖くはない」などのように言う場合がある。 さて、こういうケースを「対象を指示せずにある感覚を持つ」と表現していいだろう。「対象を指示しない」という句によって、[感覚を表す動詞に] 文法的区別が導入される。そのような感覚を「怖れる」「希求する」などの動詞で特徴付けるなら、これらの動詞は自動詞ということになる。「私は怖れる」[という自動詞] は、「私は泣く」[という自動詞] と類比的である。[もちろん] 私たちは何かについて泣くこともあろう。しかし、私たちが泣くその対象は、泣くという過程の構成物ではない。すなわち、私たちが泣くときに起こる全てのことは、泣く対象に言及することなく記述できるのだ。
では、「私は怖れる」という動詞や、その他の感覚を表す動詞を他動詞的にしか使ってはならないと、私が提案したとしよう。すると、これまでは「私は恐怖を感じる」と自動詞的に言っていたのを、これからは「私は何かを怖れている。しかしそれが何なのか知らない」と言うことになる。この用語法に反論はあるだろうか?
[あるいは] こういうこともできる。「反論はない。ただ一つ、そういう言い方をする場合、『知る』という語は奇妙な使われ方をしている、ということを除けば」。次のケースを考えてほしい。――私たちは、一般的で対象へ向かわない恐怖の感情を抱いている。後になって「私は自分が怖れていたものを知った。私はこれこれのことが起こることを怖れていたのだ」と言いたくなる経験をしたとする。[この場合] 最初に抱いていた怖れの感情を自動詞で記述するのは正しい。それとも、私の恐怖には [最初から] 対象があったのだが、そのことを知らなかったと言うべきだろうか? どちらの記述形式を使ってもよい。このことを理解するため、次の例を検証しよう。――歯の虫歯状態で、通常虫歯には付きものの歯痛を感じない場合、これを「無意識の歯痛」と呼び、歯痛ではあるがそのことを知らない状態を表現するために使うのは、実際的なことだろう。精神分析が無意識的な思考、無意識的な意志の働き等について語るのは、 [無意識という語の] まさにこの意味においてである。さて、この意味において、「私は虫歯を持っている。だがそのことを知らない」と言うのは間違いだろうか。そうではない。これはただ新しい用語法なのであり、いつでも通常言語に再翻訳できるからだ。しかし一方、この言い方は、「知る」という語を新しい方法で使っていることも明らかである。この表現の使われ方を調べたいと思うなら、「この場合、知るようになるとはどのような過程か?」「私たちは何をもって『知るようになる』『見出す』と呼ぶのか?」と自問してみることが有用である。
私たちの新しい規約に従えば、「私は無意識的歯痛を持っている」という言い方は間違いではない。なぜなら、「この言い方は、痛みを伴う悪い歯痛と痛みを伴わない歯痛とを区別しなければならない」という以上のことを、この言い方に対して望めるだろうか? [望めるはずがない。] しかしこの新しい表現は、私たちの規約を整合的に保つことを困難にするような像と比喩を喚起することで、私たちを誤った方向へ導く。さらに悪いことに、常に注意深くこの表現を観察しない限り、それらの像を捨てることが極めて困難なのである。特に、哲学をする際、私たちが何かについて言うことをよく考えようとするときに、その困難は甚だしい。従って、「無意識的歯痛」という表現によって、君は間違った考え(例えば、ある意味で私たちの理解力を完全に当惑させる、驚くべき発見が行なわれたとか)に導かれるかもしれない。あるいは、この表現によってひどく困惑させらて(その困惑は哲学の困惑だ)、「一体どのようにして無意識的歯痛は可能なのか?」と尋ねるかもしれない。そして、無意識的歯痛などありえないと言いたくなるかもしれない。しかし科学者たちは君に向かって、これは証明された事実なのだ、と言う。そのときの彼の態度は、まるで自分が世間にはびこる偏見を打破する人間なのだ、というものだ。「話は全く単純なのだよ。この世には君の知らないことがある。君が知らない歯痛もある。これはまさに新発見なのさ。」君は満足しないが、何と言い返せばよいのか分からない。この状況は、科学者と哲学者の間でいつも起こるものである。
そういう場合、問題を明瞭にするために、私たちはこう言おう。「『無意識的』とか『知る』などなどの言葉が、この場合はどう使われ、他の場合にはどう使われているのか、見てみようじゃないか。」これらの使われ方の間の類似性は、どのぐらいの範囲で成り立つだろうか?私たちはまた、慣れきっている使用法の呪縛を破るために、新しい表記法(notation)を導入するだろう。
私たちは、さっきこう言った。調査対象である特定のケースにおいて、何を「知るようになる」と呼ぶべきか自問してみることが、「知る」という語の文法(使用)を調べる方法である、と。この方法は、「『知る』という語の意味は何か?」という問いとはほとんど関係ないと思われがちである。「この場合、『知るようになる』という表現はどのようなものだろう?」と問うとき、私たちは [議論の] 横道に逸れてしまったように思う。しかしこの問いこそが、真に「知る」という語の文法に関わるものである。「私たちは何を『知るようになる』と呼ぶのか?」という形式で言えば、そのことがよりはっきり分かる。これが、私たちが「椅子に座る」と呼ぶことであるということは、「椅子」という語の文法の一部であり、これが、私たちが「意味の説明」と呼ぶことである、ということは「意味」という語の文法の一部である。同様に、他人が歯痛を有していることについての私の基準を説明することは、「歯痛」という語について文法的説明を与えることであり、この意味にで、「歯痛」という語の意味に関する説明を与えることと同じなのである。
私たちが「誰それが歯痛を持っている」という句を習うとき、歯痛を持っていると言われる人のある種の振る舞いを見せられた。一例として、頬を押さえるという振る舞いを考えよう。もし、ある特定のケースにおいて、この基準よりある人物が歯痛を持っていることが判明すると必ず、その人の頬に赤い斑点が現れることを、私が観察によって発見したとする。そして私が誰かに「Aは歯痛を持っている。ほら、彼の頬に赤い斑点が出ている」と言ったとする。するとその人は「君がAの頬に赤い斑点を見つけたときは、Aが歯痛を持っていると、どうして分かるのか」と訊いてくるだろう。これに対し私は、赤い斑点の出現とある種の現象が同時に起こることを指摘しなければならない。
さて、相手はなおも尋ねる。「彼が頬を押さえるときは、彼が歯痛を持っていると、どうして分かるのか?」私の返答はおそらく「彼は頬を押さえたとき歯痛を持っている。なぜなら、私が歯痛を持っているとき、私は自分の頬を押さえるからだ」というものだろう。しかしさらにこう尋ねられたらどう答えればいいだろうか――「それで、君が頬を押さえることと君の歯痛が同時に起こるからという理由だけで、なぜ君は、彼が頬を押さえることと彼の歯痛が同時に起こると考えるのか?」君は何と答えてよいか途方にくれるだろう。そしてここに至って、私たちは、 [もう説明のしようがない] 固い岩盤に突き当たったということが分かる。つまり、規約まで降りてきたのである(もし君が、「彼が頬を押さえるとき、彼が歯痛を持っているということを、君はどうやって知るのか」という質問に対して、彼に対して「どうしたのか」と声をかけるといつも、「実は歯痛なんだ」という返答が返ってきたから、ということを答えにしたいと思うなら、――この経験は単に、頬を押さえる行為と特定の言葉を言う行為とを結びつけることしかしない、という点を思い出してほしい)。
ここで、初歩的な混乱を避けるために、 [基準と徴候という] 二つの対照的な用語を導入しよう。「これこれのことが事実であると、どのようにして知るのか?」という問いに対して、私たちは、ある時は「基準(criteria)」を挙げることによって答え、またある時は「徴候(symptom)」を挙げることによって答える。もし医学において、特定の細菌によって引き起こされる [喉の] 炎症が「アンギーナ」と呼ばれ、ある特定の症例において私たちが「なぜあなたは、この人物がアンギーナに罹っていると言うのか」と [医者に] 尋ねたとしよう。すると、医者は「この人物の血液中にバシラス菌とかそういうものが見つかったから」と答えるだろう。この答えは、私たちに基準を、または、アンギーナの定義基準と呼べるものを与える。これに対して、もし回答が「彼の喉が腫れていたから」というものだったら、この答えはアンギーナの徴候を与えたと言っていいだろう。私が「徴候」という語で呼ぶのは、経験上、定義基準である現象と何らかの仕方で共時的に起こる現象である。だから、「バシラス菌が彼の体から見つかれば、彼はアンギーナである」と言うことは、トートロジーか、さもなくば「アンギーナ」という病気の定義を緩やかに述べる一手段にすぎない。しかし「彼の喉が腫れているときは必ずアンギーナである」と言うのは、仮説を立てることである [こんなことをしてはいけない]。
実際には、どの現象が定義基準でどの現象が徴候かを区別してくれと言われたら、大抵の場合、その場しのぎの場当たり的な判断をする以外に答えようがないだろう。現実的な道は、一つの現象を定義基準としてとることで、ある語を定義することである。しかし、最初の用法では徴候として使われていた語を [基準として] 定義しなおすよう促されることも、しばしば起こることである。[普通] 医者は、あの現象が基準でこの現象が徴候として捉えられるべきだ、という判断などせずに病気の名前を使う。この使い方は明晰性を欠いているが、だからといって責められるべきものでもない。その理由は、一般に私たちは言語を厳格な規則に従って使っているわけでも、教えられたわけでもない、ということを思い出してもらえれば分かるだろう。他方、[哲学の] 議論においては、私たちは言語を厳密な規則に従う計算手続きと常に比較する。
言語を厳密な規則に従う計算手続きとみなすことは、言語に対する非常に一面的な見方である。実際は、言語をそういう計算として使うことは滅多にない。なぜなら、私たちが言語を使う際、用法の規則や定義について考えたりしないし、そういう規則を答えろと言われてもまず答えられないからである。私たちの使う諸概念を明確に定義できない理由は、その真の定義を知らないからではなく、真の「定義」など存在しないからである。「概念の真の定義は存在しなくてはならない」という考えは、「子供がボール遊びをしているとき、そこには必ずゲームを支配する規則があるはずだ」という考えと似ている。
言語を厳密な計算における記号表現(symbolism)としてみなすとき、私たちが思い描く言語は諸科学や数学におけるそれである。日常的な言語使用がこういう厳格さの基準と合致することは滅多にない。それではなぜ、哲学の議論においては、言語使用を厳密な規則と常に比較するのか?私たちが懸命に取り除こうとしている問題の源泉が常に、言語に対するまさにこの態度 [=通常の言語使用を、厳格な規則に従う言語使用と同じように考える態度] にあるから、というのがその答えである。
例として「時間とは何か」という問題を考えてほしい。これは聖アウグスティヌスやその他の人々もかつて問うた問題だ。一見するとこの問題は、答えとして定義を求めているように見える。しかしそうだとすると、すぐに以下の問題が生じる。「定義は私たちを未定義の別の用語に導くだけなのに、一体、定義によって何が得られるのか?」そして、「椅子」の定義が欠けていることには困惑する必要がなく、まさに「時間」の定義が欠けていることに困惑しなければならない理由は何だろう? 定義を得られない全ての場合について困惑する必要がないのは何故だろう? さて、定義はしばしば語の文法を明瞭にする。そして事実、私たちを困惑させているのは、「時間」という語の文法なのである。「~とは何か?」という若干ミスリーディングな問いを発することで行なわれていたのは、単に、この困惑を表現することにすぎない。この問いは、はっきりしない気持ちや心理的不快感を示す発言であり、子供が頻繁に発する「なぜ?」の問いと似ている。子供の「なぜ?」もまた、心理的不快感を示す表現であり、必ずしも原因や理由を求めているわけではない(ヘルツ『力学の原理』[10])。さて、「時間」という語の文法についての困惑は、文法における見かけ上の矛盾とでも言えるものから生じるのである。
アウグスティヌスが「時間を測ることはどのようにして可能か?」ということを論じたとき、彼を困惑させたのもこのような [見かけ上の] 「矛盾」だった。なぜなら、過去を測ることはできない(過ぎ去ってしまっているから)し、未来を測ることもできない(まだ来ていないから)、そして現在を測ることもできない(広がりを持たないから)からである。
ここで生じるように見える矛盾は、語の――この場合は「測定」――異なる二つの用法の間の衝突とでも言えるものである。私たちに言わせれば、アウグスティヌスが [「時間を測る」という文の意味を考えるときに] 想定していたのは長さを測る過程、例えば、私たちの前を流れていく帯の上の二点間の距離を測る過程である。彼によれば、私たちの眼前に見えるのはその帯の微小な点(「現在」に対応する)にすぎない。この困惑を解決する鍵は、流れ行く帯の上の二点間の距離を測るときの「測る」という語(の文法)と、時間 [の長さ] を測るときの「測る」という語(の文法)とを比較することにある。こう言ってしまうと単純な話に思われるかもしれないが、この問題は非常に難しい。というのも、私たちの言語における二つの似通った構造の間の類比が、私たちを幻惑するからである(しばしば、子供が一つの語が二つの意味を持つことをほとんど理解できないことを思い出してもらえれば、この点を理解する助けになるだろう)。
さて、時間の概念に関するこの問題が、厳密な規則に基づく形式の答えを求めていることは明らかだ。この問題がもたらす困惑は、規則に関するものである。――別の例を出そう。ソクラテスの「知識とは何か?」という問いについて考えよう。この例では、事態はさっきよりもっと明快である。なぜなら、ソクラテスの議論は、まず一人の弟子が「知識」という語の正確な定義を与えることから始まり、次に、それに倣って「知識」という語の定義が求められるからである。このような問いが出されれば、「知識」という語の通常の使用には何か間違いがあると思ってしまう。まるで、私たちは「知識」という語の意味を知らないのだから、その語を使う権利がない、とでもいわんばかりである。[こういう場合は] 「『知識』という語の正確な使用法などない。しかし、私たちは、実際の語の用法に多少なりとも合致する幾つかの使用法を作り上げることはできるのだ」と言い返してやるべきだ。哲学的混乱に陥っている人間は、語の用法にある一つの法則を見つけ、それをどのような場合にも一貫して適用しようとする。その結果、複数のケースが互いに矛盾することになってしまう。この手の混乱に支配された議論でありがちな進行の仕方は、次のような調子だ。第一段階として、「時間とは何か」という問題が問われる。この問いは、定義を答えとして望んでいるような見かけをしている。そこで私たちは、定義こそ困難を取り除いてくれるものだと勘違いする([だが、]ある種の飢餓状態では、食べることでは飢えの感覚は取り除けない [それと同じで、定義を与えることでは哲学的混乱を取り除くことはできないのだ])。そして、例えば「時間は天体の運動である」のような間違った定義が与えれらることになる。第二段階では、この定義が不十分であることを確認する。しかしそのことが意味するのは、「時間」という語が「天体の運動」という表現と同義的には使われない、ということだけである。ところが私たちは、最初の定義は間違っていたと言う際、今度は別の定義、正しい本当の定義で置き換えなければならないと考えてしまう。
上記の [「時間」という語の] ケースと、数の定義のケースとを比較してほしい。「数は数字と同じものだ」という説明は、定義への最初の渇望を満足させる。だがそうすると、次のように問わずにはいられない。「もし数が数字でないなら、それは一体何か?」。[他の場合はいざ知らず、] 私たちが言うところの哲学とは、表現形式が私たちに及ぼす幻惑に対する戦いである。
語は私たちが与えた意味を持つという点を思い出してほしい。そしてその意味は説明によって与えられる。私が語の定義を与え、それに従って語を使う。あるいは、私に語の使用を教えた人物は、語の定義も与えたのだ、ということもできる。あるいはまた、語の説明を与えることで、訊かれれば答える用意のある説明を意味することもあるかもしれない。ただしこれは、もし私たちが、何らかの説明を与える用意があるならば、という条件つきである。だが大抵の場合、私たちはそんな用意はしていないものだ。この意味で、多くの語は正確な意味を持ってはいない。しかし、それを語の欠陥というのは当たらない。その考えはまるで、「私の読書灯は本当の光ではない。なぜならこの光は明確な境界を持っていないからだ」と言うようなものだ。
哲学者たちは非常に頻繁に、語の意味の探究や分析について口にする。だが忘れてはならない。語はその意味を、いわば人間とは独立の力によって与えられたのではない。だから、語が本当は何を意味しているのかを科学的に探究する方法もありえないのだ。語が意味を持つのは、誰か人間が語に意味を与えたからである。
確かに、明確に定義された意味を持つ語というのも、幾つかある。そういう意味を表にまとめることも簡単だ。しかし、「この言葉は、互いに重なりあう無数の異なる使い方をされる」と言いたくなる語もまた存在する。そういう語の使用についての厳密な規則を表にまとめることができなくても、驚くことはない。
「私たちは哲学において、日常言語に対する理想言語を考えている」と言うことは間違いである。なぜなら、この言い方はまるで、日常言語を改良することができるとでも言わんばかりだからだ。日常言語は全く完全である[11]。[これに対し、] 私たちが「理想言語」を作ると言う場合、その目的は、理想言語によって日常言語を置き換えることではなく、普通の語の厳密な使用を把握したと考えることで心の中に生じる諸問題を取り除くことに過ぎない。これがまた、私たちの方法が、単に語の実際の使用法を数え上げるだけでなく、新しい使用法の慎重な発明――そういう新使用法の幾つかは、[実際の使用法の] 不合理な外見のゆえに発明されるのだが――をも含む理由でもある。
「私たちの方法によって、[表現形式の] 類似性が持つミスリーディングな効果に対抗する」と私たちが言うとき、重要なことは、[表現形式の] 類似性がミスリーディングであるというこの考えが、何ら明確な定義を与えられていないことを理解するべきだ、ということだ。「彼は [表現形式の] 類似性によって誤誘導された」と言うべきケースに対して、明確な境界を決めることはできない。類似した [形式の] パターンの上に作られた表現を使うことで、普通はかけ離れた二つのケース間の類似性が強調されることがある。こういう表現は、その働きにより、極めて有用でありえる。だが多くのケースでは、[表現形式の類似性はミスリーディングなもので、] それが人を誤誘導し始める正確なポイントを示すのは不可能だ。いかなる特定の表記も、ある特定の観点を強調する。例えば、私たちが自分たちの探究を「哲学」と呼ぶなら、この呼び名は一方では適切だが、他方、他の人々にとってはミスリーディングである(人によっては、私たちが扱っているテーマは哲学ではなく、かつて「哲学」と呼ばれたテーマを継承するものの一つである、と言うかもしれない)。私たちが特に、誰かが表現形式によって誤誘導された、と言いたい場合、こう言おう。「彼がこれこれの [二つの] 語の文法における違いに気付いていたら、あるいは、彼が他の表現も可能であることに気付いていれば、そういう言い方はしなかっただろう」等々。従って、数学の哲学について考える幾人かの数学者について、「彼らが『証明』という語の多様な使用法の間の違いに気付いていないのは明白だ」と言うことができるだろう。さらに彼らは、「種類」という語の複数の使用の間の違いについても明確に理解していない。彼らが数や証明の種類について語るとき、そこでの「種類」という語は「リンゴの種類」と言うときの文脈と同じ意味で使われている。あるいはこう言ってもいい。彼らは、5角形の作図方法を発見するときと、南極を発見するときの「発見」という語の相異なる意味の違いに気付いていない。
さて以前、「希求する」「怖れる」「期待する」などの語の他動詞的・自動詞的用法を区別したとき、私たちはこう言った。「もしかすると、「二つのケースの違いは、単に私たちが望む対象を知っているか知らないかの違いにすぎない」と言うことで私たちの困難を解消しようとする人がいるかもしれない」と。私が思うに、こういう意見の持ち主は、彼が説明して消し去ろうとしている困難が、二つのケースにおける「知る」という語の使用を注意深く考えたとき再び姿を表すこと [従って、無限後退に陥り、何の解決にもなっていないこと] を分かっていない。「その違いは単に~にすぎない」という表現は、あたかも、「私たちはそのケースを分析し、そして単純な分析を発見した [従って困難は解消された] 」と私たちに思わせる。それはちょうど、全く異なる名前を持つ二つの物質が、[分析の結果、] ほとんど同じ組成をしていたことを指摘するときのような調子だ。
上記の場合、私たちが以前言ったように、「私たちは希求を感じる(自動詞的用法)」と「私たちは希求を感じるが、しかし何を希求しているか知らない(他動詞的用法)」という両方の表現が使われうるだろう。互いに矛盾すると思われる二つの表現を、私たちは正しく使えるというのは、奇妙に聞こえるかもしれない。だがそういうことは極めて頻繁に起こる。
このことを明確にするために、次の例を使おう。私たちは「方程式 x2 = -1 は解として ±√-1 を持つ」と言う。しかしかつては、この方程式には解がないと言われていた時代があった。この昔の言明が今の言明と折り合うかどうかはともかくとして、[二通りの解を与えるような] 多重性を持っていないことは確かである。しかしこの言明に多重性を与えるのは簡単だ。「方程式 x2 + ax + b = 0 は解を持たないが、しかし [実数]αに [虚数]βだけ近づく」と言えばよいのだ[12]。また同じような喩えとして、「直線は円と常に交わる。ある時は実数の点で、またある時は虚数の点で」とか「直線は円と交わるか、あるいは交わることなく、交点から [虚数]αだけ離れている」言うこともできる。この二つの言明は、正確に同じことを意味している。どちらの言明がより満足いくものであるかは、人がどういう観点を取りたがるかによって変わる。[円と直線が] 交わる場合と交わらない場合の違いをなるべく目立たせないようにしたい場合もあるだろうし、逆に、その違いを強調したい場合もあろう。どちらの傾向も、例えば特定の実際的な目的によって、正当化されるだろう。しかしそういう目的が、彼がある一つの形式を別の形式より好むことの理由には全くならないかもしれない。彼がどの [表現] 形式を好むか、[あるいはそれ以前に] そもそも彼にそのような好みがあるのかを決めるのは、一般的に深く根ざした彼の思考傾向である場合が多いのだ。
(ある人が他の人を軽蔑しているがその自覚がないと言うべきか、それとも、そういう場合は、彼はその人を軽蔑してはいないが、意図せずに軽蔑的な態度――声の調子とか、一般的に軽蔑という行為に伴うような態度――で接している、と言うべきだろうか? どちらの表現形式も正しい。だが、この二つの表現形式は、[どちらの表現を選択するかによって、表現を使う人の] それぞれ異なる心の傾向を密かに告げることはあるかもしれない。)
さて、話を元に戻して「望む」「期待する」「希求する」などの表現の文法について調べよう。そして、最も重要なケース、つまり「私はこれこれのことが起こることを望んでいる」という表現が意識過程を直接描写しているケースを考察しよう。すなわち、「君が望んだのことは本当にこれだと確信できるか?」という問いに対し、「もちろん。私は間違いなく自分の望んでいることを知っている」と答えたくなるケースである。さて、この回答を、「君はABCを知っているか?」という質問に対する回答と比較してほしい。「ABCぐらい知っているさ」という断言は、「自分の望んでいることを知っている」と言うときの断言と類似した意味を持っているだろうか? ある点では、どちらの断言も質問を [同じように] 一蹴している。だが「自分の望んでいることを知っている」という回答が言おうとしているのは、[「ABCぐらい知っている」という回答が言うような] 「そんな簡単なことぐらい、もちろん知っているさ」ということではなく、むしろ「質問自体が無意味だ」ということである。すると、この言い方で問いを一蹴するのは間違った方法であろう。「もちろん知っているさ」と言う代わりに、「もちろん、疑問の余地はない」と言うことができよう。そしてこの言い方は「この場合、疑いについて語ることは無意味だ」という意味に解釈される。このようにして、「もちろん私は自分の望んでいることを知っている」という回答は、文法的言明として解釈できるのだ。
似た例として、「この部屋は長さを持つか?」という問いに対して「もちろん持っている」という回答を返すケースを挙げられる。「無意味なことを訊ねないでくれ」と答えることもできるのだが、他方、「部屋は長さを持つ」という文は文法的言明としても使われうる。その場合は、[「部屋は長さを持つ」という文は] 「部屋は――フィートの長さである」という文は有意味だ、ということを言っているのである。
今私たちが考察している「望む」「考える」などの表現の意味には、極めて多くの哲学的困難が結びついている。こうした困難は、「人はいかにして事実ではないことを考えることが可能か?」という問いに集約できる。
この問いは、哲学的問いの見事な例である。それは「人はいかにして [事実でないことを考えること] ができるか?」ということを問うが、この問いに困惑させられる一方、私たちは、事実でないことを考えることほど容易なことはないと認めざるをえない。私が意味するのは、このことが再度示すことは、私たちの陥っている困難が生じるのは、何かを考えるとはどのようなことかを私たちが想像できないからではない、ということである。それはちょうど、時間を測ることについての哲学的困難が生じるのは、実際に時間がどのように測定されるかを私たちが想像できないからではない、ということと同じである。私がこんなことを言うのも、時として私たちの困難は、何かを考えたときに起こったことを正確に覚えておくことの難しさとか、内観の難しさとか、そういう種類の困難の一つだと思われることがあるからだ。だがそうではない。実際は、ミスリーディングな表現形式を通して事実を見ることから、私たちの困難が生じるのである。
「事実ではないことを考えられるのは何故か? もし私が、キングス・カレッジが火事ではないのに火事だと考える場合、キングス・カレッジが火事であるという事実は存在していない。それなのに何故、私はキングス・カレッジが火事であることを考えられるのか? [あるいは、今ここに] 存在しない泥棒を吊るし首にすることがどうしてできるだろう?」この問いに対し、私たちは以下の形式で答えられるだろう。「泥棒が [今ここに] 存在しなければ、そいつを吊るし首にはできない。だが、探すことはできる。」
この場合、私たちを誤まらせているのは「思考の対象」と「事実」という名詞と、「存在する」という語の異なる複数の意味である。
事実を「対象の結合」として見なすことも、この混同から生じる(『論理哲学論考』参照)[13]。試しに、「人は存在しないものを想像できるか?」と問うてみよう。回答は「想像するとしたら、存在する要素のありえない結合を想像するのだ」というふうになる。 [例えば] ケンタウルスは存在しないが、[構成要素である] 人間の頭と胴と腕、そして馬の脚は存在する。「だが、存在しているものとは全く異なる対象でも想像できるのではないか?」という反論があるかもしれない。この反論に対してはこう答えよう。「いやできない。要素や個体は存在していなくてはならない。 [なぜなら] 赤さや丸さや甘さが存在していなければ、それを私たちが想像することはできないから。」
しかし、「赤さが存在する」とは何を意味する命題なのだろう? 私の時計は、バラバラに分解されたり、破壊されたりしていなければ、存在する。 [これに対し] 「赤さを破壊する」とは一体どのようなことだというのか? もちろん、「全ての赤い対象を破壊する」ことを意味するのだろう。しかし、赤い対象が全て破壊されたからといって、それで赤い対象を想像することが不可能になるだろうか? これに対し、こう答える人がいるかもしれない。「だが、君が赤い対象を想像できるためには、以前に赤い対象が存在し、君はそれを見た経験がなくてはならない」と。――どうしてそんなことを知っているのか [それはただの仮説にすぎない] 。仮に私が「君の眼球を押すと君の脳裏に赤い像が生じる」と言ったとしよう。君が赤い色を初めて知った方法がこのようなものであるというのも、ありえなくはないではないか? そしてなぜ、眼球を押されることで脳裏に赤の像が生じることを、まさに「赤い斑点を想像すること」であると言ってはならないだろうか? [言ってよいはずだ。とすれば、赤い対象を見たことがあるという経験は、赤い対象を想像するための必要条件にはならない] (このとき君が感じる困難については、後の機会に議論せねばならない6。)
私たちは今や、こう言いたくなるかもしれない。「もしそれが存在すれば、私たちの思考を真とするような事実は、常に存在するわけではない。従って、それは私たちが考える事実ではない。」だがこのことはまさに、「事実」という語を私がいかに使いたいと望むかに拠っている。なぜ私は「キングス・カレッジが火事だという事実を信じている」と言ってはならないのか? これはただ、「キングスカレッジは火事である」ということを不器用に表現しただけなのだ。「私たちが信じているのは事実ではない」と言うことは、それ自体、混乱の結果である。私たちがそうしたことを言うときの表現は、 [例えば] 「私が食べているのは、砂糖キビではなく砂糖である」とか「画廊にかかっているのはスミス氏ではなく、彼の肖像画だ」というものだ。
次のステップとして私たちが取るであろう考えは、「私たちの思考の対象は事実ではないのだから、それは事実の影だ」というものだ。この影には様々な名前が付いている。「命題」や「文の意味」がそれである[14]。
しかしこの考えは私たちの困難を取り除いてはくれない。なぜなら、問題は今度は「いかにしてある物が、存在しない事実の影でありえるのか」という形で現れるからだ。
この問題を別の形で表現することもできる。それは「この影は何の影であるかを、私たちはいかにして知るか?」という問いである。――影は [対象の写像であるから] ある種の肖像画であると言えよう。それゆえ、私たちの問題は、「ある肖像画をN氏の肖像画たらしめるものは何か?」と言い換えられる。最初に自然と思い浮かぶ答えは、「肖像画とN氏との間の [見た目の] 類似性である」というものだ。この答えは、実際に私たちが事実の影について語るとき、何を心に抱いているかを示している。しかしながら、 [見た目の] 類似性が肖像画について私たちが持つ観念を構成しないことは全く明白である。なぜなら、肖像画の良し悪しについて語ることが意味をなさねばならないということが、肖像画の観念の本質だからである [もし見た目の類似性のみが肖像画にとって本質的なら、N氏と似ていない下手な肖像画は肖像画とは呼べないことになる]。言い換えれば、影は実物を実際の姿とは異なるようにも表現できなければならない。それが、肖像画についての私たちの観念の本質である。
「ある肖像画をこれこれの肖像画たらしめるものは何か?」という問いに対する明らかな、そして正しい答えは、それは意図である、というものだ。しかし、「これがしかじかの肖像画であると意図する」ということの意味は何か。それを知りたいなら、そう意図するときに何が起きているかを見てみよう。 [前に出した例だが、] 私たちが、ある人物が4時から4時半の間にやってくると期待するとき、何が起こっていたかについて話したときのことを思い出そう。[そのときの例と同じように] ある絵がしかじかの肖像画であると(描き手の立場から)意図することは、ある特定の心的状態でも特定の心的過程でもない。そうではなく、私たちが「~を意図する」と呼ぶべきことには、非常に多くの行為と心的状態が存在するのである。[例えば、] N氏の肖像画を描くよう言われて、N氏の前に座り、私たちが「N氏の顔を写す」と呼ぶ特定の行動を行なう、などの活動が含まれるだろう。人によっては、「 [N氏の顔を] 写す行為の本質は、写そうとする意図だ」と言って反論するかもしれない。これに対して私は、私たちが「何かを写す」と呼ぶ実に多くの異なる過程が存在する、と言って答えねばなるまい。一つ例を出そう。私が紙の上に楕円を一つ描き、君にそれを写すよう頼んだとする。このとき、写すという行為を特徴付けるものは何だろうか? というのも、君が私の楕円と似た楕円を描くことはない、ということは明らかだから。君はそれを写そうと試みて、失敗するかもしれない。あるいは、全く別の意図を持って描いた楕円が、偶然、描くべき楕円だったということもあるかもしれない [その場合、君は楕円を「写した」とは言えない。そこには「写すという意図」がないからだ] 。それでは君は、楕円を写そうと試みるとき何をするのだろうか? そう、まず楕円を見て、紙の上に何かを描いて、それを測り、元の楕円と一致しないことが分かれば、多分「くそ!」という言葉を吐く。または、「この楕円を写そう」と言って、似た楕円を描いて終わり、ということもあるだろう。このように、数限りなく多様な、互いに家族的類似性を持った行為と言葉が存在する。それらを私たちは「写そうと試みる」と呼んでいる。ある像が特定の対象の肖像画であるということは、それが対象から特定の方法で導き出されたということだ、と言ったとしよう。すると、私たちが「対象から像を導出する過程(簡単に言うと投影過程)」と呼んだことを描写するのは簡単である。しかしそのような過程も、[それによって導かれた像を] 私たちが言う「意図による表象」と同じだと認めることには特殊な困難がある。なぜなら、どのような投影過程(投影行為)を記述しようとも、この投影を再解釈する方法が存在するからである。従って――人はこう言いたいだろう――そうした過程は、絶対に意図それ自体ではありえない、なぜなら、私たちは常に、投影過程を再解釈することで逆のことを意図できるから、と。 [例えば] 以下のようなケースを想像してほしい。ある方向を指すために指差したり矢印を書いて、誰かに「この方向に歩け」と命令する。矢印を書くということは、私たちが普通、そういう命令を下すときに使う言語だとする。だが、命令を受けた人物がその矢印を、矢印の方向と逆向きに歩くよう解釈するということは、ありえないだろうか? [ありえる!] このことは明らかに、私たちが解釈と呼びうる記号を矢印の下に付け加えることによって行なわれる。例えば、誰かを騙そうとして、ある命令が通常とは逆の意味で行なわれなくてはならない、という取り決めをするケースは容易に想像できる。そして、元の矢に解釈を加える記号の一例が、矢の下に書き加えられた別の矢である。私たちが記号を何らかの方法で解釈するときは常に、その解釈は古い記号に加えられた新しい記号なのである。
私たちが誰かに、「機械的」なやり方(思考を伴わないやり方)でなく、矢印を示すことで命令を与えるときは常に、私たちはその矢印で矢印の方向か、または矢印とは反対の方向を意味している。そしてこの意味の過程は、それがどのような種類のものであれ、もう一つ別の矢印によって(最初の矢印と同じ方向か、または逆方向を指し示すよう)表現されうる。「意味する過程と言う過程」について描いたこの図 [二本の矢印が、同じ向きまたは違う向きに並んでいる図] において本質的なことは、言う過程と意味する過程は、それぞれ別の領域で起こると想像しなくてはならないことである。
従って、「どんな矢印も意味ではありえない。なぜなら、どの矢印も [矢印の向きと] 逆方向を意味しうるから」と言うのは正しいだろうか? ――言う過程と意味する過程の図式を、矢印を互い違いに上下に並べることによって描くとしよう。
→
←
→
もしこの図式が [矢印を示すことで誰かに命令を出すという] 目的に、仮にも役立つなら、この図式は3つのレベルのうちどれが意味のレベルであるかを示さなくてはならない。例えば、私が3つのレベルを持つ図式を作り、一番下のレベルが常に意味のレベルであるとすることができる。しかし、どのようなモデルや図式を採用しようとも、それは必ず最下層のレベルを持ち、そのレベルには解釈というものは存在しない [そのレベルを解釈するためには、もう一段下のレベルを必要とするから] 。この場合、「どのレベルの矢印も解釈されうる」と言うことが意味するのは、ただ単に、私が現在使っているモデルよりもう一段深いレベルを持つ、言う過程と意味する過程のモデルを作れる、ということだけである。
このことは次のようにも表現できる。――君が言いたかったことはこうである。「あらゆる記号は解釈可能である。しかし、意味は解釈可能であってはならない。それは最終解釈である。」今、私の想定では、君は意味を、言うことに随伴する過程であり、意味は記号に翻訳可能であり、記号と等価でさえあると考えている、ということになっている。従って君はさらに、ある記号とその意味を区別する目印として何を考えているか、答えなくてはならない。例えば、「意味とは、想像以外の方法によって描くあるいは作ることのできる矢印ではなく、まさに想像する矢印である [つまり「想像する」ということを目印に使う] 」と言うことで、記号と意味を区別しようとするなら、その場合君は、いかなる矢印が付加されようとも、それは君が想像した矢印の解釈とは呼べない、と言っていることになる [それはおかしなことだ]。
こうした問題は全て、私たちが何を言い、言ったことを意味するときに現実に起こることは何かを考えれば、より一層鮮明になる。――こう自問してみよう。もし私が誰かに「お会いできて大変嬉しい」と言い、そのことを意味したとする。そのとき、ある意識過程、それ自身が話し言葉に翻訳可能な過程が私の言葉に伴うだろうか? そんなことはまずありえない。
しかし、そういうことが起こる例を想像してみよう。[第一の例:] 英語を声に出して喋るとき、必ずそれに対応するドイツ語を心の中で呟く習慣を、私が持っているとしよう。そうすれば、何らかの理由で、心のうちのドイツ語を、声に出して話す英語の意味と呼ぶなら、確かに、言うことの過程に随伴する意味することの過程は、それ自体が外的な記号に翻訳可能である。[第二の例:] 私たちがあらゆる文を声に出して言う前に、その文の意味(それが何であれ)を一種の独り言として心の中で言うとする。[第三の例] 私たちが欲しがっている事例に、少なくとも似ている例がある。それは、私たちが何かを言い、それと同時に心中である像を見る、というものである。この場合、心中の像は意味であり、かつ私たちの言ったことと一致したりしなかったりするだろう。そういう事例や、それと類似の事例は存在するが、しかしそれらは、私たちが何かを言い、それを意味する、あるいは別の何かを意味するときに、通常起こることではない。もちろん、私たちが意味と呼ぶものが、ある確定的な意識過程であり、その過程が言語表現に随伴、先行または追随し、かつそれ自身が何らかの言語表現かまたは言語表現に翻訳可能なものである場合も、現実に存在する。その典型的な例は、舞台での「傍白」である。
しかし、私たちが言うことの意味は、本質的には今までに述べてきた種類の過程であると考えたくさせるものは、二つの並行する過程に言及するように見える二つの表現形式
「何かを言う」
「何かを意味する」
の間にある類似性である。私たちの言葉に随伴する過程――人はそれを「言葉を意味する過程」と呼ぶかもしれない――は、言葉を話すときの声の抑揚、あるいは顔の表情のような、それに似た過程である。これらの過程が言葉に随伴する仕方は、英語の文にドイツ語の文が随伴する仕方や、文を話すことに文を書くことが随伴する仕方と同じではない。そうではなく、歌の旋律が歌詞に随伴する仕方と同じなのである。旋律は、私たちが文を言うときに伴う「感じ」に対応する。私が指摘したいのは、この感じが、文が言われたときの表情、あるいは表情に似た何かである、ということである。
「思考の対象は何か」という私たちの問題に戻ろう。(例えば、私たちが「私はキングス・カレッジが家事だと考える」とき、この思考の対象は何か。)
この問題は、私たちの述べ方をしたのでは、既にいくつかの表現の混同を犯している。それは、この問題がまるで物理学の問題(例えば「物質の究極的構成物は何か?」)のように聞こえてしまうという事実だけからでも分かる。(「思考の対象は何か」という問題は、典型的な形而上学的問題である。形而上学的問題の特徴は、語の文法にまつわる不明瞭さを、科学的問題の形式を使って表現してしまうことだ。)
私たちの問題の起源の一つは、「I think x」という命題関数の二重の使われ方にある[15]。私たちはこう言う。「私はこれこれのことが起きると考える」、「私はこれこれが事実であると考える」、あるいはまた「私は彼が考えるのと全く同じ物を考える」。また、 [「考える」を「期待する」に置き換えれば] 「私は彼を期待する」とか「私は彼が来ることを期待する」とも言う。 [ここで] 「私は彼を期待する」と「私は彼を撃つ」を比較してほしい。彼が [今ここに] 存在しなければ、彼を撃つことはできない [しかし、彼が今ここに居ないときでも、彼を期待することはできる] 。「いかにして私たちは実現していないことを期待できるのか?」とか「いかにして私たちは存在しない事実を期待できるのか?」という問いはこのようにして生じる。
この困難から抜け出す道は次のようなものだと思われる。つまり、私たちが期待するのは事実ではなく、事実の影――いわば事実の隣にあるもの――なのだ、と。 [しかし] 既に述べたとおり、この考えは問題を一歩先送りしただけである。この [事実の] 影という考えの起源は複数ある。そのうちの一つが、「異なる言語の二つの文 [例えば「これはペンである」と「This is a pen」] が同じ意味を持つことができるのは確実だ。だから、意味は文と同じものではない」というものだ。そして私たちは「意味とは何か?」という問いを発することになり、「意味」は影のような存在であると答えてしまう。「影のような存在」とは、物質的対象が対応しない名詞に私たちが意味を与えようとするときに作り出す存在の一つである。
思考対象が影のような存在であるという考えのもう一つの源泉はこうである。私たちは影を、その意図に疑問を差し挟めない像、つまり、理解するために解釈を必要としない像、私たちが解釈なしに理解する像であると想像する。さて、[一方では] 私たちがそれを理解するには、異なる種類の像へ解釈を行なわねばならないタイプの像が存在する。 [他方には] それ以上いかなる解釈も必要なく、直接理解すると言うべきタイプの像が存在する。 [例えば] 君が暗号で書かれた電報を見て、さらにその暗号を解く鍵も知っているとする。すると普通は、電報を通常言語に翻訳する前に「この電報を理解した」とは言うまい。もしろん、[解読のとき君が行なったことは] ある種の記号[=電報]を別種の記号[=通常言語]で置き換えただけである。だがそれでも、君が通常言語で書かれた電報を読むときには、さらに電報を解釈するという過程は起こらないだろう。――あるいはむしろ、通常言語で書かれた電報をさらに一つの像に翻訳するというケースもあるかもしれない。しかしそのときでもやはり、君のやったことは、一群の記号を別の一群の記号で置き換えたにすぎない。
一般に考えられるところの影は、ある種の像、実際は、心像に非常に近いものである。そしてこの像はまた、普通の意味での描かれた表現ともかけ離れたものではない。この影という考えが生じる源泉の一つが、文を言い、聞き、読む行為が私たちの心眼に像を浮かばせる場合もある、という事実なのは確かだ。その場合に浮かぶ像は、程度に差はあれ、文と厳密に対応しており、従って、ある意味ではその文の画像言語への翻訳になっている。――だが人々が [文の] 影であると考えているような像にとって絶対的に本質的なことは、私が「類似による像」と呼ぶ像であることだ。この言い方の意味するところは、その像が表現するものと似ている像ということではなく、その像が表現するものに似ている場合にのみ正しいと認められる像のことである。この種の像を「コピー」と呼んでもいいだろう。簡単に言えば、原物と間違えられやすいコピーがよいコピーである。
[しかし、上記した二つの像とは別種の像もある。] 地球の半球の平面投影は、類似による像でもなければ、上の意味でのコピーでもない。誰かの肖像画を描くときに、奇妙ではあるが、しかしある決められたルールに従ってその人の顔を紙の上に投影するとしよう。その絵はどう見ても被写体の人に似ていないのだから、その絵を「これはよくできた誰それの肖像だ」と言う人は普通いまい。
[この例のように] 正しくはあるが、その対象に少しも似ていない像もありうることを念頭に置けば、現実と文の間に影を差し挟む必要は全くなくなる。というのも、今や文自身がそういう影の役割を果たせるからである。文はまさに、その表現するものと全く似ていない像である。「キングス・カレッジが火事だ」という文はいかにして「キングス・カレッジが火事だ」という事実の像でありうるのかと疑うなら、ただ「その文の意味を説明するとき、私たちはどのように行なうだろうか」と自問するだけでよい。ひょっとすると、説明が直示定義からできている場合もあるかもしれない。例えばこうだ。私たちは「これがキングス・カレッジだ」と言う(その建物を指さしながら)。さらに「これが火事だ」と言う(火事を指さしながら)。この説明は、語と物が結び付けられる場合の仕方を示している。
私たちが起こってほしいと願うことが私たちの願望の中に影として存在していなくてはならないという考えは、私たちの表現形式に深く根ざしている。しかし実は、このことは私たちが本当に言いたい不条理に比べれば、まだましな方である。もし言うことができるなら、私たちが願う事実 [それ自身] が私たちの願望の中に存在していなければならない、と言いたいのだ [だがそれは余りに不条理なので言えないのだ] 。なぜなら、もしその事実が私たちの願望の中に存在していなければ、まさにその事実が起こることをどうやって望むことができるだろうか? [できるはずがない。] だから、次のように言うことは全く正しい。「単なる影ではだめだ。影は対象まで届かない。だから、願望が対象そのものを含むことが望まれる。」――「スミス氏がこの部屋に入ってきてほしい」という願望は、代理人ではなくスミス氏自身が来ることを、他の部屋ではなく私の部屋へ、訪問の代用品ではなく訪問そのものを願望すべきだと、私たちは欲する。だが、これこそがまさに、 [願望の中で] 私たちが正確に言ったことである。
この [対象と影との] 混同は、こう描写することもできる。通常の表現形式に完全に合わせて、私たちは、自分が望む事実を、まだ現物としてここにはないもの、従って指さすことのできないものと考えるのだ、と。ここで、「私たちの願望の対象」という表現の文法を理解するために、この問いに対する回答をちょっと考えてみよう。「君の願望の対象は何か」という問いに対する答えは、もちろん「私はこれこれのことが起きることを望む」というものだ。ではさらに「その望みの対象は何か」という質問に対する答えはどうなるだろうか。その答えは、単に先の質問に対する答 [「私はこれこれのことが起きることを望む」] か、それを別の表現形式に翻訳したものでしか成り立たないかもしれない。例えば私たちは、私たちが望むものを他の言葉で言い表したり、絵で描写したりする。さて、私たちが願望の対象と呼ぶものは、いわば、まだこの部屋に入ってきていない人物、従ってまだその姿も見えない人である、という印象を持っているとき、私たちが想像しているのは、私たちが望むものについてのいかなる説明も、実際の事実について説明するには一歩足りない、という考えだ。私たちは、実際の事実は、その人はまだ部屋に入ってきていないのだから示すことはできない、と心配してしまうのだ。――あたかも、私が誰かに「私はスミス氏が来るのを期待している」と言い、その人が「スミス氏とは誰だい」と訊ねてきたら、「彼は今ここには居ないから君に見せるのは無理だ。写真なら見せられるがね」と答えるかのようだ。まるで、私が望むことが実際に起こるまでは、それについて完全な説明を与えることは絶対に不可能だといわんばかりである。しかしもちろん、こんな考えは幻想だ。本当は、私が望むものについての説明は、願望が果たされた後の方が果たされる前よりも、より良く与えられる必要などないのだ。なぜなら、スミス氏が部屋に入ってくる前に、私は友人に対してスミス氏を完全に良く示したかもしれないし、同様に「入ってくる」という語の意味と、私の部屋を完全に良く示したかもしれないからだ。
私たちの困難は、こう言い表すこともできよう。私たちはさまざまな物事について考える――しかしそれらの物事はいかにして私たちの思考の中に入り込むのか。私たちはスミス氏について考えるが、しかしスミス氏が今ここにいる必要はない。彼の写真も [彼について考える際に] 役に立たない。なぜなら、その写真が誰を写したものか、どうやって知ることができるというのか? 実際、 [写真に限らず] いかなる彼の代用品も役には立たないのだ。 [ということはつまり、彼の代用品ではなく、彼自身が思考の対象だということになる。] では、どうしたら彼自身が私たちの思考の対象でありえるだろうか?(私はここで「私たちの思考の対象」という表現を以前とは違う意味で用いている。今私がこの表現で意味するのは、私がそれについて考えるものであって、「考えている」ということではない)
私たちはこう言った。ある人物について考えたり、話したりすることと当人との結びつきが作られるのは、「スミス氏」という語の意味を説明するために当人を指差し「これがスミス氏だ」と言ったときである、と。この結合には何ら神秘的なものはない。つまり、スミス氏が実際にはここに居ないのに、私たちの心の中に何らかの方法でスミス氏を呼び出す奇妙な心的作用など存在しない、ということである。彼を心の中に呼び出すのはこの [思考と対象との何ら神秘性のない] 結合だということを理解しにくくさせているのは、日常言語の奇妙な表現形式 [過去時制] である。この形式が、思考(あるいは思考の表現)と思考対象との結合は、思考をしている間中持続したのでなければならない、と見せかけるのだ。
「ヨーロッパに居る私たちが、アメリカに居る人間を意味することができるとは奇妙なことではないか?」と言う人がいるかもしれない――ある人が「ナポレオンは1804年に戴冠した」と言い、私たちがその人に「君が意味しているのは、アウステルリッツの戦いに勝った人物かい?」と尋ねたとする。するとおそらく、「そうさ。私が意味したのはその人物だ」という答えが返ってくるだろう。ここで、彼が「ナポレオンが戴冠したのは1804年だ」と言ったとき、「意味した」という過去時制を使用したことで、あたかもナポレオンがアウステルリッツで勝利したという考えが彼の心の中に存在していなければならなかったかのごとく見せかけたのだろう。
私の友人が「今日の午後、N氏が私に会いに来る」と言ったとする。私が「君は彼のことを意味しているのか?」と言ってその場に居る人物を指差すと彼は「そうだ」と答える。この会話において、「N氏」という語とN氏との間に結合が作られた。だが私たちはつい、友人が「N氏が私に会いに来る」と言い、そのことを意味している間、彼の心が結合を作ったに違いないと考えたくなるのだ。
このことが、私たちに意味や思考とは奇妙な心的活動だと考えさせる一要素にもなっている。「心的」という語は、それがいかに作用するかを理解することを期待してはならない、ということを意味しているようなものだ。
私たちが「考えること」について述べたことは、また「想像すること」にも当てはまる。誰かが「私はキングス・カレッジが火事だと想像する」と言ったとする。そこで私たちは彼に訊く。「君が火事だと想像するその建物がキングス・カレッジであると、どのようにして分かるのか? それは良く似ているが別の建物ということはありえないか? 実際、君の想像力は完全無欠に正確で、君の想像した建物に一致する建物が [キングス・カレッジの他に] いくつもある、ということはありえないのか?」――それでも君はこう言う。「間違いなく、私が想像するのはキングス・カレッジであり、他のいかなる建物でもありえない。」しかしこのように言うことによって、私たちが欲している [語と対象との] 結合が作られるだろうか? [作られない。] なぜなら、このように言うことは、誰それ氏の絵の下に「誰それ氏の肖像」と書きつけるようなものだからだ。君がキングス・カレッジが火事だと想像している間中、「キングス・カレッジが火事だ」と言っていたことがあったかもしれない。しかし大半の場合は、君が像を思い浮かべている間中、説明的な言葉を話すことなどないだろう。たとえ君がそういうことをするにせよ、君 [の想像] はキングス・カレッジには届かず、ただ「キングス・カレッジ」という語に届くに過ぎない。「キングス・カレッジ」という語とキングス・カレッジが結びつくのは別のタイミングである。
これらのこと [「期待する」「考える」「想像する」などの対象は何かという問題] についての全ての推論で犯しがちな間違いは、あらゆる種類の像や経験は、ある意味で相互に緊密に結びついており、同時に私たちの心の中に存在せねばならないと考えることである。暗記している曲を歌ったりアルファベットを暗唱するとき、音や字は繋がっているように見える。そしてどれもが次に来る音や字を引き出すように見える。あたかも箱の中の真珠を一つ引き出すと、それに連なる真珠が次々と引っ張り出されるように。
もしビーズを通した糸が箱の中から蓋の穴を通して引っ張り出される視覚像を持っているとすれば、「ビーズは、引っ張り出される以前は箱の中で一緒に納まっていたに違いない」と言いたくなるのも疑いない。しかしこれが単に仮説を立てているだけだということは容易に分かる。 [なぜなら] ビーズが蓋の穴から出る瞬間に作られたとしても、私は同じ像を持ったに違いないからである。私たちは、意識された心的事象を述べることと、人が心の仕組みと呼ぶものについての仮説を立てることとの違いを間単に見過ごしてしまう。しかも [さらに困ったことに] 、私たちの心の作用についてのそのような仮説や像は、日常言語の多様な表現形式に埋め込まれている。「私はアウステルリッツの戦いに勝利した男を意味した」という文における「意味した」という過去時制は、そうした像の一部だ。その像においては、心は私たちが覚えていることが、表現される前に保存されている場所だと見なされている。もし私が良く知っている曲を口笛で吹いている最中に誰かに邪魔されて、「その先はどう続くか知っていたかい」と訊かれた、私は「もちろん知っていた」と答えるはずだ。ところでこのその先がどう続くか知っているとはどんな種類の過程なのだろう。それはまるで、曲の続き全体が、私が続きの吹き方を知っている間は [心の中に] 存在していなければならないとでもいうかのようだ。
[では、] 「曲の続き方を知るにはどの程度の時間がかかるか」と自問してほしい。あるいは、 [そもそも] それは時間的過程なのか? 私たちは、曲のレコードの存在と曲の存在を混同する過ちを犯しているのはないか? 曲が演奏されるときはいつでも、その曲を演奏するある種のレコードが存在していなければならない、と想定しているのではないか?
次のような例を考えてほしい。私の面前で銃が発砲されたとする。私は「この音は予想してたほど大きくはなかったな」と言う。するとある人が言う。「そんなことがありえるだろうか。君の想像の中では、銃よりも大きな音があったのか?」私は、そのようなものは無かったことを認めざるをえまい。すると彼はさらにこう言う。「それなら君は本当は、もっと大きな音を期待したのではない――君が期待したのは多分、もっと大きな音の影だったのだ――しかしだとしたら君は、それがもっと大きな音の影であることをどうやって知ったのか?」――このような場合、実際にどのようなことが起こったのかを見てみよう。私は多分、銃声を待ちながら口を開けて、何かにしがみついて「すごいことになるぞ」と言っただろう。そして発砲が終わると、「なんだ、それほど大きな音じゃなかったな」と言い、――体の緊張がほぐれる。しかし、このような緊張や口を開けること等々と、実際の大きな音ととの結合は何なのか? おそらくそれは、そのような [実際の] 音を聞くことと、今述べた経験をすることによって作られたのだ。
「心の中に考えを持つ」「心の前にある考えを分析する」などの表現を調べてみよう。これらの表現に誤誘導されないために、例えば、手紙を書いている際に「心の前にある」考えを正しく表現する言葉を探しているとき、実際に何が起きているのかを見てみよう。「心の前にある考えを表現しようとしている」と言うとき、私たちはごく自然に思いつく比喩を使っているのである。この比喩は哲学をしているときに私たちを誤誘導することがなければ、使っても問題ない。なぜなら、このような場合に実際に何が起きているのかを思い出せば、程度に差はあれ互いに良く似た多様な過程が見つかるからである。――私たちは、そういう全ての場合は、とにかく、心の前にある何かによって導かれると言いたくなる。しかしこのとき、「導かれる」や「心の前にある何か」という語は「考え」や「考えの表現」といった語と同じぐらい多様な意味で使われているのである。
「心の前にある考えを表現する」という句は、以下の3つのことを示唆している。
- 私たちが言葉で表現しようとするものは既に別の [心的] 言語において表現されている
- [心的言語による] 表現は私たちの心眼の前にある
- 私たちがすることは、心的言語から文字言語への翻訳である
(私たちは、定規とコンパスを使って角を三等分することが不可能なことを証明することは、角の三等分についての私たちの考えを分析することだ、と言いたくなるに違いない。しかしこの証明が私たちに与えるのは、三等分についての新しい概念、その証明が作り上げることで初めて私たちが持つようになった概念である。その証明は、私たちが行こうとしていた道に私たちを導いた。しかし、しかしその証明はまた、元居た場所から私たちを連れ去った。この証明は、私たちがずっと居た場所を明確に示しただけではなかったのである。)
さて、影が思考の表現と、思考が関与する現実の間に挿入されなければならないと想定しても何一つ得るものはない、という論点に戻ろう。もし現実の像が欲しいのなら、文自身がそのような像である、と私たちは言った(ただし、文は類似による像ではないが)。
私たちがこれまでずっと懸命に行なってきたことは、思考や希望、望む等々を表現する過程とは独立に、考える、希望する、望む、信じる等々の心的過程が存在しなくてはならないと考えたくなる誘惑を取り除くことであった。君に一つ戦術を授けよう。君が思考、信念、知識といったものの本性について困惑することがあれば、思考を思考の表現で置き換えてやるのだ。この置き換えにおける理解が困難な点――それはこの作業でまさに重要なことでもあるのだが――思考、信念、知識の表現がまさに一つの文であるという点である。――そして文が意味を持つのは言語体系の一員としてのみである。ちょうどある記号系(calculus)の内部における表現のように。ところが私たちは、この記号系をあたかも、私たちが口にするあらゆる文の後ろに常に存在している背景だと想像したり、紙の上に書かれたり話されたりした文は孤立しているとはいえ、その [背景にある] 記号系全体は考えるという心的活動の中に存在するのだと考えるよう、誘惑される。この心的活動は、 [紙の上で] 記号操作をする活動では起こりえない作用を、奇跡的な仕方でもたらすように見える。さて、ある意味で記号系全体は同時に存在していなければならないという考えが消え去れば、私たちの [記号による] 表現に並行して何か奇妙な心的活動が存在すると想定することには、何の意味もないことになる。もちろん、このことは、私たちの思考の表現に奇妙な意識の活動が伴わないことを示したわけではない! [そういうことはありえるかもしれないのだ。] ただ、もはや、心的活動が思考の表現に伴わなくてはならないと言うことはない、というだけである。
「しかし思考の表現は、常に私たちを欺くことができる。なぜなら、私たちはあることを言い、しかしそれによって別のことを意味することができるではないか」 [と反論する人がいるかもしれない。] [そういう場合は、] 私たちがあることを言い、しかしそれによって別のことを意味するときに起こる、様々なことを想像してほしい。――次のような実験をしてみよう。「この部屋は暑い」と言い、それによって「この部屋は寒い」を意味する。このとき君が行なったことを詳細に観察するのだ。
[また] 「独り言」によって私的思考を行い、声に出して何かを言うときは、その後に独り言で反対のことを言うことによって嘘をつくような人物を想像することは簡単だろう。
「しかし、意味したり考えたりすることは、私的経験である。それらは書いたり話したりなどのような [公共的] 活動ではない」といって反論する人もいるかもしれない。――しかしなぜこれらが特殊な私的経験――書いたり話したりする筋肉の、視覚の、触覚の [私的] 感覚であってはならないのか? [書く、話すなどが私的経験であっても一向に構わないのだ。]
次の実験をしてほしい。ある文、例えば「明日はきっと雨だろう」を言い、そしてその通りのことを意味する。次に再び同じこと [明日はきっと雨だろう] を考え、君がまさに意味したことを意味する。ただし、今度は何も言わずに(声に出すのはもちろん、心の中で言ってもいけない)。もし「明日はきっと雨だろう」という考えが「明日はきっと雨だろう」と言うことに伴ったとすれば、ただ考えることだけをして、言わないようにしてみよ。もし考えることと言うことが、歌の歌詞とメロディーの関係であるとすれば、ちょうど歌詞抜きでメロディーを歌うことができるように、言うこと抜きに考えることができるだろう。 [しかし現実にはそれは不可能だ。]
だが [逆に] 考えること抜きに話すことは、とにかく可能ではないだろうか? もちろん可能だ――だが考えること抜きに話すとき、君がどのようなことをしているか観察してほしい。特に何よりも観察してほしいのは、私たちが「 [何かを] 言い、そして言ったことを意味する」と呼ぶ過程が、君が言うそのときに起こることによって考えること抜きに言う過程と、必ずしも区別されていないという点である。この二つの過程を区別するのは、君が話す前、あるいは後に起こることである、ということも十分ありえるのだ。
私が、慎重に、考えること抜きに喋ろうと試みたとしよう。――このとき、実際には私は何をしているのだろう? 本からある一文を、なるべく機械的に、つまり普通にその文を読めば喚起される像や感覚を努めて持たないようにして、読み出すかもしれない。この機械的朗読を行なう一つの方法は、文を読んでいる最中、私の意識を他のことに集中させておくことである。例えば肌をつねりながら読むとか。――これを次のように表現しよう。考えること抜きに言うとは、言うことのスイッチを入れて、言うことに随伴するもののスイッチを切ることである、と。さてここで自問してほしい。ある文を言うこと抜きにその文を考えることは、(それまで切ってあったスイッチを入れ、入れてあったスイッチを切ることで)このスイッチを切り替えることであろうか? つまり、ある文を言うこと抜きにその文を考えることは、単に、言葉に随伴するものは保持し、言葉そのものは捨て去る、ということなのだろうか? ある文が持っている思想を、当該の文抜きに考えてみよ。そして、これが現実に起こることなのかどうか見てみよ。
これまでの議論をまとめよう。もし私たちが「考える」、「意味する」、「望む」などの語についての使用法を詳細に吟味するなら、私たちの思考を表現する過程とは独立な、そして [心という] 奇妙な媒体の中にある、思考の奇妙な活動を探したくなる誘惑から解放される。私たちはもはや、考えるという経験は言うというまさにその経験かもしれないしあるいは、言うという経験に加えてそれに随伴する他の経験かもしれない、という認識に達することを、確立されている表現形式によって妨げられることはない。(次の事例を調べることは有益だ。今掛け算が文の一部であると想定しよう。そこで、7×5=35と考えながら7×5=35と言うことはどのようなことか、反対に、7×5=35ということを考えずに7×5=35と言うことはどのようなことか、自問してほしい。)語の文法を吟味することによって、私たちの表現形式のある確固たる地位を弱められる。この表現形式が、偏見の無い目で事実を見ることを妨げていたのだ。私たちの探求は、「事実は私たちの言語に埋め込まれたある特定の像と一致しなければならない」という偏見を取り除こうとしたものである。
「意味」という語は、私たちの言語において半端仕事をすると言われる語の一つである。哲学的問題の大半は、この種の語によって引き起こされる。ある組織を想像してほしい。大半のメンバーは特定の正規の仕事を担っている。それは例えば、組織の規約の中に容易に書き込むことのできる仕事だ。反対に、半端仕事――極めて重要な仕事ではあるが――のために雇われているメンバーもいる。――哲学における大半の問題を引き起こす原因は、こういう「半端仕事」を引き受ける語の使用を、あたかも正規の仕事をする語のように記述したくなる誘惑に駆られることにある。
私的経験について話すことを、私がこれまで引き延ばしてきた理由は、この論点について考え始めると、私たちが普通に「私たちの経験の対象」と呼ぶべきものについての常識的概念を粉々に破壊してしまいかねない、大量の哲学的困難が生じるからである。そしてこうした困難に打ちのめされると、記号や、今までに言及してきた様々な対象について私たちが述べたこと全てが、もう一度考え直されなければならないような気がしてくるかもしれない。
この状況は、一面では、哲学の研究において典型的に見られる状況である。こういう状況に陥ると、時として「全ての哲学的問題が解かれるまでは、いかなる哲学的問題も解けない」と言われてきた。この発言が意味するのは、全ての哲学的問題が解決されない限り、新しく現れる問題が、過去の [解決の] 結果まで怪しいものにする、ということだ。この発言に対しては、もし哲学についてそのように一般論的に言うのであれば、私は次の簡単な回答をするに留めたい。つまり、新しく生起する問題はどれも、私たちの以前の部分的な解決が [解決の] 最終的な全体像の中で占めるべき位置を怪しいものにするかもしれない、と。そこである人が「以前の[部分的]解決は再解釈する必要がある」と言えば、私たちは、[必要なのは再解釈ではなく] それらの部分的解決を異なる文脈に置くことだ、と言うべきである。
図書館の本を整理しなければならないと想像してほしい。仕事を始めるときは、それらの本は床に乱雑に散らばっている。さて、本を整理して正しい場所に置く方法は色々とある。ある人は本を一つ一つ手にとってそれを正しい棚に入れていくかもしれない。これに対し私たちは、とりあえず順序だけを揃えるために、何冊かまとめて棚に置くかもしれない。この一組の本は、後で、正しい場所へ一括して移す必要がある。だが、だからといって、「順序を揃えるために本をまとめて並べる作業が、最終結果への一歩ではない」と言うことは間違いだろう。この場合、たとえ揃えた本全てを一括して他の場所へ移さなければならなかったとしても、ひとまとめに揃えられる本をまず揃えることが確固たる成果であるのは全く明白なことだ。しかし哲学における最大の成果のうちの幾つかは、一まとめに揃えられる本を取り上げ、それらを別々の棚に置く、ということと比較できるに過ぎない。それらの本が置かれる場所について得られる最終結果は、単に、もはやそれらが [同じ棚に] 並べられることはない、ということだけである。この仕事がいかに困難かを知らない傍観者は、「このような場合、それでは何も達成したことにはならない」と考えるかもしれない。――哲学における困難とは、私たちが知っている以上のことは言わないことである。例えば、私たちが二冊の本を正しい順序に並べたとき、それによって二冊を最終的な配置に置いた [そしてそれ以上のことではない] ことを理解するということである。
私たちを取り巻く物と私たちの個人的経験 [=私的経験] との関係を考えるとき、これら個人的経験は [私たちを取り巻く] 現実を構成する材料であると言いたい誘惑に駆られることがある。この誘惑がどのようにして生じるかは、後に明らかになるだろう。
このように考えると、私たちは自分を取り巻く対象について確固たる把握をしているという自信を喪失し、代わりに、互いに孤立した個々人の個人的経験のみが残されることになる。すると今度はこういう個人的経験さえ曖昧で常に移ろいやすいもののような気がしてくる――つまるところ、私たちの言語はこういう経験を記述するようにはできていない、と思われてくる。そのような個人的経験を哲学的に解明するには、私たちの言語は粗すぎるので、もっと精密な言語が必要だと考えたくなる。
こうして、私たちは一つ発見をしたような気になる――つまり、私たちが立っているこの大地、確固として信頼できるように見えていた大地が、実は泥沼であり安全でないことを発見した、と。これこそが哲学をしているときに起きることである。というのも、 [哲学をやめて] 常識的見地に立ち戻れば、この一般的不確実性は即座に消えうせるからである。
この奇妙な状況をいくらかでも解明するには、実例を見ることである。実際に、私たちが陥っている困難を描き出し、その種の困難から抜け出す方法を示す一種のたとえ話を見ることによって。私たちは、通俗科学者たちによってこう告げられる。「私たちが立っている床は、常識的には堅いと思われているが、実はそうではない、なぜなら床の木は空間を満たしている微粒子によって構成されているが、その密度は非常に低く、従って床はほぼ真空だから。」こう言われると、私たちは困惑してしまう。なぜなら、私たちはもちろん、ある意味で床が堅いこと、あるいはたとえ床が堅くなかったとしても、それは木が腐っているからであって、木が電子のような微粒子から構成されているからではないということを知っているから。木が微粒子から構成されているという理由で「床が堅くない」と言うことは言語の誤用である。なぜなら、たとえ微粒子が砂粒ほどの大きさで、かつ砂山で砂粒が密集しているのと同じぐらいの密度で密集していたとしても、砂山が砂粒から構成されているのと同じ意味で床が微粒子から構成されていれば、その床は堅くないであろう。 [従って] 私たちの困惑は、ある誤解に基づいていたのである。つまり、「微粒子の密度が低い空間」という像が誤って適用されていたのである。なぜなら、物質の構造についてのこの像は、まさに [物質の] 堅さという現象を説明するためのものだったから。
この例で見たように、「堅さ」という語は誤って使われており、私たちは、何一つ実際には堅くないのだということを示したように思われる。それと全く同様に感覚経験についての一般的曖昧さや現象の流動性についての困惑を述べる際、私たちは「流動性」や「曖昧さ」という語を、形而上学にありがちな仕方で誤って使っている。つまり、これらの語には反対概念が欠けているのである。これに対し、正しい日常的な使用においては、曖昧さは明確さの、流動性は安定性の、不正確さは正確さの、問題は解決の反意語である。人によっては、「問題」というまさにこの語が、私たちの哲学的困難に用いられるときには、誤用されているのだ、と言うかもしれない。これらの[哲学的]困難は、それが [解決の反意語としての] 問題とみなされている限り、人を焦らして苦しめる、解決不可能なものである。
私は、私自身の経験のみが実際に存在する、と言いたい誘惑を感じる。私は私が見、聞き、痛みを持つ等々のことを知っている。だが他人がそうしていることまでは知らない。私はそれを知ることができない。私は私、他人は他人だからだ。
しかし一方、私は誰かに対し「私の経験だけが唯一現実のものである」と言うのを恥ずかしく思う。彼もまた彼の経験について私と全く同じことが言えると知っているからだ。これでは、「私の経験だけが唯一現実のものである」という発言は馬鹿げた屁理屈になってしまう。さらに私はこうも言われる。「もし君が、誰かが痛みを感じていることに同情するなら、君が少なくとも彼が痛みを感じていると信じていなければならないということは確実である。」だが私は [私の経験だけが唯一現実のものであると考えているのに] どうしてそんなことを信じられようか? どうして「彼が痛みを感じていることを信じる」という言葉が私にとって意味を持ちうるだろうか? どうして、何の証拠もなしに他人の経験などという観念を思いつくことができたのか?
だがこれは、質問するには奇妙な問いではなかったか? 私は誰かが痛みを持つことを信じられないとでもいうのか? [実際には] そう信じることは極めて容易いことではないか?――物事は常識通りだというのが答なのではないか――再度繰り返すが、言うまでもなく、私たちはこうした困難を通常の生活において感じることはない。私たちの経験を内観によって吟味するときや、科学的に探究するときも、こういう困難は感じない。だがとにかく、私たちの経験をある仕方で眺めるとき、 [他人の痛みについての] 私たちの表現は混乱しがちになる。それはあたかも、ジグソーパズルの間違ったピースを持っているか、十分なピースを持っていない状況のように思われる。だが [実際は] ピースは全て揃っている。ただ、全てのピースが混ざり合っているだけだ。そしてジグソーパズルの例と私たちの [他人の痛みについての] 例との間には、さらにもう一つ類似点がある。それは、ピースを嵌めるときに力は必要ないということだ。私たちがすべきことは、ピースを注意深く見て、うまく嵌まるよう配置するだけである。
[一方には、] 物質的世界(外的世界)の事実を記述すると言いうる命題が存在する。一言で言えば、そういう命題が述べる対象は、固体、液体などの物理的対象である。ここでは、特に自然科学の法則に限定するつもりはない。「庭の花が満開だ」とか「スミスはもうすぐ来るだろう」などの命題もこのタイプに含まれる。他方、個人的経験を記述する命題というものがある。例えば、心理学の実験において被験者が自分の感覚経験を述べるような場合だ。このとき被験者は、実際に自分の眼前に見えている物体とは無関係に、そしてまた注目すべきことに、網膜、神経、脳、あるいは体の他の部位で生じることが観察されるかもしれないあらゆる過程とも無関係に、自分の視覚的経験を述べる。(つまり、この視覚的経験についての命題は、物理的事実と生理的事実の両方と無関係な命題である。)
一見したところでは、異なる材料から作られた二種類の世界、心的世界と物質的世界があるように思われる。(なぜそう思われるのかは、後にならないと分からない。)心的世界は、実際にはガス状の、あるいはむしろエーテル状のものだと想像されがちである。しかしここで、ガス状のものやエーテル状のものが哲学において演じる奇妙な役割りのことを思い出してもらいたい。名詞は私たちが一般に対象の名前と呼ぶべきものではないと認識したとき、それゆえ、名詞はエーテル状の対象の名前なのだと言わざるをえないときの奇妙な役割りを。私が言いたいのは、私たちがある語の文法について困惑し、私たちに分かることはその語が物質的対象の名前ではないことだけであるとき、言い逃れとしての「エーテル状の対象」という観念を、私たちは既に知っているということである。このことは、心と物という二つの材料についての問題がいかにして解消されていくのか、ということに対するヒントになる。
時折、私たちは、物質的現象が大地で起こるのに対し、個人的経験という現象はある意味で大気の上層で起こる現象であるかのように思う。このような上層での現象が起こるのは、物質的現象がある程度複雑になったときである、という見解がある。 [この見解に従えば] 例えば、感覚経験、意志、等々の心的現象は、ある種の動物の体が特定の複雑さに進化したときに生じるのだ、となる。ここには幾分の真実があるように思われる。確かにアメーバは話さないし、書いたり議論したりもしない。だが私たちはする。だが他方、この問題はここで、次のように表現しうる問題を提起する。すなわち「機械は考えることができるか?」という問題である。(この機械の動きが、物理学の法則、あるいはもしかしたら、生物の行動に適用される何種類かの法則によって記述、予測されうるとしても、である。)この問題において表現される困難は、考えることのできる機械を私たちはまだ実際には知らない、ということではない。この問題は、100年前にのある人が訊ねた「機械は気体を液体にすることができるか?」という問題と類似してはいない。この問題の困難はむしろ、次のように言い表せる。「機械が考える(知覚する、望む)」という文は何か無意味に思われる、と。これはまるで「数5は色を持っているか?」と訊ねるようなものなのだ。(「 [もし数5が色をもっているとしたら、] それは一体何色でありうるだろうか? 明らかに、私たちが知っているどんな色でもないのだから。」)なぜなら、この問題を一面から見ると、個人的経験は、物理的、科学的、生理学的過程の産物などでは断じてなく、そのような過程について私たちが何らかの意味をもって述べること全ての基礎に他ならないからだ。個人的経験をこのように眺めると、私たちは、 [世界の] 構成材料という観念をまた別の誤解を招く方法で使いがちになる。そして「心的世界と物理的世界を合わせた世界全体はが [個人的経験という] 一つの材料から出来上がっている」と言いたくなってしまうのだ。
私たちが知っている全てのことを見て、世界は個人的経験を基礎にして出来上がっているのだ言えるとすれば、私たちが知っていることはその価値の大半や信頼性、堅固さを失うように見える。そして私たちは、私たちの知っていることは全部「主観的」だと言いたくなる。ここでの「主観的」という語は、「その意見は主観的だ」と言うときと同じで、単に好みの問題だ、という軽蔑的意味で使われている。さて、この「世界は個人的経験を基礎に成り立っている」という観点は、経験と知識の権威を揺るがすように見える。そしてこのことは、私たちの言語はあるミスリーディングな類比を描くよう、私たちを誘惑していることを示している。このことで思い出すのが、通俗科学者たちが、床が電子から成り立っていることを理由にして、「床は本当は堅くない」ことを私たちに示したように見えたケースである。
[どちらのケースでも] 私たちは、私たちの表現方法が引き起こす困難に直面しているのだ。
もう一つ別のよく似た困難は、次の文で表現される。それは「私に知ることができるのは、私が個人的経験を持っていることだけである。他人が個人的経験を持っていることは知りえない」という文だ。――それでは、他人も個人的経験を持つというのは不必要な仮説なのか?――しかしそれはそもそも仮説だろうか? というのも、 [人間が経験できる] あらゆる可能な経験を超越した仮説など、一体どうやって立てることができようか? [仮説を立てるにはまず経験が必要なのだから。] いかにしてそのような仮説は意味によって裏づけされうるだろうか?(そのような仮説は金(gold)に裏づけされない紙幣に似ているのではないか?)――こう言う人がいるかもしれない。「私たちは他人が痛みを感じているかどうか知らなくても、例えば彼に同情するときには、確かに彼が痛みを感じていることを信じているはずだ」と。だがそんなことを言われても役に立たない。確かに、他人が痛みを感じていることを信じなければ、私たちはその人に同情はしない。しかしこの信念は哲学的、形而上学的信念だろうか? [もしそうなら、哲学的信念を持つ] 実在論者(realist)の方が [哲学的信念を持たない] 観念論者(idealist)や独我論者(solipsist)よりも深く私たちに同情してくれるとでもいうのか? ――事実、独我論者は [実在論者に対して] こう訊ねるだろう。「私たちはいかにして他人が痛みを持つことを知ることができるのか? それを信じることは何を意味するのか? 他人が痛みを持つことを想定する表現はいかにして意味を持つのか?」 これに対する常識的哲学者――注意してほしいが、彼は実在論とも観念論とも無縁な常識人とは違う――の答えは、「確かに、私が持っているもの [例えば私の痛み] を他人も持っていると想定したり考えたり想像するという観念には何の困難もない」というものだ。しかし実在論者の相手をしていつも困らせられる点は、彼が、彼の論敵 [= 観念論者と独我論者] が直面している困難を解決するのではなく、飛ばしてしまっている点である(もっとも、観念論者や独我論者も解決に成功してはいないのだが)。私たちから見れば、実在論者の答えは、当の困難を [議論の外に] 除外しているだけである[16]。というのも、この手の論者は「持つ」と「想像する」という二つの語の間の用法の違いを見逃しているからである。 [例えば] 「Aは金歯を持っている」という文は、金歯がAの口内に存在するということを意味している。これは、私がAの金歯を見ることができないという事実の説明になるかもしれない。 だがここで、Aの歯痛について考えるとどうなるだろう。歯痛はAの口内にあるから、私はそれを感じることができない、と言う場合、これは金歯の場合と類比的ではない。両者には表面的な類似があるが、しかし [本当の] 類似が欠けている。そのため私たちは困難が生じる。これは、私たちの文法の厄介な特徴である。実在論者はこの特徴に気付かないのだ。他人の口内の歯痛を私が感じるということは、考えられることである。「私は他人の歯痛を感じることはできない」と主張する人でも、このことまでは否定しない [その人には感じられなくても、私には感じられるかもしれないから] 。私たちが陥っている文法的困難を明確に見て取るためには、他人の体の痛みを持つという観念 [の使用法] に慣れ親しむ以外にない。なぜなら、そうでないと、私たちは「私は彼の痛みを持つことができない」という形而上学的命題と「私たちは他人の歯に痛みを持つことはできない(通常は持たない)」という経験的命題を混同して使いがちになるだろうから。後者の[経験的]命題においては、「できない」という語は「鉄の釘はガラスに傷をつけることができない」という文の「できない」と同じ使い方をされている。(この経験的命題はまた「経験によれば、鉄の釘はガラスに傷をつけない」という形式でも書くことができよう。従って「できない」という語は除去できる。)ある人が他人の体に痛みを持つということも、考えられることであることを見て取るためには、私たちが、どのような事実をもって、ある特定の箇所に痛みがあることの基準と呼ぶのかを調べる必要がある。次のようなケースを想像するのは簡単だろう。私が自分の手を見るとき、必ずしもそれが私の体の他の部分と繋がっているかを意識してはいない。つまり、自分の手が動くのを見てはいるが、手を胴体と繋げる腕は見ていない、ということは頻繁にある。またその時、腕の存在について見る以外の方法で確認するわけでもない。それゆえ、もしかしたら私の手は [私の視界の外で] 他人の胴体に繋がっているかもしれない(それどころか、人間以外のものに繋がっていることだってもちろんありうる)。私が目を閉じて、痛みだけを根拠に、自分の左手に痛みと呼ぶべきものを感じると想定しよう。誰かが私に「右手で左手の痛い箇所を触って欲しい」と頼むとする。私はそれに従って自分が痛いと思う箇所を触り、 [目を開けて] くるっと首を捻ると、実は隣の人の手を触っている(私の左手は、隣の人の胴体に繋がっていた、という意味だ)。
ここで自問してほしい。痛い箇所を指せと言われたとき、いかにして私たちは指すべき箇所を知るのか? この種の指示は、「この紙の上の黒い点を指せ」と言われたときに黒い点を指すこと [つまり、空間内のある箇所を指すこと] と比較しうるだろうか? 誰かが君に「君がこの箇所を指したのは、君が指す前に痛みがそこにあることを知っていたからだ」と言ったと想定せよ。そして「痛みがそこにあることを知るとはどのようなことか?」と自問してほしい。「そこ」という語は場所を指示する。――しかし、それはどんな空間内にあるのか、それはどのような意味での「場所」なのか? 私たちは痛みの場所がユークリッド空間内にあると知っているのか? [だとしたら] 私たちが痛みを持つ場所を知っているなら、その痛みがこの部屋の二つの壁と床からどの程度の距離にあるかを知っていることにならないか? もし私が指先に痛みを持つときに痛い指で歯を触ったら、指の痛みに加えて歯痛も持つことにならないか? 確かにある意味では、その痛みは歯の上に位置すると言うことができる。このケースにおいて、「私は歯痛を持つ」と言うことが間違いである理由は、痛みが歯の中にあるためには、痛みが私の指先から16インチ離れていなければならない、ということなのか? 「どこ」という語は多くの異なった意味で場所を指示することができることを思い出してほしい。(「どこ」という言葉を使うことで、程度に差はあれ互いに似通った、様々な文法ゲームが行なわれる。数「1」という語の様々な使用についても考えよ。)私が物のある場所を知り、その知識によって物を指すということはあるかもしれない。その知識は私たちに指すべき場所を教える。この場合、知識は対象を意識的に指すための条件であると、私たちは考える。従って人は次のように言うことができる。「私が君の意味する場所を指すことができるのは、私がそれを見て [それがどこであるかを知った] からだ。」「私はその場所を君に指示することができる。なぜならそれがどこかを知っているからだ。まず右を向いて・・・」等々。すると人は「私がある物を指すためには、その前にその物がある場所を知っていなくてはならない」と言いたくなるだろう。きっと君は、「私がある物を見るためには、その前にその物がある場所を知っていなくてはならない」ということには、気乗りしないだろう。時には、もちろんそういうことは正しい。しかし私たちは、ある物を意識的に指したりそれに向かって歩く以前には、ある特定の心理的状態や心理的事象、つまり場所に関する知識というものが存在するのだと考える誘惑に駆られるのだ。これと似たようなケースとして、 [前に論じた] 「人は命令を理解した後でないとその命令に従えない」という事例を考えてほしい。 [「黄色い点を想像せよ」という命令に従う場合を考えれば、「人は命令を理解した後でないとその命令に従えない」と言うのは間違いであることが分かる。]
私が自分の腕の痛い箇所を指すとき、私はそこを指す前に痛い箇所を知っていたと、どのような意味で言うことができるだろう? 痛い箇所を指す前に、私は「痛みは私の左腕にある」と言うことができただろう。私の腕の表面のどの箇所でも [(4,7)のように座標で] 指示できるよう、番号の振られた線を持つ網で腕が覆われていたと想定しよう。すると、痛い箇所を指す前に、そこを座標によって記述できなければならない、ということが必要だったろうか? [そんなことはない。] 私が言いたいのは、指すというその行為が痛みの場所を決定するということである。ついでだが、この指すという行為を、指すことによって痛い箇所を発見する行為と混同してはならない。事実、この二つの行為は異なる結果をもたらすこともありうるのだ。
ある人が他人の体に痛みを持つという事例のバリエーションは数限りなく考えることができる。例えば、家具とか空っぽの空間に痛みを持つなど。もちろん、私たちの体の特定の部位、例えば上の歯にある痛みは、特有の触覚や筋感覚を伴うことを忘れてはならない。手を少しの距離だけ上に上げれば目に触る。このとき「少しの距離」という語が示すのは、触覚的距離か筋感覚的距離、またはその両方である。(触覚的距離と筋感覚的距離が、普通ではない仕方で相関している場合を想像することは簡単だ。 [例えば] 私たちの口から目までの距離は、指を口から目まで動かすときは、「腕の筋肉にとっては」非常に大きいと思われるかもしれない。歯医者が歯にドリルで穴を開けて中を調べるときの穴を、君がどれほど大きく想像するか、考えてほしい。)
さっき私が「手を少し上に動かせば、その手は目に触る」と言ったとき、私は触覚的証拠のみに言及した。つまり、私の指が眼を触ったかどうかの基準は、ただ、私に「私は私の目に触っている」と言わせる特定の感覚を持っているということのみであった。たとえ私が何ら視覚的証拠を持っていなくても、鏡をのぞいたら実は目ではなく額に触っていたとしても、である。私がさっき言った「少しの距離」という語が、触覚的距離または筋感覚的距離でもあったように、「それら [口と目] は少しの距離はなれている」というときの場所もまた、 [指の感覚を基準に判断する限り] 触覚的場所であった。触覚的空間または筋感覚的空間の中で私の指が口から目に移動すると言うことが意味するのは、私たちが普通「私の指が口から目に動く」と言うときに持つ触覚的・筋感覚的経験を私が持つ、ということである。しかし、私たちが「私の指が口から目に動く」という命題の証拠と見なすものは、周知のように、決して触覚的・筋感覚的なものに限らない。実際は、先述のような触覚的・筋感覚的感覚を私が持ったとしても、私はまだ、私が見たものを理由にして、「私の指が口から目に動く」という命題を否定するかもしれない。 [私は指を口から目に動かしたつもりでも、私の眼にはそう見えないことだってありうるのだ。] この命題は、物理的対象についての命題である。(ただし、「物理的対象」という語で、何か他の種類の対象 [例えば心的対象] から区別しようとしているわけではないので注意してほしい。)つまり、私たちが物理的対象についての命題と呼ぶ命題の文法は、その種の命題には様々な証拠がありえることを許すということである。「私の指が動く」等の命題の文法の特徴は、この命題の証拠として、「私は指が動くのを見る」、「私は指が動くのを感じる」、「彼は私の指が動くのを見る」、「彼が私の指が動くと言う」などなどの命題が認められる、ということである。さて、もし私が「私は私の手が動くのを見る」と言うとすると、一見このことは、私が「私の手が動く」という命題に同意していることを前提としているように思われる。だが、もし私が「私は私の手が動くのを見る」という命題を「私の手が動く」という命題の証拠の一つとしてみなすなら、当然、「私の手が動く」という命題の真理性は、「私は私の手が動くのを見る」という命題の真理性を前提としない。 [だから、「私は私の手が動くのを見る」という命題が偽であっても、「私の手が動く」という命題が真であることはありうる。] 従って人は、「私は私の手が動くのを見る」という表現の代わりに「あたかも私の手が動いているように見える」という表現を提案するかもしれない。だが、この表現は確かに、本当の手の動きがなくても手が動いて見えることはありうるということを指示するが、やはり結局のところ、手が動いて見えるには手が存在しなくてはならないということも示唆している。だが、視覚的証拠を記述する命題が真であり、同時に、残りの証拠に拠れば、私は手をもっていないことになる、という場合は容易に想像できる。私たちの普通の表現方法では、この点が曖昧になっている。日常言語では、私たちの言いたいことが目や指などの存在を論理的に導かないときでも、触覚的感覚を物理的対象(「目」、「指」など)を表す語によって記述せねばならない。そのため、私たちは不利な立場に立たされている。感覚について記述するとき、私たちは回りくどい記述を使わなければならないのだ。もちろん、このことは、日常言語が私たちの特殊な目的のために不十分であるという意味ではない。ただ、少し厄介でミスリーディングなだけだ。私たちの[日常]言語にこのような特異性がある理由は、もちろん、特定の感覚的経験が規則的に同時に起こる、ということにある。私が私の腕が動くのを感じるとき、大抵の場合、腕が動くのを見ることもできる。また、私が私の腕でもう一方の腕に触れば、その触った腕は触られた腕の動きを感じる。(足を切断された人は、特定の痛みを、彼の [切断された方の] 足の痛みとして記述するだろう。)このような場合、私たちは [「指が頬から目に移動する」という物理的事実を記述するために] 「触覚的頬から触覚的目まで感覚が移動する」という表現が必要だと強く感じるのだ。私がこのようなことを述べてきた理由は、もし君が痛みの触覚的・筋感覚的環境に気付けば、自分の歯の中以外のいかなる場所にも歯痛を持ちうるのだと想像することに、困難を感じると思ったからだ。しかし、私たちが自分の歯の中以外に歯痛を持つ場合を想像するなら、それが意味するのは単に、視覚的・触覚的・筋感覚的などの諸経験の間に、通常の相関とは異なる相関を想像することでしかない。従って私たちは、歯痛を持つと同時に、普通は手が歯から鼻や眼などへ移動することに結びついているが、今の例では、他人の鼻や眼などへ移動することに結びついている触覚的・筋感覚的経験を持つ人物を想像することができる。あるいはまたこういう人物も想像できる。つまり、その人は、手が動く筋感覚を持つと同時に、指と顔には指が顔の上をなぞる触覚を持ち、さらに、筋感覚と視覚は指が膝の上をなぞる感覚として記述されるべきものとして感じるのだ[17]。もし私たちが、歯痛に加えて、普通は痛い歯とその周りを触るときに特徴的な感覚をを持つとしたら、さらに、もしその感覚に私の手がテーブルの縁に触って動き回るのを見るということが伴ったとしたら、この経験をテーブルに歯痛を持つ経験と呼んでよいかどうか迷うに違いない。逆に、今述べた触覚と筋感覚が、私の手が他人の歯と歯の周りに触るのを見るという視覚的経験と結びついたなら、私はその経験を「他人の歯の中に [私の] 歯痛を持つ」経験と呼ぶことに疑問は持たないだろうに。
私は先ほどこう言った、他人の痛みを持つなど不可能だと頑固に主張する人でも、だからといって、ある人が他人の体に [自分の] 痛みを持つことができるということまで否定しようとはすまい、と。実際、この人物はこうも言うだろう。「私が他人の歯に自分の痛みを持つことはあるかもしれないが、その歯痛は彼の歯痛ではない」と。
従って「Aは金歯を持っている」という命題と「Aは痛みを持っている」という命題は類比的に用いられてはいない。一見したところでは違いがないように見えるが、実はその文法において両者は異なっているのである。
「想像する」という語の使用について、「他人が痛みを持つことを想像するという確定的行為が存在することは確実だ」と言う人がいるかもしれない。もちろん、私たちもそのことは否定しないし、 [それ以外であっても] 事実についての言明であれば何だって否定はしない。だが考えてみよう。私たちが他人の痛みについて像を持つとき、他人が持つ黒い瞳 [つまり物理的対象] について像を持つときと同じ方法でその像を用いるだろうか? ここで再び、普通の意味での想像するという行為を、絵を描くという行為によって置き換えてみよう。(絵を描くということは、ある種の人にとってはまさに想像するという行為のやり方でありうる。)さて、このようにして「Aが黒い瞳を持っている」ことを想像してみよう。この像の非常に重要な使い方は、像が正しいかどうかを判断するために本物の黒い瞳と比較することであろう。誰かが痛みに苦しんでいる様をありありと想像するとき、その像に痛みの影――それは、彼が痛みを持つと私たちが言う場所に対応する――と呼ばれるものが頻繁に入り込んでくる。しかし、ある像がどのような意味で像であるかを決定する方法は、その像を現実と比較することである。この方法を、投影の方法と呼んでもいいだろう。ではAの歯痛についての像を実際のAの歯痛と比較することを考えよう。どのようにしてこの二つを比較するのか? もし君が [直接比較するのは無理だから] 彼の体の振る舞いによって「間接的」に比較しよう、と言うのなら、私の答えは、その比較方法では、彼の振る舞いについての像を彼の振る舞いと比較しているのだから、歯痛の像と歯痛を比較したことにはならない、というものだ。
または君が「私は、君がAの痛みを知ることができない、君はただ推測することができるだけだ、という点には同意しよう」と言うならば、君は「推測する」という語と「知る」という語の異なる使用の間に横たわる困難を見ていないのだ。君が「知ることはできない」と言ったとき、どのような種類の不可能性について言及していたのか、君は分かっているだろうか? ある人が金歯を持っているかどうか分からないのは、彼が口を閉じているからだ、というケースと類比的な意味での不可能性を考えていたのではないか? この金歯の場合、君が知らなかったかもしれないが、それでも知ることを想像することはできたのだ。つまり、 [実際には] 金歯を見なかったが、「金歯を見た」ということは [偽な命題ではあるが] 有意義である。あるいはむしろ、君が彼の歯を見ないということは有意義なのだから、[その否定である] 彼の歯を見るということも有意味なのだ、といった方がいい。反対に、人は他人が痛みを持つかどうかを知ることはできない、ということに賛成してもらえるなら、君は、事実として、人々が [他人が痛みを持つかどうかを] 知らないと言いたいのではなく、彼らがそのことを知っていると言うことは意味をなさない(従ってまた、知らないと言うことも意味をなさない)、と言いたいのだ。従ってこの場合、もし君が [「知る」という語の代わりに] 「推測する」とか「信じる」という語を使うのなら、君はこれらの語を「知る」の反意語として使っているのではない。すなわち、君が言っていることは、 [他人が痛みを持つかどうかを] 知るというのは到達できないゴールであり、推測することで満足しなければならない、ということではない。むしろ、このゲームにゴールはないのである。ちょうど誰かが「人は自然数を数え尽くすことはできない」と言うとき、それは人間の能力の無さについての事実を述べているわけではなく、私たちが作った規約(convention)について述べているのと同じように。「人は他人が痛みを持つかどうかを知ることはできない」という言明は、「人は大西洋を泳いで渡ることはできない」のような [人間の能力の限界による不可能性を述べる] 言明と比較可能ではない。それなのに、いつも間違って比較されてしまう。実際は、「耐久レースにゴールはない」のような言明と類比的なのである。そしてこのことが、「君は・・・を知ることはできないが、・・・を推測することはできる」という説明に満足しない人が、漠然と感じていることなのだ。
私たちは、寒い日に熱があるにも関わらず外出しようとする人間に向かって、怒ってこう言うことがある。「風邪ひくのは僕じゃないんだからな。そんなに風邪ひきたければ勝手にしろ!」この言葉が意味しうるのは、「君が風邪をひいても、それで僕が苦しむわけではない」ということである。これは経験によって [その意味を] 学ぶ命題である。なぜなら、いわば無線で結ばれた二人の人間がいて、片方が冷気に頭を晒すともう一人が頭に痛みを持つという事態も [現実には起こりえないが] 想像することができるから。この場合、痛みを感じた方の人間は、その痛みは私の痛みである、なぜならそれは私の頭で感じられるから、と主張するかもしれない。だがここで、私と誰かが体の一部、例えば手を、共有していると想定してみよう。手術によって、私の腕の神経と腱が、Aのそれらと結び付けられたとする。さて、その手が蜂に刺されたと想像してほしい。私たちは二人ともきゃっと叫び、顔を歪めて、痛みについて同じ記述をしたりするだろう。さて、私たちは同じ痛みを持ったのか、それとも違う痛みを持ったのか、どちらだろう? このような場合に、君が「二人は同じ体の同じ箇所に痛みを感じ、その記述も一致するが、それでも、私の痛みは彼の痛みではない」と言うならば、私が思うに、その理由として君は、「私の痛みは私の痛みで、彼の痛みは彼の痛みだからだ」と言いたいであろう。そしてここで君は、「同じ痛み」のような句の使用についての文法的言明を行なっているのである。 [その場合、] 君は「彼は私の痛みを持った」とか「私たち二人は同じ痛みを持った」という句が適切だとは思うまい。代わりに、「彼の痛みは私の痛みと極めてよく似ている」という句を使うのがよいと考えるだろう。(異なる二人が同じ痛みを持つことはできない、という点に異論はないだろう。なぜなら、片方の人間に麻酔をかけたり、あるいは殺しても、もう一方の人間は痛みを持つこともあるからだ。)もし私たちが「私は彼の痛みを持つ(あるいは感じる)」という句を私たちの言語から排除したとすれば、当然、それによって、「私は私の歯痛を持つ(感じる)」という句もまた、排除することになる。すると、私たちの形而上学的言明 [私は彼の痛みを持つことができない] の別の[表現]形式はこうである。「人の感覚与件はその人にとって私的なものである。 [それゆえ、他人はそれを感じることも知ることもできない。] 」だがこの表現方法はより一層ミスリーディングである。なぜなら、これはますます経験的命題のように見えるからである。「人の感覚与件はその人にとって私的なものである」と言う哲学者は、自分が一種の科学的真実を表現していると考えがちになる。
私たちは「二つの本は同じ色を持っている」という句を使うが、しかし、「二つの本は同じ色を持つことはできない。なぜなら、結局のところ、この本は自分独自の色を持ち、あの本も自分独自の色を持っているからだ」と言うことも、全く問題なくできるだろう。これもまた、文法的規則――たまたま、私たちの日常的な用法とは一致しない規則であるが――を述べた文と言えるだろう。そもそも、なぜ人が異なる二つの用法を考えねばならないか、という理由は、私たちが感覚与件の場合と物理的対象の場合と比較するからである。物理的対象の場合、私たちは「この椅子は一時間前に見た椅子と同じ椅子だ」と言うことと「この椅子は一時間前に見た椅子と同じ椅子ではないが、とても良く似た椅子だ」と言うことを区別する。 [同様に、] 物理的対象の場合、「AとBは同じ椅子を見ることはできなかったはずだ。なぜなら、Aはロンドンにいて、Bはケンブリッジにいたから。彼らは瓜二つだが異なる椅子を見たのだ」という経験的命題は有意味になる。(ここで、「対象の同一性」と呼ばれることの基準として、色々と異なるものを考えてみるのは有用であろう。「これは・・・と同じ日だ」、「これは・・・と同じ語だ」、「これは・・・と同じ場合だ」のような言明を、私たちはどのように使うだろうか?)
これまでの議論で私たちがしたことは、普段私たちが形而上学的命題の中で「できる(can)」という語に出くわしたときにすることと同じである。 [つまり] 形而上学的命題は文法的規則を隠蔽する、ということを示したのである。すなわち、形而上学的命題と経験的命題の見かけの類似性をはぎとり、形而上学者が持つ欲求――それは、私たちの日常言語では満たされず、それが満たされない限り形而上学的問題が生み出される――を満たす表現形式を見つけ出そうとしたのだ。繰り返すが、形而上学的な意味で私が「私が痛みを持つときは常に私はそのことを知らなければならない」と言うとき、この言明はただ、「知る」という語を冗長にしただけだ。だから、「私は痛みを持っていることを知っている」と言う代わりに、単純に「私は痛みを持つ」と言えばいい。ただし、 [たとえば] 「無意識的痛み」という句に、痛みを持っているがそのことを知らないという経験的基準を割り当てることで意味を与え、かつ、私たちが(正しいにせよ間違っているにせよ)事実として、本人が知らないような痛みを持ったことがある人は未だ一人もいない、と言うならば、もちろん事情は異なる。
私たちが「私は彼の痛みを感じることはできない」と言うとき、 [彼の痛みを知るには] 超えられない壁 [=物理的不可能性] があるのではないか、という考えが自然に思い浮かぶ。そこで、 [これが本当に超えられない壁なのかどうか確かめるために] すぐに類似のケースを考えてみよう。それは「同一の場所が同時に緑であり、かつ青であることはできない」という場合だ。この場合も、物理的不可能性の像が浮かんでくる。ただしここではその像は壁の形ではなく、むしろ「二つの色は互いに排除しあう」というように、私たちは感じる。この物理的不可能性の起源はなんだろうか?――私たちは、このベンチに3人が並んで座ることはできない、ベンチにはそのスペースはないから、と言う。色のケースは、このベンチのケースと類比的ではない。むしろ「3×18インチは、3フィート以内には収まらない」と言うケースと類比的である[18]。この長さについての文は、文法的規則であり、論理的不可能性を述べる文である。 [これに対し] 「3フィートのベンチに3人が並んで座ることはできない」という文は物理的不可能性を述べている。この例は、なぜ私たちが二つの不可能性を混同するかの理由を明瞭に示している。(「彼は私より6インチ高い」という命題を「6フィートは5.5フィートより6インチ長い」という命題を比較してほしい。この二つは全く別種の命題だが、実によく似た外観をしている。 [前者は物理的事実を述べる経験的命題であり、後者は文法的規則を述べる論理的命題である。] )こうした色や他人の痛みといった事例において、物理的不可能性が私たちの頭に浮かんでくる理由は、一方では、特定の表現形式を使わないよう心に誓いながら、他方では、その表現形式を使うよう強く誘惑されるからである。なぜそのような表現形式に誘惑されるのか、その理由は以下の2つである。
- その表現形式は英語やドイツ語として全く問題ないから
- 私たちの言語の [哲学以外の] 他の分野でよく似た表現形式が使われるから
論理的不可能性と物理的不可能性の間で揺れ動くとき、私たちは「もし私が常に私の痛みだけを感じるならば、他人も痛みを持っているという想定は何を意味するのか?」という言明を行なう。そういう場合、私たちがするべきことは、いつでも、それらの語が私たちの言語において実際にどのように用いられているのかを見ることである。 [なぜなら] そういう場合、私たちは、それらの語が日常言語において使われるのとは異なる使用を考えている [からだ] 。その使用は、まさにそうした場合において、 [私たちがその使用を選ぶというより] 逆に、私たちに自分を使うよう強く働きかけてくる。私たちの語の文法について何か奇妙なものを感じたとしたら、その理由は、その語を異なる複数の方法で使う誘惑に交互に駆られるからである。だから、形而上学者の言明が経験的事実を述べるためにも使うことができる場合は、それが実は語の文法に対する不満を表現するものだということを発見するのはとりわけ困難である。それゆえ、形而上学者が「私の痛みだけが本当の痛みだ」と言う場合、この文は「他人は痛い振りをしているだけだ」という [経験的命題] を意味することもあるかもしれない。あるいはまた、形而上学者が「この木は誰からも見られていないときは存在しない」と言うとき、それは「この木は私たちが背を向けると消滅する」という [経験的命題] を意味することもありうるのだ。 [しかし実際には、] 「私の痛みだけが本物だ」と言う人が意味するのは、他人が痛みを持つというのは全て嘘だということを、公共的な基準――すなわち、私たちの言葉に公共的な意味を与える基準――によって発見した、ということではない。そうではなく、そうした公共的基準との連関においてこの [「私の痛みだけが本物だ」という] 表現を使うことに対して、彼は反発している。すなわち、彼は、この語が普通使われる仕方で使われることに反対しているのだ。しかし一方で、彼は [実は] 自分がある規約に反対していることに気付いていない。彼は、通常の地図における国の分割方法とは違う分割方法を見ている。彼は、いわば「デボンシャー」 [=イギリス南西部の地名] という名前を、慣習的に設定されている境界の郡ではなく、違う境界を持つ地域のために使う誘惑を感じているのだ。この誘惑は、「ここに境界を引いてこれを一つの郡にするなんて馬鹿げた話だ」という表現で表すことができる。しかし彼は [そうは言わずに] 「本当のデボンシャーはこうだ」という言い方をする。私たちは彼にこう答えることができるだろう。「君が欲しているのは、単に新しい表記法にすぎない。そして、この新表記法によって地理上の事実は何も変わるわけではない」と。しかしながら、ある表記法に抵抗しがたい魅力を感じたり、逆に不快感を感じたりするのも、また事実である。(私たちは容易に忘れてしまうが、ある表記法や表現形式は、非常に多くのことを意味しているのである。そして [日常言語における] 表記法を変えることは、数学や科学における表記法を変えることに比べて、必ずしも簡単ではない。洋服や名前を変えることは、ほとんど意味を持たない場合もあれば、多大な意味を持つ場合もあるのだ。)
私がやろうとしているのは、実在論者、観念論者、私、そして独我論者によって論じられた問題を、その問題と密接に関連するある問題を示すことによって明瞭にすることである。そのある問題とは、「私たちは、無意識的思考や無意識的感覚などを持つことはできるか?」というものだ。無意識的思考があるという考えは、多くの人々を不快にさせる。 [だが一方で] 意識的思考のみが存在すると考えるのは間違いで、精神分析は無意識的思考を発見したのだと言う人々もいた。無意識的思考 [の存在] に反対する人々は、彼らが反対しているのは、新しく発見された心理学反応ではなく、それが記述される仕方に対してであることに気付いていなかった。反対に、精神分析家は、彼ら自身の表現方法に誤誘導されて、自分たちは新しい心理的反応を発見する以上のことをしたのだと考えるようになってしまった。つまり、ある意味で、無意識であった意識的思考を発見したのだと [勘違いして] 考えてしまったのだ。無意識的思考への反対者たちは、「私たちは『無意識的思考』という句を使いたくない。『思考』という語は精神分析家が『意識的思考』と呼ぶもののためにとっておきたい」と言って反論を述べることができただろう。 [しかし] 彼らが「あるのは意識的思考だけであって、無意識的思考などない」と言うとき、彼らは自らの主張を誤って述べているのだ。なぜなら、もし彼らが「無意識的思考」について話したくないと言うのなら、また「意識的思考」という句も使ってはならないからである。
だがいずれにせよ、意識的思考と無意識的思考の両方について話す人は、「思考」という語を異なる二通りの使い方をしている、と言うことは正しくないだろうか? ―― [別の例を出そう。] ハンマーで釘を [板に] 打つときと、穴に杭を打つときとでは、ハンマーを異なる二通りの方法で使っているのではないか?[19] また、杭をこの穴に打つときと、別の穴に打つときとでは、私たちはハンマーを二通りの方法で使っているのか、同一の方法で使っているのか、どちらだろう? あるいは、何かを何かに打ち付ける場合と、何かを粉々に砕く場合だけ、私たちはハンマーを異なる使い方をした、と言うべきだろうか? それともこれら全ての場合において、ハンマーは同一の使われ方をしたのか、そして、ハンマーをペーパーウェイトとして用いるときだけ、その使い方は区別されるべきなのだろうか? ――私たちはどういう場合に、ある語が二通りの使い方をされ、どういう場合に同一の使い方をされると言うのか? ある語が二つ(またはそれ以上の)複数の仕方で使われると言ったとしても、それだけでは、その語の使用についていかなる考えも私たちに与えはしない。ただ、その語の用法に対する見方を、その語の使用を記述するための、二つの(またはそれ以上の)下位区分を持つ枠組みを提供することによって、明確にするだけである。「私はこのハンマーで二つのことをする。一つはこの板に釘を打ち付けること、もう一つはあの板に釘を打ち付けることだ」と言うことは全く問題ない。しかしまた次のように言うこともできたのだ。「私はこのハンマーで [打ち付けるという] ただ一つのことをする。つまり、この板に釘を打ち付け、あの板に釘を打ち付ける」と。ある語が一通りの仕方で使われるか二通りの仕方で使われるか、ということについては、二通りの議論がありうる。
- 「cleave」という英単語が、物を割るという意味でのみ使われるのか、物をくっつけるという意味でも使われるのか、ということについて二人の人間が議論することがあるだろう。これは特定の実際の用法の事実についての議論である。
- 「altus」という「深い」という意味でも「高い」という意味でも使われる英単語があったとして、それゆえ、この語は二通りの異なる使われ方をするのか、ということについて二人が議論することがあるだろう。
さて、独我論者が「私の経験のみが本当である」と言うとき、彼に向かって「もし君が、私たちが君の言葉を本当は聞いていないと信じているのなら、なぜ私たちに話し掛けるのだい?」と答えても無駄である。あるいは、ともかく私たちが独我論者にこの答えを返してしまえば、私たちは彼の困難に答えたのだ、と信じてはならない。哲学的問題に常識的回答はないのである。哲学者の攻撃から常識を守ろうとするなら、彼らの困惑を解決してやるしかない。すなわち、常識を攻撃したくなる誘惑から解放してやるしかない。常識的見解を繰り返し述べても無駄である。哲学者は話の分からない人間ではないし、皆が見るものを見ない人間でもない。しかしまた、彼が常識と一致しないのは、科学者が素人の粗雑な見解と一致しないのと同じ意味での不一致ではない。すなわち、彼の常識に対する不一致は、もっと微妙な事実についての知識に基づいているのではない。従って、私たちは彼の困惑の源を [ほかに] 捜し求めなくてはならない。すると私たちが見出すことは、困惑と心理的不満が生じるのは、何も、ある事実についての私たちの好奇心が満たされないときや、私たちのあらゆる経験に合致する自然法則が見つからない場合だけでなく、ある表記法に――多分、その表記法が様々な連想を呼び起こすからだろう――私たちが満足できないときも含まれる、ということだ。日常言語とは、あらゆる可能な表記法のうち、私たちの生活に広く浸透している一つの表記法であり、いわば私たちの心を一箇所に固くつなぎとめている。しかし、時として、私たちの心はこの場所に縛られている(cramped)と感じ、別の場所へ移りたいという願望を持つのだ。従って、私たちは時に、ある差異を日常言語の表記法よりも強く強調するような表記法や、あるいは [逆に] 特定のケースにおいては日常言語よりもずっと類似性の強い表現形式を使う表記法を望むのだ。私たちの心理的拘束感が和らぐのは、これらの欲求を満たす表記法を見せられたときである。 [だが] こうした欲求は実に多岐にわたる。
さて、私たちが独我論者と呼び、自分の経験だけが本物であると言う人物は、だからといって、実際的な事実の問題について私たちと一致しないわけではない。私たちが痛みを訴えるときは、彼は「君たちは [痛い] 振りをしているだけだ」とは言わずに、他の人と同じくらい同情してくれる。ただし、それと同時に彼は、「本当の」という語の使用を、私たちが彼の経験と呼ぶべき経験に限定したいと考えているのだ。そして多分、彼は私たちの経験を「経験」と呼ぼうとは全く思わないのだ(繰り返すが、彼はいかなる事実の問題についても私たちと一致しないわけではない)。なぜなら、彼は、自分以外の人物の経験が本当であるなど考えられないと言うだろうから。従って彼が使うべき表記法では、「Aは本当の歯痛を持っている(Aは彼ではないとする)」という句は無意味であり、ちょうどチェスの規則では、ポーンがナイトの動きをすることが禁じられるように、この句が禁じられる。独我論者の勧めによれば、「スミス(独我論者)は歯痛を持っている」という句の代わりに [スミスの歯痛だけが本当の経験なのだから、] 「本当の歯痛がある」という句を使うべきだということになる。この表記法を許してはならない理由が私たちにあるだろうか? [ない! 認めてよいのだ。] 言うまでもなく、混乱を避けるために、彼はこの場合、「本当の」という語を「振りをする」に対立する語としては使わない方がいい。このことはまさに、「本当の」/「振りをする」の区別を別の仕方でつけなくてはならないということを意味している。 [なぜなら、独我論者といえど、とにかく「本当の」と「振りをする」という語の区別はしなくてはならないからだ。] 「私だけが本当の痛みを感じる」とか「私だけが見る(聞く)」と言う独我論者は、ある意見を述べているのではない。そのことが、彼が自分の言うことを深く確信している理由である。彼はある特定の表現形式を使うよう抗しがたい誘惑を感じている。だが、なぜ彼がそのような誘惑を感じるのか、その理由はなお見つけなければならない。
「私だけが本当に見る」という句は、「他人がある物を見ているとき、彼が実際に何を見ているかを、私たちは決してしらない」とか「他人が『青』と呼ぶ色が私たちが『青』と呼ぶ色と本当に同じ色かどうかを、私たちは決して知ることができない」という表明によって表現される考えと密接に結びついている。事実、私たちは「彼が何を見ているか、あるいはそもそも彼は [本当に] 見ているのか、私は全く知りえない。なぜなら、私が手にしているのは、彼が私に与える様々な種類の信号(sign)だけであり、従って、彼が何かを見ているというのは、全く不必要な仮説である。私にとって、見るということは、私自身が見ることからしか知ることができない。私は『見る』という語を、私がすることを意味するよう習ったのである」と論じるかもしれない。しかしもちろん、これは正しくない。なぜなら、ここで述べたよりもずっと複雑な「見る」という語の使用を私が習ったことは明らかであるから。私がこのように述べたときに私をそうさせるよう導いた傾向について、少し異なる領域からの例を引いて明らかにしてみよう。「実際には紙が赤くないときに、紙が赤いと望むことはどのようにして可能か」という議論を考えてほしい。これは、そもそも存在しないものを無い物ねだりしているということではないのか? すると、私の願望が含むことができるのは、 [紙が赤いということではなく] 紙が赤いということに似た何かでしかない。従って、 [現実には赤くない] 何かが赤いと望むときは、「赤」という語の代わりに別の語を使うべきではないか? [なぜなら] 願望の心像(imagery)が私たちに示すのは、確かに、紙が赤いという現実よりも不確定で、なにかもやもやしたものだからである。従って私は、「私は紙が赤いことを願う」と言う代わりに、「私はこの紙に薄い(pale)赤を願う」と言うべきである。しかし、もし普通の会話の中で「私はこの紙に薄い赤を望む」と言った人がいたら、彼の願望に答えるために私たちは紙を薄い赤色に塗るべきであったろう――だがこれは彼が望んだことではなかった。逆に、彼が提案するこの表現形式を採用することには、彼が「私はこの紙に薄いxを望む」という句を、常に私たちが通常「私はこの紙にx色を望む」と言って表現することを意味すると分かっている限りにおいて、異論はない。彼が言ったことは、実は、ある表記法が [どんな表記法であれ] 推奨されてよいという意味で、彼の表記法の推奨だったのだ。だから、彼は私たちに新しい真実を述べたわけでも、私たちがそれまで言っていたことが間違いだったことを示したわけでもない。(以上のこと全ては、私たちが今抱えている問題を否定の問題と結びつける。) [以上の論点について] 君にヒントだけあげよう。大雑把に言って、ある性質が必ず二つの名前を持つような表記法を考えることができる。一つは物がその性質を持つと言われるときの性質の名前、二つ目は、物がその性質を持たないと言われるときの性質の名前である。 [例えば] 「この紙はアカイ(red)」の否定 [=「この紙はアカくない」] を、「この紙はアガイ(rode)」と言うことができるだろう。実際、こういう表記法は、私たちの日常言語からは否定される願望と、時には否定の概念に関する哲学的困惑の痙攣を引き起こす願望のうち、幾つかを満たすのだ。
「彼が(正直に)青い斑点を見ていると言うとき、私は彼が何を見ているか知ることができない」と言うことで表現される困難の起源は、次のような考えにある。その考えとは、「彼が何を見ているか知る」ということは「彼が見ているものを [私も] 見る」ということを意味しているが、しかしそれは、私と彼の眼前に同じ対象があるときに二人でその対象を見る、という意味ではない。その対象は、いわば、彼の頭の中に、あるいは彼の中にある、という意味である。この考えは、同じ対象が私と彼の眼前にあるが、しかし、「彼の視野における本当の直接的対象が私の視野にある本当の直接的対象になるように」私の頭を彼の頭に(私の心を彼の心に、でも同じことだが)差し込むことはできない、というものだ。 [しかし] 「私は彼が何を見ているか知らない」と言うことで私たちが実際に意味していることは、「彼が何に眼を向けているか知らない」ということである。この場合、彼が眼を向けている物は [彼の心の中に] 隠されており、彼はそれを私たちに見せることができない。それは彼の心の眼の前に [だけ] あるのだ。従って、この困惑を取り除くためには、「私は彼が何を見ているか知らない」という言明と「私は彼が何に眼を向けているか知らない」という言明の間の文法的差異を、二つの言明が[日常]言語において実際に使用されている有り様に沿って、調べてなくてはならない。
私たちの抱えている独我論を実に上手に満足させる表現は「何が見られるにせよ(本当に見られているとする)、その時見ているのは常に私である」だと思われる場合がある。
この表現について印象的なのは、「常に私が」という句である。いったい常に誰だというのか? ――なぜこんな疑問を提起するかというと、奇妙にも、私はこの表現で「常にL.W.が」を意味してしないからだ。このことは、人格の同一性の基準について私たちに考えさせる。私たちが「この人は私が一時間前に会ったのと同じ人だ」と言うのはいかなる状況下においてだろう?「同じ人」という句と人の名前の実際の使用は、私たちが [人格の] 同一性の基準として使う多くの特徴群が、大多数の場合において一致するという事実に基づいている。普通、私は身体的外見によって [他の人から] 認識される。私の身体的外見の変化は、非常にゆっくりとした、比較的幅の小さいものだ。声や癖なども同じようにゆっくりと狭い範囲内でのみ変化する。私たちに人名を普通使うように使う傾向があるのは、こうした事実のおかげにすぎない。このことは、現実ではない事例を想像してみると良く分かる。なぜなら、そのような事例は、事実が今ある現実と異なる場合、いかに異なる「幾何学」を私たちが使おうとするかを示してくれるからだ。例えば、人間の体がみな同じように見え、 [身体的ではない] 異なる特徴群が、いわばその住みつく体を他の体と区別させるような事例を考えてみよう。そうした特徴群は、例えば、甲高い声とのろまな動きを持った穏和さだったり、深い声と性急な動きを持つ短気な気質だったりする。このような状況下では、それぞれの体に名前を付けることは、可能ではあるが、しかし、食堂の [どれもこれも同じ外見をした] 椅子に一つ一つ名前を付けるのと同じくらい、およそやろうと思わないことになるだろう。反対に、 [身体的ではない] 特徴群に一つ一つ名前を付けることは有用であり、この名前を使うことと、私たちの現在の言語において人名を使うことが、大体対応するとみなせるだろう。
あるいは、人の形や大きさ、振る舞いの特徴が定期的にガラリと変わる人がいるという仕方で、二つの性格を持つ人間 [がいる社会] を想像してほしい。 [その社会では、] 人が二つの状態を持つことは普通であり、突然一つの状態からもう一つの状態へ移るのだ。そのような社会では、あらゆる人に二つの名前を付け、一つの体の中にいる二人の人について語ろうとするに違いない。さて、ジキル博士とハイド氏は、二人の人だろうか、それとも単に変化するだけの一人の人だろうか? どちらでも好きな言い方をしてよい。別に二重人格について語るよう強制されているわけではないのだから [二人の人だと答える義務はない] 。
「人格」という語には、私たちが採用してもよいと思う多くの使用が――どれも程度に差はあれ似通ったものだが――ある。同じことが、ある人物の記憶を頼りに人格の同一性を定義する際にも当てはまる。以下のような人物を想像してみよう。この人は、人生の偶数日には、 [過去の] 偶数日に起きたことは全て覚えているが、奇数日に起きたことはすっぽり忘れてしまう。反対に、奇数日には過去の奇数日の記憶はあるが、偶数日の記憶が抜け落ちてしまう。しかも、彼には不連続の感覚はないとする。私たちが望むなら、彼は偶数日と奇数日で外見と性格を変えるのだと想定することもできる。この場合、一つの体に二人の人が住んでいると言うしかないのだろうか? 言い換えれば、一つの体に二人の人が住んでいると言うことが正しく、そうではないと言うことは間違っているのだろうか? どちらでもない。なぜなら、「人」という語の日常的な使用は、いわば、日常的な諸状況に適用できる合成的使用(composite use)とでも言うべきものだからだ。 [だから] 今やったように、その諸状況が変化したと想定すれば、「人」とか「人格」という語の適用も、状況の変化に合わせて変わるのだ[20]。そして、私がこの語を保存し、今までの使用と類比した使用をこの語に与えたいと思うなら、私は多くの使用、すなわち、多くの異なる種類の類比を、自由に選択できることになる。そのような場合、「人格」という語に一つの正当な使用があるのではない、と言うことができるだろう。(こういう考えは、数学の哲学において重要である。「証明」、「式」などの語の使用について考えてほしい。また、なぜ私たちがここで行なっていることが「哲学」と呼ばれるべきなのか、なぜ私たちがここで行なっていることが、過去の時代に哲学という名で呼ばれていた様々に異なる諸活動の唯一正当な相続人とみなされねばならないのか、考えてほしい。)
さて、私たちが「何であれ、それが見られるとき、それを見ているのは常に私だ」と言うとき、一体私たちはどのような種類の人格の同一性について言及しているのか、自問してみよう。私が [何かを] 見るというこれらの事例全てに共有していてほしいと思うことは何だろうか? この問いに対する答えとして、それは肉体的外見ではない、ということを告白せねばならない。 [なぜなら] 私が見るとき、私は常に体の一部を見ているわけではないからだ。さらに、私の体は、私が見る物の中に含まれていたとしても、それが常に同じように見えねばならないということは、本質的なことではない。事実、私は自分の体がどんなに変わって見えたとしても気にしない。そしてそれは私の体の全ての属性や振る舞いの特徴、そして記憶までにも言えることだ。――もう少し時間をかけて考えてみれば、私が言いたかったことは、「何であれ、何かが見られているとき、何かが見られている」とういことだったことが分かる。すなわち、私が、見るという全経験の間持続すると言ったものは、「私」という特定の実体ではなく、見るという経験それ自体だったのだ。このことは、 [「何であれ、それが見られるとき、それを見ているのは常に私だ」という] 独我論的言明をする人が、「私」と言う間彼の眼を指すという状況を想像すれば、もっと明確になるかもしれない。(多分、彼は正確を期そうとして、どちらの眼が「私」と言う口に属し、 [どちらの] 眼が彼の体を指す手に属するかをはっきりと言うとして、こういう行為をするのだ。)しかし彼は何を指しているのか? 物理的同一性を持った特定の眼を、だろうか? (この文を理解するためには、物理的対象を表すと言われる語の文法が、、「~は物理的対象を表す」と言うときに、私たちが「同じ~」とか「同一の~」という句を使うのと同じ仕方で特徴づけられているということを思い出さねばならない。)私たちはさっき、彼 [=独我論者] は特定の物理的対象を指そうとしたのでは全くない、と言った。彼が有意味な(significant)言明をしたという考えの起源は、私たちがある混同をしていることにある。その混同は、私たちが「幾何学的眼」と「物理的眼」と呼ぶものの間の混同に対応する混同である。 [そこで] この二つの用語の使用を示そう。もしある人が「君の眼を指せ」という命令に従おうとすれば、彼は多くの異なることをするだろうし、眼を指したということを彼が受け入れるための、多くの異なる基準があるだろう。もしこれらの基準が、普通そうであるように、互いに一致するならば、私が自分の眼に触ったことを自分に示すために、私はそれらの基準のどれかを代わる代わる用いてもいいし、異なる組み合わせを用いてもいい。もしこれらの基準が互いに一致しないならば、「私は私の眼を触る」と「私は私の指を私の眼に向けて動かす」という句の意味の違いを区別せねばならない。例えば、私が目を閉じているときに、それでも、私の手を眼に向かって上げる筋感覚的経験と呼ぶべき特徴的な筋感覚的経験を私の腕に感じることはできる。その行為に成功したということは、眼を指が触るという特異な触覚的感覚によって確かめられるだろ。しかしもし私の眼がガラス板の後ろに固定されていて、指で眼を押すことができなかったとしたらどうだろう。それでも、「今私の指が眼の前にある」と言いたくさせるような筋肉の感覚という基準はあるだろう。視覚的基準として、私たちは二つ採用することできる。 [一つは] 私の手が上がり眼に向かって近づくのを見るという普通の経験である。この経験は、もちろん、二つの物(例えば指先同士)が触れあうのを見ることとは違う。私の手が眼に向かって動くことのもう一つの基準として、鏡を覗き込んで指が眼に近づくのを見るという経験を使うことができる。もし、私たちの体において「見る」と言われる場所が、この第二の基準によって決定されるとすれば、 [鏡を使わない] 他の基準によれば鼻の先、額のある場所、あるいは、私の体の外部とみなされる場所を指すこともあるかもしれない。私がある人に「第二の基準だけに従って自分の眼(あるいは両眼)を指してほしい」と頼むとき、私はその望みをこう表現しよう。「君の幾何学的な眼を指せ」と。「幾何学的な眼」という語の文法の「物理的眼」という語の文法に対する関係は、「木についての感覚与件」という表現の文法の「物理的木」という表現の文法に対する関係と同じである。どちらの場合でも、「幾何学的な~と物理的な~は別種の対象である」と言うことは全てを混乱させる。なぜなら、「感覚与件は物理的対象とは別種の対象である」と言う人は、「種類」という語の文法を誤解しているからだ。ちょうど、「数(number)と数字(numeral)は別種の対象である」と言う人と同じ間違いを犯している。こういう言明をする人々は、それによって「列車と駅と車両は別種の対象だ」という言明と同じような言明をしていると考えているが、実は、「列車と列車事故と列車法は別種の対象だ」という言明と類比的な言明をしているのだ。
「何がみられるにせよ、見ているのは常に私だ」と言いたくさせる誘惑は、また「これ」と言いながら視野を抱くような素振りをして「何であれ見られるとき、見られているのはこれだ」と言いたくさせる。(しかし、「これ」という語によって、私がその瞬間たまたま見ていた特定の対象を意味しているのではない。)同じことを「視野そのものを指しているのであって、視野の中の何かを指しているのではない」と言うこともできよう。そしてこのように言うことが役に立つのは、前者の表現 [「何がみられるにせよ、見ているのは常に私だ」] が無意味であることを暴露する点だけである。 [なぜ無意味なのかは、後に述べられる。]
さてそれでは、「何がみられるにせよ、見ているのは常に私だ」という表現から「常に」を捨ててみよう。それでも「私が見る(あるいは今みている)ものだけが本当に見られている」と言うことで独我論的言明を行なうことができる。そしてここで私は、「私は『私』という語によってL.W.を意味しているのではないが、もし今まさに事実として私がL.W.ならば、他人が『私』という語をL.W.を意味すると理解しても、問題はない」と言いたくなる誘惑に駆られる。そして同じことを「私は命の乗り物である」と言うことによっても表現できるだろう。しかしよく聞いてほしい。私がこれを言う相手は誰も、私を理解できてはならない、ということが本質的なのである。他の人は、実際には、私が言いたいことを理解して、彼の表記法の中で私に例外的位置を認めるかもしれないが、しかしやはり、他人が「私が本当に言うこと」を理解すべきである、ということは論理的に不可能である。すなわち、「彼が私を理解する」という言明は、偽ではなく無意味なのである。従って、私の表現は、哲学者たちによって様々な機会に使われる多くの表現の一つであり、そのように言う人本人には何かを伝えると思われているのだが、本質的には [この表現では] 他人に何一つ伝えることはできないのである。さて、もし例えば、意味を伝えることがある経験に随伴される、あるいは、経験を生み出すことを意味するならば、私たちの表現は、あらゆる種類の意味を持ちうるだろうが、私はそれらの意味について何も言うつもりはない。しかし私たちは、事実として、私たちの表現が、非-形而上学的表現が持つのと同じ意味で意味を持つという考えに誤誘導された。その理由は、「私の言う独我論的言明を他人が理解できない」という事例を、他人がある情報を持っていないために私の言うことを理解できない事例と、誤って比較してしまうからだ。(このことは、文法と意味・無意味の関係を理解しないと明らかにならない。)
ある句の私たちにとっての意味を特徴づけるのは、私たちがその句に対して行なう使用である。その意味は、表現に対する心的な随伴物ではない。 [私たちは心理主義はとっくに捨て去っている。] 従って、「私はそれによって何かを意味していると、私は考えている」とか「私はそれによって何かを意味していると、私は確信している」という句は、哲学的議論においてある表現の使用を正当化するために非常に頻繁に耳にするが、私たちにとっては何の正当化にもなっていない。私たちは訊ねる。「君は何を意味しているのか?」すなわち「この表現をどのように使っているのか?」と。誰かが私に「ベンチ」という語を教えて、彼はときどき、あるいはいつも、「ベンチ」というように、単語の上に横棒を引くとする。そして「これは私にとっては何かを意味しているのだ」と言ったとする。このとき、私が彼に返すべき答えは、「君がその横棒でどういう種類の考えを連想しているのかは知らない。しかし、君が『ベンチ』という語を使おうと望む記号系(calculus)において、その横棒の使用が存在することを示してもらわない限り、私はその横棒に興味はない」というものだ。―― [他の例を挙げよう。] 私は誰かとチェスをしようと思う。すると相手が白のキングに紙でできた王冠をかぶせた。キングの使用自体に変化はない。しかし彼は言う、「この王冠は私にとってゲームの中である意味を持っているんだ。ただそれを規則によって表現することはできないんだ」と。これに対し私は言う。「王冠は、キングの使用を変えない限り、私が意味と呼ぶものを持っていない。」
私が視野の一部を指しながら「これはここにある」と言うとき、そのような句は他人に情報を伝えることはありえないが、私にとっては原初的意味を持つことが、時としてある。
私が「これだけが見られる」と言うとき、私は、私たちの言語の記号系において全く使用を持たない文が、ごく自然に口を突いて出ることがあるということを忘れている。「a = a」という同一性の法則について考えてほしい。そして、ある対象を見て「この木はこの木と同じ物だ」と繰り返し呟くことで、その意味を把握し、視覚化しようとして、時に私たちがどれほどの努力を傾けるか、考えてほしい。外見上はこの文に意味を与えるかに見える私の身振りと像は、「これだけが本当に見られる」という文の場合に私が使う身振りと像とよく似ている。(哲学的問題について明らかにするには、私たちが形而上学的表明をしたくなる特定の状況の一見重要でなさそうな細部に意識を向けることが有用である。だから、 [例えば] 変化しない周囲を見るときには「これだけが本当に見られる」と言いたくなるかもしれないが、歩きながら [移りゆく周囲を] 見ているときには全然そういうことを言いたくはならないだろう。)
先述のように、ある特定の人物が常にあるいは一時的に例外的位置を占めるような記号表現(symbolism)を採用することには、何の反対もない。従って、私が「私だけが本当に見る」という文を口にすれば、それを聞いた私の友人たちは、彼らの表記法が私に合うように、「L.W.は~を見る」等々の代わりに「~が本当に見られる」等々と言うことは、考えられることである。しかしながら、この表記法を選択したことを私が正当化できると考えることは間違いである。私が心から「私だけが本当に見る」と言ったとき、私はまた、「私」という語で本当にL.W.を意味してはいなかった、と言いたかった。しかし、友人たちのために、本当はそういうことを意味してはいなかったが、「本当に見るのは、今はL.W.である」と言ったかもしれない。私はまた、「私」という語で、他人には見えないが、今現在L.W.に住んでいる何かを意味することも、ほぼ可能であろう。(私は心のことを言っているのだが、それは私の体を通してしか指すことができない。)他人に対して、彼らの表記法の中で私が例外的な位置を占めるよう示唆することには、何も悪いことはない。しかし、この体が今は、何か本当に生きているものの座席であるという考えのために与えようと望む正当化は――無意味である。なぜなら、明らかにこれは、普通の意味で経験的な事実を述べているわけではない。(そして、私だけが特定の経験を持つ位置にいるがゆえに私だけが知りうる経験的命題なのだ、などと考えてはならない。)さて、本当の私が私の体に住んでいるという考えは、「私」という語の特異な文法と、この文法が引き起こしがちな誤解に関係している。「私」(または「私の」)という語の使用には、二つの異なるケースがある。それを私は「客体としての使用」と「主体としての使用」と呼ぶかもしれない。「客体としての使用」の例は、「私の腕が折れる」、「私は6インチ背が伸びた」、「私の額にはコブがある」、「風が髪を吹き揺らす」などだ。「主体としての使用」の例は、「私は~を見る」、「私は~を聞く」、「私は腕を挙げようと試みる」、「私は雨が降ると思う」、「私は歯痛を持っている」などだ。この二種類のカテゴリーの違いを次のように言うことで指摘できるだろう。「客体としての使用」の場合は特定の人物を認識することが含まれており、そこには認識間違いの可能性がある。あるいはむしろ『間違いの可能性が与えられている』と言うべきか。 [反対に、二番目のカテゴリーでは、認識間違いは起こりえない。] ちょうどピンボールにおいて点数を取ることに失敗する可能性が与えられているように。一方、お金を入れたのに球が出てこないとすれば、それはゲームに用意されている失敗ではない。例えば、私が腕に痛みを感じ、折れた腕を見て、折れたのは私の腕だと考えたとする。しかし実際にはその腕は私の隣の人の腕だった、ということは起こりうることである。あるい別の例として、私が鏡を覗き込んで、隣の人の額のコブを私のコブだと間違えることも起こりうる。これに対し、 [「主体としての使用」の場合、] 私が「私は歯痛を持っている」と言うとき、認識間違いなど起こりようがない。「痛みを持っているのが本当に君だと、君は確信しているか?」と聞くことは無意味である。さて、「主体としての使用」において認識間違いの可能性がない理由は、私たちが間違いと考えたくなるような動き、つまり「悪い動き」が、実はゲームの [規則で許されている] 動きではないからである。(私たちはチェスにおいて良い手と悪い手を区別する。クイーンをビショップの行動範囲内に置くような手は間違った [悪い] 手と呼ばれる。しかしポーンがキングに成るのは、間違い [悪い手] ではない[21]。 [単純にルール違反なのである。] )そして今、私たちはごく自然に私たちの考えをこういう言い方で述べたくなる。「他人の痛みを自分の痛みと間違えて痛みにうめくことが不可能であるのと同様に、『私は歯痛を持っている』という言明をする際、 [歯痛を持っている人物を] 他の人を取り違えることは不可能である。うめきがある特定の人に対する言明ではないように、『私は痛みを持っている』と言うこともある特定の人に対する言明ではない。」するとこういう反論があるかもしれない。「確かに、『私』という語はその語を発した人を指すはずだ。その語はその人自身を指す。そして非常に多くの場合、『私』という語を発する人は、実際に、指で自分を指している。」しかし、 [指で] 自分を指すということは全く余計なことである。ただ手を挙げるだけでもよかったかもしれない。誰かが手で太陽を指すとき、彼は太陽と自分自身の両方を指している、なぜなら指すのは彼だから、と言うことは誤りである。一方、指すことによって太陽と自分に対する注意を惹きつけることはできるかもしれない。
たとえ私がL.W.であっても、「私」という語は「L.W.」と同じものを意味しないし、「現在話している人」という [確定記述の] 表現が表すものと同じものを意味しない。しかしこのことは、「L.W.」と「私」が別のものであるということを意味するわけではない。ただ、「L.W.」と「私」が私たちの言語における異なる道具であるということを意味しているのだ。
語を使用によって特徴づけられる道具だと考えてほしい。そしてハンマーの使用、鑿(のみ)の使用、定規の使用、膠壺の使用について考えてほしい。(また、ここで私たちが言うことの全ては、言語の文を使って行なわれる多種多様なゲームを理解することで初めて理解できる。そのゲームとは例えば、命令を与え、命令に従う、質問をし、それに答える、ある事件を記述する、作り話を語る、冗談を飛ばす、直接的経験を記述する、物理的世界の事件について推測をする、科学的な仮説や理論を作る、誰かに挨拶する、などなど。)「私」という口、あるいは、話そうとしているのは私だということや私が歯痛を持っていることを示そうとして挙がる手は、それによって何かを指しているわけではない。反対に、もし私が痛みの場所を指そうと思えば、私は [その場所を] 指す。ここで再度、眼によって導かれずに痛いことを指すことと、体の傷を見てからそれを指すこと(「ここに予防接種を受けたんだ」)の違いを思い出してほしい。――痛みのあまり泣き叫ぶ人や、痛みを持っているという人は、痛いと言う口を選ばない。
以上全てのことから言える結論は、私たちが「彼は痛みを持っている」という当の人物は、 [言語の文を使って行なわれる多様な] ゲームの規則によって泣いたり顔を歪めたりする人なのだ、ということである。 [私が感じる] 痛みの場所は――既に述べたとおり――他人の体にあることもありうる。私が「私」と言いながら自分の体を指すとき、指示詞「この人」や「彼」の使用に倣って、「私」という語の使用を作るのだ。(二つの表現を類似させるこの仕方は、数学において時おり採用される、三角形の内角の和が180度であることの証明に用いられる方法と幾分類比的である。
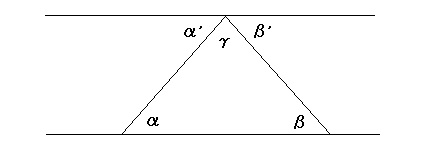
私たちは「α=α」、「β=β」、そして「γ=γ」と言うが、最初の二つの等式と三つ目の等式は全く別種のものである。)「私は痛みを持つ」における「私」は指示代名詞ではないのである。
次の二つの事例を比較してほしい。
- 「君はどうやって彼が痛みを持っていることを知るのか?」――「なぜなら、彼がうめいているのを聞くからだ。」
- 「君はどうやって君が痛みを持っていることを知るのか?」――「なぜなら痛みを感じるからだ。」
しかし「私は痛みを感じる」は「私は痛みを持つ」と同じ意味である。従って [「なぜなら~」という説明文の形をしているが、実は、] 説明になっていない。しかしながら、私の答えにおいて、私は「私」という語よりも「感じる」という語を強調しがちだということは、「私」という語によって一人の人物を(他の人々から)選び出そうとは望んでいない、ということを示している。
「私は痛みを持っている」と「彼は痛みを持っている」の間の違いは、「L.W.が痛みを持っている」と「スミスが痛みを持っている」の間の違いと同じではない。むしろそれは、うめくことと「誰かがうめく」と言うことの間の違いである。―― [するとこう言う人がいるかもしれない。] 「しかし、確かに『私は痛みを持っている』における『私』は、私を他の人々から区別することに役立っている。なぜなら、『私』という記号によってこそ、『私は痛みを持つ』と言うことを『誰か他人が痛みを持つ』と言うことから区別するからだ。」 [こういうことを言う人は] 「私は部屋に誰もいないことを発見した」と言う代わりに「私は部屋に無人氏(Mr. Nobody)がいることを発見した」と言う言語を想像し、この取り決めから生じる哲学的問題を想像してほしい。この言語を使う環境で育てられた哲学者の中には、「無人氏」と「スミス氏」の [表現上の] 類似性を好まない者もいるだろう。 [同様に、「私」と「彼」の類似性が気に入らなくて、] 「私は痛みを持つ」の中の「私」を捨て去りたいと感じるとき、この痛みを表す言語表現をうめきによる表現のようなものにしたいと感じるのだと、言うことができよう。――私たちは忘れがちだが、語に意味を与えるのはその語の特定の使用なのである。以前出した語の使用についての例を再度考えよう。「5つのリンゴ」と書いた紙をある人に渡して、その人をお使いにやる、というやつだ。語の現実の使用がその意味なのである。私たちの周りの物に名前を書かれたラベルが貼られていて、それによって物を指示するのが普通であると想像してほしい。ラベルの語のいくつかは固有名であり、またあるものは一般名(テーブル、椅子など)であり、さらに色や形の名前もあろう。このとき、ラベルが意味を持つのは、私たちが [ラベルに対して] 特定の使用をできる限りにおいてである。ところが容易に想像がつくように、私たちは物についているラベルをみるだけで感動してしまい、ラベルを重要なのものにしているのはその使用であるということを忘れてしまう。このようにして、私たちが指示の身振りをして「これは~だ」(これが直示定義の形式である)という語を発すれば、物に名前をつけたと信じてしまうことが時としてあるのだ。私たちはあるものを「歯痛」と呼び、特定の状況下で私たちが自分の頬を指して「これが歯痛だ」と言うとき、言語を使って行なうやりとりにおいて、「歯痛」という語は特定の機能を授けられたと考える。(私たちの考えは、私たちが何かを指し、他人は「私たちが指しているものだけを知りさえすれば」、他人はその語の使用を知る、というものだ。そしてこのとき私たちは、「指すもの」が、例えば、人であり、「私が指すものを知る」ということは私が現在どの人を指しているかを見ることであるという、特殊な事例を心に思い描いている。)
「私」が主語として使われている事例において、私たちは身体的特徴によってある特定の人を認識するのだから、「私」を [主語として] 使っているのではないと感じる。そしてこの考えは、「私」という語は何か身体的ではないもの、しかし私たちの体の中にいる何かを指すために使うのだという幻想を生み出す。事実、これこそが、本当の自己であると思われる。そのうちの一つが「我思う、ゆえに我あり」と言われるときの自己である。――「だがそれなら、心はなく、体だけがあるというのか?」こう言う人には次のように答えよう。「心」という語はちゃんと意味を持っている。すなわち、私たちの言語における使用を持っている。しかしこの答えだけでは、まだどのような種類の使用を私たちが行なっているかまでは言及していない。
事実、次のように言ってもよい。これまでの探究において私たちが関心を抱いていたのは、私たちが「心的活動」――見る、聞く、感じるなど――と呼ぶものを記述する語の文法である。これは次のように言い換えることもできる。私たちは「感覚与件を記述する句」の文法に関心を抱いているのだ、と。
哲学者たちは、哲学的意見や哲学的確信として、感覚与件は存在すると言う。だが、「私は感覚与件が存在すると信じる」と言うことは、「私は自分の眼前に対象がないときでも、それが見えることはありうると信じる」と言うことにつながる。今や、「感覚与件」という語を使うときは、その文法の特異性について明確に分かっていなければならない。なぜなら、この表現を導入するという考えは、「現実」という語に言及する表現に倣って「あらわれ(appearence)」に言及する表現を作ることと同じだからだ。例えば、もし二つの物が同じに見えるならば、 [現実に] 同じ二つの何かが存在しなければならない、と言われたのだ。もちろん、このことが意味するのは、「これら二つの物のあらわれは同じである」と「これら二つの物は同じに見える」を同義の表現として用いると決めたこと以上のことではない。 [しかし] 実に奇妙なことに、この表現方法を導入したことで、人々は、何か新しい実体、世界の構造の新しい要素を発見したという考えに導かれてしまう。まるで「私は感覚与件が存在すると信じる」と言うことは「私は物質が電子から構成されていると信じる」と言うことと類似しているとでもいわんばかりである。あらわれや感覚与件について語るとき、私たちは「同じ」とうい語の新しい用法を導入する。AとBの長さが同じに見えねばならず、BとCの長さも同じに見えねばならないのに、AとCの長さは同じには見えない、ということは起こりうる。それをこの新しい表記法で表現すると、「Aのあらわれ(感覚与件)とBのあらわれは同じで、BのあらわれとCのあらわれも同じだが、AのあらわれとCのあらわれは同じではない」と言わねばなるまい。この言い方は、君が「同じ」という語を非推移的に使うことを嫌に思わなければ、全く問題ない。
感覚与件による表記法を採用するときに私たちが陥る危険は、感覚与件についての言明の文法と、それと見かけはよく似た、物理的対象についての言明の文法が、異なるものであることを忘れることである。(こういう危険に陥ると、私たちはさらに「私たちは完全な円を見ることはできない」とか「私たちの感覚与件は全て曖昧である」などの文で表現される誤解について語ることになる。またこれによって、ユークリッド空間における「位置」「動き」、「大きさ」などの語の文法と視覚空間におけるそれらの語の文法を比較するようになる。例えば、視覚空間にも [ユークリッド空間と同じように] 絶対的位置、絶対運動、絶対的大きさが存在する、ということになる。)
さて、私たちは、「ある物体のあらわれを指す」とか「視覚的な感覚与件を指す」のような表現を使うことができる。大雑把に言うと、この種の指示は、例えば、銃の重心にそって狙いをつけるのと同じことになる。従って何かを指してこう言うことができる。「これは私たちが鏡に映る私の像を見る方向である。」あるいはまた、「私の指のあらわれ、あるいは感覚与件が木の感覚与件を指している」のような表現を使うこともできる。ただし、こういう指示の事例と、声が聞こえてくるように思われる方向を指すとか、眼を閉じて額を指す場合を区別を区別する必要がある。
今、私が独我論的に「これが本当に見られる」と言うとき、私は自分の前方を指している。ここでは、視覚的に指すということが本質的である。もし私が体の横や後ろの方を――いわば私が見ていないものを――指せば、その指示は私にとって無意味である。 [なぜなら] その指示は、私が指そうと望む意味での指示ではないからだ。しかしこのことは、「これが本当に見られる」と言いながら前方を指すとき、何かを指す身振りはするものの、ある一つの物を他の物を区別して指しているのではない、ということを意味している。これはちょうど、車に乗っていて急いでいるとき、まるで中から車を前に進めるかのように、本能的に前方にある物を押してしまうことと同じである。
私が見ているものを指しながら「私がこれを見る」とか「これが見られる」と言うことが意味を持つならば、私が見ていないものを指しながら「私はこれを見る」とか「これが見られる」と言うこともまた、 [偽な命題ではあるが] 意味を持つ。 [しかし、前段落で] 私が独我論的言明をしたとき、私は指しはしたたが、指す主体と指される対象を分かちがたく結びつけることで、その指示から意味を奪ってしまった。 [いわば] 歯車などの部品全部を揃えて時計を組み立てたのに、最後に文字盤を針と結びつけてしまい、一緒に回転するようにしてしまったのだ。このようにして、「これだけが本当に見られる」という独我論的言明は、私たちにトートロジーを想起させる。
もちろん、私たちがこのような擬似命題を作る誘惑に駆られる理由の一つは、周囲にある、他の物と区別された特定の物を指して、あるいは、(視覚的空間ではなく)物理的空間の特定の方向を指して「私はこれだけを見る」や「これが私の見る範囲だ」と言うときの命題と [「これだけが本当に見られる」のような独我論的擬似命題と] の間の [みかけ上の] 類似性にある。もし私がこの意味で指し、「これが本当に見られるものだ」と言うならば、人はこう言って私に答えることができる。「これは君、つまりL.W.が見ているものだ。しかし、私たちが『L.W.が見るもの』と言う代わりに『本当に見られるもの』という表記法を採用することには何の異論もない。」だがそれでも、私の文法において隣人を持たないものを指すことによって、(他人にではなくとも)私自身に何かを伝えることができると信じるなら、私は間違いを犯すことになる。その間違いは、「私はここにいる」という文が意味を持つような非常に特殊な状況(例えば、私の声と私の話す方向が他人によって認識される場合)以外の状況下で、この文が私に意味を持つ(ついでに、常に真である)と考えることの間違いと類似している。この場合もまた、語が意味を持つのはその特定の使用によってであるということを学ぶことができる重要な事例である。私たちはさしずめ、チェスやチェッカーの駒に似た形をした木片がチェス盤の上にあったら、どのように使うかについては何も言われていないのに、ゲームがやれると考える人に似ている。 [同様に、語が与えられただけで、その用法が与えられていなければ、言語ゲームはやれないのだ。]
「それは私に近づいてくる」と言うことは、たとえ物理的には何も近づいてきていなくても [偽ではあるが] 意味を持つ。そして同様に、「それはここにある」や「それは私に到達した」と言うことは、何も私の体に到達しなかったとしても [偽ではあるが] 意味を持つ。これに対して、「私はここにいる」は、私の声が他人から認識され、公共空間のある場所から聞こえてきたときに、意味を持つ。 [これに対して、] 「それはここにある」の中の「ここ」は、 [公共空間ではなく] 視覚空間におけるここである。大雑把に言うと、それは幾何学的な眼である。「私はここにいる」が意味をなすには、この文が公共空間内のある場所に対する注意を喚起しなくてはならない。(そしてこの文の使われ方は複数ある。) [他人には意味を持たなくとも、] 自分自身に対して「私はここにいる」と言うことが意味を持つと考える [独我論的な] 哲学者は、この言語表現を「ここ」という語が公共空間内のある場所を指す文から取ったのであり、「ここ」という語を視覚空間内のここだと考えている。従って、彼が言っていることは実際には、「ここはここだ」という [トートロジーの] ようなものなのだ。
しかしここで、私の独我論を別の仕方で表現してみよう。私と他人が、それぞれ自分の見ているものについての記述を、絵または文章で表現していると想像する。そして出来上がった記述が私の前に提出される。私は自分が書いた記述を指して「これが本当に見える(見えた)ものだ」と言う。つまり、私は「この記述だけがその背景に現実(視覚的現実)を持っているのだ」と言いたい誘惑に駆られる。他人の記述はこう呼ぼう――「空白の記述」と。私はまた「この記述だけが現実から導かれる、これだけが現実と比較される」と言うこともできよう。さて、私たちが「この絵や記述は一群の対象――例えば私が見ている木々――の投影である」とか「この記述はこれらの対象から導かれた」と言うとき、この言明は明確な意味を持っている。しかし、「この記述は感覚与件から導かれる」のような句の文法については、よく調べなければならない。私たちが今話していることは、特異な誘惑と結びついている。その誘惑とは、「私は他人が『茶色』という語で何を意味するか決して知りえない」とか「他人が茶色の対象を見ると(嘘をつかずに)言うとき、彼が何を見ているか私は決して知りえない」と言いたくなる誘惑である。――このように言う人には、「茶色」という語の代わりに、異なる二つの語を使うよう提案することができるだろう。1つは、彼の特定の印象 [=感覚与件] を表すための語、もう1つは、彼以外の人も彼と同じように理解できる [公共の] 意味を持った語である。この提案について考えてもらえば、「茶色」やその他の語の意味、あるいは機能についての彼の概念に間違いがあることが分かる。 [つまり、] 彼は自分のための正当化を探しているが、そんなものはないのだ。(ちょうど、理由の連鎖には終わりがあってはならないと信じる場合と同じ間違いである。)数学の演算をすることに対する一般公式による正当化について考えてほしい。この公式は、私たちが現実にそれを使っているよう、この特定のケースにおいても公式を使うよう、私たちに強制するだろうか? 「私は視覚的現実からある記述を導く」と言うことが意味するものは、「私は、ここで私が見るものからある記述を導く」と言うことが意味するものと類比的ではない。例えば、色のついた正方形が「茶色」という語と対応している図を見て、さらに正方形と同じ色をした斑点を見ると、私は「この図は『茶色』という語をこの斑点の記述のために使わねばならないことを私に示している」と言うことができる。これが私が記述において必要とされる語 [の使用] を導く方法である。だが、私が受ける特定の色の印象 [=感覚与件] から「茶色」という語 [の使用] を導くと言うことは無意味であろう。 [それを「私に対してだけ通用する意味」と呼ぶこともできない。なぜなら公共の場で使用されて初めて、語に意味が与えられるからだ。]
さて、「人間の [心ではなく] 体は痛みを持つことはできるか?」と質問しよう。するとある人はこう答えたくなるだろう。「どうやったら体が痛みを持てると言うのだ? 体それ自体は死んでいるというのに。だって体は [それだけでは] 意識を持っていないじゃないか!」この人物もまた、痛みの本性を探し、そして痛みというのはその本性として物質的対象が持つことのできないものだということを発見した、痛みを持つのは、物質的対象とは別種の本性――すなわち心的本性――を持った実体である、と言わんばかりである。だが、「自我は心的である」と言うことは、数字3が物理的対象を表す記号としては用いられないと認識するとき、「 [記号3が表す] 数3は心的な、あるいは非物質的な本性を持つ」と言うようなものである。
これに対して、私たちが「この体は痛みを感じる」という表現を採用することには全く何の問題もない。そして普通するように、痛みを感じる体を医師のところへ運び、ベッドに横たわらせ、前回痛みを持ったときは一日たてば収まったな、ということを思い出しさえする。「しかしこの表現形式は、 [心的対象について物質的対象を使って表現しているのだから] 少なくとも間接的なものではないか?」という疑問を持つ人には逆にこう訊ねたい。ある式において「 [数]xを [数]3で置き換えよ」と言う代わりに「 [記号]xを [記号]3で置き換えよ」と言うことは、 [記号によって数を表現しているのだから] 間接的な表現を使っていることになるのだろうか?(あるいは逆に、幾人かの哲学者が考えているように、「心が痛みを持つ」とか「xを3で置き換えよ」という表現だけが直接的表現なのだろうか?) [そうではない。] ある表現が別の表現より直接的であるなどということはない。表現の意味は、私たちがそれをどう使っていくかということに全面的に依存している。心が語と物の間に作り上げるオカルト的な結合が意味であり、この結合が語の用法全体を――種子が木を含んでいると言われるように――含んでいるなどという考えは捨ててしまおう。
痛みを持ったり考えたりするものは心的本性を持つものだ、という命題の核は、「私が痛みを持つ」の中の「私」という語が特定の体を記述するのではないということだけである。というのも、「私」をある体で置き換えることはできないからである。
原註
1 この約束は果たされなかった。――編者
2 しかし行なわれなかった。――編者
3 テアイテトス 146D-7C.
4 『論考』5・02を見よ。
5 ラッセル『心の分析』III章を参照。
6 この議論は行なわれなかった。――編者
訳註
[1] 「直示定義は誤解されうる」という主張は『探究』にも引き継がれます。『探究』第28節を参照。
[2] occult という語は、大森訳・黒崎訳ともに「神秘的」と訳されていますが、ここではそのまま「オカルト」と訳しました。「神秘的(mystical)」という語を、ウィトゲンシュタインは特別な意味で用いるため、これと区別しようと考えたためです。例えば以下のような節を参照。
世界がいかにあるかはではなく、世界があるというまさにそのことが神秘的である。
(『論考』6.44)
世界を永遠の相の下に観るということは、世界を――限られた――全体として観る、ということである。[3] 形式主義(formalism)という言葉からは即座にヒルベルトの名前が連想されます。ですが、該当の引用箇所でフレーゲが直接批判している対象はヒルベルト以前のもっと原始的な段階の形式主義(フレーゲは形式的理論と呼んでいます)です。ウィトゲンシュタインが読んだのは、例えば以下のような文章でしょう。
世界を限られた全体として感ずるその感情は神秘的なるものである。
(『論考』6.45)
私は既に以前に算術において流布している形式的理論の欠陥に言及したことがあります。形式的理論では、何の内容ももたず、またもつべきでもない記号について語りながら、しかし、にもかかわらず、当然記号の内容にのみ帰せられるような諸性質が、それらの記号に対し帰せられているのです。
(「関数と概念」[1891]『哲学論集 フレーゲ著作集4』(勁草書房 1999))
記号をこの学問の対象だけと称する形式的理論を、拙著『算術の基本法則』第二巻における私の批判が、多分決定的に片付けてしまったと見なすことができよう。記号と表示されたものとが、必ずしも常に明確に区別されてこなかった結果、演算表現(expressio analytica[解析表現])ということで、[記号のみではなく]半ばその[表現の]意味とも解してきたのである。
(「関数とは何か」[1904]『哲学論集 フレーゲ著作集4』 p.164)
[4] G.H.ハーディー (Godfrey Harold Hardy, 1877-1947)。解析学を専門とした数学者。ケンブリッジ大学トリニティ校卒。トリニティ校で講義(1906-19)、ケンブリッジ大学(1919-31)、オックスフォード大学教授(1931-42)。数学教育の改革を推進し、ラマヌジャンを援助したことでも知られます。
ゴールドバッハの予想は「4以上の全ての偶数は二つの素数の和で表せる」というものです。現在のところ、この予想が正しいことの証明はなされていませんし、反例も見つかっていません。現在の人間の知識段階では、真偽を判定できない命題です。
[5] 「可能無限」の概念です。1930年代のウィトゲンシュタインの無限観は、大筋において直観主義の可能無限と同じものでした。
[6] F.ゴールトン (Francis Galton,1822-1911)はダーウィンの従兄弟で、優性学の創始者として知られ、1904年には優生学研究所を設立し、人間の改良運動を展開しました。また統計学における回帰分析の考案者でもあります。
ここでウィトゲンシュタインが言及しているのは「合成写真」の技術です。ゴールトンは、同じ種類の人格や民族の人々の顔写真を重ね合わせていけば人格や民族性の“観相学”的な本質が、写真上にはっきりと顕現するに違いないと信じ、重ね焼きによる合成写真を発明しました。例えば、犯罪者の顔を次々と重ね焼きして“理想的な犯罪者”を作り出したり、日本人の典型的な顔写真を作り出したりしました。
また、この写真の喩えは、後期の重要な概念である「家族的類似性」の萌芽とみなすことができるでしょう。
[7] 「意味の物化」批判です。『探究』第40節も参照。
[8] 感覚のみを所与として、それに基づいて認識ないし知識を構成しようとする場合、その所与としての感覚を感覚与件(sense-data)と呼びます。この立場(虚構主義)を積極的に推し進めたのが、ラッセルとカルナップです。
[9] 『探究』第71節も参照。
[10] H.ヘルツ(1857-1894)はドイツの物理学者。実験と理論の両方で成果を残し、実験では電磁波の検証が有名であり、理論では力学の公理化が有名です。彼は、定義が明確でない力という概念を消去し、質量の概念を導入して力学を公理化しました。ウィトゲンシュタインは哲学に入る以前から彼を尊敬していました。
ここで言及されている『力学の原理』の序文では、本質への問いは、それに対して正面からまともに答えるのではなく、矛盾を除去することによって、問いを解消する、つまり問いを立てる気をなくさせるという方策が述べられています。これは非常にウィトゲンシュタイン的な考え――というより、ウィトゲンシュタインがヘルツ的な考えを哲学に応用した、というべきでしょうか。
[11] 「日常言語は論理的に完全である」という考えは、前期-後期を通してウィトゲンシュタインが生涯持ちつづけたものです。『論考』の以下の箇所を参照。
私たちの日常言語の全命題は、実際、その有りのままにおいて、論理的に完全に秩序づけられている。ウィトゲンシュタインにとって、理想言語を作ることの目的は、日常言語の紛らわしい表現を取り除き、日常言語が持つ論理形式を明確に浮き上がらせることでした。この点において、ウィトゲンシュタインはラッセルやフレーゲと鋭く対立することになります。
(『論考』5.5563)
[12] この一見意味不明な箇所は、黒崎氏の解説が分かりやすいと思います。以下に引用します。
方程式 x2 + ax + b = 0 は、αが0に近づき、βが1に近づくとき、方程式 x2 = -1 に近づく。さて一般に、方程式 x2 + ax + b = 0 は、-a/2 ±√a2 - 4b/2 という解を持つ。この解をβ±αとおく。しかし方程式 x2 + ax + b = 0 は、(a2 - 4b) < 0 のときは実数解を持たない。従って方程式 x2 = -1 は実数解を持たない。さて、方程式 x2 + ax + b = 0 の解β±αは、aが0に近づき、bが1に近づくとき、方程式 x2 = -1 の解に近づく。その近づき方は、実数βに対し、虚数αだけの距離を持って、両側から近づく、という事である。
(黒崎宏『「青色本」読解』 p.49)
[13] この段落は、『論考』における議論の解説であり、次の段落で批判の対象となる考えです。
[14] この段落から、ウィトゲンシュタインが「事実の影」 = 「命題」 = 「文の意味」という等式が成り立つと考えていることが分かります。ここで批判されている「事実 ― 影(命題) ― 文」という3層の図式は、ラッセルが考えていたものです。
同様の批判が『探究』第第93節-94節にも引き継がれます。
[15] 命題関数(propositional function)はラッセルの用語です。対象を入力項として命題を出力します。例えば、「I think x」に「John」を入力すると、「I think John」という命題が出力されます。フレーゲの「述語(Funktion)」と似ていますが、述語が命題の真偽を出力とするのに対し、命題関数は命題そのものを出力するのが大きな違いです。
[16] 「除外する」の原語はbring outです。黒崎訳では、「暴露する」という訳を当てて「『暴露』ではなく『隠蔽』の間違いではないか」という註が付けられています。そうとることもできますが、ここでは「外に出す」という基本の意味から展開して「除外する」と訳しました。もっとも、bring outの「外に出す」のニュアンスは、「隠れているものを明るみに出す」の意味なので、やはりこじつけの訳であることは否めません。
[17] この文章は「手が動く筋感覚を持つと同時に」という句が入ると、顔をなぞることと膝をなぞることの両方の筋感覚を持つことになり、意味が通じません。そのため大森訳では黙って省略され、黒崎訳では断って省略されています。ここは、一応原文のまま訳しておきます。おそらくウィトゲンシュタインの言い間違いでしょう。
[18] ここでは人間一人の幅が18インチと想定されています。
[19] 操作の同一性を保証する条件は何か、そもそもそのような条件はあるのか、という問題は、中期以降のウィトゲンシュタイン哲学の主要問題の一つです。
ある操作と別の操作が「同一である」と言える必要十分条件は容易に決められません。ここでウィトゲンシュタインが述べているように、「釘を板に打ち付ける」という操作と「杭を穴に打ち込む」という操作を、あるいはまた「この釘を板Aに打ち付ける」という操作と「この釘を板Bに打ち付ける」という操作を、同一とみなすか異なるとみなすかは、意見が分かれるところでしょう。
『論考』におけるウィトゲンシュタインは、操作は基底(操作施す対象を「基底」と呼びます)と独立に決まると考えていました。例えば、操作「+1」は基底0に適用すれば出力として1が得られます。この1に再度「+1」を適用すれば、2が得られます。このように、操作の出力は次々に新しい操作の基底に繰り込むことができます。これが『論考』における無限への唯一のアプローチでした。だから、他にも例えば、「二つに折る」という操作は、基底に「折り紙」が来るか「新聞」が来るかに無関係に、決まっている、ということになります。
しかし、操作は本当に基底と独立に決まると言えるでしょうか。「二つに折る」という操作は紙には適用できても水には適用できません。「水を二つに折れ」――困ってしまいます。すると、何を基底に持ってくるかによって、操作の内容も変わるのではないか? 中期以降のウィトゲンシュタインは、そのような方向へと考えを変えていくことになります。
[20] ここで述べられている、「社会的状況が言語の使用形態を決定する要因になる」という考えは、後に『探究』で導入される「生活形式(Lebensform)」の概念につながる考えだと思われます。言語の社会的側面を考察するという視点は、フレーゲ、ラッセル、そして前期ウィトゲンシュタインにはなかったものです。『探究』の第19節、第23節も参照。
[21] チェスでは、将棋の歩がト金に成るのと同じように、ポーンが盤の一番端まで辿り着くと、キング以外の駒に成ることができます。しかしキングにだけは成ることができません。
著:L.ウィトゲンシュタイン 1933-34
訳:ミック
作成日:2003/12/01
最終更新日:2017/06/22

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

 Tweet
Tweet