| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
一般に進歩とは、実際よりもずっと偉大に見えるものである。
ネストロイ
序文
以下において私は、自らの思想、つまりここ16年間私が従事してきた哲学的探究の成果を述べようと思う。この探究の扱うテーマは多岐にわたっている。例えば意味、理解、文、論理、数学の基礎、意識状態といった概念が扱われる。私はこれらの思想全てを覚え書きや短い断章として書き留めてきた。それらの断章は、時には一つのテーマについての長い連鎖を成し、時には一つの分野から別の分野へ次々に跳び移っている。私の意図は、最初から、これら全てを一つの本にまとめることにあった。本の体裁についてはその時々で色々な形式を考えていたが、本質的な点では、これらの思想が一つのテーマから別のテーマへ自然で間隙のない連続をなすべきであると考えていた。
しかし個々のテーマについての成果をそのような完全な形にまとめることに何度も失敗した後、私はこの試みに成功の可能性がないことを悟った。それゆえ、私に書けるものは、せいぜい哲学的な覚え書きの域を出ないであろう。私の思想は、その自然な傾向に反して無理に一つの方向へまとめようとすると、あっさりその力を失ってしまったのだ。 ―― そしてこのことが探究それ自体の本質に関係していたことは言うまでもない。哲学的探究の本性というのは、私たちに、広い思想領域を縦横に色々な方向から見てまわることを強いる。 ―― この本に含まれる哲学的な覚え書きは、いわば、私の歩んだ長く錯綜した道程の途上で書かれた一群の風景スケッチである。
同じ論点、あるいはほとんど同じ論点が、常に新しい、様々な方向から考察され、常に新しい像が構想された。その像の多くは描きそこないか平凡なものであり、下手な画家の絵のあらゆる欠点を備えていた。だがそういう下手な像を取り除いたところ、まあまあ悪くない像も幾つか残った。そこで私は、読む人に一つの風景の像を見せられるよう、これらを順序良く並べ、余分な箇所を切り揃えねばならなかった。そのため、この本は実際のところ、一冊のアルバムに過ぎない。
私は、つい最近まで、私の仕事を生きている間に公表するという企てを放棄していた。その企ては、もちろん折につけ私の心に湧き起こったし、そういう気持ちになる場合の多くは、私が講義や草稿や議論で人々に伝えた私の成果が伝達の過程で幾重にも誤解され、程度に差はあれ薄められたりバラバラにされたりしたことを耳にせざるをえなかったときだ。私の虚栄心は傷つき、心を鎮めるのに苦労したものだ。
だが2年前、私の最初の本(『論理哲学論考』)を再び読み、その思想を説明する機会を持った。そのとき突然、昔の思想と今度の思想を併せて公表すべきであるという考えが浮かんだ。古い考え方と対比し、それを背景に置くことによってのみ、新しい思想は正しく理解されうるであろう、と。
なぜそのような考えが浮かんだかといえば、16年前に再び哲学に取り組み始めて以来、最初の本に書き記したことに重大な誤りがあることを認めざるをえなくなったからである。
この誤りを悟るために、私は ―― 自分でもほとんど判断できないぐらい ―― フランク・ラムゼイによる批判に助けられた。彼の最後の2年間、私たちは数え切れないぐらい話し合い、議論した。しかしこの ―― 常に力強く正確な ―― ラムゼイの批判よりも多くの恩恵を与えてくれたのは、当大学の教師P.スラッファ氏が長年にわたって絶えず私の思想に加えてきた批判である。私がこの本で述べている考えの大部分は、彼の激励のおかげで生まれた。
幾つかの理由から、私がこの本で公表することは、他の人が今日書いていることと合致するだろう。 ―― だが、私の覚え書きが、それ自身、私のものと認められる印を持っていないならば、 ―― 私は自らの著作権についてことさら主張するつもりはない。
私は疑念を抱きながら自らの思想を公にする。この仕事は未だ不十分であり、暗い時代に産み落とされた。この仕事が幾人かの頭脳に一筋の光を投げかけるということは、ありえないことではないが、もちろん、期待できるほどの公算はない。
私はこの本によって他人に考える手間を省かせようとは思っていない。そうではなく ―― もしそんなことが可能であればだが ―― 読む人に自ら考えるよう仕向けたいと思っている。
私はとにかく良い本を作り上げたかった。その目的は中断されてしまった。しかし、この本を改善するための時間は、私にはもう残されてはいない。
ケンブリッジ
1945年1月
第 I 部
1. アウグスティヌスは『告白』(第1巻 第8章)でこう述べている。「大人が何か対象の名前を呼び、それの方を向くとき、私はその様子を見て、彼らがその対象を指示したいときは、彼らの発声によってそれが言い表されるのだということを理解した。しかし私はこのことを、彼らの身振り、つまり、全ての人の生得言語から見て取ったのだ。この言語は、人が何か物を熱望し、保持し、拒否し、あるいは避けるときに、顔や眼の変化や手足の動き、声の抑揚などを通じてその人の感情を示す。このようにして、様々な文の特定の箇所にこれらの語が発声されるのを繰り返し聞くことで、私は次第に、それらの語が何を言い表すのかを学んできた。そして私の口がそれらの語に慣れるに従って、語を使って自分の願望を表現するようになった。」
この文章から、人間の言語の本質についてのある種の像を読み取ることができると思われる。すなわちそれは、「言語の語は対象を名指す名前であり、文はそうした名前の結合である」というものだ。 ―― この言語像において、いかなる語もその意味(Bedeutung)を持ち[1]、その意味は語に対応づけられているという考えの根源を認めることができる。この場合の意味とは、語が表す対象のことである。
アウグスティヌスは、語の種類の違いについては何も言及していない。私が思うに、言語の習得についてアウグスティヌスのように記述する人は、まず「机」、「椅子」、「パン」のような名詞と人名、その次にある種の活動や性質の名前を考え、残りの語については、いずれ自然に分かるだろうぐらいの気持ちでいる。
ここで、次のような言語使用の場面について考えてほしい。私が誰かをお使いにやるとする。私は彼に「5個の赤いリンゴ」と書いてあるメモを渡す。彼は店の人にそのメモを渡す。店の人は「リンゴ」と書いてある箱を開け、それから表を見て「赤い」という語を探し、それに対応する色見本を見つける。そして彼は数字を ―― 彼は数字を暗記していると仮定する ―― 「5」まで数え、一つ数える度に色見本と同じ色のリンゴを箱から取り出す。 ―― このように、あるいはこれと似たように、人は語を使う。 ―― [ある人が言う。] 「しかし、どこをいかにして「赤」という語を探すべきか、「5」という語で何を始めるべきかを、店の人はどのようして知っているのか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 私は、とにかく、店の人が私が記述したとおりに振舞うと仮定しているのだ。説明はどこかで終わりになる。 ―― [ある人が言う。] しかし「5」という語の意味は何か? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] ここではそうしたことは全く問題ではない。「5」という語がどのように使用されているかということだけが問題なのだ。
2. 意味という哲学的概念は、言語が機能する仕方についての原初的な表象(Vorstellung)に由来している。しかしまた、その場合、私たちの言語よりも原初的な言語を想像しているのだと言うこともできる。
そこで、アウグスティヌスの与えた記述に合致するような、ある言語を考えよう。その言語は、石積み人のAと助手のBの意思疎通に役立たねばならない。Aは石材の上に家を建てている。石材には、台石、柱石、板石、梁石がある。Bは、Aが必要とする順番に石材を渡さなくてはならない。この目的のために彼らは一つの言語を使う。その言語は、「台石」、「柱石」、「板石」、「梁石」という4つだけの語から構成される。Aが叫ぶ ―― Bが、その叫びに応じて運ぶよう教わった石を運ぶ。 ―― これを完全で原初的な言語としてみなせ。
3. アウグスティヌスは意思疎通の一つのシステムを記述していると言うことができるだろう。しかし、私たちが言語と呼ぶものが、全てこのシステムであるわけではない。「この描写は役に立つか立たないか?」という問いが生ずる多くの場合において、「役に立つ。ただし限定された狭い領域に対してのみであって、君が描写しようと望んでいた全体に対して有効なわけではない」と答えねばならない。
これはちょうど、誰かが「ゲームとは、人が物をある規則に従って平面上で動かし・・・」と説明し ―― そして私たちが「君はボードゲームについて考えているようだが、ボードゲームがゲームの全てではない。君の説明が正しいためには、明確にボードゲームに限定しなければならない」と答えるようなものである。
4. 一つの文書を考えてほしい。そこでは音を表すために文字が使われている。しかしまた、アクセントを表すためや、句読点としても使われている。(この文書を、音像を記述する一つの言語としてみなすこともできる。)ここで君には、ある人がこの文書を、各文字にそれぞれ一つの音が単純に対応し、文字はそれ以外の機能は全く持たないと理解していると考えてほしい。アウグスティヌスの言語理解は、このあまりに単純な文書の理解と同じである。
5. 第1節の例を観察すれば、おそらく、語の意味という一般的概念が言語の機能に霧をかけ、それを明確に見ることを不可能にしていることが推察されるだろう。もし私たちが言語の諸現象を、使用の原初的な場面において調べれば、この霧は吹き飛ばされ、語の目的と機能をはっきりと見通すことができる。
子供は、言語を話すことを習得するとき、このような原初的形態を使う。その場合、言語の習得とは説明ではなく訓練なのである。
6. 第2節の言語を、AとBの全言語であると想像することができるだろう。否、それどころかそれは、ある部族の全言語であると想像することもできる。その部族の子供は、AとBのような行為を行うように、これら4つの語を使うよう、そして他人の語に対しても同じように反応するよう、教育を受ける。
この子供の訓練において重要な点は、教える人が対象を向いて、子供の注意をその対象に向け、ある語を発するということにある。例えば、板を子供に見せて「板石」という語を発する。(これを私は「直示的説明(hinweisende Erklärung)」とか「直示的定義(hinweisende Definition)」とは呼ばない。なぜなら、子供はまだ名前について質問することができないからだ。そこで私はこれを「語の直示的教示(hinweisendes Lehren)」と呼ぶことにする。 ―― 私は言っておきたいのだが、これは訓練の重要な一部分を形成する。なぜなら、人間の場合はこの教示が実際に行なわれるからである。決して、この教示以外の仕方を想像できないからではない。)このような語の直示的教示は、語と物の間に連想的結合を打ち立てると言える。
しかし連想的結合とは何なのか? それは色々なことを意味しうる。だがおそらく、真っ先に考えつくのは、子供が語を聞いたときに、物の像を心に抱く、ということだろう。しかし、仮に今それが起こるとして ―― それは語の目的だろうか? ―― もちろん、それは意味でありうる。 ―― 私は語(音の列)のそのような使用を考えることができる。(ある語を発音することは、表象を紡ぐピアノの鍵盤を叩くこと同じである。)しかし第2節における言語の目的は、表象を喚起することではない。( [ただし] 表象を喚起することが語の本来の目的に寄与することは、無論ありうる。)
直示的教示が表象を喚起させるとき、直示的教示は語の理解を引き起こすと言うべきなのか? 言うべきではない。「板石!」という叫びに応えて板石を持っていく人が、その叫びを理解しているのではないのか? 理解している。 ―― 確かに直示的教示は叫びに応えて板石を持っていくことを助けるが、しかし、それは、ある特定の教育と併せてのことである。別の教育が行なわれたなら、語の同じ直示的定義が語の全く異なる理解を引き起こすだろう。
「棒をレバーと結ぶことでブレーキを修理する」 ―― もちろんそうだ。ただし、 [それでブレーキが直るには、] 残りの全機構が与えられている必要がある。残りの全機構と一緒になって初めて、棒とレバーを合わせた物がブレーキレバーになる。ブレーキレバーはそれを支える機構から分離されれば、ただのレバーですらない。それは何でもありうるか、または何でもないものである。
7. 第2節の言語を実際に使用する場合、一方が語を叫び、もう一方がそれに従って行動を起こす。だが、その言語の教育においては、次のような過程も見出せるだろう。つまり、教える人が石を指したら、教わる人が対象の名を呼ぶ、すなわち、語を話す、という過程だ。いや、さらに単純な練習もある。教師が発した単語を生徒が復唱する、というものだ。 ―― どちらの例も言語使用に似た過程だ。またこう考えることもできる。第2節の言語使用の全過程は、子供たちが彼らの母語を習得するための手段とするゲームの一つである、と。このようなゲームを、私は「言語ゲーム(Sprachspiel)」と名付けよう。そして時に、原初的な言語についても、言語ゲームとして語るだろう。
すると、石の名を呼ぶ過程と、教師の後について復唱する過程を、ともに言語ゲームと呼ぶことができるだろう。わらべ歌における語の多くの使用についても考えよ。
私はまた、言語と、言語が織り込まれる活動の全体を「言語ゲーム」と呼ぶ。
8. 第2節の言語を拡張することを考えよう。「台石」、「柱石」など4つの語の他に、第1節で店の人が数詞を使ったように、語の列を含むとする。(たとえばアルファベットの文字列でもよい。)これに加えて2つの語を追加する。それはたとえば、「そこへ」と「これ」でもよい。(なぜなら、この2つの語は大体の意味を示しているから。)この2つの語は、指示する手の動きと一緒に用いられる。そして最後に、若干の色見本を追加しよう。さて、Aは「d-板石-そこへ」といった種類の命令を与える。その際、Aは助手のBに色見本を見せ、「そこへ」という語で家を建てる場所を [手振りと一緒に] 示す。Bは板石の在庫から、色見本と同じ色の板石を、アルファベットを順に「d」まで辿って、dの板石をAが指定した場所に運ぶ。 ―― 別の場合には、Aは「これ-そこへ」という命令を与える。この場合「これ」という語で、Aはある石材を示す等々。
9. 子供がこの [拡張された] 言語を習得するとき、子供は数詞「a,b,c・・・」を暗記しなければならない。そのようにして子供は数詞の使用を習得する。 ―― この教育において、語の直示的教示は存在するだろうか? ―― 例えば、石板が指され、「a,b,c 石板」のように数えられるだろう。 ―― 数を数えるためではなく、一目で把握できるぐらいの物の集合を表すための数詞の直示的教示は、「台石」、「柱石」などの語の直示的教示に、ずっとよく似ている。そのようにして、子供は最初の5つや6つぐらいの基数の使用を習得する。
「そこへ」と「これ」も直示的に習得されるのだろうか? ―― どうやればこういう語の使用を [直示的に] 教えることができるか、想像してほしい! 場所や物を指して行なわれるだろう。 ―― しかし、この指示はまた語の使用においても見られるのであって、使用の教示においてのみ見られるというわけではないのだ。 ――
10. この拡張された言語の語は何を表すのだろうか? 語が表すものが、語の使用の仕方であるならともかく、それ以外のものであるとしたら、それをどのように示すべきか? 私たちはまさに語の使用を記述してきた。「この語はこれを表す」という表現は、従って、この記述の一部分でなくてはなるまい。あるいはその記述は「この~という語は・・・を表す」という形式に達するべきである。
さて、確かに「板石」という語の使用の記述は、「この語はこの対象を表す」という表現に短縮できる。例えば、「板石」という語が、実際は私たちが「台石」と呼んでいる形の建築用石材と関連づけられているという誤解を取り除くことだけが問題であれば、人は [板石を指して] 「『板石』という語はこの形の石材を表す」と言うだろう ―― しかし、このような「指示(Bezug)」の仕方、つまり、語のこのような使用の仕方は、その他の場合にもよく知られているものである。
これと同様に、「a」、「b」、「c」がこの拡張された言語において、実際には「台石」、「板石」、「柱石」が果たすのと同じ役割を果たしているなどの誤解を除去するときには、「a」、「b」などの記号が数を表すと言うことができる。そしてまた、文字はa,b,c,dという順序で使用されるのであって、a,b,d,cという順序ではない、とういことが明らかになるならば、「c」はこの数を表すが、あの数は表さないと言うこともできる。
しかし、語の使用の様々な記述を [「この~という語は・・・を表す」という形式で] 似たものにするとしても、それによって語の使用まで似たものにはなりえない! なぜなら、実際に私たちが見るように、それらは似ても似つかないものだからだ。
11. 道具箱の中の道具について考えよ。ハンマーにペンチ、ノコギリ、ねじ回し、定規、膠壺、膠、釘、ねじ ―― 様々な異なる機能を持った道具、様々な異なる機能を持った語。(そして類似性はいたるところで見られる。)
もちろん、私たちを当惑させるのは、話された語や文書に書かれた語、そして印刷物の語に私たちが出会ったとき、それらが似た形で現れることである。なぜなら、それらの使用が私たちにとってそれほど明確でないからだ。哲学をしているときは特にそうである!
12. 機関車の運転室を覗いたらどんな様子だろう。そこには、程度に差はあれ、皆似通った外見をしたレバーがいくつもある。(手で握られなくてはならないのだから、似ているのも当然なことだが。)しかし、そのうちの一つは、カーブしたレバーで、連続的に調節することができる。(これで弁の開き具合を調節する。)別の一つはスイッチのレバーで、倒されているか立っているかの2つの状態のみを取る。3つ目は、ブレーキの握りである。強く引けばひくほど強いブレーキがかかる。4つ目は、ポンプのレバーで、前後に動かされている間だけ働く。
13. 「言語の全ての語は何かを表す」と言うとき、私たちがどのような区別をしようと望んでいるかということが、まさに説明されていない限り、それだけではまだ何も言っていないに等しい。(それはたとえば、第8節の言語の語を、「意味を欠いた」語 ―― ルイス・キャロルの詩に見られる語や、ある歌の歌詞「ジュヴィヴァレラ」のような語 ―― から区別しようと望むことかもしれない。)
14. 誰かが「全ての道具は何かを変化させることに役立つ。例えば、ハンマーは釘の位置を、ノコギリは板の形を変える、などなど。」 ―― それなら、定規や膠壺、釘は何を変えるのか? ―― 「 [ハンマーは] 物の位置についての私たちの知識を、 [膠壺は] 膠の温度を、そして [ノコギリは] 箱の頑丈さを変えるのだ。」 ―― [道具についての] 表現をこのように同じ形式にしたところで、何が得られるというのだろう? ――
15. 「表す」という語が最も直接的に用いられるのは、おそらく、記号が表す対象に当の記号が貼り付いている場合である。そこで、Aが家を建てるときに必要な道具に、ある記号が貼られているとしよう。Aが助手に対してそれらの記号を示し、助手はその記号が付いている道具をAに渡す。
このようにして、あるいはこれ以外の仕方だとしても、程度に差はあれこれと似た仕方で、一つの名前が一つの物を表し、一つの名前に一つの対象が与えられる。 ―― 何かを名指すことは、物に名札を貼り付けるようなものだと言いきかせることが、哲学において、しばしば有用であることが分かるだろう。
16. [第8節で] A が B に示す色見本はどうだろう? ―― それは言語に属しているだろうか? そう、好きに考えてよい。色見本は語-言語には属していない。しかし、私が誰かに「『これ』という語を発音してくれ」と頼む場合、君は「これ」という語を文の構成要素の一つに数えようとするだろう。だがそれでも、「これ」という語は第8節の言語ゲームにおける色見本と全く同じような役割を演じる。すなわち、他人が言うべきことの見本である。
私たちが見本を言語の道具の一つに数えることは、ごく自然なことであり、それで混乱が起こることはまずありえない。((「この命題」という再帰代名詞について考えよ[2]。))
17. 第8節の言語には様々な語の種類があると言うことができよう。なぜなら、「板石」と「d」の機能よりも、「板石」と「台石」の機能の方が、互いによく似ているからだ。しかし、語を種類によって分類するやり方は、分類の目的 ―― および私たちの好み ―― に依存することになってしまう。
道具、あるいはチェスの駒を分類できる観点がいかに様々か考えてみよ。
18. 第2節と第8節の言語が命令だけから成り立っているということそれ自体は、全く問題ではない。もし君がこの言語が不完全だと言いたいのなら、次のように自問せよ。私たちの言語は完全か? ―― 化学の記号表現や微積分の表記法が組み込まれる前は完全だったのか? なぜなら、化学や微積分の記号表現は、私たちの言語の、いわば新興の郊外部だから。(そして、一体どれだけの数の家と道路を備えることが、都市が都市であるための条件なのか?)私たちの言語を旧都市とみなすことができる。細い路地の迷路と広場、古い家と新しい家、色々な時代に増築された家。これらごちゃごちゃした旧市街を、真っ直ぐで規則的に整備された道路と一様な形の家々を持つ多くの郊外部が取り囲んでいるのだ。
19. 戦いにおいて命令と応答だけから成る言語を想像することは、簡単である。あるいは、問いとそれに対する肯定と否定の返事だけから成る言語など、他にも数え切れないほどの例を挙げられる。 ―― 一つの言語を想像するということは、一つの生活形式を想像するということである。
しかし第2節の言語の場合はどうだろうか。「板石!」は文だろうか、それとも語だろうか? もし語であるとすれば、しかし、私たちの日常言語の同じ発音の語「イタイシ」と同じ意味を持ってはいない。なぜなら、第2節ではそれはまさに一つの叫びだからだ。 [反対に] もし文であるとしても、やはりそれは、私たちの言語の [「板石を持ってこい!」という文を省略した] 「板石!」という文と同じではない。
[ある人が言う。] 最初の問いに関して言えば、君は「板石!」を一つの語とも文とも呼ぶことができる。おそらく、適切には(「退化した双曲線」[3]という言い方に倣って)「退化した文」と言うべきだろう。そして確かにこれは、私たちの「省略」文である。 [ウィトゲンシュタインが言う。] だがそれはあくまで、「板石を持ってこい!」という文の短縮された形でしかない。そしてこの文は第2節の言語には存在しない。 [ある人が言う。] だが反対に、「板石を持ってこい!」が「板石!」という文の引き伸ばされた形であると、なぜ呼んではならないのか? ―― その理由は、「板石!」と叫ぶ人は、本質的には「板石を持ってこい!」と考えているからだ。 [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし君は、いかにして、「板石!」と言う間、そのことを思うのか? 内心で自分に省略されていない文を言い聞かせているのか? そしてなぜ私は、人が「板石!」という叫びで考えることを言うために、この「板石!」という表現を他の表現に翻訳しなくてはならないのか? そしてどちらも同じことを意味するのなら、なぜ私は「彼が『板石!』と言うとき、彼は『板石!』と思っている」と言ってはならないのか? あるいは、なぜ君は、「板石を持ってこい!」と考えることができるときに、「板石!」と考えることができないのか? [ある人が言う。] しかし、私が「板石!」と叫ぶとき、私は「彼が板石を持ってこなくてはならない!」と望んでいるのだ。 [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに。だが、「こう望む」ということの本質は、君が言う [「板石!」という文] とは異なる文を、何らかの形で考えているということに存するのだろうか? ――
20. しかし、ある人が「板石を持ってこい!」と言ったとすると、今や、彼がこの表現を [「イタセキヲモッテコイ」という] 長い一つの語として考えることもできると思われる。つまりその語は「板石!」という1語に対応するわけである。 ―― すると、この表現をある時は1語として、またある時は4語として考えることができるのか? そして人は、普通この表現をどう考えるのか? ―― 私の考えでは、「私に板石を手渡して!」や「彼に板石を渡して!」や「板石を2枚持ってこい!」などの他の表現と対比してこの表現を使う場合は、4語から成る文だと言いたくなる。従って、「板石を持ってこい!」という命令に含まれる語が、この命令とは異なる結合の仕方で含まれている文と対比して使うときには、4語から成る文だと言いたくなるのだ。 ―― しかし、ある文を他の色々な文と対比して使うとは、どのようなことなのか? ある文を使うときに他の文が頭に浮かぶことか? もしそうなら、全ての文が浮かばねばならないのか? その文を言っている間中浮かんでいる必要があるのか? それとも言う前、言った後だろうか? ―― そうではない! たとえ説明が私たちに幾らかの魅力を感じさせるときでも、実際に起きていることを少し考えてみれば、説明が間違った道であることが分かる。私たちがこの命令を他の文と対比して使う、というのは、私たちの言語がこうした他の文の可能性を含んでいるからである。私たちの言語を理解しない外国人が、「板石を持ってこい!」という命令をしばしば聞いたとすれば、その音列全体が1語であり、自分たちの言語の「建築用石材」に相当する語だと考えることもありえよう。もしこの外国人自身がこの命令を与えるとすれば、彼は [私たちとは] 違ったふうに発音するだろう。そして私たちは言うであろう。「彼がこの命令をそのように奇妙に発音するのは、彼がそれを1語だと考えているからだ。」 ―― しかし、彼がその命令を発音するとき、もっと違った何かが彼の中に起きていないだろうか ―― 彼がこの文を1語と見なしていることに対応する何かが? ―― 彼の中では、私たちと同じことが起こりうるし、違うことも起こりうる。では、君がこのような命令を与えるとき、君の中では何が起きるか? 君はそれを発音する間中、4つの語から成っていることを意識するか? 確かに、君はこの言語をマスターしている ―― この言語には他の色々な文も含まれる ―― しかし、言語をマスターしているということは、君がその文を発音する間中「起きている」ことなのか? ―― 確かに私は、外国人が [私たちとは] 別様に理解している文をおそらく別様に発音するだろうということを認めた。しかし、私たちが間違った理解と呼ぶものが、その命令を発音することに随伴する何らかのものでなくてはならない、というわけではない。
文が「省略」文である理由は、私たちがその文を発音するときに考えることを抜かしているからではない。それが ―― 私たちの文法の特定の具体事例と比較して ―― 短縮されているからである。ここで当然、こういう反論がありうるだろう。「君は短縮された文と短縮されていない文が同じ意味(Sinn)を有していることは認めるという。 ―― それなら、その2つの文が共有する意味とはどのようなものか? 一体、この意味を表現する言語表現はないのだろうか?」 ―― しかし、2つの文が意味を共有するということは、それらが同じ使用をされることではないのか? ―― (ロシア語では、「石が赤い(der Stein ist rot)」の代わりに「石赤い(Stein rot)」と言うが、ロシア人にとって繋辞は意味を持たないのだろうか? あるいは、彼らは繋辞を付け加えて考えているのか?)
21. ある言語ゲームを想像せよ。そこでは、BがAの質問に応えて、石材置き場にある板石や台石の数、あるいは、辺りに置かれている建築石材の色や形を報告する。その報告の言葉は「5枚の板石」というものかもしれない。すると、この「5枚の板石」という報告や主張と、「5枚の板石!」という命令との間にある違いは何だろうか? ―― それは、言語ゲームにおいてこの言葉を発することが担う役割である。確かに、語調や顔つきなど相違点は他にも色々あるだろう。しかし、命令や報告は様々な語調と顔つきで行なわれるのだから、語調と顔つきが同じで、ただそれらの使用のみが違うという場合も想像できる。(もちろん、「主張」とか「命令」という語を、文法的な命題形式や抑揚を表す記号として使うこともできよう。その場合、「今日はよい天気じゃありませんか?」という文は、主張として用いられているにも関わらず、疑問文と呼ばれる。)全ての主張が修辞疑問文の形式と語調を持つ、あるいは、全ての命令が「君はこれをしてくれますか?」という疑問文の形式を持つような言語を想像できるだろう。すると人は「この言語を話す人の言葉は疑問文の形式をしているが、実際には命令文である」と言うだろう。 ―― これはつまり、言語の実際の使用においては、命令の機能を持っているということである。(同様に人はまた、「君はこれをするだろう」を予言ではなく命令だと言うだろう。何がこの文を予言とし、何が命令とするのだろう?)
22. 主張の中には主張されていることについての想定(Annahme)が含まれているというフレーゲの見解は[4]、私たちの言語においては、全ての主張命題は「これこれであると主張されている」という形式で書くことができるということを、本質的な基礎としている。 ―― しかし、「これこれであること」は、私たちの言語における命題ではない ―― 言語ゲームにおける指し手(Zug)ですらない。そして「~であることが主張されている」と書く代わりに「主張されている:~である」と書けば、この場合、「主張されている」という言葉は全く余計である。
私たちはまた、全ての主張を、肯定の答えを付け加えた疑問文として書くことができよう。例えば「雨が降っっているか? はい!」のように。このことは、全ての主張が疑問を含んでいるということを示しているのだろうか?
人は確かに、 [フレーゲの] 主張記号 [ |― ] を、例えば、疑問記号 [ ? ] と比較して使う権利を持っている。あるいは、主張を空想や仮定から区別する権利を持っている。間違っているのはただ、主張が、思考することと(真理値を付与するなどによって)主張することの二つの行為から成り立っていて、楽譜に従って歌うように、命題記号に従ってその二つの行為を行うのだという考えである。もちろん、楽譜に従って歌うことと、書かれた命題を大きな声や小さな声で読むことを比較することはできる。しかし、読まれた命題を「思う」(考える)ことと楽譜に従って歌うことを比較することはできない。
フレーゲの主張記号は、文の開始を強調する。従ってそれは、句点(ピリオド)と似た機能を持つ。それは、文全体を文の一部分から区別する。もし私が、誰かが「雨が降っている」と言うのを聞き、しかし文全体の始まりと終わりを聞いたかどうか分からないとき、この文は、私にとって、意思疎通のための手段にならないのだ[5]。
ファイティング・ポーズをとったボクサーが描かれた絵を想像せよ。この絵は、ボクサーがどのように立っているか、どのように立つべきか、どのように立つべきでないか、または、ある人がどこそこに立っていた、などなどのことを人に伝えるために使うことができる。この絵を(化学の言い方に倣って)文基と呼ぶことができるだろう。フレーゲも恐らく、「想定」をこの文基と似たようなものと考えていたのだ。
23. ところで文の種類はいくつぐらいあるのだろう? 例えば、主張、疑問、命令などのような? ―― そのような種類は無数にある。私たちが「記号」とか「語」とか「文」と呼ぶものの全てには、無数に異なる種類の使用がある。そしてこの多様性は、固定的なもの、はっきりと与えられた所与のものではない。いわば、言語の新しいタイプ、新しい言語ゲームが誕生し、他の言語ゲームが廃れ、忘れられるのである。(この生成変化のおおよその像は、数学の [言語の] 変化が与えてくれる。)
「言語ゲーム」という語は、ここでは、言語を話すことが人間の活動の一部である、あるいは、生活形式の一部であるということを強調するべきものである。以下に挙げる例や、あるいは他の例において、言語ゲームの多様性を想像せよ。
| 命令し、それに従って行動する― |
| ある対象を観察によって、または測定によって記述する― |
| 記述(図面)を元に対象を作る― |
| 経過を報告する― |
| 経過を推測する― |
| 仮説を立て、検証する― |
| 実験の結果を表やグラフで描写する― |
| 物語を作り、読む― |
| 劇を上演する― |
| 輪唱する― |
| 謎を解く― |
| 冗談を作り、話す― |
| 計算の応用問題を解く― |
| ある言語から別の言語へ翻訳する― |
| 願う、感謝する、罵る、挨拶する、祈る。 |
―― 言語の道具の多様性やその使用法の多様性、つまり、語や文の種類の多様性を、論理学者が言語の構造について言ってきたことと比較することは興味深いことである。(そしてまた、『論理哲学論考』の著者が言っていたことと比較することも。)
24. 言語ゲームの多様性に目を向けない人には、例えば「問いとは何か?」と問う傾向がある。 ―― 問いとは、私はこれこれのことを知らない、ということを断言するものだろうか? あるいは、他人が私に・・・と言ってくれることを望んでいる、ということを断言するものだろうか? あるいは、私の不確実な心の状態を記述するものだろうか? ―― それでは「助けて!」という叫びも、記述なのか?
どれほど多様な種類のものが「記述」という一語で呼ばれるか考えてほしい。例えば、体の姿勢の座標による記述、顔の表情の記述、触覚の記述、気分の記述。
確かに、通常の疑問形の代わりに、断言や記述を使うことはできる。例えば「私は・・・かどうか知りたい」とか「私は・・・かどうか疑っている」のように。 ―― しかしそれで異なる言語ゲーム同士を近づけられたわけではない。
そのような変形 ―― 例えば全ての主張文の「私の考えるところ」や「私の信じるところ」のような但し書きで始まる文(従っていわば内面の記述)への変形 ―― の可能性の意味は、別のところ(独我論について論じる箇所 [第402節、第403節] )でより明白に示されるであろう。
25. 人はときに、動物が話さないのは、彼らに精神的な能力が欠如しているからだ、と言う。つまり、「動物は考えない。ゆえに話さない」というわけだ。だが、動物は [考えないから話さないのではなく] まさに話さないのである。より正確には、動物は ―― 原初的な言語形態を無視すれば ―― 言語を使用しないのである。 ―― 命令する、質問する、数える、雑談するなどの言語行為は、行く、食べる、飲む、遊ぶなどの行為と同様に、私たちの自然史に属しているのである。
26. 言語を習得することの本質は、対象の名を言うことにあると考えられている。しかも、人、形、色、痛み、気分、数など [具体的な指示対象のない名] についてもそうなのだ。前に [第15節で] 言ったように、名を呼ぶということは、物に名札を貼ることに似ている。これを、語を使用するための準備と呼ぶことができる。しかし一体、何に対する準備なのか?
27. 人は言う、「私たちは物に名前を付け、そうすることで物について話したり話の中でそれらを呼ぶことができる。」 ―― まるで、名付けという行為において、その後私たちが行うことまで既に与えられているような言い方だ。あたかも「物を名付ける」というただ一つのことが存在するとでも言うようだ。実際には、私たちが文を使ってすることは種々多様である。感嘆詞一つとってもそうだ。全く異なる機能を持った感嘆詞について考えてみよ。水! 先へ! ああ! 助けて! すばらしい! 違う!
これでもまだ君はこれらの語を「対象の名前」と呼ぼうとするのか?
第2節と第8節の言語には、名についての問いは存在しない。この問いと [答えとしての] 直示的説明は、いわば、それ自体一つの言語ゲームである。本来私たちは「これは何と呼ぶのか?」と問う ―― それに対して名前を教えてもらうのだが ―― よう教育され、訓練される。そしてまた、何かについて一つの名前が見出されるという言語ゲームが存在する。つまり、「これは・・・である」と言い、今や新しい名前が使われるようになるのである。(例えば子供は人形を名付け、人形について話し、人形に話しかける。そこですぐよく考えよ。名付けられた人を呼ぶときの人名の使用がいかに特異なものであるかを!)
28. [ある人が言う。] ところで人は、人名、色の名前、物の名前、数詞、方角の名前などを直示定義することができる。二個の木の実を指して「これは『2』と言う」のような数2の定義は全く正確である。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかしいかにして2をそのように定義できるのか? この定義を与えられた人は、それだけではまだ、人が「2」で何を呼ぼうとしているかを知らない。彼は、君が木の実のこの集まりを「2」と呼んでいると理解するかもしれない! ―― 彼がこのように理解することは、 [実際には] おそらくないだろうが、しかし可能性はあることなのだ。彼はまた、反対に私が木の実のこの集まりに名前を付けようとするとき、それを数の名前だと誤解するかもしれない。同様に、私が人名を直示的に説明するとき、それを色の名前、人種の名前、さらには方角の名前だと理解するかもしれない。つまり、直示的定義にはどのような場合でも色々な解釈の仕方があるのである。
29. おそらく人はこう言うだろう。2は「この数は『2』と言う」という直示定義によってのみ定義できる。なぜなら「数」という語は言語、つまり文法のどの場所に私たちが「2」という語を置くかを示すからである、と。しかしこのことは、その直示定義が理解される前に「数」という語が説明されていなくてはならないということを意味する。 ―― この定義における「数」という語は、もちろん、私たちが「2」という語を置く場所を示す。そして私たちは、「この色はこれこれと言う」とか「この長さはこれこれと言う」と言うことで誤解を予防することができる。つまり、時には誤解はそのようにして避けられるのだ。しかし、「色」とか「長さ」という語は、そのようにしてのみ理解されるのか? ―― 今や私たちは、まさにそれらの語を説明するほかない。 ―― 従って、他の語によって! するとこの連鎖における最後の説明とはどんなものだろうか?(「最後の」説明など存在しないとは言わないでほしい。それははちょうど「この通りには最後の家はない。なぜなら、いつでも新しい家を建てることができるから」と言うようなものだ。)
2の直示定義において「数」という語が必要であるか否かは、「数」という語がなければ、2が私の意図とは別様に理解されるかどうかに依存している。そしてこのことは、直示定義が与えられる状況と与えられる相手に依存している。
そして、直示定義を与えられた相手がその説明をどのように「把握」したかは、彼が説明された語をどのように使うかによって示されるのである。
赤くないものを指すことで「赤」という語の説明をすることができるだろうか? これは、ドイツ語のできない人に [ドイツ語の] 「謙虚な」という語を説明すべきときに、尊大な人を指して「この人は謙虚ではない」と言って説明することに似ている。このような説明法は曖昧であると言っても、それでは議論にならない。いかなる説明も誤解されうるからだ。
しかしなお次のように問うことができるだろう。このような [曖昧な] 説明をまだ説明と呼ぶべきなのか? なぜなら、この説明は、記号演算(Kalkül)において、私たちが普通「赤い」という語の「直示的説明」とは異なる役割を演じるのだから。たとえこの説明が実際には同じ結果、同じ作用を教わる側にもたらすとしても、である。
30. 従って人はこういうことができよう。「直示定義は、その語が言語において一般的に果たすべき役割が明らかであれば、語の使用 ―― 意味 ―― を説明する。」それゆえ、誰かが私に色の言葉を説明しようとしているということを私が知っていれば、「これは『セピア』という」という直示定義は、私にその語を理解させる。 ―― そして人がこのように言うことができるのは、様々な問いが「知っている」や「明らかである」という語と結びついていることを知っている場合である。名前について問うことができるためには、既に何かを知っている(ことができる)のでなくてはならない。しかし一体何を知っていなくてはならないのか?
31. ある人が誰かにチェスのキングの駒を見せて「これがチェスのキングだ」と言うとき、彼はそれによって ―― 教わる側が、キングの駒の形についての規定以外に、ゲームの他の規則を既に知っているのでなければ ―― 駒の使用を説明したことにはならない。教わる側が実際の駒を見せられることなくゲームの規則を習得したということは、考えられることである。その場合、ゲームの駒の形は語の響きや字面に対応する。
しかし、ある人が、規則を習ったり規則を言葉に出すことをせずにゲームを習得した、ということも想像可能である。その人は最初とても簡単なボードゲームを観戦することでそのゲームを習得し、だんだん複雑なゲームへと進歩してきたのである。この場合にも ―― 例えば、その人が見知らぬチェスの駒を見せて ―― 「これがキングだ」という説明を与えることができるだろう。この説明もまた、彼に駒の使用を教えるとすれば、その理由は、その駒が置かれる場所が、いわば、既に用意されているからに過ぎない。あるいは別の言い方をすれば、直示的説明が彼に使用を教えるのは、駒の場所が既に用意されているときだけである。そしてこの場合、駒の場所が既に用意されている理由は、説明を与えられた人が既に規則を知っているからではなく、その人が別の意味で既にゲームをマスターしているからなのである。
次のケースを観察せよ。私が誰かにチェスを教えるとする。私はまず、ある駒を見せて「これがキングだ。これはこういう風に動く」と言うことから始める。 ―― この場合、「これがキングだ」(あるいは「これはキングという」)という言葉は、教わる人が既に「ゲームの駒とは何か」を知っているときにのみ、語の説明となる。他のゲームで遊んだり他人のゲームを「理解して」観戦したり ―― そういう経験を教わる側が持っているときも同様である。そういう場合のみ、彼はゲームを習う際、「これは何というのか?」と ―― つまり、キングの駒を何と言うのかと ―― 適切に問うことができるであろう。名前で何をするのかを前もって知っている人だけが、名前について有意義な(sinvoll)問いを発することができると言えよう。
私たちはまた、問われた人が「名前は自分で決めよ」と答えることも想像できる ―― すると質問した人は、全てについて自ら責任を負わねばならないことになるであろう。
32. 見知らぬ土地へ来た人は、時として、自分に与えられる直示的説明を通じてその土地の言語を習う。そして彼は、しばしばその説明を推測するしかない ―― 時には正しく、時には間違って。
さて、私が思うに、アウグスティヌスが描く人間の言語習得の様子は、見知らぬ土地へ来た子供が、まだその土地の言語を理解していない状況と同じようなものである。つまり、子供は既にある言語を話せるが、その土地の言語は話せない、あるいは、子供は既に考えることはできるが、ただ話すことができないかのように、記述されている。そしてアウグスティヌスの言う「考える」とは、自分自身に語るといったことと同じである。
33. しかし、もし人からこう反論されたらどうだろう? 「人が直示定義を理解するためには言語ゲームをマスターしていなくてはならないというのは正しくない。そうではなく、直示定義を理解するためにはただ ―― 当然のことだが ―― 説明者が何を指しているのか、例えばそれが対象の形や色、数などであることを知っている(または推測する)必要があるだけなのだ。」 ―― それでは一体、「形を指す」とか「色を指す」ということの本質は何に存するのか? 例えば、一枚の紙を指してみよ! ―― さらに今度は紙の形や紙の色、そして数(これは滅多にやらないだろうが)を指してみよ! ―― さて、君は指すという行為をどのように行なったのか? ―― きっと、指すたびに違うものを「考えて」いたと言うのではないだろうか。そしてもし私が「指すものを考えることはどのように行なわれるのか」と訊ねたら、君は「色や形に注意を集中させたのだ」と答えるだろう。しかしさらに訊ねたい。注意を集中させることはどのように行なわれるのか、と。
誰かが花瓶を指して「この素晴らしい青をよく見て! ―― 形は問題じゃない」と言ったと想像せよ。あるいは逆に「この素晴らしい形をよく見て! ―― 色はどうだっていい」と言ったと想像してもいい。君がこの二つの要求に従うとすれば、それぞれ異なることをするのは疑いない。だが、色に注意を向けるとき、君は常に同じことをするだろうか? とにかく色々な事例を想像してみよ! 以下に幾つかを挙げてみよう。
- この青はあの青と同じだろうか? 君には違いが分かるか? ――
- 君は絵の具を混ぜて言う。「この空の青とぴったりの色を作るのは難しい。」
- 「晴れてきた。また青い空が見える。」
- 「見よ、この二つの青がいかに異なった印象を与えるか。」
- 「あそこにある青い本が見えるかい? あれを持ってきてくれ。」
- 「この青信号の意味は・・・。」
- 「この青は何ていう名前なの?」 ―― 「インディゴのことかい?」
人は時にまた、形をスケッチしたり、色をはっきり見ないようにまばたきしたりすることによって、形に注意を向けるという行為を行う。そこで私は言いたい。人が「色や形に注意を向ける」間には、ここに挙げたことや類似のことが起きているのである。しかし私たちに「ある人が色や形に注意を向けている」と言わせるのは、これらのことだけではない。ちょうど、駒が盤の上を移動するだけでは、そのこと自体がチェスの指し手にはならないように。 ―― しかしまた、駒を動かすことに付随する指す人の思考や感情において指し手が成立するわけでもない。そうではなく、チェスの指し手が成立するのは、「チェスを一局する」、「チェスの問題を解く」などと呼ばれる状況においてなのである。
34. しかしある人が次のように言うと想像せよ。「私は形に注意を向けるとき、常に同じことをする。輪郭を眼でなぞり、その際・・・と感じる、というように。」さらにその人が別の人に、これら全てのことを経験しながら、ある丸い形をした対象を指して「これは円である」という直示的説明を与えると想像せよ。 ―― しかし、説明を与えられた人が説明者が見た物を見、説明者が感じたことを感じるとしても、それでもなお、与えられた説明を説明者の意図とは別様に解釈することは可能ではないか? つまり、この場合の「解釈」もまた、説明された語をいかに使用するか、例えば「円を指せ!」という命令を受けるとき何を指すか、ということにおいて成立するのである。 ―― なぜなら、「説明をこれこれと思う」という表現も「説明をこれこれと解釈する」という表現も、説明を与えることと聞くことに付随する過程を表しているわけではないからである。
35. 確かに、形などを指すことに付随する「特徴的な経験」と呼びうるものが存在する。例えば、指す際に指や眼で輪郭をなぞることがそうである。 ―― しかしこのことが私が「形を意味する」全ての事例において起こるということはありえないし、他のこれとは違う特徴的な過程が全ての事例において起こるということも、それと同じぐらいありえない。 ―― しかしまた、全ての事例において再現される特徴的な過程があったとしても、私たちが「彼は形を指しているのであって、色を指しているのではない」と言うか否かは、状況 ―― つまり指示の前後に起こること ―― 次第なのである。
というのも、「形を指す」とか「形を考える」などの言葉は、(あの本ではなく)「この本を指す」とか「机ではなく椅子を指す」などの言葉とは異なる使われ方をするからである。 ―― このことを理解するには、私たちが「この物を指す」とか「あの物を指す」という語の使用を習う仕方と、「形ではなく色を指す」とか「色を考える」などの語の使用を習う仕方がいかに異なるものであるかを考えるだけでよい。
先に述べたように、幾つかの事例、特に「形を」あるいは「数を」指示する際には、それに特徴的な体験と指示の種類がある。 ―― それらは形や数が「考えられる」とき、しばしば(いつもではない)再現されるがゆえに「特徴的」である。しかし君はまた、ゲームの駒を [ただの木片としてではなく] ゲームの駒として指すことに特徴的な体験をも知っているか? [知らないであろう。] だがそれでも人は「私は、私が指しているこのゲームの駒を、特定の木片ではなく、『キング』だと考える」と言うことができる。(再認、希望、想起などについても同様である。)
36. そして私たちはここで、幾千もの似たような事例において私たちが行うことをしている。私たちは、(例えば色を指すことに対する)形を指すと呼ばれる一つの身体的行為を挙げることはできない。それゆえ、この「形を指す」という言葉に対応するのは一つの精神的活動であると言う。
私たちの言語が私たちに身体を推測させるところで、しかし身体が存在しない場合、私たちはそこに精神が存在すると言いたくなるのだ。
37. 名前と名付けられた物との関係はどのようなものだろうか? ―― さて、それは一体何であるのか? 第2節の言語ゲーム、あるいは別の言語ゲームを見よ! そうすれば、それらの言語ゲームにおいてこの関係が例えば何において成立しているかを見ることができる。この関係は多くの異なるものの下に成立しているが、また、名前を聞くと名付けられた物の像が心に浮かぶということにおいても成立している。この関係はまた、名付けられた物の名前が書かれることや、名付けられた物を指示する際にその名前が発せられることにおいても成立している。
38. しかし、例えば第8節の言語ゲームにおける「これ」という語や「これは・・・という」という直示的説明における「これ」という語は一体何を名指しているのか? ―― もし混乱に陥りたくないのなら、これらの語が何かを名指しているとは言わないのが一番よい。 ―― だが奇妙なことに、かつては「これ」という語こそが本来の名前であると言われていた[6]。普通私たちが「名前」とよぶものは、従って、不正確で近似的な意味でのみの名前だというわけである。
この奇妙な考えは、いわば、私たちの言語の論理を洗練しようとする傾向から湧き起こってくるものである。この考えに対する本来あるべき回答は、「名前」という語で私たちが呼ぶのは、実は非常に様々な語であるというものだ。「名前」は、ある一つの語の使用の異なる多くの種類 ―― それらは様々な仕方で互いに類似している ―― を特徴付ける語である。だがこのような使用の種類の中に「これ」という語の使用は含まれていない。
私たちがしばしば、例えば直示定義において名付けられる物を指しながらその名前を発するということは、確かに真実である。そして私たちは同様に、例えば直示定義においてある物を指しながら「これ」という語を発する。つまり「これ」という語と名前はどちらも、文という関連(Satzzusammenhang)の同じ箇所に現れる[7]。しかし名前に特徴的なことは、まさに名前が「これはNである」(または「これはNという」)のように直示的に説明されるという点である。翻って、私たちは「これ」という語に対してまで、「これは『これ』である」とか「これは『これ』という」のような [直示的]説明をするだろうか?
「これ」という語が直示的に説明されるという考えは、名付けを、いわば、オカルト的な過程とみなす考え方と関係している。その考え方によれば、名付けは語と対象の奇妙な結合としてみなされる。 ―― そしてこの奇妙な結合は、哲学者が名前と名付けられた物との関係を探り出そうとしてある対象を見つめ、その名前や「これ」という語を何度も繰り返すときに実際に生じるのである。というのも、哲学的問題は言語がその機能を停止しているときに生じるからである。そしてその場合私たちは確かに、名付けとは、対象に洗礼を施すことさながらの奇妙な精神的活動であると想像することができる。そしてまた私たちは、「これ」という語を対象に対して言い、それによって当の対象に話しかけることもできる ―― これが、哲学をするときにだけ起こる、何とも奇妙な「これ」という語の使用である。
「これは青い」という言葉が、あるときは人が指す対象についての言明を意味し、またあるときは「青い」という語の説明を意味するということはいかにして起こるのだろう? 後者の場合、「これは青い」という言葉は本当は「これは青という」を意味している。 ―― すると、「である」という語は、あるときは「~という」を意味し、「青」という語は「『青』」を意味し、またあるときは、「である」という語はそのまま「である」を意味しうるのだろうか?
あるいはまた、報告を意味していたことから、ある人が語の説明を引き出すということも起こりうる。[ウィトゲンシュタインによる余白への書き込み:ここには重大な迷信が隠されている。]
私は「ブブブ」という語によって、「雨が降らなければ私は散歩に行くだろう」を意味することができるだろうか? ―― 私は、言語においてのみ、何かで何かを意味することができる。このことが示すことは明らかだ。つまり、「意味する」という語の文法は、「何かを想像する」という表現などの文法とは異なるということである。
39. しかしなぜ人は、この明らかに名前ではない「これ」という語を名前にしようと考えるのか? ―― まさにそれが名前ではないからである。なぜなら、通常名前と呼ばれるものに対して反対したいと思うからである。その反論はこう表現できる。「名前とは本来、単純なものを表すものでなければならない。」そして人はこの主張を次のように根拠付けるかもしれない。通常の意味での固有名(Eigenname)としては、例えば「ノートゥング」という剣の名前がある。ノートゥングという剣は幾つかの部分がある特定の仕方で組み合わされてできている。もし各部分が異なる仕方で組み合わされたとしたら、ノートゥングは存在しない。さてしかし、ノートゥングが完全な姿で存在していようとすでに破壊されて粉々になっていようと、「ノートゥングは鋭い刃を持つ」という命題は明らかに意義を持つ。もしノートゥングがある対象の名前であるとすれば、ノートゥングが破壊されればこの対象ももはや存在しないことになる。するとその場合、「ノートゥング」という名前に対応する対象は存在せず、この名前は意味を持たないことになり、「ノートゥングは鋭い刃を持つ」という命題の中には意味を持たない語が含まれることになる。従ってこの命題はナンセンスであるという結論に達する。しかしこの命題は [ノートゥングが破壊されたとしても] 意義を持つ。だから、この命題を構成する各語は常に何らかの対象に対応していなくてはならない。以上のことから、「ノートゥング」という語は意義の分析によって消え去り、その代わり、 [ノートゥングを構成している] 複数の単純なものを名指す語が登場しなければならない。これらの語を本来の名前と呼ぶことは全く正当である。
40. まず、前節のような思考過程の問題点を述べよう。それは、もし語に何も対応していなければその語は意味を持っていないという考えである。 ―― ここで、もし「意味」という語によってある語に「対応する」ものを表すなら、「意味」という語の使い方を間違えているのだということを確認しておくことが重要である。つまりその場合、名前の意味と名前の担い手(Träger)が混同されているのである[8]。 [例えば] N.N氏が死んだとしたら、その名前の担い手が死んだと言うのであって、その名前の意味が死んだとは言わない。「語の意味が死ぬ」と言うことはナンセンスなのだ。なぜなら、 [もしそのような言い方が正しいとすれば、名前の意味はN.N氏が死ねばもはや存在しなくなり、] 名前は意味を持つことをやめ、「N.N氏が死んだ」という文は意義を持たなくなるだろうから。
41. 第15節において、私たちは第8節の言語ゲームに固有名を導入した。そこで「N」という名前の付いた道具が壊れたと考えよ。Aはそのことを知らずにBに「N」という記号を与える。この場合、「N」という記号は意味を持つだろうか、それとも持たないだろうか? ―― この記号を与えられたとき、Bはどう反応すべきなのだろうか? ―― 私たちはそれについて何も取り決めていなかった。それゆえ人はこう問うかもしれない。「Bは何をするのだろう?」 ひょっとすると、Bは途方に暮れて立ち尽くすかもしれない。あるいはAに壊れた破片を指すかもしれない。そのとき人は、「N」は無意味(bedeutunglos)になってしまった、と言うかもしれない。そしてこの表現は、私たちの言語ゲームにおいて記号「N」はもはや使用されなくなったことを意味するであろう。(私たちが「N」に新しい使用を与えてやれば話は別だが。)また理由は何であれ、「N」という名前の道具に別の名前が付与され、言語ゲームにおいてそれ以上「N」が使われなくなった場合においても、やはり「N」は無意味(bedeutunglos)になるであろう。 ―― しかし、AがBに壊れた道具の名前を与えたとき、Bはそれに対する答えとして首を振らなくてはならないという取り決めを作ることもできる。 ―― この取り決めがあれば、たとえ道具がもはや存在しなくても、「N」は命令として言語ゲームに受け入れられるのであり、記号「N」は担い手が存在しなくなっても意味を持つのである。
42. しかし例えば、今のゲームにおいて決して道具としては使用されない語も意味を持っているのだろうか? ―― そこで、「X」をある記号として、AがBにこの記号を与えるとしよう ―― この場合、「X」はこの言語ゲームに受け入れられるだろうし、Bはそれに答えて首を振るなどしなくてはならないであろう。(これを、AとBの間の一種の冗談として考えることができよう。)
43. 「意味」という語が用いられる ―― 全ての場合ではないによせ ―― 幾つかの場合について、この語を「言語における語の使用である」と説明することができる。
だが人はときに、語の担い手を指すことによって意味を説明するのである。
44. 私たちは [第39節で] たとえノートゥングが既に破壊されていたとしても、「ノートゥングは鋭い刃を持つ」という命題は意義を持つ、と言った。その理由は、担い手不在の名前であっても言語ゲームにおいて用いられるからである。しかし私たちはまた、担い手が存在するときにのみ用いられる名前(すなわち、私たちが確実に「名前」と呼ぶであろう記号)を使用するような言語ゲームを考えることもできる。それゆえ、指示の身振りを伴なう指示代名詞によって、常に置き換え可能な名前を含む言語ゲームを考えることができる。
45. 「これ」という指示代名詞は、担い手を持たない使い方が絶対にできない。人は「これが存在する限り、これが単純なものであろうと合成されたものであろうと、「これ」という語も意味を持つ」と言うかもしれない。 ―― しかしだからといって、そのことによって「これ」という語が名前になるわけではない。そうではないのだ。なぜなら、名前は身振りを伴って使われるのではなく、ただその身振りによって説明されるだけだからである。
46. さて、本来名前は単純なものを名指すのだという考えの背景にある事情はどのようなものだろう? ソクラテスは(『テアイテトス』 [第39節] において)こう言っている。「もし私の勘違いでなければ、私は数人の人から、私たちや他の全てのものを合成している原要素(Urelement) ―― こう表現すべきもの ―― についてはどのような説明も存在しない、ということを聞いた。なぜなら、それ自体において存在するものについては、ただ名前によって名指すことができるだけであり、それ以外の規定の仕方、例えば『それは存在する』とか『それは存在しない』のような言い方はできないからだ、と。(中略)それ自体において存在するものは、他のあらゆる規定を抜きにして名指すしかない。それゆえ、原要素について説明的に語ることはできない。なぜなら原要素にはただの名指し以外に何も存在しないからだ。原要素はただ名前だけを持っている。だがこのような原要素から合成されたものは、それ自身が合成的な構成物であるように、その名前もまた原要素の名前から合成された構成物であり、この構成物については説明的に語ることができる。というのも、説明的に語ることの本質は、名前を合成することにあるからだ。」
ここで言われている原要素がすなわちラッセルの「個体」(individual)であり、私の「対象」(Gegenstand)だったのである。(『論考』を参照。)
47. ところで、実在を合成している単純な構成要素とは何か? ―― 椅子の単純な構成要素とは何か? ―― 椅子を組み合わせるのに使われている木片だろうか? あるいは分子や原子だろうか? ―― 「単純」とはすなわち合成されていないことである。だからここでの問題は、「合成されている」とはいかなる意味において「合成されている」ことなのか、ということである。「絶対的に単純な椅子の構成要素」について語ることは意義を欠いているのだ。
あるいはこう問うてみよう。「この木やこの椅子の視覚像は複数の要素から成り立っているのか? もしそうなら、その単純な構成要素とはどの要素のことなのか?」 多色刷りの絵は色による一種の合成である。あるいは複数の直線から成るジグザグの図形も一種の合成である。そしてまた、ある曲線は上昇する部分曲線と下降する部分曲線から合成されていると言うこともできる。
もし私が誰かに「私の眼の前に見えるものは合成されている」と言い、それ以上の説明をしなければ、相手は次のように問う権利を持っている。「君は『合成』ということで何を意味しているのか? それは実に様々なことを意味しうるじゃないか!」 ―― 「君が見ているものは合成されているか?」という問いは、どのような種類の合成物が、つまり「合成された」という語のどのような使用が問題であるのかが事前に確定されていれば、確かに意義を持つ。もし「人が幹だけではなく枝も見ている場合、その木の視覚像は『合成されている』と言わねばならない」ということが [事前に] 確定されているなら、「この木の視覚像は単純か、それとも合成されているか?」 とか「この木の単純な構成要素はどれか?」 という問いは明確な意義 ―― 明確な使用 ―― を持つであろう。そしてこの二番目の問いに対する答えは当然、「枝」ではなく(これは「この場合、単純な構成要素を何と呼ぶか?」 という文法的な問いに対する答えの一つであろう)、個々の枝の記述である。
しかし例えばチェス盤は明らかに絶対的な意味で合成されてはいないだろうか? ―― 君はきっと、チェス盤は32個の白い正方形と32個の黒い正方形の組み合わせだと考えているのだろう。だが例えば、チェス盤は白色と黒色と格子状の枠組みを組み合わせたものだと言うこともできるのではないか? そして全く異なる多様な見方が存在するとすれば、それでも君はまだ、チェス盤は明らかに絶対的な意味で「合成されている」と言うだろうか? ―― ある特定の言語ゲームの外で「この対象は合成されているか?」と問うことは、かつてある若者がしていたことと似ている。彼は幾つかの例文において動詞が能動形で用いられているのか受動形で用いられているのかを述べねばならないときに、 [動詞を文から切り離して] 例えば「眠っている」という動詞が能動的な何かを意味しているのか受動的な何かを意味しているのかということに頭を悩ましていたのである。「合成された」という語は(従って「単純な」という語も)私たちによって無数の異なった、しかし相互に関連した仕方で使われる。(チェスの升目は単純なのか、それとも純粋な白と純粋な黄色から構成されているのか、あるいは、虹の色から構成されているのか? ―― この2cmの線分は単純なのか、それとも1cmの線分二つから構成されているのか? しかしなぜ、3cmの線分と逆向きにおかれた1cmの線分から構成されているとは言わないのか?)
「この木の視覚像は合成されているか? そしてもしそうなら、その構成要素はどれなのか?」という哲学的問いに対する正しい答えはこうである。「それは君が『合成された』という語で何を理解しているかによる。」(そしてもちろんこれは答えではない。問いを差し戻したのである。)
48. 第2節の方法を『テアイテトス』における描写に応用してみよう。つまり、ソクラテスの描写が実際に有効であるような言語ゲームを考察するのだ。その言語は、ある平面上の色のついた正方形の色々な組み合わせを描写することに使われる。これらの正方形はチェス盤のような形をした複合体を形成し、正方形の色は赤、緑、白、黒である。この言語における語は(色に対応した)「R」、「G」、「W」、「S」の4つがある。そして文はこれらの語の羅列である。語は順番に連なって正方形の配置を記述する。
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
従って例えば、「RRSGGGRWW」という文は次のような正方形の配置を記述する。
この場合、文は、要素の複合体に対応した名前の複合体である。原要素は色のついた正方形一つ一つである。「しかしこれらの正方形は単純だろうか?」 ―― この言語ゲームにおいて、何をもって正方形より自然に「単純なもの」と呼ぶべきか、私は知らない。状況が異なれば、私はこの色のついた正方形を「合成されたもの」と呼ぶこともあるだろう。その場合、正方形は例えば二つの長方形から合成されているとか、色と形から合成されていると言われる。だが合成という概念はまた、ある平面を、それをすっぽり覆うより大きな平面と、そこから差し引かれるはみ出した平面によって「合成されている」と言われる程度に拡張することもできよう。これを力の「合成」とか線分の外側の点による「分割」 [数学における外分] と比較せよ。こうした表現が示すのは、様々な状況において、私たちは小さいものを大きいものの合成の結果として把握し、大きいものを小さいものの分割の結果として把握する傾向がある、ということである。
ところで私は、私たちが「RRSGGGRWW」とうい文によって記述する図形は4つの要素から成り立っていると言うべきか、9つの要素から成り立っていると言うべきかを知らない! さて、この文は [R, S, G, W という] 4つの文字 [のタイプ] から成り立っているのか、それとも [R, R, S, G, G, G, R, W ,W という] 9つの文字 [のトークン] から成り立っているのか? ―― そしてこの命題の要素はどちらなのか? ―― 文字のタイプなのか、それとも文字 [のトークン] なのか? どちらの答えを選ぶにせよ、特殊な場合にだけ誤解を避けられるならば、どうでもよいことではないか?!
49. ところで、私たちは要素について説明(すなわち記述)することができず、ただ名付けることしかできない、とはどういうことだろう? これは例えば、もし複合体がただ一つの正方形から成る場合には、その複合体の記述は単にその正方形の名前になる、ということになるだろう。
そこで次のように言うことができよう ―― もっとも、こう言うと簡単に種々の哲学的迷信へと人々を導いてしまうのだが ―― 「R」や「S」などの記号は、あるときは語であり、またあるときは文である、と。 [実際には] これらの記号が「語であるか文であるか」はそれが言われたり書かれたりする状況に依存するのである。例えばAがBに対して、色のついた正方形から成る複合体について記述せねばならない場合に、「R」という語だけを用いるなら、その「R」は記述 ―― つまり文 ―― であると言うことができる。しかし例えばAが語とその意味を憶えている場合や、あるいは他人に語の使用を教えるために直示的教示において語を発する場合には、私たちはそれらの語が文であるとは言わないであろう。こうした状況では、「R」という語は記述ではない。そのとき、人は「R」によって要素を名指すのである。 ―― しかしだからといって、要素を名指すことしかできないと言うのは奇妙な話であろう! 名指しと記述は決して同一の平面上にはない。つまり、名指しは記述の準備作業なのである。名指しは決して言語ゲームにおける指し手ではない。 ―― ちょうど、チェスの駒を盤上に置くことがチェスにおける指し手ではないのと同じように。 [それゆえ] 事物を名指すことでは、まだ何も行なわれていないと言うことができるのだ。事物はゲームの外ではいかなる名前も持たない。これはまた、フレーゲが [『算術の基礎』の序文で] 「語はただ文という関連においてのみ意味を持つ」と言うことで意味していたことでもある。
50. さて、要素について、「それは存在するとも存在しないとも言うことができない」と言うことは一体何を意味しているのか? ―― ある人はこう答えるかもしれない。「私たちが『存在する』とか『存在しない』と言うことのできるもの全てが、要素間の様々な結合が成立するかしないかということであるならば、要素の存在(非存在)について云々することには意義がない。ちょうど、私たちが「破壊」することのできるもの全てが諸要素を分離することであるならば、要素の破壊について云々することに意義がないのと同じである。」
また次のように言いたい人もいるだろう。「要素について存在すると言うことはできない。なぜなら、もし要素が存在しなければそれを名指すこともできないのであり、従ってそれについて語ることも当然できないからだ。」 ―― さてこれと類似の事例を考察してみよう! 世界には、これは1mの長さであるとか1mの長さではないと語ることのできないものが一つだけある。それはパリにあるメートル原器である。 ―― もちろん、このように言うことで私たちはメートル原器に何か特殊な性質を与えたわけではない。ただ、メートルという尺度を使った単位のゲームにおけるメートル原器固有の役割を特徴付けただけである。 ―― これと同じように、色見本もパリに保存されていると想像してみよう。すると私たちは、「セピア」という色について説明する場合、それは真空状態で保存されているセピア原器のことであると言うだろう。その場合、このセピア原器について、「これはセピア色だ」とか「これはセピア色ではない」と語ることには意義がない。
これはつまり、色見本は、私たちが色についての言明を行うときに用いる言語の道具である、ということである。色見本は、ゲームにおいて表現の対象ではなく、表現の手段なのである。 ―― 全く同様のことが、第48節における「要素」にも当てはまる。つまり、要素を名指して「R」という語を発するとき、私たちはその物に言語ゲームにおける一つの役割を与えたのである。今や、それは表現の手段となったのだ。そして「もしそれが存在しなければ、それは名前を持つことはできないであろう」と言うことは、「もしこの物が存在しなければ、私たちはゲームにおいてそれを使うことはできないであろう」と言うことと全く同じことなのである。 ―― 存在しなければならないと思われたものは、言語に属しているのである。それは私たちのゲームにおける範例(Paradigma)なのであり、他の物は [全て] この範例と比較される。この範例の確認は、重要な確認であると言えるだろう。だがこれはあくまでも私たちの言語ゲームにおける確認、私たちが用いる表現方法に [だけ] 該当する確認であるという点に注意が必要である。
51. 第48節の言語ゲームの描写において、私は、「R」、「S」などの語は正方形の色に対応すると言った。ところでこの対応は、何において成立するのか? つまり、いかなる意味でこれらの記号が正方形の色に対応すると言うことができるのか? 第48節の説明では、「R」や「S」といった記号と私たちの言語の語(「赤」とか「黒」といった色の名前)との間にある関係を作り上げたにすぎない。 ―― 第48節における記号の使用は、別の仕方、つまり範例を直示的に指示することによって習得されるということが前提されていたのだ。そう、確かにその通りである。だがそれなら、「言語の実践において、ある要素が記号に対応する」と言うことはどのようなことなのか? ―― それは、色のついた正方形の複合体を記述する人が、赤い正方形があるところでは常に「R」と言い、黒い正方形のあるところでは常に「S」と言う、ということか?しかし黒い正方形を見たときに、誤って「R」と言ってしまったらどうだろう? ―― それが誤りであると判断する規準は何か? ―― それとも、「R」が赤い正方形を名指すということは、「R」という記号を使うとき、それを使う人間の心のうちに常に赤い正方形が思い浮かぶということなのか? この問題をより明確に見るためには、無数の類似の事例と同様に、私たちの眼前で起きていることの詳細を把握しなくてはならない。起きていることを仔細に観察しなくてはならない。
52. もし私が、ネズミはネズミ色のゴミから自然発生する、と仮定したいのなら、どうしたらネズミは自らをそのようなゴミの中に秘めることができるのか、どうしたらネズミはゴミから発生することができるのか、などといったことを解明するためにこのゴミを探究することは、正しいことである。 しかし、私が「ネズミはゴミからは生まれない」と確信している場合には、おそらくこの探究は余計なことである。
しかし私たちがまず理解するよう学ばねばならないことは、哲学においてそのような探究に反対するものは何か、ということである。
53. さて、第48節の言語ゲームには、私たちが「ある記号はこれこれの色の正方形を名指す」と言うような様々な場合、様々な可能性がある。例えば、この言語を用いる人間が記号をこれこれの仕方で使うよう教え込まれたということを私たちが知っている場合がそうである。あるいは、この記号があの要素に対応するということが表の形で記録されている場合や、言語を教える際、またはある論争に決着を着ける際にこの表が引き合いに出される場合もそうである。
だが私たちはまた、そのような表が言語の使用における道具であるような場合も想像できる。その場合、ある複合体の記述は次のようにして行なわれる。複合体を記述する人は、 [記号と要素の] 対応表を持ち歩いていて、まずその表の中から複合体の要素と一致する要素を探し出す。次に、その要素と対応する記号へと指でなぞるのである。(そしてこの記述を与えられた人は、記号から表を逆に辿ることで、色の付いた正方形の像へと翻訳することができるのである。) [それゆえ] この表は、普通ならば記憶とか連想が担うであろう役割を代わりに引き受けているのだと言うことができよう。(「赤い花を持ってこい!」という命令を果たすとき、普通は、わざわざ色見本から「赤」という色を探しだし、その色と一致する花を持ってくる、などという手間をかけたりしない。しかし、仮にある特定の [微妙な] 色合いの赤を選ぶ、または調合することが重要な場合であれば、色見本や表に頼ることになるであろう。)
こうした表を言語ゲームの規則の表現と呼ぶならば、私たちが言語ゲームの規則と呼ぶものは、当の言語ゲームにおいて実に様々な役割を引き受けることができるのである。
54. それでは、あるゲームが一定の規則に従って行なわれる場合とは、どのような場合であるか考えてみよ!
規則はゲームを教える際の補助手段でありうる。教わる側は規則を知らされ、それを適用することを練習する。 ―― また、規則はゲームの道具そのものでもありうる。 ―― はたまた、ゲームを教える際にもゲーム自体を行う際にも規則は使用されず、規則記号の形として記録されてもいないこともありうる。人は、他人がゲームを行う様子を観察することによってゲームを習得する。だが私たちは、「ゲームはこれこれの規則に従って行なわれている。なぜなら観察者はゲームにおける実地適用からその規則をゲームの実践から ―― ちょうどゲームの行動から自然法則を読み取ることができるように ―― 読み取ることができるから」と言う。 ―― しかし、この観察者は、ゲームの実演者の正しい行為と間違った行為をいかにして区別するのか? ―― 実演者の振舞いには、それを見分けるための指標があるのである。例えば、いい間違いを訂正する人に特徴的な振舞いについて考えよ。たとえ私たちがその人の言語を理解しなくとも、彼が訂正を行なったときにそれと気付くことは可能であろう。
55. [ある人が言う。] 「名前が名指すものは破壊不可能でなくてはならない。なぜなら、人は破壊可能なものは全て破壊されつくした状態を記述できるのでなくてはならず、その記述においては様々な語が存在するであろうから。それらの語に対応するものが破壊不可能でなければ、この記述に現れる語は [対応するものを失って] 意味を持たなくなってしまう。」 私は自分が座っている枝を切断することは許されない、というわけだ。
さてこれに対し、すぐにこう言って反論する人がいるかもしれない。「確かに、破壊可能なものが全て破壊され尽くされた状態の記述は可能でなくてはならない。 ―― しかし、その記述における語が対応し、従って破壊不可能なものは、その記述が真である場合に、語に意味を与えるものである。 ―― それがなければ語は意味を持たないのだ。」 ―― しかし、ある人間は確かにある意味でその人の名前に対応するものではないのか。だが彼は破壊可能である。そしてたとえ担い手である彼が破壊されたとしても、彼の名前が意味を失うことにはならない。名前に対応し、それがなくては名前が意味を持たないものとは、例えば、言語ゲームにおいて名前と結びついて用いられる範例である。
56. しかし、このような見本が属していない言語の場合はどうであろうか? 例えば、ある語が指す色を私たちが憶えている場合はどうか? ―― あるいは次のように言う人がいるかもしれない。「私たちがそれを憶えているということは、その語を言うときに色が念頭に浮かぶということである。従って、私たちがいつでもその色を思い出すことが可能でなくてはならないのならば、その色自身は破壊不可能でなくてはならない。」 しかし、その思い出した色が正しいかどうかを判断する規準として、一体何を見ればいいのだろう? ―― 記憶の代わりに見本を使う場合なら、「見本の色が変わった」と言うとき、場合によっては記憶をその規準として用いるであろう。しかしまた場合によっては(例えば)記憶像が次第に薄れていくことも、私たちは語りうるのではないか? そして私たちは、見本と同程度に記憶にも頼るのではないか? (なぜなら人は「もし私たちが記憶を持っていなければ、見本に頼るだろう」と言いたいであろうから。) ―― あるいは見本の代わりに化学反応に頼っても構わない。例えば、化学物質XとYが結合するときに見られる「F」という色を塗らなくてはならない、という状況を想像してみよ。 ―― さて、ある日、その色がいつもより明るく見えたとしよう。すると君はことによると「私は間違っているに違いない。この色は確かに昨日と同じ色である」と言うのではないか? この事例が示すのは、私たちは、記憶が語ることを常にそれ以上控訴することのできない絶対の権威として用いているわけではない、ということである。
57. [ある人が言う。] 「赤い物を壊すことはできる。しかし赤 [そのもの] を壊すことはできない。だから、『赤』という語の意味は、赤い物が存在するか否かには依存しない。」 確かに、(範例ではなく色としての)赤について、引き裂くとか砕くと言うことには意義がない。だが私たちは「赤が消えた」とは言わないだろうか? そして君は、たとえもはや赤い物が存在しなくなったとしても、私たちは赤い色を念頭に思い浮かべることができる、などという考えに固執してはならない! このような考えは、もはや赤い物が存在しなくなったとしても、なお赤い炎を生じさせる化学反応は存在する、などと言おうとするようなものだからである。 ―― なぜなら、もし君がもはや赤い色を思い出すことができなくなったとしたらどうであろう?「赤」という名を持つ色がどのような色であったかを忘れてしまえば、私たちにとって「赤」という名前は意味を失う、すなわち、「赤」という名前を使った特定の言語ゲームを、もはや行うことができなくなるのである。この状況は、かつて私たちの言語の道具であった範例がもはや使われなくなった状況と対比することができる。
58. [ある人が言う。] 「私は、『Xは存在する』という語の結合において成立しえないものだけを『名前』と呼ぼう。 ―― 『赤は存在する』と言うことはできない。なぜなら、もし赤が存在しなければ、そもそもそれについて語ることはできないのだから。」 ―― この意見をより正しく表現するとこうなる。いわく「もし『Xは存在する』という命題が『X』は意味を持つということと同じことを意味するべきであるならば、 ―― 『Xは存在する』はXについての命題ではなく、私たちの言語使用、すなわち、『X』という語の使用についての命題なのである。」
私たちは、「赤は存在する」という命題は意義を持たないと言うことで、まるで赤の本性について何事かを述べたかのように思う。何事か、というのは要するに、赤はまさに「それ自身において」存在している、ということである。これと同じ考え ―― 「赤は存在する」という命題は意義を持たないと言うことは、赤についての形而上学的言明である、という考え ―― は、「赤は非時間的存在である」とか、あるいはもっと強烈な「赤は破壊することができない」という言明の中にも表現されている。
だが本来私たちがやりたいと思っていたことは、ただ、「赤は存在する」という表現を、まさに「赤」という語は意味を持つという言明として理解することなのである。あるいはより正しく言うならば、「赤は存在しない」という表現を「『赤』という語は意味を持たない」という言明として理解することなのである。私たちは、「赤は存在する」という表現が「『赤』という語は意味を持たない」ということを語ると言いたいのではなく、ただ、もしこの表現が意義を持つならば、それは「『赤』という語は意味を持つ」ということを語らねばならない、と言いたいだけなのである。しかし「赤は存在する」という表現が「『赤』という語は意味を持つ」ということを語ろうと試みると自己矛盾に陥る。 ―― なぜなら、赤は「それ自体において」存在するからだ、と。しかし矛盾は、ただ、「赤は存在する」という命題がまるで色 [そのもの] について語っているように見えるという点に存在するに過ぎない。実際は、この命題は「赤」という語の使用についてこそ語るべきものなのである。 ―― 実際、私たちは非常に頻繁に、ある特定の色が存在すると言い、その場合この言明は、その色を持つ何物かが存在している、ということと同義なのである。だから「赤は存在する」という表現が「赤い色を持つものが存在する」という表現に比べて正確さを欠いているわけでではない。特に、「色を持っているもの」が物理的対象ではない場合はそうである。
59. [ある人が言う。] 「名前が名指すのは、ただ現実の要素だけである。それは破壊することができない。それは決して変化することがない。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] だがそれは一体何なのか? ―― [ある人が言う。] 私たちが今の命題を語ったとき、既に念頭に浮かんだではないか! 私たちは既に、非常に明確な表象、私たちが用いようとする明確な像について語ったのだ。なぜなら、経験が私たちにそのような要素を示すのではないのだから。 [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし私たちは、合成物(例えば肘掛け椅子)の構成要素を見ることもあるのだ。私たちは肘掛けは肘掛け椅子の一部分であると言う。しかし肘掛け自身もまた、様々な木材が組み合わされてできている。その反対に、椅子の脚は単純な構成要素の一例である。あるいはまた、構成要素はなんら変化しないまま、全体が変化する(壊れる)ということも、私たちは見るのである。私たちはこれらを素材にして、現実の像を作るのである。
60. さて、私が「ほうきがそこの角に立て掛けられている」と言うとき、 ―― これは本当は、ほうきの柄とブラシについての言明なのだろうか? そうであるか否かは措くとして、ほうきの状態についての言明を、柄の状態ついての言明とブラシの状態についての言明によって置き換えることは可能であろう。そして後者の言明が、前者をさらに分析した形式[9]になっていることも確かである。 ―― だがなぜ私は後者の形式を「より分析された」と呼ぶのか? ―― もしほうきがそこにあるのなら、柄とブラシもまたそこにあり、両者がある一定の位置を占めていなくてはならないからである。そしてこのことは第一の言明においては、いわば、命題の意義の中に隠されており、それは分析された命題において、初めて表明されるものである、というのだ。すると、「ほうきがそこの角に立っている」ということを語る命題は、本来は「柄とブラシがそこにあり、かつ、柄がブラシにささっている」ということを語るのものなのだろうか? もし誰かにこのことを訊ねたなら、きっと彼は「私は『ほうきがそこに立っている』と言うことで、別に柄やブラシについて考えていたのではない」と答えるだろう。そしてこれは正しい答えであろう。彼は実際、 [ほうきについて語りたかったのであって] 柄やブラシについて語りたかったわけではないのだから。君が誰かに「ほうきを持ってきてくれ!」と言う代わりに ―― 「柄と、それにささったブラシを持ってきてくれ!」と言ったと想像せよ。 ―― 回答は「君はあのほうきのことを言っているのかい? それならなぜそんな奇妙な言い方をするのか?」というものではないだろうか。 ―― このとき、命令された人は、「ほうきを持ってきてくれ!」という文よりも、「柄と、それにささったブラシを持ってきてくれ!」という文の方をよりよく理解するであろうか? ―― この分析された文は、普通の文と同じ程度のことを成し遂げるのである。ただ、やり方が普通より回りくどいだけである。 ―― ある人に、多くの部分から成る合成物を持ってくる(または動かす、運ぶ)よう命令を与える言語ゲームを想像せよ。すると、このゲームのやり方には次の二通りがある。
(a)合成物そのものが、第15節のゲームと同様に名前(ほうき、椅子、机など)を持っている場合。
(b)名前を持っているのは合成物の各部分だけで、合成物は部分の名を利用することで記述する場合。
―― さて、(b)における命令は、一体いかなる意味で(a)における命令の分析された形式だと言えるのだろう? (b)における命令は、(a)における命令の中に隠されており、それが分析によって取り出されるとでも言うのか? ―― 確かに、人が柄とブラシを分離すれば、ほうきは分解される。しかし、だからといって、「ほうきを持ってきてくれ!」という命令もまた、「柄を持ってきてくれ!」という命令と「ブラシを持ってきてくれ!」という命令に分解されるのか?
61. [ある人が言う。] 「だが、(a)の命令も(b)の命令も同じことを言っているのだという点は、君も否定しないだろうね? それなら、(b)の命令は(a)の命令の分析された形式だと言わずして、一体何と言うのかね?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに、私も、(a)の命令と(b)の命令が同じ意義を持っているということは認めてもよい。あるいは先の言い方をするなら、両者は同じことを成し遂げる。つまり、(a)のやり方である命令が私に示され、「この命令と矛盾する(b)の命令はどれか?」と訊かれたなら、私はその問いに対しこれこれであると答える。しかしだからと言って、そのことで「同じ意義を持つ」とか「同じことを成し遂げる」という表現の使用について、一般的な合意に達したわけではない。すなわち依然としてこう問うことができる。「どのような場合に私は、『これは同一のゲームの二つの異なる形式に過ぎない』と言うことができるか?」と。
62. 例えば、ある人に(a)の命令と(b)の命令が与えられる場合、彼は要求された物を持ってくる前に、どの名前がどの像に相互に対応しているかを示す表を調べなければならない、という状況を考えよ。さて、(a)の命令に従うときと、それに対応する(b)の命令に従うときとでは、彼は同じことをするのだろうか? ―― そうとも言えるし、違うとも言える。君は「どちらの命令も肝心な点は同じである」と言うことができるし、私もこの場合はそれに同意しよう。 ―― しかし、命令の「肝心な点」と呼ぶべきものが、常に明らかであるわけではない。(同様に、人はある物について、「これの機能はこれこれである」と言うことができる。これはランプであり、部屋の中を照らすことはこの物にとって本質的なことであるが、部屋を飾ったり空間を満たしたりすることは、非本質的なことである、という具合に。しかしだからといって、本質的/非本質的の区別が常に明確に行なわれているわけではないのである。)
63. 「(b)における命題は(a)における命題の『分析された』形式だ」という表現を使うことで、私たちはたやすく「この形式の方が基礎的なのだ」とか「この形式にして初めて、(a)の命題で意味されていたことが示される」などといった考えに誘惑されてしまう。例えば私たちは、未分析の形式しか持っていない人には分析が欠けているとか、分析済みの形式を知っている人は、そのことによって全てを知っている、などと考えてしまうのである。 ―― しかし、未分析の形式においては事態の一つの相が失われているのと同様に、分析済みの形式においても、やはり、事態の別の相が失われていると言うことはできないだろうか?
64. 第48節のゲームを変更して、名前は単純な正方形を名指すのではなく、二つの正方形から成る長方形を名指す、としてみよう。例えば、半分赤で半分緑の長方形は「U」、半分緑で半分白の長方形は「V」と呼ばれる、という具合だ。すると私たちは、そのような色の組み合わせの名前は持っているが、個々の色の名前は持っていない人間を考えられるのではないか? 私たちが「この色の組み合わせ(例えばフランスの三色旗)はある全く特別な特徴を持っている」と言う場合について考えよ。
この変更後のゲームの記号は、どのような意味で分析を必要とするのだろうか? ―― そもそも、この言語ゲームを第48節の言語ゲームで置き換えることは、どの程度まで可能なのか? ―― このゲームは、全く別の言語ゲームなのである。たとえ第48節と同系の(verwandt)ゲームだとしても。
65. ここで私たちは、こうした考察の背後に常に控えている一つの大きな問題に直面する。 ―― というのも、人は私に次のように反論できるからである。「君は逃げの手を打っているな! なぜなら、君は考えうる全ての言語ゲームについて語っているが、しかし、言語ゲームの本質については何も語っておらず、ひいては、言語の本質について何も語っていないからだ。君は、これら全ての『言語ゲーム』と呼ばれる過程に共通のもの、『言語ゲーム』を言語、あるいは言語の一部となすものについて何も語っていない。それゆえ君は、かつて『論考』において自身が最も頭を痛めた問題の一部 ―― すなわち、命題の一般形式の探究 ―― に該当する問題に答えずに済まそうとしているのだ。」
[ウィトゲンシュタインが言う。] 実にその通りである。私は、私たちが言語と呼ぶものに共通する何かを挙げる代わりに、次のように言いたい。これら全ての事象が共通に持ち、それゆえに「言語ゲーム」という同じ名前で呼ばれるような、そういう共通項があるのではなく、これらの事象は互いに異なる様々な仕方で血縁関係にあるのである。そしてこの血縁関係 ―― 一つとは限らない ―― のゆえに、私たちはこれら全ての事象を「言語」と呼ぶのである。以下、この点について説明しよう。
66. 例えば、私たちが「ゲーム」と呼ぶ諸過程について考察せよ。つまり、ボードゲームやカードゲーム、ボールゲームや格闘ゲームなどについて。これら全てに共通のものとは何か? ―― 「これらの過程には共通項があるはずだ。そうでなければ、それらは『ゲーム』とは呼ばれないから」と言うのはなしだ。 ―― そうではなく、これら全てに共通のものがあるか否かという点を良く見よ。というのも、君がこれらを観察するなら、全てに共通のものなど何もないということを見出すであろうからだ。代わりに君が見出すのは、類似性や血縁関係であり、しかもそれらは一つの完全な系列を形作っている。繰り返す:考えてはいけない、見よ! 例えば多様な血縁関係を持つボードゲームを見よ。そして次にカードゲームに目を移そう。ここに君はボードゲームとの一致点を多く見出すが、しかしボードゲームに共通であった多くの特徴は消え去り、代わりに別の特徴が現れている。さらにボールゲームに目を移そう。まだ幾らかの共通項は残っているが、多くは失われている。 ―― 「だがそれでもまだ、これらのゲームは「娯楽」という点で共通しているのではないか?」 そう思うなら、チェスを三並べと比較せよ。三並べを娯楽とは言えまい。「しかし、全てのゲームにはプレーヤーの間に勝敗や競争があるのではないか?」 そう思うなら、ペイシェンス [トランプの一人遊び] について考えよ。そこに勝敗はない。ボールゲームの場合なら、確かに勝敗があるが、しかし、子供が壁に向かってボールを投げては受け取るというゲームをしている場合は、勝敗という特徴も消え去る。ボールゲームにおいて熟練と運が果たす役割を見よ。そして、チェスにおける熟練とテニスにおける熟練がいかに異なっているかを見よ。さて今度はダンスゲームについて考えよ。このゲームには確かに娯楽という要素はあるが、いかに多くの他の特徴が消え去ってしまったことか! そしてこのようにして私たちは、膨大な数のゲームのグループを通って行くことができる。色々な類似性が現れては消えていくのを見ながら。
こうした考察から得られる結果はこうである。私たちが見ているのは、多くの類似性 ―― 大きなものから小さなものまで ―― が互いに重なり合い、交差してできあがった複雑な網状組織なのである。
67. 私は、この類似性を特徴付けるのに「家族的類似性(Familienähnlichkeiten)」という言葉以上に適切なものを知らない[10]。なぜなら家族の構成員の間に成り立つ様々な類似性 ―― 体格、顔つき、眼の色、歩き方、気性、等々 ―― は、まさにそのように重なり合い、交差しているからである。そこで私はこう言いたい、「ゲーム」もまた一つの家族を構成しているのだ、と。
同様に、例えば数の種類も一つの家族を構成している。私たちがあるものを「数」と呼ぶ理由は、そのあるものが、今まで数と呼ばれてきたものと、ある ―― 直接的な ―― 血縁関係を持っているからである。そしてそのことによって、そのあるものは、私たちがやはり「数」と呼ぶ別のものと、ある間接的な血縁関係を持っている。私たちはこのようにして、ちょうど織物をするときに繊維と繊維を縒り合わせて糸を作るように、数の概念を拡大していく。この糸の強さは、ある一本の繊維が全体を貫いていることにあるのではなく、何本もの繊維が互いに重なり合っていることにあるのである。
だが、次のように反論したい人がいるかもしれない。「君の言うことが正しいのなら、そうした全ての構成物に共通な何かが存在するのだ ―― すなわちそれは、そうした構成物同士の間の共通項の選言からなるものである。」 ―― こんなことを言う人には、次のように返そう。「君はただ言葉遊びをしているに過ぎない。もし君の言うことが正しいなら、次のように言うことも同様に正しいであろう。『糸の全体を貫いているあるものが存在するのだ ―― すなわちそれは、隙間のない繊維の重なり合いである』。だがこんなものはただの言葉遊びである。」
68. [ある人が言う。] 「いいだろう。それなら君にとって数の概念は、互いに血縁関係にある個々の諸概念 ―― 基数、有理数、虚数、等々 ―― の論理和として説明される、ということなのだな。そして同様にゲームの概念も、対応する多くの部分概念の論理和として説明されるわけだ。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 必ずしもそうである必要はない。なぜなら、私は「数」という概念に対して明確な境界を定めることも、すなわち、「数」という記号をある明確な境界を持つ概念の記号として用いることもできるからだ。しかし私はまた、この概念を、境界によって閉じられていない概念の記号として用いることもできる。そしてもちろん、「ゲーム」という語についても同じことが言える。そもそもどうすればゲームという概念が閉じられるのか? 何がなおゲームであり、何がもはやゲームではないのか? 君はゲームという概念の境界をはっきりと示すことができるか? できないだろう。確かに、境界を引くことならできる。なぜなら境界は未だ引かれていないのだから。(しかしそれでも、君が今までに「ゲーム」という語を使ったとき、境界が引かれていないことが使用の妨げになったことなど一度もない。)
[ある人が言う。] 「しかし、それでは語の使用は規則に従ってはいないことになる。私たちが語を使って行う『ゲーム』は、規則に従っていないということになる。」 [ウィトゲンシュタインが言う。] そうではない。ただ、言語ゲームはいつでも規則によって制限を受けているわけではない、ということだ。例えば、テニスには、ボールを上げる高さや打つときの強さまで制限した規則はないが、それでもテニスは一つのゲームであり、幾つかの規則を持っているのである。
69. そもそも私たちは、誰かに何がゲームであるかを説明するとき、どうするであろうか? 私が信じるところでは、まず相手に色々なゲームの様子を記述するだろう。この記述にさらに「これらと、これに似たものを人は『ゲーム』と呼ぶ」という補足を付け加えることもできよう。私たち自身、一体それ以上のことを知っているだろうか? 私たちは、例えば、他人にだけは何がゲームであるかを正確に言うことができないだけで、自分に対しては知っているのだろうか? どちらも違う。しかしこのことは無知ではない。私たちがゲームの境界を知らないのは、それが一度も引かれたことがないからである。前節で述べたように、例えばある特定の目的のために境界を引くことはできる。それによってゲームという概念は初めて使用可能になるのか? その特定の目的のために使う場合でなければ、全く違う! ちょうど、「一歩=75cm」という定義を与える人が「一歩」という長さの単位を使用可能にするするのではないように。境界など引かなくても私たちは概念を使うことはできるのだ。そしてもし君が「これまでは「一歩」という単位は不正確な単位だったのだ」と言いたいのなら、私は次のように答えよう。「よろしい。君がそう言うなら、それは不正確な単位だったのだ。 ―― だがそれでもなお、君は私に、正確性という概念の定義を与える義務を負うのだ。」
70. [ある人が言う。] 「しかし、もし『ゲーム』という概念をこのように正確な仕方で境界づけることができないのならば、君は、君が『ゲーム』という語で意味するものを、本当は知らないのである。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] もし私が「地面一杯に植物が植わっていた」という記述を与える場合、 ―― 君は、私が植物の定義を与えることができるまでは、私が自分の語ることについて知らない、とでも言うつもりか? 私が意味することについての説明は、例えば、その風景のスケッチと「地面は大体こんな感じに見えた」という言葉によって与えられるのだ。あるいはまた私は「地面は正確にこのように見えた」と言うかもしれない。 ―― [ある人が言う。] それは、この草と葉がこの格好でそこにあった、ということか? [ウィトゲンシュタインが言う。] そうではない。私が言うのはそういうことではないのだ。私は、君の言うような意味において、いかなる像も正確な像として認知いるわけではないのだ。
ある人が私に次のように言う。「子供にあるゲームを示してみよ!」 そこで私は子供たちに、お金を賭けるサイコロゲームを教えてやった。するとその人がまた言う。「私はそういうゲームを意味していたのではない。」 彼が私に命令を与えたとき、サイコロゲームは排除するということが彼の念頭に浮かんでいなくてはならないのだろうか?
71. 「ゲーム」という概念はぼやけた輪郭を持つ概念だと言うことができる。 ―― [ある人が言う。] 「しかし、ぼやけた概念などというものは、そもそも概念だろうか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] では、ぼやけた顔写真はそもそもその人物の像ではないのだろうか? ぼやけた像は明確な像で置き換えたほうが、常にいいことがあるのだろうか? 私たちが必要とするのは、むしろぼやけた像であることも多いのではないか?
フレーゲは概念と区域を比較して「不明確な境界を持つ区域はそもそも区域と呼ぶことができない」と述べている[11]。これはつまり、私たちは不明確な境界を持つ区域からは何もすることができない、ということである。しかしそれなら、「大体この辺に立っていろ!」と命令することも無意義なのだろうか? 私が誰かとある場所に立っていて、この発言をする場面を考えよ。このとき、私は境界など引かず、例えば手で ―― まるで相手に特定の地点を示すかのような ―― 身振りをするであろう。そしてまさにこのようにして、人は、例えばゲームが何であるかを説明する。つまり、幾つかの実例を挙げ、それらがある意味において理解されるされるよう期待するのである。しかし、私はこういう言い方で「相手はこれらの実例のなかに、私が ―― 何らかの理由で ―― 言い表すことのできない共通項を見出さなくてはならない」ということを意味しているのではない。そうではなく、「今や相手はこれらの実例を特定の方法で使用することができなくてはならない」ということを意味しているのである。実例を示すということは、ここでは、他に適当な手段がないということで仕方なしに採用された、説明の間接的な手段ではない。なぜなら、いかなる一般的説明も誤解されうるからである。このようにして、私たちはまさにゲーム(私は「ゲーム」という語で言語ゲームを意味している)を演じるのである。
72. 共通項を見ること。私がある人にカラフルな絵を幾つか見せて「全部の絵に共通して見える色が『黄土色』という色だ」と言っている場面を想定せよ。 ―― これは、相手に全部の絵をよく見てもらい、共通の色を探してもらえば、理解してもらえる説明だ。この場合、彼はその共通色に眼を向け、それを指差すことができる。
これと次のケースを比較せよ。私は相手に同じ色で塗られた様々な形の図形を示し、こう言う。「これらが互いに共有しているものが『黄土色』だ。」
さらに次のケースとも比較せよ。私は相手に色々な色調の青の見本を示し、こう言う。「これら全てに共通の色を私は『青』と呼ぶ。」
73. もし誰かが私に色を説明するとき、見本を示して「この色は『青』という、これは『緑』・・・」という風にやるとしたら、この事例は、彼が色と語の対応表を私に手渡す場合と、色々な観点から比較できる。 ―― この比較は幾つかの意味で誤解を招く可能性があるにせよ。人はこの比較を次のように拡張したいであろう。つまり、説明を理解するということは、説明されたものの概念、すなわち見本だとか像を、心のうちに持つことだと、考えたいのである。
[ある人が言う。] さて、人が私に様々な葉を示して、「人はこれを『葉』と呼ぶ」と言うなら、私は葉の形についての一つの概念、つまり葉についての一つの像を心の中に抱くことになる。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし、葉の像、特定の葉の形を示すのではなく「全ての葉の形に共通な」葉の形とは、どのような形に見えるものだろう? 緑色についての「私の心のうちの見本」とやらは、緑色のどのような色調を ―― それはもちろん、全ての緑色の色調に共通なものである ―― しているのだろう?
[ある人が言う。] 「しかし、そのような『一般的な』見本は存在しえないであろうか? 例えば、葉の型(Schema)とか、純粋な緑の見本というものが。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かにそういうものは存在しうる! だが、そういう型が型として理解されるということは、それが一つの特定の葉の型として理解されるということではないこと、また、純粋な緑のカケラが、純粋な緑の見本としてではなく、全ての緑色の物の見本として理解されるということは、繰り返しになるが、この見本の使用方法にかかっているのである。
自問せよ。緑色の見本はどのような形を持つべきか? 四角くなければいけないのか? もしそうだとすれば、その見本は緑色の長方形のための見本になるのだろうか? [そしてそれ以外の形の緑色の物の見本にはならないのだろうか? そんなことはありえない。見本は全ての緑色の物の見本でなくてはならない。] 従って、その見本は「不規則な」形でなくてはならないのだろうか? そうだとすれば、私たちがその見本を、ただ不規則な形の物の見本としてのみ見る ―― すなわち用いる ―― ことがないようにしてくれているものは、何なのか?
74. この葉を「一般的な葉の形」の見本として見なす人は、同じ葉を例えば特定の形のための見本としてみなす人とは、異なって見るのだ、という考えも、ここで論じるのがふさわしい。さて、確かにそういうことは ―― 実際にはないとはいえ ―― あり得なくはない。なぜならこの考えは、通例、この葉を特定の仕方で見る人は、それをこれこれの、あるいはしかじかの規則に従って用いているのだ、ということを述べるに過ぎないからである。もちろん、見方にはこういう見方もあれば別の見方もある。見本をある見方で見る人は、同じような使い方をするのが一般的であろうし、異なる見方をする人は、異なる使い方をするであろう。例えば、立方体の見取り図を一つの正方形と二つの菱形から成る平面図形として見なす人と[12]、空間像として見なす人とでは、「こういう物を持ってこい!」という命令の実行の仕方も、恐らく異なるであろう。
75. ゲームとは何かを知っているとはどのようなことか? そのことを知ってはいるが、語ることはできないとはどのようなことか? この知識は、言語によって表明されていない定義と何らかの意味で同等のものなのか? もしそうなら、この知識が言語によって表明されれば、私はその表明を知識の表現として認知できるのだろうか? ゲームについての私の知識、私の概念は、私の与えうる説明において完全に表現されてはいないのか? すなわち、私はその説明において、多様な種類のゲームについての例を挙げて記述したり、いかにして人はこれらのゲームとの類比によって、ありとあらゆる他のゲームを構成することができるかを示したり、「私がこれをゲームと呼ぶことは、もはやほとんどないであろう」と言ったりする ―― そしてさらに多くの同様のことをも行うのである。
76. もし誰かが明確な境界を引いたとしても、私はそれを、私もまたずっと引こうと思っていた、あるいは心の中では引いていた境界として認知することはできないであろう。なぜなら、私は境界を引こうとは全く考えていなかったからである。それゆえ人は、「彼の概念は私の概念と同じではない。しかし両者は血縁関係にある」と言うことができる。そしてこの血縁関係は、二つの絵 ―― 一つは不明確に境界づけられた色面から成る絵、もう一つは、同じような形をし、同じような配置をしているが、明確に境界づけられた色面から成る絵 ―― の間の関係なのである。それゆえ、両者が血縁関係を持つということは、ちょうど両者が差異を持つことが否定できないように、否定できないことなのである。
77. そしてこの比較をさらに推し進めるなら、明確な絵がどの程度不明確な絵に似ることが可能かは、不明確ながどの程度不明確なのかによる、ということが明らかになる。というのも、君が、あるぼやけた絵に対して、それに「対応する」明確な絵を描かなくてはならないと想像せよ。ぼやけた絵には不明確な赤色の長方形があり、それに対して君は明確な長方形を描くわけである。もちろん ―― 不明確な長方形に対する明確な長方形は複数描くことができよう。 ―― これに対し、もともと色の境界なく混ざり合っている長方形の場合はどうであろうか。 ―― このぼやけた長方形に対応する明確な絵を描くことは実現不可能な課題になるのではないか? それゆえ君は次のように言うほかないのではないか?「この場合、長方形やハート形と同じように円を描くこともできよう。その円には、実にあらゆる色が混ざり合っており、従って、全ての絵と対応し、かつ、どの絵とも対応しない。」 ―― そして、例えば美学や倫理学において、私たちが日常使う概念に対応する定義を探そうとする人が置かれている状況こそが、まさにこれなのである。
次の困難について、常に自問せよ:そもそも私たちはいかにして語(例えば「善い」)の意味を習得したのか? どのような例をもって、また、どのような言語ゲームにおいて? (そうすれば、語が様々な意味から成る家族を持っていなくてはならないということが、容易に理解されるだろう。)
78. 知っていることと言うことを比較せよ。
モンブランの標高はどれほどか ――
「ゲーム」という語はいかに用いられるのか ――
クラリネットはどのような音色なのか ――
何かを知ってはいるが言うことができない、ということを不思議に思う人は、おそらく1番目のような例を考えている。間違っても3番目のような例を考えているのではない。
79. ある人が「モーゼは存在していなかった」と言う事例を考察せよ。この発言は様々なことを意味しうる。例えば、「エジプト脱出のとき、イスラエル人は一人の指導者によって導かれていたのではない」とか「彼らの指導者はモーゼとは呼ばれていなかった」とか「聖書のモーゼについての記述と完全に合致する人間は存在しなかった」とか、まだまだ色々考えられる。ラッセルだったら、「モーゼ」という名前は様々な記述によって定義できる、と言うだろう。例えば、「イスラエル人を率いて荒野を渡った男」、「この時代この場所に生きていて、当時『モーゼ』と呼ばれていた男」、「子供のとき、ファラオの娘によってナイル川から拾われた男」、といった具合だ。そして私たちが受け入れる定義に応じて、「モーゼは存在していた」という命題、そしてモーゼについて述べる他のあらゆる命題が持つ意義も変わってくる。 ―― そして [これを一般化すると] ある人が私たちに「Nは存在していなかった」と言えば、私たちは「君は何を意味しているのか? ・・・ということなのか、それとも・・・ということなのか、それとももっと別のことなのか?」と問うことになるであろう。
しかし、すると今、私がモーゼについての言明を行うなら、常に私は「モーゼ」という固有名を、前段で挙げた記述のどれか一つで置き換える用意があるということのか? 例えば私は、「モーゼ」という名前で、聖書のモーゼについての記述を全て行った男、あるいは全部でなくともその多くを行った男だと理解している。しかしどれほど多ければいいのだろう? この命題を偽として棄却するためには、どれほどの聖書の記述が偽として立証されねばならないか、私は前もって決めておいたのだろうか? 従って私にとって、「モーゼ」という名前は、あらゆる場合に一義的で固定的な使用を持っているのだろうか? もしそうでないのなら、私は、いわば一連の完全な足場を用意しており、そのうちの一つが取り除かれたり、ひっくり返されたりしたら、別の足場によって身を支える用意がある、ということではないか?
―― もう一つ別の事例を考察せよ。私が「Nは死んだ」という場合、「N」という名前の意味には、例えば次のようなケースがありうる。すなわち、私は、実際に生きていたある人間について以下の4つの項目を信じている。
(1) 私はその人をどこそこで見かけたことがある。
(2) その人はこれこれの風貌をしていた。
(3) その人はこれこれのことをしていた。
(4) その人は人々の間で「N」と呼ばれていた。
―― 従って、「N」という名前で何を理解しているか、と問われれば、私はこれら全てか、あるいは幾つかの項目を、その時々の状況に応じて様々に選んで答えるであろう。それゆえ、「N」についての私の定義は、例えば「上記4項目の全てが当てはまる人」となるであろう。 ―― しかし、今これらの項目の一つが偽だと判明したらどうなるのか! 私に「Nは死んだ」という命題は偽であると説明する用意が ―― 私から見れば枝葉末節としか思われない項目だけが偽の場合であっても ―― あるだろうか? だが枝葉末節の項目とそうでない項目の境界はどこにあるのか? ―― 実のところ、私にある用意は、むしろそういう場合は名前の定義の方を修正する用意であろう。
このことは次のように表現できる。私は、「N」という名前を固定的な意味なしに用いるのだ、と。(しかし、このことは名前を使用することをいささかも困難にするものではない。ちょうど、テーブルの脚が3本ではなく4本になったからといって不安定になるわけではないのと同じである。)
「君はその意味を知らない語を用いているのであり、それゆえ君の言うことはナンセンスだ」と言う人には、次のように答えよう。「君の好きなように言ってよい。ただし、私の使う語がどのように振る舞うかを君が見ることの妨げにならない限りで。」(そして語の振る舞いを見れば、君も多くを言う気にはなるまい。)
(学問的な定義の変化:今日では現象Aに経験的に随伴する現象とみなされているものが、明日には「A」の定義として使われるであろう。)
80. 私が「そこに椅子がある」と言う。私がそこへ行き、椅子を持ってこようとしたら突然椅子が視界から消えたとしたら? 「それならそこにあったのは椅子ではなく、何か幻覚だったのだ。」 ―― しかし、まばたきする間に再び椅子が現れ、それを手で掴むことができたとしら? 「それなら、椅子はずっとそこにあったのだ。それが消えたように見えたのが幻覚だったのだ。」 ―― しかし、またもやすぐに椅子が消えた ―― あるいは消えたように見えたとしたら? 今度は何と言うべきなのか。君はこの場合でも、ある物をなおも「椅子」と呼んでよいか否かを決める規則を用意周到に持っているのか? だが私たちが普段「椅子」という語を使用する際には、そういう規則はない。すると私たちは、「私たちが『椅子』という語の使用の全ての可能性に対して規則を準備していない場合、この語は実は何の意味とも結びついていない」と言うべきなのだろうか?
81. かつてF.P.ラムゼイが私との会話の中で、論理学は「規範の学問(normative Wissenschaft)」であると強調したことがあった。そのとき彼にどのような考えが浮かんでいたのか、正確には分からない。しかし彼の考えが、後になって初めて私が理解した考えと密接な関係を持っているということは、疑いない。その考えとは、私たちはしばしば哲学において、語の使用を確固たる規則に従うゲームや計算と比較するが、しかし、 [日常において] 言語を使用する者がそのようなゲームを行わなければならないと言うことはできない、というものだ。 ―― しかし今、ある人が、私たちの言語的表現は、そうした計算にただ近似していくだけだと言うのなら、即座に誤解の縁に立たされることになる。なぜなら、この発言は、あたかも私たちが論理学において理想言語について語っているかのように聞こえるからである。いわば、私たちの論理学は [現実には存在しない] 真空のための論理学であるかのように。 ―― だが論理学は、自然科学が自然現象を扱うような意味において言語や思考を扱うのではない。せいぜい言えるとすれば、私たちは理想言語を構成するということだけである。しかしこの場合の「理想」という語はミスリーディングである。なぜなら、まるでその言語は私たちの日常言語よりも良い、より完全な言語であり、論理学者が人々に正しい命題とはいかなるものかを最終的に示すために必要とする言語である、と言うかのように響くからである。
しかしこれら全てのことを正しく見るためには、理解、意味、思考といった概念についてより一層の明晰性を獲得しなければならない。なぜなら、そうすることによって、命題を言い、それを意味したり理解したりする者は、それを行うことで、一定の規則に従って計算を遂行しているのだという [誤った] 考えに私たちを誘い込むもの(そしてかつて実際に私を誘い込んだもの)が何であるかも、また明らかになるであろうから。
82. 何をもって私は「彼が従う規則」と呼ぶのか? ―― 私たちが観察する彼の語の使用を満足に記述できる仮説だろうか、あるいは、彼が記号を使用する際に参照する規則であろうか、それとも、実際彼に規則について訊ねたときに返ってくる答えであろうか? ―― しかし、観察しても一向に規則が分からず、質問してもさっぱり分からなかったとしたらどうすればいいのだろう? というのも、私の質問に対して、彼が「N」という語で理解するものについて説明してくれたとしても、彼はいつでもその説明を取り消す、あるいは変更する準備があるのだから。 ―― 一体、私はどのようにして、彼がゲームを演じるときに従う規則を規定するべきなのか? 彼自身そんなものは知らないのである。 ―― あるいは、より正確にはこう言うべきである。「彼が従う規則」という表現は、ここでは上記の3つ以外の何を、なおも意味すべきなのか?
83. ここで、言語とゲームの類比が光を投げかけてくれるのではないか? 私たちは実に容易に、人々がボールでゲームをする様を想像できる。確かに、最初は既存のボールゲームから始まるが、多くの人々は最後までやらずに、ゲームの途中で特に考えもなくボールを高く放り投げたり、ふざけてボールを持って追いかけっこやぶつけ合いをしたりする。さてすると次のように言う人がいる。「始まってからずっと人々は一つのボールゲームをしている。それゆえ彼らは、ボールの一投ごとに一定の規則に従って動いているのだ。」
だが、ゲームをしながら「その最中に規則を作っていく」という場合もまたあるのではないか? そう、あるのだ。そしてさらに、規則を変更する場合まであるのだ ―― ゲームをしながら。
84. [第68節で] 私は語の使用について「常に規則によって縛られているわけではない」と言った。しかし、そもそも「常に規則によって縛られているゲーム」とはどんなものなのか? そのゲームの規則にはいかなる疑念を挟む余地もなく、いかなる抜け穴も存在しないのである。 ―― 私たちはそのようなゲームのために、規則の使用を規制する規則というものを想像することができるのではないか? そしてそれぞれの規則が取り除く疑念などを想像することも。しかしこれは、私たちがある疑念を想像できるがゆえに疑念を持つ、ということではない。自宅のドアの前に立つ度に、「ドアの向こうには奈落が口を開けているのではないか」と疑い、ドアを開ける前にそれについて確認する(そしてその疑念が正しかったことが証明されることもないわけではない)人物を、私は容易に想像することができる。 ―― だからといって、私もドアの前に立つ度に同じ疑いを持つわけではない。
85. 道しるべのような規則がある。これは私が行くべき道を疑いなく明らかに示しているだろうか? 私がそこまで行ったとき、どの方向へ進むべきかを示しているだろうか? 私は、そのまま道なりに進むのか、あるいは農道へ入るのか、それとも野原を横切るのか、どの方向を選ぶべきか? だが私はどの意味でその道しるべに従うべきか。矢印の方向へ行けばいいのか、それとも(例えば)反対の方向なのか。 ―― もし仮に、一つの道しるべの代わりに、道しるべが連続して立っていたり、チョークで地面に線が引かれていたりしたら、 ―― これらにはただ一つだけの解釈が存在するのだろうか? もしそうなら、道しるべは疑念の余地なく明らかだと言うことができる。 あるいはむしろ次のように言うべきである。道しるべは、解釈に疑念の余地が残ることもあれば、残らないこともある。するとこれはもはや哲学的命題ではなく、経験的命題である。
86. 第2節のような言語ゲームは表の助けを借りて行われる。その場合、AがBに与える記号は文字記号になる。Bは表を持っていて、その表の第1列にはゲームで使われる文字記号が、第2列には建築石材の絵が書かれている。AがBにそうした記号の一つを見せると、Bは表の中からその記号を探し、それに対応している絵を見る、などのことをする。それゆえ、表は一つの規則であり、Bは命令を遂行する際、この規則に従うのである。表の中から絵を探すことは、訓練によって習得される。その訓練の一部には、生徒が表の中で指を左から右へ水平に動かすこと、すなわち、水平な矢印を何本も引くということが含まれる。
今、表を読むために様々な方法が導入されたと考えよ。あるときは、先に述べたように、
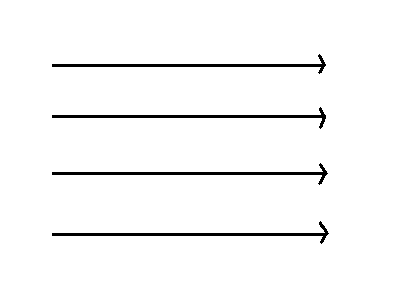
という図式に従い、またあるときは、
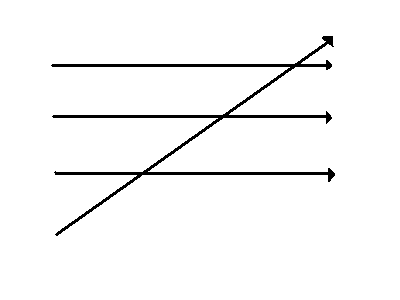
という図式、あるいはさらに別の図式に従う、といった具合だ。 ―― それゆえ、この図式は表が用いられる規則として、表に付け加えられるわけである。
さて、するとこの図式を説明するためのさらなる規則を想像することもできないか? 一方、最初の表は、矢印の図式がないがゆえに不完全だったのだろうか? 他の表もそれぞれの図式がないと不完全なのだろうか?
87. モーゼについて私が次のように説明するとしよう。「もしイスラエル人の出エジプトを指揮した人間が存在したなら、たとえその人物が当時何と呼ばれ、そして、他に何を為し、何を為さなかったとしても、私はその人物を『モーゼ』という名前で理解する。」 ―― [ある人が言う。] しかし、その説明に現れるほかの語についても、モーゼの場合と同様の疑問が生じうる。(君は何をもって「エジプト」と呼ぶのか、誰をもって「イスラエル人」と呼ぶのか、等々) [ウィトゲンシュタインが言う。] その通り。そしてその疑問は、「赤い」、「黒い」、「甘い」などの語に達するまで終わることなく生じる。 ―― [ある人が言う。] 「だがそれなら、終わりに達していない説明はいかにして私の理解に寄与するのか? そのとき、説明はまだ終わっていないのだから、私はその説明が意味するところを、未だ理解していないのであり、理解することはありえないのだ!」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 説明は、もし他の説明によって支えられていなければ、いわば、空中に浮かんでいるようなものだ。確かに、説明は、既に与えられた別の説明の上に依拠することができるが、誤解を避けるために必要とするとき以外は、特に他の説明を必要とはしない。次のように言うことができよう。「説明は誤解を取り除く、あるいは予防することに役立つ。しかし、私が想像可能な全ての誤解に対して有用なわけではない」と。
どのようなものでも疑問というのは [言語ゲームに] 根本的な欠陥が存在していることを示すものであり、それゆえ確実な理解を得ることができるのは、まず疑いうるあらゆるものを疑い、それら全ての疑いを取り除いたときだけである、と思い込みがちである。
道しるべは、普通の状況においてその役目を果たすなら、欠陥などないのである。
88. 私が誰かに「およそこの辺りに立っていろ!」と命令するとき ―― この説明は完全には機能しないのだろうか? 他の曖昧な命令も、機能しえるだろうか?
[ある人が言う。] 「しかしやはりこの説明は不正確ではないか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに不正確である。だが、なぜこの説明を「不正確」と呼んではならないのか? [呼んでもかまわない。] ただし、「不正確」が何を意味するかだけは理解するとしよう! なぜなら、「不正確」は「使用不可能」の意味ではないからだ。そして私たちはなお、「不正確な」説明と反対の意味で私たちが「正確な」説明と呼ぶものについて、良く考えなくてはならない! 例えば、チョークで線を引いて範囲を画定するという行為はどうか? すると、線にも幅があるということがすぐに念頭に浮かぶ。それゆえ、より正確には色の境界を考えなくてはならない。しかし、この正確性はなお何らかの機能を果たすだろうか? 空回りしているのではないだろうか? そして私たちは、何をもってこの明確な境界からの逸脱とみなすべきなのか、その逸脱はどのような道具で、いかにして確定されるのか、等々のことをまだ決めていないのだ。
懐中時計を正確な時刻に合わせることや、それが正確に動くよう調整する、というのがどのようなことか、私たちは理解している。だが、ある人から「その正確さは理想的な正確さなのか、それとも、理想的な正確さからどの程度の距離にある正確さなのか」と訊ねられたら、どうであろう? ―― 確かに私たちは、懐中時計による時間の測定よりも大きな正確さを持つ、別の時間の測定について語ることができる。その場合、「時計を正確な時刻に合わせる」という言葉は、懐中時計の場合の「時計を正確な時刻に合わせる」と血縁関係にあるとはいえ、別の意味を持つし、「時間を読み取る」なども別の過程となる。 ―― [ある人が言う。] もし私が誰かに「君はもっと時間どおりに食事に来なくてはいけない。君は食事がちょうど一時に始まるということを知っているのだから」と言うとしよう。 ―― ここでは本来、正確さが話題になっているのではないか、なぜなら、次のように言うことができるからだ。「実験室または天文台における時刻の規定について考えよ。そこで君は『正確さ』が何を意味するかを知るのだ。」
[ウィトゲンシュタインが言う。] 「不正確な」はもともと非難の言葉であり、「正確な」は賞賛の言葉である。そしてこれは、不正確なものは、より正確なものに比べて、目的を完全には達成しない、ということである。だから、ここで何を「目的」と呼ぶかが問題なのである。私が太陽までの距離を1mまで正確に言わなかったり、家具職人に机の幅を0.001mmまで正確に言わなかったりしたら、それは不正確なのだろうか?
正確さの一つの理想 が予定されているのではない。私たちは、そのような理想として何を思い浮かべるべきかを ―― 君自身がそれを確定するのでない限り ―― 知らない。しかし、君を満足させるような確定を見出すことは困難であろう。
89. これまでの考察によって、私たちは、「論理学はいかなる点で崇高か」という問いへとさしかかった。
というのも、論理学には特別な深遠さ ―― 普遍的な意味 ―― が備わっており、諸学の基礎に鎮座するかのように見えるからである。 ―― なぜなら、論理的考察は万物の本質を探究するからである。それは事物を根底から見ようとするものであり、あれやこれやの現実的な出来事など気にかけてはならないのである。 ―― 論理学は、 [自然科学のように] 自然現象の諸事実に対する興味や、因果関係を把握する必要からではなく、全ての経験的なものの基礎あるいは本質を理解しようとする努力から生まれる。しかし、その探究のために新しい事実を探り出すべきではなく、むしろ私たちの探究にとって本質的なことは、何一つ新しいことを学ぼうとしない、ということである。私たちは、すでに公然と眼の前に横たわっているものを理解しようとする。なぜなら、ある意味において、私たちはそれを理解していないからである。
アウグスティヌスは『告白』(第11巻 第14章)で述べている。「それでは、時間とは何なのか? 誰も私に訊ねないのなら、私は知っている。しかし、そう訊ねる人に説明しようとすると、知らないのである。」 ―― こういうことは、自然科学の問い(例えば、水素の比重を問う問題)については言えないであろう。誰からも訊かれないときは知っているが、誰かに説明しなくてはならないときにはもはや知らないもの、それは、人が想起しなくてはならないものである。(そしてそれは明らかに、何らかの理由によって、想起することが困難なものである。)
90. 私たちは現象の本質を見通さなくてはならないと思われる。しかし、私たちの探究の対象は現象ではなく、言ってみれば、現象の「可能性」である。すなわち、私たちは、現象についてなされる言明の種類を想起するのである。それゆえ、アウグスティヌスもまた、出来事の持続性やその過去、現在、未来についてなされる様々な言明について想起しているのである。(当然、それは、時間、過去、現在、未来についての哲学的命題ではない。)
私たちの考察は、それゆえ、文法的考察である。この考察は、言語の使用に関する誤解、とりわけ、私たちの言語の異なる分野における表現形式の間の類比から生じてくる誤解を除去することによって[13]、私たちの問題に光を当ててくれる。これらの誤解の多くは、ある表現形式を別の表現形式で置き換えることによって取り除くことができる。これを表現形式の「分析」と呼ぶことができる。なぜなら、この過程は、しばしば、ものごとを分解する過程に似ているからである。
91. ところで、ある表現形式を別の表現形式で置き換えることは、あたかも、私たちの言語形式の最終的な分析、それゆえ、一つの完全に分解された表現形式が存在する、と思わせることがあるかもしれない[14]。その考えはつまり [裏を返せば] 私たちが日常使う表現形式は、本質的に、分析されていない形式である、とか、日常の表現形式の中には光を投げかけるべき何かが隠されている、という考えである。もしこのような最終的分析がもたらされれば、日常の表現はそれによって完全に解明され、私たちの課題は解消されることになる。
また、次のように言うこともできる。「私たちは表現をより正確にすることで、誤解を取り除くことができる。しかし、私たちがあたかも、完全な正確さという特定の状態を目指して努力しており、これこそが私たちの探究の本来の目的であるかのように思われることがありうるのだ。」
92. 上記のことは、言語、文、思考の本質への問いにおいて表現されている。 ―― というのも、私たちの探究において、言語の本質 ―― 機能、構造 ―― を理解しようと努力しても、それはこの問いの目的ではないからである。なぜなら、この問いが本質において見てとるものは、既に公然と明るみに曝されているものや整理によって見通されるものではなく、表層の下に横たわっているものだからである。それは内部にあるもの、私たちが事柄を見通したときに見るもの、そして分析が掘り起こすべきものだというのである。
「本質は私たちから隠されている」、これが、今私たちの問題が仮定している形式である。私たちは「言語とは何であるか?」、「文とは何であるか?」と問う。そして答えは、きっぱりと最終解決として、将来のいかなる経験とも無関係に与えられるべきものだ、というのである。
93. ある人はこう言うかもしれない。「命題、それは世界で最もありふれたものである。」 別の人は、逆に、「命題 ―― それはなんと奇妙なものなのか!」と言うかもしれない。後者の人は、命題がいかに機能するかを単純に見て取ることができない。命題と思考に関する私たちの表現方法の形式が、彼の邪魔をするからである。
なぜ私たちは、「命題は奇妙なものである」と言うのか? 一つには、命題に備わっている途方もない意味のせいである。(そしてこれは正しい。)もう一つは、この意味と言語の論理に対する誤解が、私たちを誤った方向に導き、命題というのは何か特別なこと、特異なことを成し遂げなければならない、と考えてしまうからだ。私たちは誤解を通じて、命題が何か不可思議なことを行なっているかのように考えるのだ。
94. 「命題とは何と不思議なものか!」 既にこの発言の中に、全ての叙述を昇華(Sublimierung)しようとする傾向が存在する。命題記号と事実との間に純粋な媒介物を想定しようとする傾向、あるいはまた、命題記号自身を純化し、昇華させようとする傾向が。 ―― というのも、私たちの表現形式が、私たちを、架空の怪物キマイラの後を追いかけるよう駆り立てることによって、様々な手口で、命題記号が何の変哲もないものであることを見て取るのを邪魔するからである[15]。
95. [ある人が言う。] 「思考は特異なものでなくてはならない。」 [ウィトゲンシュタインが言う。] 「事態はしかじかである」と言い、そう思うとき、私たちは、思った内容を持って事実の手前で立ち止まっているのではない。そうではなく、まさに私たちは「これこれである」とか「しかじかである」と思うのである。 ―― ところで、このパラドクス(といっても、形の上では自明のものだが)は次のように表現することもできる。「人は事実でないことを思考できる」。
96. ここで思われている [文と事実の間に媒介物が存在するという] 特殊な錯覚には、様々な側面から、別の錯覚が繋がっている。その錯覚に騙されると、思考と言語は、世界に対する特異な相関者である像として、私たちの前に現れる。命題、言語、思考、世界 ―― こうした概念は、一つの系列を成して、互いに同等なものとして並んでいる。(しかし、これらの語は何のために必要なのか? これらの語には、それが使用されるべき言語ゲームが存在しない。)
97. [私たちはときにこう考える。] 思考は [可能的事実という] 光暈に囲まれている。 ―― その本質、つまり論理は、一つの秩序を描き出す。しかもそれは、世界のアプリオリな秩序、つまり世界と思考が共有しなくてはならない可能性の秩序である。この秩序は、しかし、最も単純でなくてはならない。それは、あらゆる経験に先立ち、あらゆる経験を貫き通すものでなくてはならないが、それ自身には、経験にまつわる一切の曇りも不確かさも付着していてはならない。むしろそれは、最も純粋な結晶でなくてはならない。だがこの結晶は、抽象的なものとして現れるのではなく、具体的なものとして、そう、最も具体的な、いわば最も堅固なものとして現れる。(『論考』5.5563節を参照[16]。)
[上のように考えるとき、] 私たちは錯覚に陥っているのだ。私たちの探究が特別なもの、深遠なもの、私たちにとって本質的なものであるのは、この探究が言語の比類なき本質 ―― 命題、語、推論、真理、経験といった概念間に成立する秩序 ―― を把握しようと努力するものであるからだ、という錯覚に。この秩序は、言うなら、メタ概念同士の間に成立するメタ秩序である。「言語」、「経験」、「世界」という語は、もしそれらが使用を持つならば、「机」、「ランプ」、「ドア」などと同じ低俗な使用を持たなければならない。
98. 一方では、私たちの言語の全命題が「あるがままにおいて秩序づけられている」ことは明白である。つまり、私たちは理想言語を手に入れようと努力しているのではない ―― あたかも、日常使われる曖昧な命題は完全無欠な意義を持たず、完全な言語は私たちによって初めて構成されるというような ―― 。他方また、意義のあるところには完全な秩序があらねばならないことも、明白だと思われる。 ―― それゆえ、完全な秩序は最も曖昧な命題にも隠れていなければならない。
99. 人は言うかもしれない。「命題の意義はもちろん、色々なことを未決定のままにしておくことができる。しかし、それでも命題は一つの確定的な意義を持たなくてはならない。不確定な意義は、決して本当の意味での意義ではないであろう。ちょうど、不明確な境界が、決して本当の意味での境界ではないように。」 そこで人は例えば次のように考える。もし私が「私はその男を部屋の中に閉じ込めた ―― ただし、ただ一つのドアだけは開いている」と言うとき ―― 全く彼を閉じ込めたことにはならないのだ、と。彼はただ、見かけ上閉じ込められたように見えるだけである。すると人は、「それなら君は、それによって何も為さなかったのだ」と言いたいであろう。抜け穴のある囲いなどないも同然である、と。 ―― だが果たしてそうであろうか?
100. [ある人が言う。] 「規則に曖昧さがある場合は、その規則を使うゲームはやはりゲームではない。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし、その場合でもそれはゲームであるのではないか? ―― [ある人が言う。] 「ああ、君はもしかしたらそう呼ぶかもしれない。だがそれでもやはり、それは完全なゲームではない。」 つまり、それは不純にされてしまったものであり、私が興味を抱くのは、不純にされた当のもの [不純にされる前の純粋なゲーム] だけである。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし私はこう言いたい。私たちは、自分たちの表現方法における理想が果たす役割を誤解しているのだ、と。つまり、私たちはその理想をもゲームと呼ぶであろうが、ただ、その理想に眩惑されて「ゲーム」という語の実際の使用を明瞭に見ていないのである。
101. 私たちはこう言いたくなる。論理において曖昧さは存在しえない。今や私たちは、「ねばならない」という理想は現実の中に見出されるという観念を持って生きている。たとえ、まだその理想がいかにして現実の中に見出されるか、その「ねばならない」の本質が何であるのかが理解されていなくとも。私たちは、この理想が現実の中に隠されていると信じている。なぜなら、それを既に現実の中に見ていると信じているからである。
102. [ある人が言う。] 論理的な命題構造の厳密で明確な規則は、背後に控える何物かとして ―― つまり、理解の媒介物の中にある何物かとして ―― 現れる。私は既にそれを見ている(媒介物を介してではあるが)。なぜなら、現に私は記号を理解し、記号によって何かを意味するからである。
103. [ある人が言う。] 理想は、私たちの思考の中に確固として居座っている。君はそこから一歩たりとも出ることはできない。君は何度でも連れ戻されるに違いない。外部というものが一切ないのである。外部には生きる余地がないのである。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] このような観念はどこから生じたのだろう? これはいわば、私たちの鼻にかかった眼鏡であり、私たちはこの眼鏡を通してものを見る。思考からこの眼鏡を取り外すことなど思いつきもしないのである。
104. 人は事柄 [=命題記号] に対して、表現方法の中にあるもの [=像] を述語づける。 [つまり「命題記号は像である」と言う。] この比較可能性は、私たちに強い印象を与える。私たちはこの可能性を最も一般的な事態の知覚であると見なすのだ。
105. かの秩序、理想が、現実の言語において見出されねばならないと信じるならば、日常生活において「命題」、「語」、「記号」と呼ばれるものに不満を抱くであろう。
論理学が扱う命題や語は、純粋なもの、そして明確に境界づけられているものでなくてはならない。そして私たちは、本来の記号の本質について頭を悩ます破目に陥るのである。 ―― その本質は、例えば記号の表象であろうか? あるいは、今この瞬間における記号の表象なのだろうか?
106. このような状況に陥ると、勇気を持って、道を踏み外さないよう、日常思考される事物に留まらねばならないということを見て取ることが難しくなる。道を踏み外すと、日常言語では決して記述できないような、究極の精巧さを記述せねばならないと勘違してしまう。私たちにとってこの難しさは、いわばもつれた蜘蛛の巣を指で元通りにしなければならないときの難しさと同じなのである。
107. 日常言語について精密に考察すればするほど、日常言語と私たちの要求の間の対立は厳しくなっていく。(論理が持つ結晶のごとき純粋さは、結果として生じたものではなく、一つの要求だったのである。)この対立は我慢できないものとなり、私たちの要求は空虚なものになっていく。 ―― 私たちは摩擦のない氷の上に迷い出たのだ。そこでは、条件はある意味で理想的なのだが、しかし私たちはそれゆえにまた、先に進むこともできないのである。私たちは前へ進みたい。そのためには摩擦が必要だ。ざらざらした大地へ戻れ!
108. 私たちは、自分たちが「命題」、「言語」と呼ぶものが、私がかつて思い描いていた形式的な統一体ではなく、多少なりとも血縁関係にある家族なのだということを認識している。 ―― しかし論理についてはどうなるのか? 今やその厳密さは瓦解してゆくと思われる。 ―― それによって論理は完全に消えてしまうのだろうか? ―― 一体どうすれば論理はその厳密さを失うことができるだろう? それは無論、人が論理から厳密さを割り引くことによってではない。 ―― 結晶のような純粋性という先入見は、私たちが考察の方向を180度転回させることによってのみ、取り除くことができるのである。( ただし考察の転回は、私たちの本来の必要を軸として行われねばならない。)
論理の哲学は、命題や語について、日常使う意味 ―― 例えば私たちが「ここに中国語の命題が書かれている」とか「違う、これは文字記号のように見えるだけで、実は装飾の模様なのだ」などと話す場合の意味 ―― においてのみ語る。
私たちは言語の空間的・時間的現象 [=トークン、命題記号] について語るのであって、非空間的・非時間的な馬鹿げたもの [=タイプ、命題] について語るのではない。 [ウィトゲンシュタインによる余白への書き込み:ただ、現象に対する関心の持ち方が人によって様々に異なるだけだ。] だが私たちは、現象について語るとき、チェスの駒について語るときと同じように、物理的な特性を記述するのではなく、それに適用されるゲームの規則を述べてしまう。
「本来の語とは何か?」という問いは、「チェスの駒とは何か?」という問いと似ている。
ファラデーの『ろうそくの科学』。水は一つの個体である ―― それは決して変化しない。
109. 私たちの考察は科学的考察であってはならない、ということは正しかった。先入見に反してあれやこれやを考えることができる、という経験は ―― たとえそれが何を意味しようと ―― 私たちの興味外のことだった。(思考の力学的な理解。) それゆえ、私たちには、一切の理論を立てることが許されない。いかなる仮説も考察の中に入り込んではならない。一切の説明が排除され、後には記述だけが残らなければならない。そしてこの記述は、その光、つまり目的を、哲学的諸問題から受け取るのである。これらの問題は確かに経験的なものではない。これらは、私たちの言語の働きを洞察することによって解消されるのであり、その洞察は言語の働きを誤解しようとする衝動に対抗して認識されるものである。問題の解決は、新しい経験を引き合いに出すことによってではなく、昔から知られていたことを配列することによって実現される。哲学とは、言語によって私たちの知性にかけられた魔法に対する戦いである。
110. 「言語(または思考)は特異なものである」 ―― これは、それ自体、文法的錯覚によって引き起こされた迷信である(誤りではない!)。
そして今や、これらの錯覚と、そこから引き起こされる [哲学的]諸問題に [科学的]情熱が向かうのである。
111. 私たちの言語形式の誤解から生じる諸問題は、深遠さという特徴を備えている。それは深遠な不安の種である。その根は私たちの言語形式と同じだけ深く、その重要性は私たちの言語のそれと同じだけ大きい。 ―― 自問せよ、なぜ私たちは文法的なしゃれを深遠と感じるのか? (そして確かにこれは哲学的な深遠さだ。)
112. 私たちの言語の形式の中に受け入れられている比喩が、間違った外観を作り出す。その外観が私たちを不安にさせる。「だがその比喩はそうではない!」 ―― 私たちはそう言う。「しかし、それでもその比喩はそうでなくてはならない。」
113. 「だがそれはそうなのだ ―― 」 私は繰り返しそう呟く。私がこの現実に目を向け、焦点を完全に合わせることさえできるなら、事柄の本質を把握できるに違いないと思われる。
114. 『論理哲学論考』4.5節「命題の一般形式は、事態はしかじかである、という形をしている。」 この種の命題は何度となく繰り返される。人は本性を追求していると繰り返し信じるが、実は、本性を考察する際の形式に沿って進んでいるだけである。
115. 一つの像が私たちを捕えて離さなかった。そして私たちはそこから脱出することができなかった。なぜなら、その像は私たちの言語の中にあり、言語はそれを、ただ容赦なく私たちに繰り返し見せていただけだったからである。
116. 哲学者が「知識」、「存在」、「対象」、「自我」、「命題」、「名前」といった語を使い、事物の本質を把握しようとしているとき、常にこう自問しなくてはならない。「これらの語はその故郷、つまり日常言語においても、本当にそのように使われているのか?」と。
[哲学者と違って] 私たちは、これらの語を形而上学的な使用から再び日常的な使用へと連れ戻す。
117. ある人が私に言う。「だが君はこの表現を理解するのだろう? それなら ―― 君の知っている意味において、私もまたこの表現を使っているのだ。」 ―― この言いようは、まるで意味とは語が持っている雰囲気であり、どのような使用においても語はそれを持ち歩く、と言うかのようだ。
もし例えば誰かが、(彼の前にある物を指差して)「これはここにある」という命題は私にとって意義を持つ、と言うならば、この命題が実際に使われるのはいかなる特定の状況下においてか、と自問してほしい。その状況において初めて、この命題は意義を持つのだから。
118. 私たちの考察はどこからその重要性を得ているのだろう? 私たちの考察は、関心の対象全てを、すなわち、偉大で重要なもの全てを、ただ破壊しているだけのように思われるというのに。(いわば、建築物全体を破壊しているようなものだ。残るのは石塊と瓦礫だけである。)しかし、私たちが破壊しているのは、実は幻の楼閣なのだ。私たちは、その幻が建っていた言語の基盤を発掘しているのである。
119. 哲学の成果とは、全くのナンセンスと、言語の限界に突進することで知性にできた瘤の二つを発見することである。ナンセンスの発見の価値は、こうした瘤から分かる。
120. 言語(または語、命題など)について語るなら、日常言語で語らなくてはならない。だが日常言語は、私たちが言おうとしていることを表現するには、あまりに粗雑で抽象性に欠けるのではないか? もしそうだとすれば、一体、日常言語以外の言語をどうやって構成するというのか? ―― もしそんな言語が構成できるのなら、そもそも私たちが日常言語で何ごとかを為すことができるというのは、何と不思議なことか!
私が言語について説明する際、既に完成した言語(準備段階の、あるいは暫定的な言語ではなく)を使わなくてはならないということは、私が言語について述べられるのは外面的なことだけだということを、既に示している。
[ある人が言う。] 確かに。しかし、いかにしてその説明は私たちを満足させることができるのか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 今、君の質問も私たちの言語で行われた。すなわち、何かを質問するときは私たちの言語によって表現されなければならないのだ!
だから、君のためらいは誤解の産物である。
君の質問は語に関係したものだ。だから私も語について語らなくてはならない。
人は言う。「問題は語ではなく、その意味である。そして、たとえ語と異なる事柄であっても語と同じ種類の事柄として考えるように、意味についても考えるのだ。ここに語が存在し、同様にここに意味が存在する。お金とそれで買える牛のように、である。」(しかし他方、お金とその使用、という対比もありうる。)
121. 人は次のように考えるかもしれない。もし「哲学」という語の使用について語る哲学があるなら、それは二階の哲学でなくてはならない、と。だが全くそうではない。正書法理論は「正書法理論」という語も扱わなければならないが、だからといって二階の正書法理論があるわけではない。
122. 私たちの無理解の主な源泉は、私たちが語の使用を展望していないことにある。 ―― 私たちの文法には展望性が欠けている。 ―― 展望を可能にする描写は、語の使用についての理解を与えてくれる。その理解は、私たちが「 [様々な語の使用の間の] 諸関係を見る」ことのうちにまさに成立するものである。だから [第23節におけるように] 中間の使用を発見したり、発明したりすることが重要なのである。
展望を可能にする描写という概念は、私たちにとって根本的な意味を持っている。それは私たちの描写の形式、つまり私たちの事物を見方を表している。(これは一つの「世界観」であろうか?)
123. 哲学的問題の形式は「私は何一つ知らない」という形をとる。
124. 哲学は、いかなる仕方でも言語の日常的な使用に傷をつけてはならない。哲学にできるのはそれゆえ、結局のところ、使用を記述することのみである。
なぜなら、哲学は言語の使用を基礎付けることもできないからである。
哲学は全てをあるがままにしておく。
哲学は数学もあるがままにしておく。そして、いかなる数学的発見も哲学を進歩させることはできない。「数学的論理学の主要問題」は、私たちにとっては、他の問題と同じく数学の問題である。
125. 矛盾を数学的または論理数学的な発見によって解決することが哲学の仕事ではない。矛盾が解決される前の、私たちを不安にさせる数学の状況を展望できるようにすることが、哲学の仕事である。(だがこれによって、例えば数学の困難が回避されるわけではない。)
[数学の矛盾についての] 根本的な事実は次の通りである。私たちは規則や技術を一つのゲームのために定めるが、いざ規則に従おうとすると、思っていたようにうまくいかない。つまり私たちは、自分たちの規則に絡まってしまう。
私たちが理解したい、すなわち展望したいことは、この規則による絡まりである。
この展望は、「思う」という私たちの概念に光を投げかけてくれる。というのも、絡まりが起こる場合というのは、私たちが思っていた、つまり予測していたことと異なることが起こる場合だからである。例えば矛盾に直面したとき、私たちはまさに「こうなるとは思っていなかった」と言う。
矛盾の市民的身分、あるいは市民世界における矛盾の身分、これが哲学の問題とすることである。
126. 哲学は、全てをまさにあるがままにしておく。そして何も説明せず、何も推論しない。 ―― 何も隠されてはいないのだから、何も説明する必要がないのである。なぜなら、例えば、隠されているものには、私たちは興味がないのだから。
あるいは、全ての新たな発見や発明に先立って可能であるものを「哲学」と呼ぶこともできるだろう。
127. 哲学の仕事は、ある特定の目的のために記憶を収集することである。
128. 哲学においてテーゼを立てようとするなら、それについて論争は起こりえないであろう。なぜなら、万人がそのテーゼに賛成するであろうから。
129. 私たちにとって極めて重要な事物の諸相は、それらの単純性と一般性によって隠されている。(人はそのことに気づけない ―― なぜなら、常に眼の前に見ているから。)哲学者の研究の本当の基礎は、かつて彼がそれに気づいたことがない限り、決して気づかれない。 ―― すなわち、一度気づけば最も目立ち最も強力なものに、私たちは気づかないのである。
130. [第2節のような] 私たちの明快で単純な言語ゲームは、将来、言語を規則で定めるための予備的研究、言い換えれば、摩擦と空気抵抗を無視した第一近似ではない 。 むしろ言語ゲームは、類似性と非類似性を通して言語の諸状態に光を投げかけるべき比較対象として存在しているのだ。
131. というのも、私たちが不当な、あるいは空虚な主張を回避するためには、具体事例をあるがままに、比較対象として ―― 現実の方がそれに対応せねばならない先入見としてではなく ―― いわば物差しとして提示することによってのみ可能だからである。(哲学において、私たちは容易に独断論に陥ってしまう。)
132. 私たちは言語使用の知識に一つの秩序を確立しようとする。この秩序は、ある特定の目的のために役立つものだが、数ある可能な秩序のうちの一つであって、唯一の秩序というわけではない。私たちはこの目的のために、私たちの日常言語の形式を展望しやすくする区別を常に強調する。それによって、あたかも私たちが言語の再構築を自らの仕事とみなしているかのような印象を与えるかもしれない。
特定の実際的な目的のために言語を再構築したり、実際の語の使用において誤解を避けるため用語法を改良することは、確かに可能である。しかし、それらは私たちには関係ない。私たちが向かい合う困惑は、いわば、言語が空回りするときに生じるものであり、言語が機能しているときには生じないのである。
133. 私たちがやりたいのは、語を使用するための規則体系を聞いたこともない方法によって洗練したり完全することではない。
というのも、私たちが希求する明晰性は、確かに完全な明晰性ではあるが、それはただ、哲学の問題は完全に消滅すべきである、という意味に過ぎないからだ。
本当の発見とは、私が望むときに哲学をやめられるようにする発見である。 ―― 本当の発見は哲学に安息をもたらす。そしてもはや、問い自身を問題にする問いによって哲学が駆り立てられないようにする。 ―― そうなれば、諸事例において一つの方法が示されても、その諸事例の列を途中で打ち切ることができる。 ―― 複数の問題が解消される(複数の困難が除去される)のであって、一つの問題が解消されるのではない。
哲学には一つの方法があるのではない。あるのは複数の方法であり、いわば様々な治療法である。
134. 「事態はしかじかである」という命題を考察しよう[17]。 ―― 私はいかにしてこれが命題の一般形式だと言うことができるのか? ―― 何よりもまず、これ自身が一つの命題、一つの日本語の命題だからである。なぜなら、これには主語があり、述語がある。 ―― しかしこの命題はどのように適用されるのか ―― つまり、私たちの日常言語において? というのも、そこからのみ私はこの命題を取り出してきたのだから。
例えば私たちは、「彼は自分の状況を説明し、事態はしかじかなので前払金が必要だと言った」と言う。それゆえ、この使い方の限りでは、この命題は何かしらの言明を表明していると言うことができる。 [しかしそれ以外の場合、] この命題は命題のシェーマとして用いられているのだが、それはただ、この命題が日本語の命題構造をもっているからに過ぎない。また、この命題の代わりに「これこれが実情である」とか「事柄はしかじかである」等と言うこともできるだろう。あるいは記号論理学におけるように、ただの文字記号、つまり変項を使うこともできよう。しかし「p」という文字記号を命題の一般形式だと呼ぶ人はいまい。前述のように、「事態はしかじかである」という命題が命題の一般形式と呼ばれる理由は、ただそれ自身が日本語の命題と呼ばれるものだからである。しかし、たとえそれが一つの命題であるとしても、命題変項としてのみ使用されるに過ぎない[18]。この命題が現実と一致する(あるいは一致しない)と言うことは、明らかにナンセンスである。この命題はそれゆえ、私たちの命題という概念の一つの特徴が、命題らしい音の響きであることを例示しているのである。
135. [ある人が言う。] だがそうすると私たちは、命題が何であるのか、「命題」という語で何を理解するのか、ということについて、概念を持っていないことになるのではないか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] そうではない。私たちが「ゲーム」という語で何を理解するのかについての概念を持っている限り、「命題」の概念もまた持っているのだ。
命題とは何か、と問われれば ―― 他人あるいは自らのどちらに答えねばならないとしても ―― 私たちは幾つかの例を挙げるだろうし、また、それらのもとで命題の帰納的系列と呼びうるものも挙げるだろう。ともかく、こういう方法によって、私たちは命題の概念を手にするのである。(命題の概念を数の概念と比較せよ[19]。)
136. 「事態はしかじかである」を命題の一般形式として提示することは、「命題とは真か偽のどちらかでありうる全てのものである」と説明することと、根本的には同じである。なぜなら「事態は・・・である」と言う代わりに、「これこれは真である」(あるいは「これこれは偽である」)と言うこともできるからである。さてところが、
「p」は真である = p
「p」は偽である = not-p
と置くならば、「命題とは真か偽のどちらかでありうる全てのものである」と言うことは、結果的に、私たちが日常言語において真理関数の演算を応用するものを命題と呼ぶ、ということなのである。
するとこの説明 ―― 命題とは真か偽でありうるものである ―― は、「真」という概念に当てはまるもの、または「真」という概念が当てはまるものが命題であると述べることによって、命題とは何かを規定するかのように思われる。それゆえ、何が命題で何が命題でないかを規定する際に援用した真や偽の概念を、私たちは既に持っているということになる。真という概念に(歯車のように)かみ合うもの、それが命題だ、というわけである。
しかし以上のことは間違った像である。これはまるで「チェスのキングとは、王手をかけられる唯一の駒だ」と言うようなものである。この説明が意味するのはただ、チェスにおいて王手がかかるのはキングだけだ、ということだけである。同様に、命題だけが真でありうると言うことは、私たちは、自らが命題と呼ぶものに対してのみ「真」や「偽」を述語づける、ということを述べたに過ぎない。そして命題が何であるかは、ある意味では(例えば日本語の)命題構造の諸規則によって規定され、また別の意味では言語ゲームにおける記号の使用を通して規定される。そして「真」と「偽」という語の使用もまた、このゲームの構成要素でありうる。だから、私たちにとってその使用は命題に属しているのであって、命題に「適合」しているわけではないのである。ちょうど、王手はキングという概念に(いわばその構成要素として)属していると言うことができるように。王手はポーンの概念には適合しないと言うことは、ポーンに王手をかけられるようなゲーム、例えばポーンを失うと負けになるゲーム、 ―― そのようなゲームは面白くないとか、馬鹿げているとか、複雑すぎる等々のことを意味するであろう。
137. それでは、命題の主語を「誰が、あるいは何が・・・?」という問いを通して学ぶ場合はどうか? ―― この場合も、やはりこの問いに対して主語が適合する場合が存在する。なぜなら、そうでなければ私たちはいかにして、この問いを通して主語が何であるかを知ったというのか? 私たちは、アルファベットの「K」の次に何の文字が来るのかを、「K」まで唱えてみることで知るのと似通った方法で、命題の主語を知る。さて、「L」はどのようにアルファベットの文字列に適合しているのか? ―― そしてその限りにおいて、「真」と「偽」は命題に適合すると言うことができよう。子供に命題と命題以外の表現の区別を教えるとき、「それの後に『は真である』と続けられるか否かを考えなさい。もし続けられるならそれは命題だ」と教えることは可能である。(同様に、「それの前に『事態はこうである、すなわち』と付けることができるかどうかを考えなさい」と教えることも可能であろう。)
138. [ある人が言う。] だがそれでは、私が理解する語の意味は、私が理解する文の意義に対して適合しえないのではないか? あるいは、ある語の意味は別の語の意味に対して適合しえないのではないか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] もちろん、意味が、私が使う語の使用であるならば、そうした適合について語ることは意義を持たない。 [ある人が言う。] さてしかし、 [現実には、] 語を聞きまた自分でそれを発するとき、私たちはその意味を理解するのである ―― それも瞬間的に把握して。そしてやはり、私たちがそのとき把握するものは、時間軸上に広がる「使用」とは異なる何ものかである!
私は語を理解しているか否かを知っていなければならないのか? 語の意味を理解している(ちょうど計算方法を理解しているように)と思い込んでいて、実は理解していなかったことに気付く、ということもありうるのではないか? (自分が「『相対』運動や『絶対』運動が何であるかを知っていると信じていたが、実は知らなかったことに気付いた」ということがありうるように。)
139. もし誰かが私に、例えば「立方体」という語を言うとき、私はそれが意味するものを知る。しかしそれでは、私がそれを理解することで、その語の全使用までもが私の念頭に浮かぶことなどありえるだろうか?
だが他方、語の意味はその使用を通して規定されるのではないのか? そしてその規定には矛盾がありえるのか? 私たちが瞬時に把握するものは、使用と一致しうるのか、適合しうるのか、あるいは適合しえないのか? そして一瞬のうちに私たちの記憶に生じるもの、あるいは私たちの念頭に浮かぶものは、使用に適合しうるのか?
それでは、実際のところ、私たちが語を理解するときに念頭に浮かぶものとは何なのか? ―― それは像のようなものではないのか? 像ではありえないのか?
では、「立方体」という語を聞くと、君の念頭に一つの像、例えば立方体の見取図が浮かぶとしよう[20]。いかなる意味でこの像は「立方体」という語の使用に適合しうる、あるいは適合しえないのか? ―― おそらく君はこう言うだろう。「それは簡単だ。もしこの像が私の念頭に浮かび、例えば三角柱を指差して、これは立方体だ、と言うなら、この使用は像に適合していない。」 ―― しかし果たしてそうであろうか? 私がわざとこの例を選んだのは、この使用が像に適合するような投影法を想像することが実に容易な例だからである。
立方体の像は、もちろん、ある種の使用を私たちに思いつかせるが、しかし私は、この像を別様に使うことだってできるのである。
(a) [ある人が言う。] 「私は、この場合における正しい語は・・・であると信じる。」この信念は、語の意味が私たちの念頭に浮かぶものであり、いわば私たちがここで用いようとしている正確な像である、ということを示しているではないか? 例えば私が、「りっぱな」、「威厳に満ちた」、「誇り高い」、「尊敬に値する」などの語の中から適切な語を選んだ、と考えよ。この行為はいわば、ファイルの中から適切な図面を選ぶようなものではないか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] そうではない。適切な語について語ることは、そのような正確な像の存在を示すものではない。むしろ、ある語が適切であると感じられるがゆえに、像のようなものについて語りがちになるのである ―― 大抵の場合、似てはいるが同じではない幾つかの像の中から適切な像を選ぶように語を選ぶことによって。というのも、人はしばしば、語や語の図解などの代わりに像を用いるからである。
(b) 私はある像を見る。それは一人の老人がステッキをついて急な山の斜面を登っている様子を描いたものである。 ―― それはどのようにしてその事実を表しているのか? 老人がその姿勢で山を降りているとしても、やはり像はそのように見えるのではないか? ひょっとして火星人なら、その像を老人が山を降りている像として記述するかもしれない。しかし私は、なぜ私たちがこの像を火星人のように記述しないかの理由を説明する必要がない。
140. しかしそうすると、私の間違いはいかなる種類のものだったのだろう? 人は、像が私に特定の使用を強いると私が信じていたのだ、と言いたいかもしれない。では私はどのようにそれを信じることができたのか? 何を私は信じていたのか? 私たちに特定の適用を強いるような像、あるいは像に似た何かが存在しており、従って私の誤りは [心理的な強制と論理的な強制の] 混同だったのだろうか? ―― というのも、私たちには、この強制がせいぜい心理的なものであって論理的なものではないと表現したくなる傾向もありえるからである。そしてここにおいて、確かに私たちは、論理的な強制と心理的な強制という2種類の場合を知っていたかのように思われるのである。
では一体、私の議論は何をなしたのか? それは、場合によっては、私たちが最初に考えていた立方体の適用とは異なる過程であっても「立方体の適用」と呼ぶ用意がある、という事実について、私たちに注意を喚起した(思い出させた)のである。だから、私たちが抱いていた、「像が特定の適用を私たちに強いるという信念」は、要するに、ただ一つの場合しか思いつかず、他の場合は思いつかない、ということなのである。「別の解法も存在する」ということは、つまり、私たちが「解法」と呼ぶ別のものもあり、それに対して、これこれの像やこれこれの類比などを適用する用意がある、ということである。
そしてここで本質的なことは、語を聞いたとき、同じものが私たちの念頭に浮かぶとしても、それに対する異なる適用がありうることを、私たちが見てとっている点である。すると、ある語を2回聞いたとき、それぞれの場合に念頭に浮かぶ像は、同じ意味を持つのだろうか? 私たちは、否と答えるであろう。
141. [ある人が言う。] しかしそれなら、私たちの念頭に浮かぶのは、単に立方体の像だけではなく、投影法も合わせて浮かぶとすればよいのではないか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] そのことをどう考えるべきだろうか? ―― [ある人が言う。] 例えば、投影法の図式を見ると考えるのだ。その図式は、例えば、二つの立方体が投影の線によって結ばれているという像である。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] だが、そのような図式を思い浮かべることによって本質へと近づけるのだろうか? その図式に対しても再度異なる適用を考えることができはしないか? ―― [ある人が言う。] できるだろうが、しかし、それでも一つの適用が私の念頭に浮かぶことは可能ではないか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに可能である。ただ、ここで私たちがすべきことは、この [ 「ある投影法の図式が念頭に浮かぶ」という] 表現の適用についてより明晰になることである。例えば、私が誰かに様々な投影法を説明し、彼はその説明に従って投影法を適用する、と仮定しよう。そして次のように自問せよ。私たちはいかなる場合において、私が考えているのと同じ投影法が彼の念頭にも浮かんでいる、と言うのか?
さて、それを知るための規準は、明らかに2種類のものが認められる。一つは、ある時点で彼の念頭に浮かぶ像(それがいかなる種類のものであれ)である。もう一つは、彼がその表象について ―― 時間の流れの中で ―― 行う適用である。(そしてここで、その像が、彼の前に置かれた見取図や彼が作った模型ではなく、彼の想像の中に浮かぶ表象であるという点が全く非本質的であることは、明白ではないか?)
ところで、像と適用が衝突することはありうるだろうか? そう、衝突はありうる。だがそれは、像が私たちに通常とは別の使用を期待させる限りにおいてである。なぜなら、一般的にはこの像にはこの適用というように使われるのだから。
従って私はこう言いたい。この場合、一つの通常の場合と複数の異常な場合がある、と。
142. 語の使用が明らかに示されるのは、通常の場合だけである。私たちは、自分があれこれの場合に何を述べるべきかを、疑いなく知っている。だが、異常な場合になればなるほど、その場面で何を言うべきか疑わしくなってくる。そして事柄が事実とは全く異なる様相を呈する場合 ―― 例えば、痛み、恐怖、喜びに特徴的な表情が一切ない場合、あるいは、規則であるものが例外になり、例外が規則になるになる場合、はたまた、規則であるものと例外がおよそ同程度の頻度で起こる場合 ―― そうした場合、私たちの通常の言語ゲームはその機能を失ってしまう。 ―― ちょうど、明らかな原因もないのに突然針の振幅が小さくなったり大きくなったりすることが頻繁に起きるようになったら、チーズの塊をはかりにかけて、針の振れ具合で価格を決める手続きがその機能を失うように。この見解は、私たちが、表情の感情などに対する関係といった事柄について語るとき、より明確になるであろう。
ある概念の意味 ―― ここでは意義(Wichtigkeit)のことだが ―― の説明のために私たちが言わねばならないことは、しばしば非常に一般的な自然の諸事実である。だがそれらは、その大きな一般性のために、殆ど言及されることがない。
143. さて、次のような種類の言語ゲームを考察しよう。BはAの命令により、ある特定の生成規則に従って、数列を書きつけなければならない。
この数列の最初の数は10進法における自然数でなくてはならない。 ―― Bはどのようにしてこの10進法を理解するか? ―― まず最初に、Bに対して数列を書いて見せてから、それをまねて書くよう言われるだろう。(「数列」という言葉に不満を持たないでほしい! この語はここで、数学における厳密な定義を曲げて用いられているわけではないのだ。) そして既にここに、学習者の通常の反応と異常な反応が見出される。 ―― 私たちはBに、例えば0から9までの列をまねて書くよう、手をとって指導する。しかし、教えたことが通じた可能性は、彼が今や自力で書くことができるかどうかに掛かっている。 ―― そしてここで例えば、Bは確かに自分で数字を書き写すが、しかしそれは数列に沿った数字ではなく、不規則に次はこれ、次はあれ、というように書く、ということも考えうる。従って、この段階で教えたことが通じたという可能性は消滅する。 ―― しかしまた、彼が順序を「間違えて」書くこともありうる。 ―― 不規則に書く場合と、 [規則は理解しているが] 順序を間違えて書く場合の相違は、もちろんその頻度である。 ―― あるいは、彼は系統的に間違えるかもしれない。例えば、彼は、数を二つおきに書いたり、0, 1, 2, 3, 4, 5, .... という数列を、1, 0, 3, 2, 5, 4 .... と書き写すのである。こういうとき、私たちは「彼は私たちの教えたことを間違って理解したのだ」と言いたくなる抗し難い誘惑を感じる。
しかし、注意せよ。不規則な間違いと系統的な間違い、すなわち、君が「不規則な間違い」と呼ぶ傾向のあるものと、「系統的な間違い」と呼ぶ傾向のあるものの間に、厳密な境界などない。
おそらく、Bに系統的な間違いをやめさせることは可能だろう(悪い習慣をやめさせるように)。あるいは、彼の書き写し方を認めた上で、通常の方法を、彼の方法の変種、ヴァリエーションとして教えようと努力する。 ―― だがここでもまた、私たちの生徒の学習能力は挫折するかもしれない。
144. では私は、「ここで私たちの生徒の学習能力は挫折するかもしれない」と言うとき、何を意味しているのか? 自分の経験からそのことを報告しているのか? もちろんそうではない。(たとえ過去に私がそういう経験をしていたとしても。)では一体、私はこの文で何をしているのか? 実は私は、君に「確かにそうだ、そういう事態は想像できるし、実際に起こりうることだ」と言ってもらいたいのだ。 ―― すると私は、これを想像することができるという事実について、誰かに注意を喚起しようとしていたのか? ―― [そうではない。] 私が意図していたのは、彼の目の前にこの像を提示し、彼がその像を承認するということは、今や与えられた事態を別様に考察したくなっている、すなわち事態をこの像の系列と比較したくなっているということに他ならない、ということだったのだ。私は彼の直観の仕方を変えたのである。(インドの数学者は言う。「これを見よ!」)
145. いま生徒が、私たちの満足のいくように0から9までの列を書き付けているとしよう。私たちが満足するのは、彼が頻繁に成功するときだけであり、100回に1回の割合で成功するときではない。いま私は、彼に数列をさらに先までたどらせ、1の位、ついで10の位に、再び1から9までの数字が現れていることに彼の注意を向けさせる。(それはただ、私がある種の強調を行ったり、数字の下に下線を引いたり、これこれの方法で上下に並べて書いたりすることに過ぎない。) ―― そして今や、彼は自力で数列を続けるに至るのである ―― あるいは続けないかもしれないが。 ―― [ある人が言う。] しかしなぜ君はそんなことを言うのか、それは自明のことではないか! ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] もちろん、私が言いたかったのはただ、これ以上いかなる説明をしても、その効果は彼の反応に依存している、ということである。
しかし今、教師の努力によって、生徒が数列を正しく続けられるようになった、つまり、私たちと同じように数列を続けるようになったと仮定しよう。このとき私たちは「彼はこの体系をマスターしている」と言うかもしれない。 ―― しかし、私たちが正当にそう言えるためには、どの程度まで彼は数列を正しく続けなければならないのだろう? ここにいかなる境界も引けないことは明白である。
146. いま私が「彼が100まで数列を続けられたら、かれはこの体系を理解しているのではないか?」と問うなら ―― あるいは、私たちの原初的な言語ゲームにおいては「理解する」ということについて語るべきではないのだとすれば、彼がそこまで正しく数列を続けられたとき、彼はこの体系を体得したと言えるのか? こう訊くと、君はおそらくこう言うだろう。「この体系を体得している(あるいは理解している)ということは、数列をこの数やあの数まで続けることではない。それは理解の適用に過ぎない。理解それ自身は一つの状態であって、そこから正しい適用が生じるのである。」
では、 [理解は一つの状態であると言うことで] 本当のところ何が思い描かれているのか? 代数式からある数列を導出すること、あるいはそれに類似したことを考えているのではないか? ―― しかし私たちは既に一度この点に触れた。私たちはまさしく代数式の適用を一つ以上考えることができるのだ。そして確かに、いずれの適用法も再び代数的に書くことができるが、それによって私たちが前進しないことは自明である。 ―― 適用は理解の一規準にとどまるのである。
147. [ある人が言う。] 「しかし、いかにして代数式の適用は理解の規準でありうるのか? 私が「私は数列の規則を理解している」と言うとき、その根拠は、今までその代数式をしかじかに適用してきたという経験にあるのではない! だがいずれにせよ、私は、私がこれこれの数列を意味している、ということを自分自身に対して知っているのであって、実際に私がどこまで数列を展開したかということはどうでもよいのである。」
[ウィトゲンシュタインが言う。] すると君はこう言いたいのか。君は、特定の数への実際の適用を記憶することを全く別にしても、数列の規則の適用を知っている、と。さらに君はおそらくこうも言うだろう。「そんなことは当然だ! なぜなら数列は無限だが、私が展開できた数列の部分は有限なのだから。」
148. するとこの [実際の適用を度外視した数列の規則についての] 知識は何において成り立っているのか? 私はこう尋ねたい。「君はいつこの適用を知っているのか? 常にか? 昼と夜か? あるいは君がまさに数列の規則について考えている間か? つまり君は、ABCや九九を知っているのと同じ仕方で数列の規則を知っているのか? あるいは君は、『知識』を意識の状態だとか、[意識の] 過程 ―― 例えば何かについて考えるという ―― だとか、そういうものだと言うのか?」
149. 人が「ABCの知識は心の状態である」と言うとき、彼は心の装置(例えば私たちの脳)の状態について考え、それを介して知識の様々な表出を説明する。そのような状態を、人は傾向性(Disposition)と呼ぶ[21]。しかし、ここで心の状態について語ることは、この状態に対して二つの規準 ―― 装置の作用と、それを度外視した装置の構成についての認識 ―― がある限り、反論を免れない。(ここで、意識状態と傾向性と対照させて「意識」と「無意識」という語を使うことほど混乱を招くものはあるまい。というのも、「意識」と「無意識」という語のペアは、 [「意識状態」と「傾向性」の間にある] 文法的差異を覆い隠してしまうからである。 )
(a) 「語を理解する」こと、それは一つの状態である。しかし心の状態であろうか? ―― 悲しみ、興奮、痛み、これらを私たちは心の状態と呼ぶ。そこで次のような文法的考察を行え。私たちは次のように言う。
「彼は一日中悲しかった。」
「彼は一日中とても興奮していた。」
「彼は昨日から間断なく痛み通しだ。」 ――
私たちはまた「私は昨日からこの語を理解している」とも言う。しかしその理解は「間断なしに」か? ―― 確かに人は理解の中断について語ることができる。しかしそれはどのような場合か? 「君の痛みはいつ和らいだのか?」と「君はいつこの語を理解しなくなったのか?」を比較してみよ。
(b) 人が「君はいつチェスをすることができるのか?」と尋ねたらどうであろう? 常にか、それとも駒を動かしている間か? そしてどの駒を動かすときでも、チェス全体を知っているのか? ―― もしそうなら、チェス全体 [の理解] にそんな短時間しか要さないのに、一勝負するのにずっと長い時間が必要であるというのは、何とも奇妙な話である。
150. 「知っている」という語の文法は、明らかに「できる」や「能力がある」という語の文法と密接に関係している。同時にまた、「理解する」という語とも密接に関係している。(ある技術を「マスターする」こと。) [第78節も参照。]
151. さてしかし、「知っている」という語には次のような使用もある。すなわち私たちは、「今や私はそれを知っている!」と言い ―― また同様に「今や私はそれをできる!」とか「今や私はそれを理解している!」と言う。
こういう例を示そう。AがBに対して数列を書き出して見せている。Bはそれを見て、数列の中に法則を見つけようと努力している。もしBが法則を見つけたら、「今や私は先を続けることができる!」と叫ぶ。 ―― この能力、この理解は、それゆえ、一瞬のうちに起こるものなのだ。そこで、一体このとき何が起こったのか、注意して調べてみよう。 ―― Aは1, 5, 11, 19, 29のように数字を書き連ねた。それを見たBは、今やその先を知っている、と言う。そこで何が起こったのか? 様々なことが起こりえた。例えば、Aがゆっくりと数字を一つづつ書いてゆく間、Bは様々な数式を書かれた数字に当てはめようと躍起になっている。Aが19を書いたとき、Bはan = n2 + n - 1 という式を試していた。すると、直後の数 [29] が彼の仮定の正しさを証明した。
あるいは別の場合。Bは式を考えていない。彼はある種の緊張感を持って、Aが数字を書く様子を見ている。そのとき、彼の頭には雑多で不明瞭な考えが浮かんでいる。そしてついにBは「項差の数列はどうなるか?」と自問する。それが4, 6, 8, 10となることを発見し、彼はこう言う。「今や私は先を続けることができる。」
さらに別の場合。彼は数列を見て、「ああ、この数列なら知っている」と言い ―― そして先を続けてゆく。ちょうどAが1, 3, 5, 7, 9と書いた場合にそうしたように。 ―― あるいはBは何も言わずに、ただ数列を続ける。恐らく彼は、人が「こんなの簡単さ!」と呼びうる感覚を持ったのだろう。(そのような感覚は、例えば、少し驚いたときに、小さく素早く息を吸い込むような感覚である。)
152. しかしそれでは、私が記述したこれらの過程が理解なのだろうか?
「Bは数列の体系を理解している」ということは、Bの念頭に「an = ・・・」という数式が浮かんでいる、というような簡単なことではない。なぜなら、Bの念頭に式が浮かびながら、Bがそれを理解していない、ということも十分考えられるからである。 [従って] 「彼は理解している」ということは、彼の念頭に式が浮かんでいること以上のことを内容として含まなくてはならない。そして同様に、理解するということに多かれ少なかれ特徴的な、随伴過程や外的表出よりも多くのことを含まなくてはならない。
153. いま私たちは、理解の心的過程、すなわち [心的過程よりも] ずっと粗くて私たちの眼にも見えやすい、かの随伴現象の背後に隠れていると思われる過程を把握しようと試みている。しかしこの試みは成功しない。より正確に言うなら、それは全く本当の試みにならない。なぜなら、仮に理解のあらゆる場合に起こる何かを私が発見したとして ―― なぜそれが理解でなくてはならないのか? 理解しているからこそ、「今や私はそれを理解している」と言うのに、理解の過程が隠されていることなどありえようか?! そして私が「理解の過程は隠されている」と言うとき、 ―― いかにして私は自分が探しているものを知るのか? 私は混乱に陥ってしまう。
154. [ある人が言う。] だが待ってほしい! ―― もし「今や私はこの体系を理解している」が「・・・・・・という式が私の念頭に浮かぶ」(あるいは「私はその式を口に出して言う」、「私はその式を書き出す」)と同じことを言うのでなければ、 ―― そのことから、私は「今や私は・・・・・・を理解している」や「今や私は先を続けることができる」という命題を、ある過程 ―― 式を口に出して言うことの背後に存在する、あるいはそれに随伴する過程 ―― の記述として用いている、ということが帰結するだろうか?
[ウィトゲンシュタインが言う。] もし「式を口に出して言うことの背後に」過程が存在しなければならないとすれば、それは、念頭に式が浮かんだとき、私が「私は先を続けられる」と言うことを正当化してくれるある種の状況である。
決して理解が「心的過程」であると考えてはならない! ―― なぜならそれは、君を混乱に落とし入れる言い回しに他ならないからだ。代わりに次のように問え。どのような場合、どのような状況において、私たちは「今や私は続きを知っている」と言うのか? つまり、式が私の念頭に浮かんだとして、である。 ――
理解にとって特徴的な諸過程(心的過程も含む)が存在するという意味では、理解は決して心的過程ではない。
(痛みの感覚の増減、音楽や文を聴くこと、これらは心的過程である[22]。)
155. それゆえ私はこう言いたくなる。彼が突然、数列の続きを知り、体系を理解したとき、恐らく彼はある特別な体験 ―― その体験は、例えば彼に「君が体系を突然把握したとき起きたことは、どんなことだったのか?」と聞いたときに、彼が描写してみせるものであり、私たちが [第151節で] 述べたことと似たようなものである ―― をしたのだ、と。しかしそのような場合、私たちにとって、彼の「理解している」とか「続きを知っている」という言葉を正当化するものは、 [彼の特別な体験ではなく] 彼がそのような体験をした状況である。
156. この論点は、別の語、すなわち「読む」という語についての考察を挿入することで、より明確になる。まず最初に断っておかなければならないが、私はこの考察における「読む」に、読まれたものの意義を理解することを含めない。ここでは、読むということは、書かれたものや印刷されたものを音声に置き換える行為である。しかしまた、口述筆記をすること、印刷物を書き写すこと、楽譜に従って演奏することなども含めよう。
日常生活の様々な状況におけるこの「読む」という語の使用は、もちろん私たちにとって極めて馴染み深いものである。しかし、生活においてこの語が果たす役割は、それゆえまた私たちがこの語を用いて行う言語ゲームは、大まかに描写することさえ困難であろう。人間、例えばドイツ人は、学校や家で、私たちにとっては普通の教育方法を受け、授業で母国語を読むことを習った。その後で彼は、本、手紙、新聞などを読むのである。
さて、彼が例えば新聞を読むとき、そこでは何が起こっているのか? 彼の眼が印刷された言葉に沿って ―― いわば ―― 滑ってゆく。そして言葉を声に出して読む、あるいは、心の中で言う。しかも彼は、ある種の言葉はその表現形式を全体として把握して読み、別の言葉は彼の眼が最初の音節を把握した後に読む。さらに幾つかの言葉は分節ごとに読み、また一つか二つの言葉はアルファベットごとに読むかもしれない。 ―― あるいはまた、彼が読む間、声に出すことも心の中で言うこともしなかったとしても、その文をもう一度正確に、あるいはほぼ正確に繰り返すことができたなら、私たちは「彼は文を読んだ」と言うであろう。 ―― 彼は読むものに注意を集中することができるし、あるいはまた ―― 言うなれば ―― 単なる音読機械として機能することもできる。音読機械とはつまり、読むものに注意を集中させることなしに声を出して正しく読むということである。その場合、読んでいる間、彼の注意は全く別のものに向けられているであろう。(それゆえ、読んだ直後に誰かが読んだものについて質問しても、彼は答えることができない。)
それでは、この音読機械と初心者を比較してみよ。初心者は、苦労しながら言葉を文字を判読して読み進める。 ―― だが中には文脈から推測のつく言葉もあれば、部分的には既に暗記している箇所もあるかもしれない。すると教師は、彼はその言葉を本当に読んでいるわけではない、と言う(そして場合によっては、読んでいる振りをしているだけだ、とまで言う)。
この読み、すなわち初心者の読みについて考え、読むとは何において成り立っているのかと問うとき、私たちは「読むとは、ある特別で意識的な心的行為である」と言いたくなるであろう。
私たちはまた、生徒についてこうも言う。「生徒が本当に言葉を読んでいるか、それともただ暗記して喋っているだけか知っているのは、生徒本人だけである。」 (「彼だけが・・・を知っている」という命題については、さらに議論が必要である。)
しかし私は言いたい。 ―― 印刷された語のどれか一つを声に出すということに関しては ―― それを読む「振りをしている」生徒の意識の中では、それを本当に「読んでいる」熟達した読者の意識の中で起こることと、全く同じことが起こりうる。「読む」という語は、初心者について用いられるときと熟達した読者について用いられるときとでは、異なる使われ方をするのである。 ―― すると私たちは、当然こう言いたくなる。同一の語を熟達した読者が発する場合と初心者が発する場合に起こることは、同じことではありえない。そして、両者に直接意識されていることの間に差異がないとすれば、彼らの心の無意識的活動のうちに、あるいは彼らの脳のうちに、差異があるに違いない。 ―― 従って次のように言いたくなる。「いずれにせよ、ここには二つの異なった仕組みがある! そして二つの仕組みのうちで起きていることは、読むことを読まないことから区別するものに違いない。」 ―― だがこの仕組みはただの仮説である。つまり、説明のための、あるいは君が知覚するものをまとめるためのモデルに過ぎない。
157. 次の例についてよく考えよ。人間、または別の生物が、私たちによって音読機械として使われるとしよう。彼らはこの目的のために訓練されるのである。教師は、彼らのうちのある者について「もう読むことができる」と言い、他の者については「まだ読むことができない」と言う。いま、この訓練に初めて参加する生徒について考えよう。書かれた文字をこの生徒に見せると、彼は時には何らかの音声を発する。そして時々、「偶然」彼の音声が語の正しい発音と、大体一致することがある。その場合を聞いた第三者が「彼は読んでいる」と言う。しかし教師は「いや、読んでいない。今のはまぐれだ」と言う。 ―― しかし、生徒がさらに幾つもの語について正解を連発したらどうであろう? 今度は教師も「今や彼は読むことができる!」と言う。 ―― だがそうすると、あの最初の語の場合はどうだったのか? 教師は「私が間違っていた。彼は最初の語も読んでいた」と言うべきなのか ―― それとも「彼が最初に読み始めたのは、もっと後だ」と言うべきなのか? ―― 一体、生徒はいつ最初に読み始めたのだろう? 彼が初めて成功した語はどれだったのだろう? 今の場合、この問いは無意義である。もっとも、初成功の語を「続けて正しく読んだ最初の50語」(例えばである)と定義するなら話は別だが。
反対に、「読む」という語を、記号から音声へ置き換える、ある種の体験のために用いるなら、彼が本当に読んだ最初の語について語ることは、意義を持つ。例えば彼は「私はこの語のときに初めて『今や私は読んでいる』という感覚を持った」と言うことができる。しかしまた、これとは異なった、自動ピアノのような仕方で記号を音声に置換する音読機械の場合は、「これこれのことが機械に起こった ―― かくかくの部分がワイヤーで結ばれた ―― 後で、機械は読むようになった。それゆえ、この機械が読んだ最初の記号は・・・である」と言うこともできよう。
だが生きた音読機械の場合、「読む」ということは、文字記号に対してしかじかに反応するということである。従ってこの概念は、心の仕組みや他の何らかの仕組みには全く依存しなかったのだ。 ―― このとき、教師は訓練を受けた者について「おそらく彼は、既にこの語を読んでいたのだ」と言うことはできない。なぜなら、生徒がしたことには、全く疑いはないのだから。生徒が読み始めたときに起こった変化は、 [彼の心の仕組みの変化ではなく] 彼の振舞いの変化であった。そしてそのとき、「 [彼が読み始めたという] 新しい状態における最初の語」について語ることは、何の意義も持たない。
158. [ある人が言う。] しかし、「新しい状態における最初の語」について語ることが意義を持たないのは、脳や神経組織の中の諸過程についての私たちの知識が乏しいせいではないか? もしそれらについてより詳細な知識を持てば、私たちは、訓練を通じていかなる神経結合が作られるのかを知るだろうし、そうすれば生徒の脳の中を覗いて「いま彼はこの語を読んだ。なぜなら、いま読書神経の結合が作られたから」と言うことができるだろう。 ―― そのことは間違いない ―― なぜなら、そうでなくては、そのような結合が存在するという確信をいかにして持つことができるだろう? それはきっとア・プリオリにそうなのだ ―― それとも、ただ蓋然的にそうなのだろうか? もしそうなら、それはどのぐらい蓋然的なのか? [ウィトゲンシュタインが言う。] だが自問せよ。君はこうした事柄について一体何を知っているのか? ―― それでもそうした結合の存在がア・プリオリならば、それが私たちにとって、極めて分かりやすい表現形式だということである。
159. しかし、このことについてよく考えると、「読んでいるということの唯一本当の規準は、読むという意識的活動、文字を声に出して読むという意識的活動である」と言いたい誘惑に駆られる。「読んでいる人間は、自分が読んでいるか、読む振りをしているだけか知っている!」というわけだ。 ―― Aが、自分がキリル文字を読むことができるということを、Bに信じさせようとするとしよう。Aはロシア語の文を暗記して、それから印刷された文字を見て、まるでそれを読んでいるかのように振舞う。この場合、確かに私たちは「Aは、自分が読んでいないこと、そして読む振りをする間中、まさに自分が読んでいないことを知っている」と言うだろう。なぜなら、程度に差はあれ、印刷された文を読むということに特徴的な感覚が多数存在するのは当然だからである。そのような感覚を思い起こすことは難しくない。言いよどむ、文を正確に見る、読み間違う、個人差はあれ流暢に読む、などなどの感覚を想起せよ。そして同様に、暗記した文章を口に出すことに特徴的な感覚というのも存在する。今の場合、Aは読むことに特徴的な感覚は一つも持たず、例えば嘘をつくときに特徴的な一連の感覚を持つであろう。
160. だが次のような例を考えよ。ある文章を流暢に読むことができる人間に、まだ彼が一度も読んだことのない文章を渡す。彼はそれを私たちに読んで聞かす ―― ただし、暗記した文章を口に出すときに持つ感覚を伴って、である(こういうことは、何かの薬物の作用によってありえよう)。この場合、私たちは、彼はテキストを実際には読んでいない、と言うだろうか? つまりこの場合、私たちは彼の感覚を、彼が読んでいるか否かを見分ける規準とみなしているだろうか?
あるいはまた、こういう例を考えよ。ある特定の薬物の影響を受けている人間に対し、一連の文字列を見せる。その文字列は現存のアルファベットに属している必要はない。すると彼は、記号のまとまりに応じて、あたかもその記号がアルファベットであるかのように文字を発音する。しかも読むことの全ての外的特徴と感覚を伴って。(似たような経験を私たちは夢の中で持つことがある。そして目覚めた後、「全く記号ではないのに、まるで記号を読んでいるかのように思った」などと言う。)そのような場合、大抵の人は、その人は記号を読んでいるのだと言いたいであろう。別の人は、読んでいないと言うかもしれない。 ―― 彼がこの仕方で一群の4つの記号をOBENと読んだ(あるいは解釈した)と仮定せよ。 ―― 今度は、同じ記号を逆順にして見せると、彼はそれをNEBOと読んだ。そしてそれ以後の試みにおいても一貫して、この4つの記号に対して同じ解釈を与えるのである。このとき、私たちはきっと、彼は毎回、一つの記号に一つのアルファベットを適切に当てて、それから読んでいるのだと言いたくなるであろう。
161. ところでまた、読むべきものを暗記して口にする場合と、文脈からの推測や暗記した知識の助けを借りずに各語を一文字づつ読む場合との間には、一連の連続的な推移が存在するという点にも注意せよ。
次のことを試みよ。まず1から12までの数列を言え。次に時計の文字盤を見て、書いてある数列を読め。 ―― 後者の場合、君は何を「読む」と呼んだか? つまり、後者の場合を読むということにするために、君は何を行なったのか?
162. 「人が手本から複製を導き出している場合、その人は読んでいる」という説明を調べてみよう。ここで「手本」とは、彼が読む、あるいは書き写すためのテキスト、書き取るための口述、演奏するための楽譜、などのことである。 ―― さて、例えば誰かにキリル文字を習わせて、各文字の発音を教えたとする。そして彼に文章を見せ、彼が各文字を教えた通りの発音で読んだなら ―― 私たちはきっと、彼は、私たちが彼に与えた規則の助けを借りて、語の音を記号像から導き出している、と言うだろう。そしてこれもまた、読むという事例の明確な一例なのである。(私たちは彼に「アルファベットの規則」を教えた、と言えるかもしれない。)
しかしなぜ私たちは、彼が印刷された語から発音される語を導き出したと言うのか? 私たちは彼に各語の発音を教え、それから彼が語を声に出して読んだ。それ以上のことを、私たちは知っているのか? もしかしたら、私たちはこうこう答えるかもしれない。この生徒は、与えられた規則の助けを借りて、印刷物から音声への推移を示しているのだ、と。 ―― どのようにすればこのことを示しうるかは、今の例を次のように修正するとより明確になる。つまり、生徒はテキストを朗読する代わりに、それを書き取ることにし、印刷された文書を手書きの文書に移させるのだ。というのも、このようにすると、規則を表の形で彼に与えることができるからである。表の一列目には活字体の文字があり、二列目には筆記体の文字がある。そして彼が印刷された文書から手書きの文書を導き出すということは、彼が表を調べることのうちに示されるのである。
163. しかし、彼がこの作業を行うとき、Aをbに、Bをcに、Cをdに・・・Zをaに書き換えたとしたらどうであろう? ―― それでも私たちは、これも表に従った導出と呼ぶだろうか? ―― いわば彼は、第86節の一番目の図式の代わりに二番目の図式に従ったのだと言えよう。
これもまた表に従った導出であるには違いなく、単純な規則性は全くないが、やはり図式によって再生されるであろう。
しかし、彼が一つの書き換え方を継続せず、別の単純な規則によってそれを変更すると仮定せよ。一旦Aをnに書き換えたら、次はoに書き換え、その次はpに書き換えるといった具合である。 ―― このやり方と不規則なやり方の境界はどこにあるのか?
今や「導き出す」という語は、その意味を追っていくと溶けて消えてしまうように思われる。すると、この語は本当は全く意味を欠いていたのだろうか?
164. 第162節の事例では、「導き出す」という語の意味は、私たちにとって明確であった。しかし私たちは、それは導出の極めて特殊な一例、極めて特殊な装いをした例に過ぎず、もし導出の本質を知りたいなら、それを剥ぎ取らなくてはならないと自らに言い聞かせた。そして私たちはその特殊な装いを剥ぎ取ったのだが、すると導出そのものが消え去った。 ―― 本当の玉葱を見つけようとして、皮を全て剥いてしまったのである。第162節の事例は、もちろん導出の特殊例ではあったが、導出の本質はこの事例の外見に隠されていたのではなく、この「外見」の方こそ、導出の諸事例から成る家族の一員だったのである。
同様に、私たちは「読む」という語も、諸事例から成る一つの家族に対して用いる。そして私たちは、「読む」ことの様々な規準を状況に応じて使い分けているのである。
165. それでも私たちは、読むとは完全に確定的な過程であると言いたくなる。印刷物のページを読んでみよ、そうすればそのとき、特別な何か、極めて特徴的な何かが起きていることが分かる。 ―― さて、私が印刷物を読むとき、一体何が起きているのか? 私は印刷された語を見て、それを口に出す。だがもちろんそれだけではない。なぜなら、私は確かに印刷された語を見て、それを口に出すことができるが、それだけではまだ読むことではないであろうから。そしてまた、私が発する語が、現存するアルファベットに従って人が印刷物から読み取るべき語と一致していたとしても、それだけではまだ読むことではないであろうから。 ―― もし君が、読むとはある確定的な体験だと言うのなら、君が人々によって一般的に認められたアルファベットの規則に従って読むか否かということは、全く何の役割も果たさない。すると、読むという体験に特徴的なこととは、どういうものなのか? ―― ここで私は言いたい。私が発する語は、特別な仕方で現れる、と。すなわち私が発する語は、私がそれを思いつくときとは異なる現れ方をするのである。 ―― それらは自ずから現れる。 ―― しかしこれでもまだ十分ではない。なぜなら、確かに印刷された語を見ている間、語の音が私の念頭に浮かぶことはあり得るが、それによって語を読んでいることにはならないからである。 ―― だがなお私は言うことができる。発せられた語は、例えば何かがそれを思い出させるときのように私の念頭に浮かんでくるのではない、と。私は、例えば印刷された「ない」という語が常に私に「ない」という音を思い出させると言いたいのではない。そうではなく、発された語は、読む際に、いわば [自ずから] するっと入り込んでくると言いたいのだ。私は確かに、ある印刷されたドイツ語の単語を、その語の音を心の中で聞く固有の過程なしには見ることができないのである。
「完全に確定的な」(雰囲気)という表現の文法。
人は「この顔は完全に確定的な表情を持っている」と言い、例えばその表情を特徴づける言葉を探す。
166. 私は、読むときに語は「特別な仕方で」現れると言った。だがそれはどのような仕方なのか? それは幻想ではないのか? 個々の文字を見て、どのような仕方で語の音が現れるのか注意してみよう。Aという文字を読め。 ―― さてその音はどのように現れたか? ―― 私たちはそれについて何を言うべきか全く知らない。 ―― では小文字のaを書け! ―― 書くときの手の動きはどのように現れたか? ―― さっき試みたときの音とは異なる現れ方をしたのか? 私は印刷された文字を見て、筆記体の文字を書いた。それ以上のことは知らない。 ―― さて、
167. では、「読むことは完全に確定的な過程である」という命題においては、何が言われているのか? それはもちろん、読む際に常にある確定的な過程が起こり、私たちはそれを再認する、ということである。 ―― だが、私があるときは印刷された文を読み、別のときにその文をモールス記号で書くとすると ―― 本当にどちらの場合にも同一の心的過程が生じるだろうか? これに対し、しかし、印刷された一ページを読むという体験においては当然、ある同質性が存在する。なぜなら、その過程は確かに同質的なものだからである。そしてこの過程が、 [
語の視覚像は、聴覚像と同程度に私たちにとって馴染み深いということに注意せよ。
168. また、視線が印刷された列の上を滑るとき、その滑り方は任意の鉤型や渦巻き模様の列の上を滑るときとは異なる。(私はここで、読む人の眼の動きを観察することで確認できる事実について述べているのではない。) いわば視線は、特に抵抗もなく、ひっかかることもなく滑るが、かといって上滑りしているわけではない、と言うことができよう。そしてそのとき、表象の中で無意識的な発声が行われている。私がドイツ語や他の言葉を読むとき、印刷されたものにせよ手書きのものにせよ、また様々な書体で書かれていても、そうしたことが行われている。 ―― だがこれら全てのうちで、読むことについて本質的なものは何か? それは読むという全ての場合に共通して起こる一つの特性、ではない! (見慣れた印刷物を読む際の過程と、クロスワード・パズルの答えのような、全て大文字で印刷された言葉を読むことを比較せよ。およそ似つかない過程である! ―― または、普通の文章を右から左へ読むことと比較せよ。)
169. [ある人が言う。] しかし私たちは読むとき、語の形象を一種の原因として私たちの発声が引き起こされていると感じるのではないか? ―― まずある文を読め! ―― 次に
&8§≠§≠?ß +%8!'§☆
という記号列を見ながら文を声に出せ。最初の場合、発声は記号を見ることと結びついているように感じられたが、二番目の場合、そのような結びつきはなく、記号は見ることの傍らを通り過ぎていったように感じられたのではないか?
[ウィトゲンシュタインが言う。] しかし、なぜ君は因果関係を感じると言うのか? 因果関係とは実験によって確認されるものである。例えば、複数の出来事が規則的に同時に生起することを観察することによって。一体、実験によって確認されることを感じるなどと、どうして言うことができようか? (因果関係を確認する仕方が、規則的な同時生起を観察することだけではない、ということは確かに正しいのだが。) むしろ、文字を、なぜ私がしかじかに読むかの理由であると感じる、ということは言えるかもしれない。なぜなら、「なぜそう読むのか?」と訊ねられたなら ―― 私はそこにある文字によって根拠づけを行うからである。
しかし私がいま述べ、考えた根拠づけを感じるとは、一体どういうことか? 私はこう言いたい。私は読む際に、文字の私に対するある種の影響を感じるが ―― しかし、あの任意の渦巻きの列が私の語ることに及ぼす影響は感じない、と。 ―― 再度、個々の文字を個々の渦巻きと比較してみよう! 私は「i」の文字を読むとき、その文字の影響を感じる、とも言うだろうか? 当然、「i」を見てiの音を発することと、あるいは「§」を見てiの音を発することは、異なることである。この相違は例えば、文字を見るときにiの音の内的な響きが自動的に、つまり私の意志に逆らって生じ、私がその文字を読むとき、その発声は「§」を見て発声するときよりも努力を要しない、ということである。すなわち ―― 私がこの試みを行うときは、そういうことが起こるが、しかしもちろん、私が偶然「§」を眼にしてiの音が含まれる語を発するときには、そういうことは起こらないのである。
170. 文字の場合を任意の線記号の場合と比較しなければ、私たちは「読む際に文字が私たちに及ぼす影響を感じる」という考えには到達しなかったであろう。確かに私たちは両者にある差異を認める。そしてこの差異を私たちは、影響の存在と影響の欠如として解釈する。
確かに私たちは、読む際に一体何が起きているのかを見るために意図的にゆっくり読む場合、とりわけこの解釈に傾くものである。いわば私たちが、まさに意図的に文字によって導いてもらう場合、である。しかしこの「私が導いてもらう」ことは、やはり、文字をよく見つめることによって ―― 例えばある種の他の考えを排除することによって ―― のみ成立する。
私たちはいわば、ある感情によって、語の形象と私たちが発する音との結合メカニズムを知覚するのだと想像している。なぜなら、影響を受ける体験、因果関係の体験、導かれる体験について私が語るとき、それが意味するのは、いわば、文字を見ることを発声と結びつけるようなレバーの動きを感じているということだからである。
171. 私は、語を色々な読み方で読む際の自分の体験を、適切な言葉で表現することができるかもしれない。もしそうなら、書かれた文字は私に音声を吹き込むと言うことができよう。 ―― あるいはまた、文字と音声は読む際に一つの統一体 ―― いわば合金のような ―― を形成するとも。(似たような融合は、例えば有名人の顔と名前の響きの間にもある。私たちには、この名前が顔に対する唯一正しい表現であるように思われる。) この統一体を感じるとき、私は書かれた語の中に音声を見、あるいは聞いている、と言えるかもしれない。 ――
しかしもう一度、読むという概念について考えない普段どおりのやり方で、印刷された文章を幾つか読んでみよ。そして、読んだとき、統一体や影響を感じるような体験を持ったかどうか自問せよ。 ―― 「無意識のうちにそういう体験を持った」という答えは却下する! また「もっとよく見れば」そのような現象が現れるであろう、という考えに眩惑されてはならない! [なぜなら] ある対象が遠くからどのように見えるかを記述しなければならないとき、対象をもっと近くで見たときに分かることを述べたとしても、それによって記述がより正確になることはないからである。
172. 導かれるという体験について考えよう! 例えば私たちがある道へ導かれるとき、この体験は何において成り立つのか? ―― 次のような場合を想像せよ。君はある広場にいて、例えば目隠しをされている。そして誰かに手を引かれ、時には左へ、時には右へ曲がる。君は常に彼の手の引き方を予期しなければならず、また、不意の動きにもつまづかないよう注意しなければならない。
あるいはまた、誰かに無理やり手を引かれて、行きたくもない所へ連れて行かれる。
あるいは、ダンスのときパートナーに導かれる。君は相手の意図を予測し、僅かな押しにも従うために、可能な限り受動的に踊る。
あるいは、誰かが君を散歩に連れて行く。話しながら歩く。彼がどこへ行こうと、君もそこへついていく。
あるいは、農道に沿って歩き、道が導くままに歩く。
これら全ての状況は互いに似通っている。しかしこれら全ての体験に共通のものとは何だろう? [第66節 - 第67節も参照。]
173. 「しかし導かれるというのはやはり一つの確定的な体験だ!」 ―― これに対する答えはこうである。「君は今、導かれるという一つの確定的な体験について考えている。」
[第162節 - 第163節の例のように] ものを書く際、印刷された文章や表によって導かれている人の体験をありありと思い浮かべようとするとき、私は「良心的に」表に従うといったことを想像する。私はその際、特定の顔の表情さえ想像するのである。(例えば良心的な帳簿係の表情を。) この表情にとても本質的なことは、例えば注意深さである。一方、あらゆる固有の意志が排除されていることをその本質とする表情もある(普通の人間なら不注意な表情を伴って行うことを、注意深い表情を伴って ―― そしてなぜ注意深い感覚ではないのか? ―― 行う人間について考えよ。 ―― さて、彼は本当に注意深いのか? ウェイターが、注意深さを示す外面的な特徴を伴いつつ、トレイを皿ごと落としてしまう、という場面を想像せよ。) このように特定の体験をありありと思い浮かべれば、私には、それが導かれている(あるいは読んでいる)という体験そのものであるように思われる。しかしここで私は自問する。お前は何をしているのか? お前はそれぞれの記号を見、こういう表情をし、慎重に文字を書きつける(等々)。 ―― だからこれが導かれるという体験だというのか? 私はこう言いたくなる。「そうではない。そうした体験はもっと内的な、もっと本質的な何かである。」 ―― それではまるで、これら全てが確定的な雰囲気に包まれてはいるが、程度に差はあれ非本質的な過程であり、もっとよく見れば消え失せるものであると言わんばかりである。
174. 「慎重に」ある直線を与えられた直線と平行に引く、あるいは慎重に直角に引く、ということをいかにして行うのか、自問せよ。慎重という体験は何であるか? すぐに思いつくのは、ある確定的な表情や身振りである。 ―― そして君はこう言いたくなる、「これぞまさに確定的で内的な体験である」と。(もちろん、こう言うことで、君はそれ以上の何も言っていない。)
(ここで言われていることは、意図や意志の本質についての問いと関係している。)
175. 紙の上に適当に絵を描け。 ―― それから、元の絵に導かれるままに模写してみよ。 ―― このとき私はこう言いたくなる。「間違いない! いま私は導かれている。しかしその際どのような特徴的なことが起こったのか? ―― 起こったことを私が述べたとしても、もはやそれは特徴的なことだとは思われない。」
さてしかし次のことに注意せよ。私が導かれている間は、全てが全く単純で、何一つ特別なことは認められない。ところが終わってから、そのとき起こったことを述べる段になると、語ることのできない何かが存在したかのように思われる。終わった後は、いかなる記述も私も私を満足させない。いわば私は、自分がただ元絵を見て、このような顔をし、線を引いただけだ、ということを信じられないのである。 ―― だが一体、私は他に何を思い出すというのか? 何もない。だがそれでも、あたかも何か別のものが存在しなければならなかったように思われるのだ。特に、「導く」、「影響」などの語を自分に言い聞かせているときには。「なぜなら、私はそれでも導かれていたのだから」と、私は言う。 ―― このようにして、エーテルのように捉えどころのない、影響という観念が生じるのである。
176. 後になってから体験について考えるとき、私は、それについての本質的なものが「影響を受けた体験」、ある結合の体験 ―― 複数の現象の単なる同時性と対比した意味での ―― であるという感情を抱く。しかし同時に私は、自分のいかなる体験も「影響を受けた体験」と呼びたくはない。(ここには、意志は現象ではないという観念が働いている。) 私は「なぜなら」を体験したけれども、いかなる現象も「なぜならの体験」とは呼びたくない、ということである。
177. 私は「なぜならを体験する」と言いたいのだが、しかしその理由は、私がこの体験を思い出すからではなく、ある場面で体験したことを後から考える際、「なぜなら」という概念(あるいは「影響」、「原因」、「結合」などの概念)を媒介としてこの体験を見るからである。 ―― というのも、私がこの線を手本の影響を受けて引いた、ということは、もちろん正しいからである。しかしこのことは、私が線を引く際に感じることのうちにある、というような単純な話ではなく、 ―― 事情によっては例えば、私が線を別の線と平行に引くことのうちにあるのだ。たとえこれが、導かれることに関する一般的に本質的なことではないとしても。 ――
178. 私たちはまた「君は確かに、私がそれに導かれるのを見ている」とも言う。 ―― だが、それを見ている人は何を見ているのか?
私が自分に向かって「私はそれでも導かれている」と言うとき ―― 例えば、導きを表現する手振りをする。あたかも誰かを導くような、そうした手振りをしてみよ。そして、この手振りの導きは何において成り立っているのか自問せよ。というのも、この場合、君は誰一人導いていないのだから。だがそれでも君は、この手振りを「導いている」ものと呼びたいであろう。従って、この手振りや感覚においては、導くことの本質は何もないのである。それでもこの手振りが君を駆り立てて「導くもの」という呼称を使わせたのである。これがまさに、導くということの一つの現象形式であり、私たちに「導くもの」という表現を強要するものである。
179. 第151節の例へ話を戻そう。Bの念頭に数式が浮かんでいるからといって、数式を想起すること ―― あるいは口に出すこと、書き付けること ―― と、実際に数列を続けることの間にある関係が成立していなければ、彼に「今や私は続きを知っている」と言う権利があるとは、私たちは言わないだろう。そしてそのような関係が成り立っていることは、確かに明らかである。 ―― ところで、「私は続けることができる」という命題は「私は、自分を数列を続けることに経験的に導いてくれる体験を持っている」という命題と同じようなことを意味している、と言うことができるだろう。しかしBが「私は続けることができる」と言うとき、彼はそのことを意味しているのか? 数列を続けるとき、この命題がBの心の中に浮かんでいるのか、あるいは彼にはこの命題を、自分が意味していることの説明として与える用意があるのだろうか?
そうではない。「今や私は続きを知っている」という言葉が正しく適用されたのは、数式が彼の念頭に浮かんだとき、すなわち、ある状況下においてであった。例えば、彼が代数を習得済みで、以前にそのような数式を使用したことがあった場合である。 ―― このことはしかし、「今や私は続きを知っている」という言明が、私たちの言語ゲームの舞台を構成している全状態の記述の単なる省略形に過ぎない、ということではない。 ―― 「今や私は続きを知っている」、「今や私は先を続けられる」等の表現の使い方をいかにして学ぶか、考えてみよ。いかなる言語ゲームの家族において、私たちはこうした言葉の使用を学ぶのか。
私たちはまた、こういう場合を想像できる。それは、Bの心の中で、彼が突然 ―― 例えばある閃きの感情と共に ―― 「今や私は続きを知っている」と言うこと以外のことが起こらない場合、そして今や、数式を使うことなく、実際に数列の先を計算していくような場合である。そしてそのような場合においても、やはり私たちは ―― ある種の状況においては ―― Bは続きを知った、と言うであろう。
180. 以上のようにして、これらの言葉は使用される。前節の最後の場合、これらの言葉を、例えば「心的状態の記述」と呼ぶことは全くミスリーディングであろう。 ―― むしろこの場合、それらを「合図(Signal)」と呼ぶことができるだろう。こうした言葉が正しく適用されたかどうかは、彼が続きを書き出した後で判断されるのである。
181. このことを理解するために、私たちはまた次の事例についてもよく考えなければならない。Bが、続きを知っていると言う、と仮定せよ。 ―― ところが実際に続けようとすると、言葉に詰まってしまい、続けられない。私たちとしては、先を続けられると言う権利はBにはない、と言わねばならない。だが、彼は「続けられる」と言ったときは続けられたが、ただ今だけは続けられなかったのではないか? ―― 私たちが様々な場合に様々に言う、ということは明らかである。(両方の場合についてよく考えよ。)
182. 「適合する」、「できる」、「理解する」という語の文法。問題(1) 人が、シリンダーZが空洞シリンダーHに適合する、と言うのはどのような場合か? ZがHにはまっている間だけか? (2) 人はしばしば、しかじかの時にZはHに適合しなくなる、と言う。その場合、そのときにそれが起こることについて、いかなる規準を用いるのか? (3) ある時に物の重さが変化したとき、それが秤に乗っていなかったとしたら、何を変化の規準と考えるのか? (4) 昨日、私はその詩を暗記していた。しかし今日はもう覚えていない。このとき、「私はいつその詩を忘れたのか?」という質問が意義を持つのはいかなる場合か? (5) ある人が私に訊ねる。「君はこの分銅を持つことができるか?」 私は「できる」と答える。「ではやってみよ!」と彼。 ―― しかし私は持ち上げられなかった。いかなる状況においてなら、「『できる』と答えたときは、私はできたんだ。ただ今だけはできないんだ」という言い訳が通用するだろうか? 私たちが「適合する」、「できる」、「理解する」に対して妥当させている規準は、一見してそう思われるよりもずっと複雑である。すなわち、これらの語を使うゲーム、これらを手段として行われる言語的やり取りにおけるその使用は、私たちが信じたいと思う以上に錯綜しており ―― 言語ゲームにおけるこれらの語の役割も、私たちが信じたいと思うものとは異なっている。
(哲学的パラドクスを解消するためには、これらの語の役割を理解しなければならない。そしてそれゆえ、そのためには通常一つの定義では不十分である。まして語が「定義不可能」であることを確認するだけでは、ますます不十分である。)
183. さてしかし、 ―― 第151節の例における「今や私は先を続けることができる」という言葉は、「今や私の念頭にその数式が浮かぶ」とか、あるいは他のことと同じことを意味しているのか? この二つの命題が同じ意義を持っている(同じことを行う)と言うことのできる状況が、確かにある。 [第179節を参照。] しかしまた、両者は一般的に同じ意義を持っているのではない、と言うこともできる。また私たちは「今や私は先を続けられる。つまり私が意味するところは、私はその数式を知っている、ということである」とも言う。ちょうど「私は行くことができる。つまり、私には時間がある」とか「私は行くことができる。つまり、私はもう十分健康だ」とか、あるいは私たちが脚の諸条件を他の諸条件と対比する場合に「私は行くことができる。私の足の状態に関して言えば」と言うように。このとき、事の本性に応じた全ての諸条件の総体(例えば、行くということに対しては、時間がある、健康である、脚に故障がない、などの条件の総体)というものがあり、全ての条件が満たされたなら、いわば、彼は行かざるをえないのだ、などと信じることがないよう注意しなければならない。
184. 私はあるメロディーを思い出そうとするが、思い出せない。すると突然「今分かった!」と言い、それを口ずさむ。私がそれを突然知ったとき、どういうことが起きたのか? その瞬間、メロディーの全体が私の念頭に浮かんだということはありえない! 君は恐らく言うだろう。「それは、メロディーが今そこにあるという確定的な感情だ」 ―― だがそれは本当にそこにあるのか? 私が口ずさみ始めたとき、詰まってしまったらどうなのか? ―― [ある人が言う。] だがそれでも、私が歌いだした瞬間、私がメロディーを知っているという確信はありえなかったのか? [あり得たはずである。] それゆえ、メロディーはまさに何らかの意味でそこにあったのである。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかしどのような意味で? 君はきっと「通して歌ったり、初めから終わりまでを心の中の耳で聞いたなら、メロディーはそこにある」と言うだろう。もちろん私も、「メロディーがそこにある」という言明に全く別の意義 ―― 例えば、私はメロディーが書かれた紙切れを持っている、というような ―― を与えることができる、という点は否定しない。 ―― それでは一体、メロディーを知っていると「確信」しているということの本質は何なのか? ―― 当然、次のように言うことができる。もし誰かが確信を持って「今や私はメロディーを知っている」と言うならば、メロディーはその瞬間に(何らかの仕方で)全体として彼の心の前に立ち現れているのであり ―― そして、このことこそ「メロディーの全体が彼の心に立ち現れる」という言葉の定義なのである。
185. 第143節の例へと戻ろう。生徒は今や ―― 普通の規準に従って判断するなら ―― 基数列をマスターしている。さて、私たちは彼に、別の基数列を書くことを教える。そこで彼に、例えば「+n」という形の命令に対しては、0, n, 2n, 3n, などの数列を書き出させることにする。すると「+1」という命令に対しては基数列が得られることになる。私たちはこの練習を行い、1000までの数について、生徒の理解度を試す抜き打ちテストをしたとしよう。 [そして彼が合格したとしよう。]
さて今度は、この生徒に一つの数列(例えば「+2」)を1000を超えて続けさせてみる。すると彼は、1000, 1004, 1008, 1012と書く。
私たちは生徒に「よく見なさい、何をやっているんだ!」と言う。 ―― 彼は私たちの言うことが理解できない。私たちは言う。「君は2づつ足さなければならない。数列の始めの方をどうやって書いたか、見てごらん。」 ―― 彼は答える。「ええ! でもこれで正しいんじゃないですか? 僕はこうするべきだと思っていたのです。」 ―― あるいは、彼が数列を示しながら「僕はずっと同じ仕方で続けてきたのです!」と言ったと仮定せよ。 ―― このとき、「だが君は・・・が分からないのか?」と言い ―― そして彼に同じ説明を例を繰り返しても無駄である。 ―― このような場合、私たちは例えばこう言うかもしれない。この人間は生まれつき、「+2」という命令を、私たちの説明を聞いて、ちょうど私たちが「1000までは常に2つづ加えろ。2000までは4づつ、3000までは6づつ・・・」という命令を理解するように、理解しているのだ、と。この事例は、人が手で示す手振りに反応する際、ごく自然に、指先の方向ではなく、指先から手首の方向を見てしまう場合と類似している。 [第85節も参照。]
186. [ある人が言う。] 「君が言うことは、『+n』という命令に正しく従うためには、各段階で新しい洞察 ―― 直観 ―― が必要になる、ということだ。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 正しく従うために、か! [数列の] ある地点においてどれが次の正しい数なのか、一体どうやって決められるのか? [ある人が言う。] 「次の正しい数とは、命令と ―― それが思われた通りに ―― 一致する数のことである。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] すると君は、「+2」という命令を与えた時点で、生徒は1000の次は1002と書くべきだと ―― そしてまた、1866の次には1868、100054の次には100036と書くべきだと思っていたわけだ ―― 無限に多くのそうした命題を、そのとき思っていたのだね? ―― [ある人が言う。] 「そうではない。私が考えていたのは、彼は自分が書いたそれぞれの数の後には、それより2大きい数を書くべきだということである。そしてそこから、上のような全ての命題が導かれるのである。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし問題はまさにそこだ。ある場面において、「彼は自分が書いたそれぞれの数の後には、それより2大きい数を書くべきだ」という命題から何が導かれるのか。あるいはまた ―― 私たちは何をもって、ある場面におけるこの命題との「一致」と呼ぶべきなのか(そしてまた、何をもって、君がそのときこの命題に与えていた思念(Meinungen) ―― それが何において成り立っていたにせよ ―― との一致と呼ぶべきなのか。) 各地点において直観が必要になるというよりは、各地点において新しい決断が必要になる、と言う方が正しいであろう。
187. [ある人が言う。] 「だがそれでも私は、命令を与えたときにも、生徒が1000の次に1002を書くべきだということを既に知っていたのだ!」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かにそうである。君は「そのとき私はそのことを思っていた」と言うことさえできる。ただ、「知っている」と「思う」の文法によって惑わされてはならないのだ。なぜなら、君はそのとき1000から1002への移行について考えていたわけではないからである ―― たとえこの移行については [偶然] 考えていたとしても、他の諸々の移行については考えていなかったのだから。「私はそのとき既に・・・を知っていた」という君の言明は、「ある人がそのとき私に、彼は1000の次にいかなる数字を書くべきか、と訊ねたなら、私は『1002』と答えたであろう」と同じことを意味している。私はその点を疑っているのではない。それは例えば「彼がそのとき水に落ちたなら、私は後を追って飛び込んだだろう」というのと同じ種類の仮定なのである。 ―― すると、君の間違いはどこにあったのか?
188. そこで私は、まずこう言いたい。君が考えていることは、あの命令について君が思っていたことは、その思念の仕方によって、既にこれら全ての移行を行なっていた、ということである。いわば君の心は、君が命令を思う以前に飛んでいき、君が身体的にそれぞれの移行に到達する前に、全ての移行を成し遂げてしまうのである。
それだから、君は「私が移行を手で書いたり、口に出して言ったり、思考の中で行う前に、実は移行は既に行われていた」という表現を使いたくなったのである。しかもそうした移行は他に類を見ない仕方で前もって規定されており、予期されていたかのように思われたのである ―― あたかも、命令を思念することだけが現実を予期できるかのように。
189. 「しかし、数列の展開における移行は代数式によって確定されてはいないのか?」 ―― この問いには一つ誤りがある。
私たちは「これらの移行は・・・という式によって確定されている」という表現を使う。この表現はどのように使われるのか? ―― 私たちは例えば、誰でも y = x2 という式を、xに同じ数を代入すれば、常にyとして同じ数を算出するものとして使用するよう教育(訓練)される、と言うことができる。あるいは「これらの人々は皆、『+3』という命令に対して、同じ段階で同じ移行をするよう訓練される」と言うことができる。このことを私たちは「『+3』という命令は、彼らに対して、ある数から次の数への各移行を完全に確定している」と言って表現できるかもしれない。(反対に、この命令に対し何を為すべきか知らない人々、あるいは、どのように反応するべきかを完全な確実さを持って知ってはいるが、各人の反応がバラバラな人々。)
他方、私たちは、多様な種類の式と、それに付随する多様な種類の使用(多様な種類の訓練)を互いに比較することができる。そこで私たちは、ある特定の種類の式(およびそれに固有の使用方法)を「与えられたxに対して一つのyを確定させる式」と呼び、他の種類の式(およびそれに固有の使用方法)を「与えられたxに対して一つのyを確定しない式」と呼ぶ。(y = x2 が前者の例であり、y ≠ x2 が後者の例である。) それゆえ、「・・・という式が一つのyを確定する」という命題は、この式の形式についての言明である ―― そして今や、「私が書き付けた式がyを確定する」という命題や「ここにyを確定する式がある」という命題は、、「y = x2 という式は、与えられたxに対して一つのyを確定する」という命題から区別されなくてはならない。このとき、「そこにある式はyを確定するか?」という問いは、「そこにある式は第一の種類のものか、それとも第二の種類のものか?」という問いと同じである。 ―― しかし「y = x2 は与えられたxに対してyを確定する式であるか?」という問いをどのように扱うべきか、即座に明らかでない。例えば、生徒が「確定する」という語の使用を理解しているかどうかを試すために、この問いを彼に訊ねることができよう。あるいは、この問いは、xがただ一つの平方を持っていることを特定の体系の中で証明せよ、という数学の問題であるかもしれない。
190. 今やこう言うことができる。「式がどのように思われているかが、どのような移行が行なわれるべきかを確定する。」 では、式がどのように思われているかを決める規準は何か? それは例えば、私たちが常に式を用いる仕方であり、私たちに教えられた使い方である。
私たちは例えば、見知らぬ記号を使う人に対して次のように言う。「君が『x!2』でx2を考えているならyとしてこの値を取るけど、2xを考えているならあの値を取る。」 ここで自問せよ。「x!2」ということで色々なことを思うことは、いかにして行なわれるのか?
このようにして、思念は移行を前もって確定できるのである。
191. [ある人が言う。] 「あたかも、私たちは語の全使用を一瞬のうちに把握するかのようだ。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 例えばどのように? ―― [ある人が言う。] 人はそれを ―― ある意味で ―― 一瞬のうちに把握できるのではないか? 君はいかなる意味でできないと言うのか? ―― それは、 [教育や訓練によるよりも] 一層直接的な意味において「一瞬のうちに把握」できるかのようだ。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] だが君はそのような具体事例を持っているか? 持っていないであろう。私たちには、この「一瞬のうちに把握する」という表現方法だけが与えられているのである ―― 複数の像が組み合わされた結果として。
192. 君は、語の全使用を「一瞬のうちに把握する」という途方もない事実の具体事例を持っていないが、それについて「一瞬のうちに把握する」というメタ表現を使う誘惑に駆られるのである。(これを哲学的最上級(philosophischen Superlativ)と呼ぶことができるだろう。)
193. 動作方法の象徴としての機械。機械は ―― まずこう言うことができよう ―― その動作方法を既に自分の中に持っていると思われる。これはどういうことか? ―― 私たちが機械を知る際、動作方法以外の全てのもの、すなわち機械が行うであろう動作は、既に完全に決定済みのように思われる。
私たちは、あたかも機械の部品がそのようにしか動作できないかのように、それ以外のことは何一つできないかのように語る。それはどういうことか ―― すると私たちは、それらが曲がったり、壊れたり、溶けたりする可能性を忘れているのか? その通り。私たちは大抵の場合、そうした可能性について全く考えない。私たちは機械、または機械の像を、一つの確定的な動作方法の象徴として用いるのである。例えば私たちは、誰かに機械の像を伝え、彼がその像から、部分の動作という現象を導き出してくれるだろうと前提している。(誰かにある数を伝えるのに、1, 4, 9, 16, ・・・という数列の25番目の数だ、と言うようなものである。)
「機械はその動作方法を既に自分の中に持っている」という表現が意味するのは、私たちは、既に確定済みとなっている機械の未来の動作を、既に引き出しに入っていて今や私たちによって引き出されるばかりとなっている諸対象と比較する傾向がある、ということである。 ―― しかし、機械の現実の振る舞いを予言することが問題となっているときには、私たちはそうは言わない。その場合、私たちは一般的に、部品の変形などの可能性を忘れてはいない。 ―― だが恐らく、そうした可能性を考えるのは、どうしたら機械を動作方法の象徴として使えるのか、訝しく思う場合である ―― なぜなら、機械は [現実の動作と] 全く別様に動作することも可能だからである[23]。
いわば、機械またはその像は [数列ならぬ] 「像列」の初項であると言うことができよう。私たちはこの最初の像から次々に像の系列を導き出すことを習ったのである。
しかし、機械が [現実とは] 異なる動作もしえたということを考えるなら、象徴としての機械のうちには、現実の機械のうちにおけるよりもはるかに確定的な形で動作の種類が含まれていなくてはならないと思われることがある。この場合、それは経験的に前もって確定された動作であるだけでは十分ではなく、その動作は本来 ―― ある神秘的な意味において ―― 既に現在に存在していなくてはならないように思われる。そして確かに、象徴としての機械の動作は、与えられた現実の機械の動作とは異なる仕方で、前もって決定されているのである。 [第190節を参照。]
194. では人は、どのようなときに「機械はその可能な諸動作を、何らかの神秘的な仕方で既に自身の中に持っている」と考えるのか? ―― そう、それは哲学するときである。ならば私たちを誘惑し、そのように考えさせるものは何か? 私たちが機械について語る、その仕方である。例えば私たちは、機械は動作可能性を持っている(所有している)と言う。私たちは、一通りの動作だけが可能な、理想的な硬度の材料で作られた機械について語る。 ―― 動作可能性、それは何なのか? それは動作ではない。しかしまた、動作の単なる物理的条件 ―― 軸と軸受けの間には遊びの空間があり、軸はあまりきつく軸受けにはめられてはいない、というような ―― だとも思われない。なぜなら、確かにこれは経験的な動作条件ではあるが、しかし別様の事柄も想像できるからである。動作可能性とは、むしろ、運動そのものの影のようなものであるべきである。しかし君はそのような影を知っているか? [知らないであろう。] そして私は、「影」ということで、運動のいかなる像も理解しない ―― なぜなら、そうした像は、まさにこの動作の像であってはならないのだから。ところが、この運動の可能性 [=運動の影] はまさにこの運動の可能性でなくてはならない。(見よ、ここに言語の波がいかに高くうねっているかを!)
この波は、私たちがある機械について語るとき、「運動の可能性」という語をいかにして用いているか、と自問すれば、すぐに静まる。 ―― しかしこの奇妙な考えはどこから来たのだろう? さて、私が君に、例えば運動の像を介して運動の可能性を示すとしよう ―― <それゆえ、運動の可能性は、現実性に似た何かだ。> 私たちは「それはまだ動いていない。しかし、それは既に動く可能性を持っている」と言う ―― <それゆえ、運動の可能性は現実性に極めて近いものだ。> 私たちは確かに、これこれの物理的条件がこの運動を可能にするか否かを疑うことができる。しかし、これがあの運動やこの運動の可能性であるか否かは疑わない。<それゆえ、運動の可能性は運動に対して特異な関係にある。その関係は、像の対象に対する関係よりも密接である。> なぜなら、これがこの対象やあの対象の像であるか否かは、疑いうることだからである。私たちは「これがこの軸に動作可能性を与えるかどうかは、経験が教えてくれるだろう」と言う。しかし「これがこの動作の可能性であるか否かは、経験が教えてくれるだろう」とは言わない。<それゆえ、この可能性がまさにこの動作の可能性であることは、経験的事実ではない。>
私たちは、こうした物事に関しては、自分たちの独自の表現方法に注意を払うが、しかし、それらを理解せず、誤解しているのである。哲学するときの私たちは、文明人の表現方法を耳にしてそれを誤解し、その誤解からなんとも奇妙な結論を導く原始的な未開人に似ている。
195. [ある人が言う。] 「しかし私は、私が今(語の意味を把握する際に)行うことは、語の未来の使用を因果的かつ経験的に確定することだとは考えていない。そうではなく、未来の使用それ自体が、ある奇妙な仕方で、現在に存在しているのである。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかしその存在の仕方はもちろん、「何らかの意味で」なのである。実は、君が言ったことのうちで間違っているのは「奇妙な仕方で」という表現だけである。残りは正しい。そしてこの命題が奇妙に思われるのは、これを私たちが現実に使用する言語ゲームとは異なる言語ゲームを想像するときだけなのである。(ある人が私にこう言ったことがある。「私は子供のとき、仕立屋が『服を縫うことができる』のが不思議だった。」 ―― この人物は、「服を縫う」が意味するのは、糸を糸に縫いつけながらただ縫っていけば服が出来上がる、ということだと考えていたのである。)
196. 語の使用が理解されないと、それは奇妙な出来事の表現だと解釈される。(ちょうど時間が奇妙な媒体として、心が奇妙な存在として考えられるように。)
197. [ある人が言う。] 「あたかも、私たちは語の全使用を一瞬のうちに把握するかのようだ。」 [第191節も参照。] ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに、私たちは、自分がそうしていると言う。つまり、自分のしていることを時としてそのような言葉で記述する。しかし実際起こっていることには、驚くようなこと、奇妙なことは何一つない。奇妙なことが起こるのは、私たちが、把握という行為の中に [語の] 未来における使用が何らかの仕方で現存していなくてはならないのに、実際にはそうではない、と考えるときである。 ―― というのも、私たちが言っていることは、私たちは語を理解していることは疑いないが、一方、語の意味はその使用のうちにある、ということだからである。いま私がチェスをしたいことに疑いはないが、チェスというのはその全ての規則(等々)によってチェスというゲームなのである。すると私は、自分がしようと思ったことを、実際にし終えるまでは知らないのか? それとも、全ての規則が、意図するという私の行為の中に含まれているのか? ならば、この意図するという行為から、通常この種のゲームが続いて起こるということを私に教えるのは、経験なのか? 従って私は、自分が何をしようと意図していたのか、確信することができないというのか?[24] もしそう考えることが無意義なら ―― 意図という行為と意図される対象との間には、いかなる強固な [しかも経験的ではない] 結合が存在するのか? 「チェスを一勝負しよう!」という言葉の意義とチェスの全規則との間の結合は、どこで行われるのか? ―― そう、ゲームの規則表の中で、チェスを教えることの中で、日々のゲームの実践の中で。
198. [ある人が言う。] 「しかし、この場合において私が何をすべきかということを、規則はどのようにして私に教えることができるのか? 私が何をしようと、それは何らかの解釈によって規則と一致させうるのに。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] いや、そう言うべきではない。むしろ、あらゆる解釈は、解釈されるものとともに、宙に浮かんでいる。前者は後者の支えの役割は果たせないのである。解釈だけでは意味は規定されない。
[ある人が言う。] 「それなら、私がすることは何であれ、規則と一致しうるのか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 私は問いたい。規則の表現 ―― 例えば道しるべ ―― は、私の行為と何の関係があるのか? 両者の間にはいかなる関係があるのか? ―― さて、それは例えばこうである。私はこの記号に対し特定の反応をするよう訓練された。そして私は今そのように反応する、と。
[ある人が言う。] しかしそれだけでは両者の因果的関連を述べたにすぎない。私たちが現在道しるべに従うことがどのように生じてきたかを説明しただけで、肝心の「規則に従う」ことが本来何において成り立つのかを説明していない。 [ウィトゲンシュタインが言う。] そうではない。私はまた、人が道しるべに従うのは、ある恒常的な使用、ある慣習が存在するときだけである、ということも示唆したのである。
199. 私たちが「規則に従う」と呼ぶものは、ただ一人の人間が、生涯ただ一度行う何かでありうるだろうか? ―― これはもちろん、「規則に従う」という表現の文法に対する注釈である。
ただ一人の人間がただ一度だけ規則に従った、ということはありえない。ただ一度だけ、ある報告が行われ、命令が与えられた、あるいは命令が理解された、などということはありえない。 ―― 人が規則に従い、報告を行い、命令を与え、チェスをするということは、慣習(慣用、制度)である。
ある文を理解するということは、ある言語を理解することである。ある言語を理解するということは、ある技術をマスターすることである。
200. ゲームを知らない民族において、二人の人がチェス盤の前に座り、チェスの指し手を打つ、しかも [普通チェスをする時に生じる] あらゆる心的な随伴現象を伴っている、ということは、もちろん考えられることである。その様子を私たちが見れば、「彼らはチェスをしている」と言うであろう。しかしここで、チェスがある規則に従って一連の行為 ―― 例えば足を踏み鳴らす、叫び声をあげるなど、通常はゲームで連想しない行為 ―― へ翻訳されると考えよ。するとこの二人は今や、よく知られたチェスの形式で勝負する代わりに、叫び声をあげたり足を踏み鳴らしたりする。しかも、これらの出来事を適当な規則によってチェスの勝負に翻訳できる形で。さて、私たちはそれでも「彼らはゲームをしている」と言いたくなるだろうか? どのような権利をもって、そのように言うことができるのか?
201. 私たちのパラドクスはこうであった ―― 規則は行為を決定できない。なぜなら、いかなる行為の仕方も規則と一致させうるから[25]。これに対する答えはこうであった ―― いかなる行為も規則と一致させられるなら、一致させないこともできる。だから、ここには一致も不一致も存在しないであろう。
ここに誤解があることは、私たちがこの思考過程において ―― 解釈の背後に控える別の解釈を考えるまでは、少なくとも一瞬の安心を得られるかのように ―― 解釈に次ぐ解釈を行っているということのうちに、既に示されている。すなわち、このことを通して私たちが示すのは、解釈ではなく、その場その場の [規則の] 適用において、私たちが「規則に従う」とか「規則に反する」と呼ぶものの中に現れるような規則の把握 [の仕方] がある、ということである。それゆえ、規則に従う行為は全て解釈である、と言いたい傾向が生じるのである。しかし「解釈」と呼ぶべきなのは、規則の表現を別の表現によって置き換えることだけである。
202. ゆえに「規則に従う」ことは一つの実践である。そして規則に従うと信じることは、規則に従うことではない。ゆえに、人は規則に「私的に」従うことはできない。なぜなら、そうでないと規則に従うと信じることが、規則に従うことと同じになってしまうからである。
203. 言語は迷路である。一方の側からやってくれば見通しがつくが、別の側から同じ場所に来ると、もう分からなくなる。
204. 例えば私は、実際のところ、誰にもやってもらえないゲームを発明することができる。 ―― あるいはまた、人類は全くゲームをしたことがなかったが、一度だけ誰かがゲームを発明した ―― そしてもちろん、それは誰からもやってもらえなかった ―― ということも可能だろうか?
205. [ある人が言う。] 「慣習や技術の存立が不要だというのが、意図という心的過程の奇妙なところだ。例えば、二人の人が、彼ら以外の人はゲームをしないような世界 [=ゲームの慣習がない世界] において、ほんの初めの部分だけでもチェスの勝負をし ―― そして続きが分からなくなって躓いていしまう、ということは考えられることである。」
[ウィトゲンシュタインが言う。] しかしチェスは規則によって定義されているのではないか? だとすればこの規則は、チェスをしようと意図している二人の心の中に、どのように現存しているのか?
206. 規則に従うということは、命令に従うことに類似している。そうするよう訓練され、命令に対し一定の仕方で反応する。しかし今、同じ命令と訓練に対し、ある人はこのように反応し、またある人は別様に反応するとしたら、誰が正しいのか?
君が研究者として見知らぬ土地を訪れたと考えよ。そこでは君が全く知らない言語が使われている。どのような状況のもとで君は、彼らが命令を与え、命令を理解し、従い、また命令に逆らう、等と言うか?
人間に共通の行為の様式というのは、私たちが見知らぬ言語を解釈するときの座標系(Bezugssystem)である。
207. この見知らぬ土地の人々は、普通の人間的な活動を営み、その際に、一見すると分節言語を利用しているように見える、と想定せよ。この部族を観察する人は彼らの言語を理解できるし、私たちには「論理的」であるように見える。しかし彼らの言語を習得しようとすると、それが不可能であることが分かるのである。すなわち、彼らにおいては、発音されたもの、すなわち音と、彼らの行為との間に何ら規則的な関係が成立していないのである。しかし、それにも関わらず、この音は余計なものではない。なぜなら、例えば彼らの一人に猿ぐつわをかませると、私たちの場合と同じ結果になるからである。音を発せないと、彼らの行為は混乱してしまうのである ―― 私はそのように表現したい。
この人々は、言語を持っていると、命令や報告などを行っていると、言うべきであろうか?
[この土地において] 私たちが「言語」と呼ぶものには、規則性が欠けている。
208. すると私は、「命令」や「規則」という語の意味を、 [語と行為の間の] 「規則性」によって説明するのか? ―― では、「規則的」、「同様な」、「同じ」という語の意味を誰かに説明するときは、どのようにするのか? ―― 例えば、フランス語だけを話す人に対しては、私はこれらの語を、対応するフランス語によって説明するだろう。しかしこれらの概念をまだ持っていない人に対しては、例を使って説明し、練習によって使うことを教えるだろう。 ―― そしてこのように例を使って教えるとき、私が彼に伝えることの情報量は、私自身が知っていることより少なくはならない。[第72節も参照]
だから私はこの教育において、彼に、同じ色、同じ長さ、同じ形を示し、彼にそれらを見つけさせ、または作らせるなどのことをするのである。私は例えば、命令に従って連続模様を「規則的」に続けるよう、彼を指導するだろう。 ―― そしてまた、・ ・・ ・・・ の先を、・・・・ ・・・・・ ・・・・・・ と続けていくように教えるだろう。
私が彼に手本を見せ、彼が私に続いてやる。そして私は、同意や拒絶、期待や励ましの表現によって彼に影響を与える。
君はそのような授業の目撃者だとせよ。この授業ではいかなる語もそれ自体を通して説明されることはなく、いかなる論理的循環も起こらない。
「以下同様」や「以下無限に続く」という表現も、この授業で説明されるだろう。そのためには、特に身振りが役に立つ。「そのように続けろ!」とか「以下同様」を意味する身振りは、対象や場所を示す身振りと比較可能な機能を持っている。
省略した表記である「等々」は、そうではない「等々」から区別しなければならない。「等々、無限に続く」という表現は、省略した表記ではない。私たちがπの全ての桁を書き出すことができないことは ―― 数学者が時として考えるような ―― 人間の能力の不足を意味するのではない。
提示された諸例から離れないようにしている授業は、そうした例を「超えて指示する」授業とは異なるのである。
209. [ある人が言う。] 「しかしそれでも、理解は全ての例よりも遠くに達するのではないか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 奇妙な表現だが、全く自然だ! ――
[ある人が言う。] 例による説明が全てなのか? もっと深い説明があるのではないか? または、説明の理解とはもっと深いものでなければならないのではないか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] そうすると私自身も、より深い理解とやらを持っているのか? 私は、私が [例を使った] 説明において与える以上のものを持っているのか? ―― それにしても、私がより多くのものを持っているというこの感情は、どこから来るのだろう?
それはまるで、限界のないものは、あらゆる長さよりも長い長さを持っている、と解釈するようなものだろうか?
210. [ある人が言う。] 「しかし君は、君自身が理解していることを本当に彼に説明しているか? 本質的なことを彼に推測させてはいないか? 君は彼に幾つかの例を与えた ―― しかし彼は、それらの例の傾向を、つまり君の意図を推測しなければならない。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 私が自分に対して与えることのできる説明は、これを全て彼にも与えることができる。 ―― 「私の思うところを彼が推測する」というのは、彼の念頭に私の説明の様々な解釈が浮かび、それらのうちの一つが私の意図だと推測する、ということであろう。従ってこの場合、彼は訊ねることができるだろうし、また私も、彼に答えるであろう。
211. [ある人が言う。] 「君がいかにして連続模様を続けることを彼に教えようとも、どのように自力でそれを続けるかを、彼はいかにして知ることができるだろうか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] さて、私はそれをいかにして知っているか? もしこの問いが「私は [模様をいかにして続けるかの] 根拠を持っているか?」ということであれば、答えはこうである ―― 根拠はいずれ尽きるであろう。そのとき私は、根拠なしに行為するであろう。
212. もし私が恐れている人物が、数列を続けろという命令を私に与えるなら、私はすぐに、完全な確信をもって行うであろう。そして、根拠がなくとも私は気にならない。
213. [ある人が言う。] 「しかしこの数列の初項は、明らかに様々に解釈されうる(例えば様々な数式によって)。それゆえ君はまず、そのような解釈の一つを選ばなければならない。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 全くもって違う! 状況によっては、疑うことは可能であった。しかしそれは、私が実際に疑っていたとか、疑うことしかできなかった、ということではない。(このことに関連して、出来事の心理的な「雰囲気」について言うべきことがある。)
直観だけがこの疑いを取り除くことができたのか? ―― もし直観が内的な声であるならば ―― それにどのように従うべきかを、私はいかにして知るのか? そして、それが私を誤った方向へ導かないということを、いかにして知るのか?
というのも、直観が私を正しく導けるなら、また誤った方向へも導けるのだから。
((直観とは不要な言い訳である。))
214. もし 1 2 3 4 という数列の展開に直観が必要なら、2 2 2 2 という数列の展開にも必要である。
215. [ある人が言う。] だが少なくとも同じ [もの] は同じではないのか? 同一性に対しては、私たちは誤ることのない範例を持っているように思われる。すなわち、ある物とそれ自身の同一性がそれである。私は次のように言いたい。「ここでは様々な解釈などありえない。彼がある物を眼前に見ているなら、彼は同一性をも見ているのだ。」
[ウィトゲンシュタインが言う。] すると、二つの物が一つの物のように見えるとき、それらは同一なのか? もしそうなら、その一つの物が示すものを、いかにして二つの物の場合に適用するべきなのだろうか?
216. 「物はそれ自身と同一である」 ―― 無益な命題のこれほどの好例は他にない。だがそれでも、この命題は表象のゲームと結びついている。私たちが物を、表象の中でそれ固有の形式にはめ込み、それがうまく適合するのを見るような、そういうゲームと。
私たちは「いかなる物もそれ自身と適合する」と言うこともできるだろう ―― あるいはまた「いかなる物もそれ固有の形式にはめ合わされている」とも。人はその際、ある物を眺めて、その物のための空間が用意されていたのであり、今やそれが正確に空間にはめ合わされているのだ、と想像する。
この
「いかなる色の染みも、正確にその周縁と一致する」というのは、同一性命題の特殊な形である。
217. 「私はいかにして規則に従うことができるか?」 ―― もしこれが原因についての問いでないとすれば、私が規則に従ってそのように行為することに対する正当化についての問いである。
根拠を論じ尽くしてしまえば、私は固い岩壁に突き当たり、私の鋤は反り返っている。そのとき私は「私はまさにそのように行為する」と言いたくなる。
(私たちはときに内容のゆえではなく、説明という形式のゆえに説明を求める、ということを想起せよ。その場合、私たちの要求は建築様式上のものである。説明は、何も支えない装飾のための蛇腹である。)
218. 数列の初項は、無限の彼方へと伸びる目に見えない軌道の、目に見える一部分である、という考えはどこから来るのだろう? さて、私たちは規則の代わりに軌道を考えることができる。そして際限のない規則の適用が、無限に長い軌道に相当する。
219. [ウィトゲンシュタインが言う。] 「 [数列の項から項への] 移行は、実はすべて既に行われてしまっている。」 これが意味するのは、私にはもう選択肢はない、ということである。規則は、ひとたび確定的な意味を与えられると、それに従う線を地の果てまで引くのである。 ―― [ある人が言う。] しかし仮にそんなことが実際に起こっているとしても、それが私にとって何の役に立つのだろう?
そうではない。 [「移行はすべて既に行われてしまっている」という] 私の記述は、それが象徴的に理解されたときにのみ、意義を持ったのである。 ―― 私にはそう思われる ―― 私はそう言うべきであった。
私が規則に従うとき、私は選択しない。
私は規則に盲目的に従う。
220. しかしこの象徴的命題はいかなる目的を持っているのか? それは、因果的な制約と論理的な制約の違いを際立たせるべきものだったのである。
221. 私の象徴的表現は、本来、規則の使用を神話学的に(mythologisch)記述するものであった。
222. 「この線は、私がいかに行くべきかを示唆する。」 ―― しかしもちろん、これはただの像である。そして私が、これが私にいわば無責任にあれやこれやを示唆する、と判断すれば、私はそれに規則として従うとは言わないであろう。
223. 人は、常に規則の合図(囁き)を予期していなくてはならない、と感じるわけではない。逆である。私たちは規則がいったい今何を言うのか、緊張して待っているのではない。規則は常に同じことを言い、私たちは規則が言うことを為すのである。
人は、自分を訓練する人物に向かって次のように言うことができよう。「見てください。私は常に同じことをやっています。私は・・・」
224. 「一致」という語と「規則」という語は互いに血縁関係にある。両者はいとこである。私が誰かにある語の使用を教えるとき、彼はそれによって [血縁関係にある] 別の語の使用も学ぶ。
225. 「規則」という語の使用は、「同じ」という語の使用と織り合わされている。(「命題」という語の使用が「真」という語の使用と織り合わされているように。)
226. ある人が 2x + 1 という数列を展開することで、1,3,5,7, ・・・ という数列を辿るとしよう。そして彼はこう自問した。「いったい私は常に同じことをしているのか、それとも毎回違うことをしているのか?」
一夜ごとに「明日君のところへ行く」と約束する人は ―― 毎日同じ事を言っているのか、それとも日ごとに異なることを言っているのか?
227. 「彼は毎回異なることを行うなら、私たちは、彼が規則に従うと言うことはできないのではないか?」 この問いには意義がない。
228. [ある人が言う。] 「数列は私たちにとって一つの相貌を持っている!」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに。しかしどのような? それは確かに代数的な相貌であり、展開の一部の相貌である。あるいはそれ以外の相貌も持っているのか? [ある人が言う。] 「しかし数列にはすでに全てが含まれている!」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかしそれは数列の一部や、私たちがその中に見出すことにおいて確認されることではない。そうではなく、それは、私たちが規則の言うことだけに注意して行為し、それ以外の手引きは求めないということの表現なのである。
229. 私が信じるところでは、私は、数列の部分において全く精巧な図面、無限に達するためには他に「等々」という語だけを必要とする、特徴的な数列を知覚している。
230. 「この線は、私がいかに行くべきかを示唆する。」 これはただ、その線は私がいかに行くべきかの最終審である、ということの言い換えに過ぎない。
231. 「しかし君は・・・を見ている!」 さて、これはまさに規則に強制されている人に特徴的な表現である。
232. 規則は私に、私がいかに規則従うべきかを示唆する、と想定せよ。すなわち、私がその線を眼で追うと、内的な声が「このように進め!」と言うのである。 ―― このような一種のインスピレーションに従うことと、規則に従うことの違いは何か? というのも、両者は同じことではないのだから。インスピレーションの場合、私はその指示を待つ。私はその線に従う「技術」を他人に教えることはできないであろう ―― 一種の聞き取り方、一種の感受性を教えるのならば別だが。しかしもちろん私には、彼がその線に私と同じように従うことを要求することはできない。
こうしたことは、インスピレーションや規則に従って行為したという私の経験ではなく、文法的な注釈なのである。
233. あるいはまた、一種の算術の授業を考えることができよう。子供たちはその授業において、それぞれ自分のやり方で計算することができる ―― 彼らが内的な声を聞き、それに従っている限りは。こうした計算は作曲のようなものである。
234. しかし私たちもまた、普段計算する仕方で(全員が一致するなど)、かつ計算の各段階で、魔法に導かれているかのごとく規則に導かれているという感情を伴って計算することができないだろうか? 恐らくは私たちが一致することに驚きながら? (例えば、神にその一致を感謝しながら。)
235. このことから君が見るものはただ、私たちが日常生活で「規則に従う」と呼ぶものの外貌(Physiognomie)に属するものに過ぎない。
236. 正しい結果には到達するが、しかしいかにして到達するかを言うことのできない計算の芸術家たち[26]。彼らは計算しているのではない、と言うべきなのか? (様々な事例が一つの家族を成す。)
237. ある人が、次のような仕方で規則としての線に従う、と考えよ。彼はコンパスを持っており、その先端で規則 ―― つまり線に沿ってなぞる。するとその間、もう一方の先端が線を描くが、それは規則に従って描かれたものである。そして彼がそのように規則に従う間、彼はコンパスの開きを非常な厳密さをもって変えていくが、その仕方は、常に、規則が彼の行為を規定するかのように規則に注意を集中させているかのごとくである。ところが、彼を見ている私たちには、そのコンパスの開閉に何の規則性も見出せない。私たちは、彼が規則に従う仕方を、彼から学ぶことができない。ここにおいて私たちは言うであろう。「この手本が、いかにして行うべきかを彼に示唆している。だがそれは規則ではない!」
238. 規則がその全ての帰結を生み出しているかのように思われうるためには、帰結が私にとって、この色を「青」と呼ぶほどに、自明でなくてはならない。(これが私にとって「自明」であることの規準。)
239. 「赤」という語を聞いたときどの色を選ぶべきかを、彼はいかにして知るのか? ―― [ある人が言う。] 実に簡単だ。「赤」という語を聞いたときに彼の念頭に浮かぶ像を選ぶべきなのだ。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし、どの色が「彼の念頭に浮かぶ像」の色であるのかを、彼はいかにして知るのか? 何かさらなる規準が必要なのか? (・・・という語を聞くときに念頭に浮かぶ像を選ぶ、という過程は確かに存在する。)
「『赤』は私が『赤』という語を聞いたときに念頭に浮かぶ色を意味する」 ―― これは一つの定義ではあろう。しかし、語による記号づけの本質の説明ではない。
240. 規則に従って行われたのか、そうではないのかについて(例えば数学者の間で)論争が起こることはない。例えばそのことで喧嘩になることはない。それは、私たちの言語が働く(例えば記述を行う)足場の一部なのである。
241. [ある人が言う。] 「すると君は、何が正しくて何が誤っているかは、人間同士の一致が決定すると言うのか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 正しかったり誤っていたりするのは、人間が言うことである。そして人間は言語において一致する。それは意見の一致ではなく、生活形式の一致である。
242. 言語による意思疎通には、定義における一致だけでなく、(奇妙に聞こえるかもしれないが)判断における一致も含まれている。これは、論理を破棄することのように見えるが、しかしそうではない。 ―― 測定方法を記述することは一つのことであり、測定結果を見て話すことはまた別のことである。しかし私たちが「測定する」と呼ぶことはまた、測定結果のある種の恒常性によっても規定されるのである。
243. 人は、自分を鼓舞し、自分に命令し、その命令に従い、叱責し、処罰し、質問を提示し、それに答えることができる。あるいはまた、独り言しか言わない人間を考えることもできる。そうした人間の活動には独り言がついてまわる。 ―― 彼らを観察し、その言葉に耳を傾けている研究者は、彼らの言葉を私たちの言葉にうまく翻訳できるかもしれない。(彼はそれによって、これらの人々の行為を正しく予言できる立場に置かれるだろう。なぜなら、彼はその人たちが意図し、決断を下すことをも聞くのだから。)
しかしまた、ある人が自らの内的体験 ―― 感情、気分など ―― を自分だけの用途のために書き付け、あるいは声に出すような言語をも考えることができるだろうか? ―― [ある人が言う。] それなら私たちの日常言語でやれるのではないか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 私が言おうとしているのは、そういうことではない。その言語の語彙は、話し手だけが知りうることのみを指示すべきものである。つまり、話し手の直接的で私的な感覚を、である。ゆえに他人はこの言語を理解できない。
244. 語はいかにして感覚を指示するのか? ―― そこに問題は何もないように思われる。というのも、私たちは普段、感覚について語り、その名前を言っているのではないか? しかし名前と名指されたものとの結合はどのように作られるのか? この問いは「人はいかにして感覚の名前 ―― 例えば『痛み』 ―― の意味を学ぶのか?」という問いと同じである。言葉が根源的で自然な感覚の表出に結び付けられ、それの代わりになっている、というのは一つの可能性である。子供が怪我をして泣く。すると大人たちがその子に語りかけて、感嘆詞を教え、後には文章を教える。彼らは子供に新しい痛みの振る舞いを教えるのである。
[ある人が言う。] 「すると君は、『痛み』という語は本来泣き声を意味すると言うのか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 逆である。痛みの言葉による表現が泣き声に取って代わっているのである。それを記述しているのではない。
245. それでは、私はいかにして、痛みの表出と痛みとの間に言語をもって割り込もうというのか?
246. [ウィトゲンシュタインが言う。] さて、私の感覚はいかなる意味で私的であるか? ―― [ある人が言う。] 決まっている。私が本当に痛みを持っているか否かは、私だけが知っている。他人はただ推測しうるのみである。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] だがその答えは、ある意味では間違いであり、別の意味ではナンセンスである。私たちが「知っている」という語を普通の用法で(それ以外にどういう用法があるというのか!)使うとき、私が痛みを持っているなら、他人はそのことを非常にしばしば知っているのである。 ―― [ある人が言う。] しかしそれでも、他人は、私自身ほどの確実性を持って知っているわけではない! [ウィトゲンシュタインが言う。] そもそも人は、私に対して、私が痛みを持っていることを私は知っていると言うことは(冗談の場合は別として)できない。それでは一体、「私は私が痛みを持っていることを知っている」ということは、私が痛みを持っているということ以外に、何を意味するのか?
他人は私の感覚を私の振舞いを通してのみ習得する、と言うことはできない。なぜなら人は、私について、私はその感覚を習得した、と言うことはできないのだから。私は [感覚を習得したのではなく] まさに感覚を持っているのである。他人について、私が痛みを持っているか否か疑っている、と言うことは有意義である。しかし、私自身についてそのように言うことは無意義である。
247. 「君が意図を持っていたか否かは、君だけが知りうる。」 「意図」という語の意味を誰かに説明するとき、このように言うことができよう。この言葉が言わんとすることはつまり、私たちは「意図」という語をそのように使う、ということである。
(そして「知る」という語はここでは、不確実性を表現することが無意義である、ということを意味する。)
248. 「感覚は私的である」という命題は「人はペイシェンス [トランプの占いゲーム] を独りでやる」という命題と比較可能である。
249. 赤ん坊の微笑みは偽りではない、と想定することは、ひょっとすると早計なのだろうか? どのような経験に基づいて、私たちはそう仮定するのか?
(嘘をつくことは一つの言語ゲームであり、他の言語ゲームと同様、学ばなくてはやれない。)
250. なぜ犬は痛い振りをすることができないのか? 犬があまりに慎み深いからか? 犬に痛い振りをすることを教えられるだろうか? 恐らく、痛みがなくとも、特定の機会に痛いかのような泣き方をするすることは、教えられるだろう。しかしその振舞いが本当の痛い振りであるためには、なお正しい状況が欠けている。
251. 私たちが「私はその反対を想像できない」とか「それがそうでなかったら、どうなるのか?」と言うとき、その言葉は何を意味しているのか? ―― 例えば誰かが「私の表象は私的である」とか「私が痛みを持っているか否かは、私だけが知っている」と言ったときなど。
この場合、当然、「私はその反対を想像できない」ということは、私の想像力が不足しているということではない。私たちはそう言うことによって、形の上は経験的命題に見えるが、実際は文法的命題である命題から、自らの身を守っているのである。
しかしなぜ私は「私はその反対を想像できない」と言うのか? なぜ「私は君が言うことを理解できない」とは言わないのか?
例:「あらゆる棒は長さを持つ。」 これが意味するところは、例えば、私たちはある物(あるいはこれ)を「棒の長さ」と呼ぶ、ということである ―― だが私たちは、何物も「球の長さ」とは呼ばない。さて、それでは私は、「あらゆる棒は長さを持つ」ということを想像できるだろうか? いま、私はまさに一本の棒を想像している。そしてそれが私にできる全てである。ただ、この命題と結びついている棒の像は、「この机はあそこの机と同じ長さを持つ」という命題と結びついた像とは全く異なる役割を果たしているだけである。なぜなら私は、後者の場合には、その反対の像(それは表象である必要はない)を作るということが何を意味するかを理解しているからである。
一方、文法的命題と結びついた像が示すことができたのは、例えば、人が「棒の長さ」と呼ぶものだけであった。すると、その反対の像とは一体どんなものなのか?
((ア・プリオリな命題の否定について考えよ。))
252. 「この物体は広がりを持つ」[27]という命題に対して、「ナンセンスだ!」と答えることができるだろう。 ―― だが、私たちには、「もちろん!」と答えようとする傾向がある。 ―― なぜか?
253. 「他人は私の痛みを感じることができない」 ―― どれが私の痛みなのか? この場合、同一性の規準としてふさわしいのは何だろうか? 物理的対象の場合、「二つは全く同じである」と語ることを可能にしているのが何か考えよ。例えば、「この椅子は、君が昨日ここで見た椅子と同一ではない。しかし全く同じものである。」
「私の痛みは彼の痛みと同じである」と言うことが意義を持つ限りにおいて、私たちはまた「二人は同じ痛みを持っている」と言うことができる。(あるいは、二人の人間が同じ箇所 ―― 単に対応する箇所というだけでなく ―― に痛みを感じるということも考えられる。例えばシャム双生児の場合、そいうことがありえよう。)
私は以前、この問題を議論しているときに、ある人が自分の胸を叩いて「でも他人はこの痛みを持つことはできない!」と言うのを見たことがある。 ―― これに対する答えは、「この」という語に強調のアクセントを付けたとしても、同一性の規準を定義したことにはならない、というものだ。むしろその強調は、そのような規準がよく知られているのに、私たちがそれを忘れてしまっているので思い出さねばならないかのように見せかけているだけである。
254. 「同じ」という語を「同一である」という語で置き換えることが、哲学における常套手段である。あたかも、私たちは意味のニュアンスについて語っていて、語に正しいニュアンスを付与することだけが問題であるかのように。だが哲学の際にそれが問題になるのは、特定の表現方法を使う誘惑を心理的に正確に描写することが私たちの課題であるときだけである。そういう場合、私たちが「言いたくなること」というのは、もちろん、哲学ではなく、哲学の素材である。従って、例えば数学者が数学的事実の客観性と実在性について言いたくなることは、数学の哲学ではなく、哲学が扱うべき素材なのである。
255. 哲学は問題を病気のように扱う。
256. さて、私の内的体験を記述し、私だけが理解できる言語というのは、いかなるものだろうか? いかにして私は私の感覚を語によって表すのか? ―― 普段やっているように、か? すると私の感覚語は、私の自然な感覚表出と結びついているのか? ―― その場合、私の言語は「私的」ではない。他人も私と同じようにその感覚語を理解できるからである。 ―― しかし、私が一切の自然な感覚表出を持たず、感覚だけを持っているとしたら、どうであろう? この場合、私は単純に名前を感覚と結びつけ、その名前を記述において使用するのである。 ――
257. 「人々が痛みを表現しない(呻かず、顔も歪めない)としたら、どうなるか? そのとき、子供に「歯痛」という語の使用を教えることはできないだろう。」 ―― さて、その子供は天才で、感覚の名前を自ら発明すると仮定しよう。しかしもちろん、子供はその語を他人に理解させることができない。 ―― つまり、子供は名前を理解しているが、その意味を誰にも説明できないというのか? ―― しかしそうすると、彼は「自分の痛みに名前を付けた」とはどういう意味なのか? ―― 彼はいかにして、痛みに名前を付けるということを行ったのか?! そして、彼が何をしたにせよ、それはどういう目的を持っていたのか? ―― 人が「彼はその感覚に名前を与えた」と言うとき、その人は、単なる名づけが意義を持つためには、言語において既に多くのことが準備されていなくてはならないということを忘れている。そして私たちが痛みに名前を与えることについて語るとき、「痛み」という語の文法こそが、その準備されていたものである。文法が、この新しい語が置かれることになる位置を示すのである。
258. 次のような場合を想像してみよう。私はある種の感覚が繰り返し起こることについて、日記をつけようと思う。私はその感覚に記号「E」を結び付け、その感覚を持った日には、カレンダーに「E」を書き込む。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] まず私が言いたいのは、この記号の定義を述べることはできないということである。 ―― [ある人が言う。] だがそれでも、私は自分自身に対しては、その定義を一種の直示定義として与えることができる! ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] どのようにして? 私はその感覚を指し示すことができるというのか? ―― [ある人が言う。] 普通の意味ではできない。しかし、この記号を言うか書くかする際に、この感覚に注意を集中することによって、いわば、内面に向って指し示すことによって。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかしそのような儀式は何のためにあるのか? というのも、それは儀式としか思えないからだ! 定義というのは、記号の意味を確定することに役立つものだ。 ―― [ある人が言う。] いや、それこそ注意を集中させることによってなされるものだ。というのも、それによって私に記号と感覚との結びつきが刻まれるのだから。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] だが「私に刻み込まれる」が意味しうるのは、次のことでしかない。つまり、この過程の作用によって、私は将来においてその結びつきを正しく思い出す、ということだ。しかし今の場合、私は正しさの規準をもっていない。人はここで言うだろう。私にとって正しいと見えるものは何であれ正しいのだ、と。そしてそれは、この場合「正しい」ということについて語ることはできない、ということに他ならない。
259. 私的言語の規則は規則の印象なのか? 印象を量る秤は、秤の印象ではない。
260. [ある人が言う。] 「さて、またもや私はこれが感覚Eだと信じている。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 君は信じているということを信じているのだ!
[ある人が言う。] すると、この記号をカレンダーに書き込むひとは、何も書き留めなかったことになるのか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 記号を ―― 例えばカレンダーに ―― 記入すれば、何かを書き留めたことになる、などと簡単に思い込んではいけない。覚え書きは機能を持つものだが、「E」は、まだ何の機能も持っていない。
(人は自分に対して語りかけることができる。 ―― 他人に向かって語りかけていない人は、みな自分に対して話しているのか?)
261. 「E」を感覚の名前だと呼ぶことには、いかなる根拠があるか? つまり、「感覚」というのは私たちの共通言語の語であって、私だけが理解できる言語の語ではない。ゆえに、この語を使うには、全ての人が理解する正当化が必要である。 ―― それゆえまた、「『E』は感覚である必要はない」とか「彼が『E』を書くとき、彼は確かに何かを持っている ―― ただ、私たちにはそれが何であるかまでは言えない」などと言っても、何の役にも立たないであろう。そう言ってみたところで、「持っている」とか「何か」という語もまた、私たちの共通言語に属しているのだから。 ―― そのため、哲学する際、ついには分節化されていない不明瞭な音声だけを発したくなる段階まで到達するのである。 ―― しかしそのような音声は、特定の言語ゲームの中においてのみ、一つの表現になる。今や、その言語ゲームが記述されなくてはならない。
262. 人はこう言うかもしれない。私的な語の説明を与えた人は、その語をしかじかに使うということを、内面において企てていなくてはならない、と。するとその人はいかにして企てるのか? 彼はその語の応用の技術を発明する、あるいは既にそれを手に入れていた、と仮定するべきなのか?
263. [ある人が言う。] 「だが私は、(内面において)これを将来『痛み』と呼ぶと企てることができる。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 「しかし君は、本当にそんなことを企てたのか? そのためには、注意を君の感情に集中させることで十分だった、ということを確信しているのか?」 ―― 奇妙な問いだ。 ――
264. [ある人が言う。] 「ひとたび君が、この語が何を表すかを知れば、君はその語を理解し、その全適用を知るのである。」
265. 私たちの想像の中にだけ存在するような表、例えば辞書のようなものを考えよう。辞書を使えば、語Xから語Yへの翻訳を正当化することができる。だが想像の中だけにあるこの表を参照する場合も、正当化と呼ぶべきだろうか? ―― [ある人が言う。] 「その場合は、まさに主観的正当化である。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし正当化というのは、主観とは独立のところへ訴えることで、初めて成立するのではないか? [ある人が言う。] 「だが私は、ある記憶について別の記憶に訴えることもできる。(例えば)私は列車の発車時刻を正しく憶えたかどうか自信がないので、時刻表のページの像を記憶に呼び起こす。それと同じ事ではないのか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] そうではない。というのも、その過程は、実際のところ、時刻表の正しい記憶を呼び起こすということでなくてはならないからだ。もし時刻表の表象像そのものの正しさが検証できないとすれば、どうして列車の発車時刻の記憶が正しいと分かるだろうか? (それは、今朝の朝刊の内容が正しいかどうかを確認しようとして、それを何部も買い込んでいるようなものである。)
想像の中の表を参照することは、想像の中の実験の結果を想像することが実験の結果でないのと同様、表を参照することではない。
266. 私は、何時であるかを見るために、時計を眺めることができる。しかし私はまた、何時であるかを推測するために、時計の文字盤を見ることもできる。あるいはその目的のために時計の針を調節して、自分が正しいと思う位置まで動かすことができる。このように、時計の像が時間を決定するために役立つ仕方は一つだけではない。(想像の中で時計を眺めること。)
267. 私が、自分の想像の中で建てられている橋の寸法設計を、まず想像の中で、橋の建材の強度テストを行うことによって正当化しようとする、としよう。これはもちろん、「橋の寸法設計を正当化すること」と呼ばれることの想像であろう。しかし、私たちはこれを「寸法設計の想像を正当化すること」とも呼ぶであろうか?
268. なぜ私の右手は左手に金を贈ることができないのか? 私の右手は、左手に金を与えることはできる。右手が贈与証書を書き、左手が受領証を書く。 ―― しかしそれ以上の実際的な諸結果は、贈与によって起こるものではない。左手が右手から金を受け取ったりしたとき、人は次のように問うであろう。「それで、だから何なのか?」 ある人が私的な語の説明を与えたとき、つまり、ある語を自分に言い聞かせながら、ある感覚に注意を集中させたときにも、同様に問うことができよう ―― 「それで、だから何なのか?」
269. 人が語を理解していないこと、つまり、その語が彼にとって何の意味もないということ、それによって何をすべきかを知らないということ、そうしたことに対するある種の振る舞いの規準が存在することを思い出そう。そして第二に、人が語を「理解していると信じている」こと、その語にある意味を結び付けているが、それが正しい結びつきではないことに対する規準、そしてさらに、人が語を正しく理解していることに対する規準が存在する。二番目の場合、主観的理解について語ることができる。そして、他人は理解しないが、私は「理解しているように見える」音声を、「私的言語」と呼ぶことができるだろう。
270. さて、記号「E」を日記に記入することの応用を考えよう。私は次のような経験をする。私がある特定の感覚を持つときは、常に血圧計が私の血圧が上昇することを示す。すると私は、機械の助けを借りなくとも自分の血圧の上昇を知らせることができる。これは有用な結果である。そしてこの場合、私が感覚を正しく再認していたかどうかは、全くどうでもよいことのように思われる。私のその同定を常に間違って行っていたと仮定しても、全く影響はない。そしてこのことが既に、同定を誤るという仮定が見せかけの仮定に過ぎなかったということを示している。(いわば私たちは、機械を調節できるかのように見えるボタンを回してみたのだが、実はそのボタンは、機械にはつながっていないただの飾りだったのである。)
このとき、私たちは、「E」が感覚を表す記号であるといういかなる根拠を持っているというのか? おそらくそれは、この言語ゲームにおいてこの記号が使われる仕方であろう。ではなぜそれが一つの「特定の感覚」であると、従って毎回同じ感覚であるとされるのか? そう、私たちは自分が毎回「E」を書くということを仮定しているのである。
271. 「痛み」という語が何を意味するか、記憶に留めることのできない人間 ―― 従って常に何か別のものを「痛み」と呼んでいるのだが、それにも関わらず、この語を痛みの普通の徴候と諸前提に一致するように用いる人間 ―― を想像せよ。 ―― この人間は従って、この語を私たち全員と同様に使う。そのとき私はこう言いたくなる。たとえ回すことができても、他の部分に影響を及ぼさないようなハンドルは、実は機械の一部ではないのだ、と。
272. 私的体験について本質的なことは、各人が自分固有の実例を持っているということではなく、他人もこれを持っているのか、あるいは別のものを持っているのか、誰一人知らない、ということである。従って、一部の人間はある赤の感覚を持っており、別の一部の人間は別の赤の感覚を持っている、と仮定することも ―― 検証不可能であるが ―― 可能である。
273. では「赤」という語についてはどうか ―― これは「私たち全員に相対するもの」を表す語であり、誰もが自分固有の赤の感覚を表すためにこれとは別にもう一つの語を持っているはずだ、と言うべきなのか? あるいは、「赤」という語は私たちに共通して認識されるものを表す一方、各個人とってはそのうえ、自分だけに認識されるものを表しているのか? (あるいは、この語は各個人だけに認識されるものを指示しているのか、と言った方がいいかもしれない。)
274. もちろん、「赤」は私的なものを「表す」という代わりに「指示する」と言ったとしても、この語の機能を把握することの役には立たない。しかしこれは、哲学する際の特定の体験に対しては、心理的にはより適切な表現である。これはあたかも、私は既にその語を発する際、いわば私はそれによって何を意味しているか既に知っていると自分に対して言い聞かせるために、自分固有の感覚に一瞥をくれているようなものである。
275. 青い空を見上げ、「空はなんと青いのか!」と言ってみよ。 ―― 哲学的な意図を持たず、自然にそうするとき、この色印象が自分だけのものであるなどという考えは浮かんでこない。そして君は、この叫びを他人に向けて聞かせることをためらわない。もし君がこの語で何かを指すのなら、それは空である。私が言わんとするのは、人が「私的言語」について考えているとき、「感覚を名指す」ことにしばしば随伴する、自分自身の中を指し示しているという感覚を君は持っていない、ということである。また君は、本来手で色を指し示すべきではなく、注意を向けることによってのみ指し示すべきなのだ、とも考えていない。(「注意を向けることで何かを指し示す」ことがどういうことであるのか、よく考えよ。)
276. [ある人が言う。] 「しかし、色を眺めてその色印象を名づけるとき、私たちは少なくとも全く確定的なものを意味しているのではないか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] これはまるで、色の印象を、薄皮を剥ぐように、見ている対象から剥ぐようなものである。(このことが私たちの疑惑を引き起こすのでなくてはならない。)
277. しかし、人があるときには語で全ての人が認識する色を考え、またあるときには私がいま抱いている「視覚印象」を考えると信じたくなるということは、そもそもいかにして可能なのだろうか? その場合、いかにして一つだけの誘惑が成立しうるのか? この二つの場合において、私は同じ種類の注意を色に向けるのではない。自分に属する(と言いたいような)固有の色印象を考えるとき、私は自分自身をその色の中へ ―― 「いくら見ても見飽きない」ときと同じぐらい ―― 没入させている。だから、輝く色を見たり、印象に残る色彩構成を見たりするときには、この体験はもっと容易に引き起こされるものである。
278. [ある人が言う。] 「緑という色が私にどのように見えるか、私は知っている」 ―― この文は確かに意義を持っている! ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに。 [だが] 君はその文のいかなる使用を考えているのか?
279. 「でも私は自分の身長がどれだけかを知っている!」と言って、そのしるしに頭の先に手を乗せる人を考えよ!
280. ある人が、例えば劇場でのワンシーンを見せるために絵を描く。すると私が言う。「この絵は二重の機能を持っている。まず第一に、まさに絵や言葉が伝えるところのものを他人に伝える。しかし伝える側の人にとっては、それは別の描写(あるいは伝達?)なのだ。彼にとって、その絵は自分の表象の像なのだ。彼以外の誰にとっても、そのようなものではありえない。この絵の私的な印象は、彼が想像していたことを彼に語る ―― 他人に対してはなしえない意味において。」 ―― すると、第一の場合に描写または伝達という語が正しく適用されたのだとすれば ―― この第二の場合、私は何の権利があって描写または伝達について語っているのか?
281. [ある人が言う。] 「しかし君の言うことは、痛みの振舞いなしには痛みは存在しない、ということにならないか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 人は、生きている人間、およびそれに似たもの(似た振舞いをするもの)についてのみ、感覚を持つ、見る、盲目である、聞く、難聴である、意識がある、意識がない、と言うことができるのである。
282. [ある人が言う。] 「しかし童話の中では壺だって見たり聞いたりできるではないか!」 [ウィトゲンシュタインが言う。] (その通りである。しかも壺は話すことさえできる。)
[ある人が言う。] 「だが童話は、事実ではないことを作り話にしているだけであり、ゆえに童話が語ることはナンセンスではない。 [ただ偽なだけである。] 」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う] そんな簡単にはいかない。壺が語ると言うことは、虚偽か無意義のどちらかなのか? 壺が語ると言うことについて私たちが明確な像を持つのは、いかなる状況においてか? (ナンセンス詩もまた、子供の片言と同じように無意義なのではない。)
確かに、私たちは無生物について、それが痛みを持つと言う。例えば人形と遊んでいるとき。しかし、これは痛みという概念の二次的な用法である。人々が無生物についてだけ、それが痛みを持つと言い、人形だけを気の毒に思う、と想像せよ! (子供が電車ごっこをして遊ぶとき、その遊びは彼らの電車についての知識に関係している。しかし、電車を知らない民族の子供が誰かからこの遊びを受け継ぎ、自分たちが何の真似をしているのか知らないまま遊ぶということもありえる。その場合、この遊びが彼らに対して持つ意義は、私たちに対して持つ意義とは異なる。)
283. 私たちは、事物、対象が何かを感じることができるという考えさえ抱くわけだが、その考えはどこからやってくるのだろう?
まず、私の受けた教育が私の中にあるその感じに注意を向けさせ、次に、私がその観念を外界の対象にも転用することによって、であろうか? すると私は、他人の言語使用と矛盾することなしに「痛み」と呼びうるものがそこに(つまり私の中に)あることを認識しているのか? ―― [しかし] 私は石や植物などに「何かを感じることができる」という観念を転用してなどいない。
こういうことは考えられないだろうか。私は激痛を持つと、それが持続する間、石になってしまうのである。そう、眼を閉じているとき、自分が石になっていないことを、私はどうやって確認するのか? ―― 今もしこういうことが起きたなら、その石はどのような意味で痛みを持つだろうか? どのような意味で、その石について「痛みを持つ」と言うことができるだろうか? そもそもこの場合、なぜ痛みが担い手を持たねばならないのか?!
石について、心を持つとか、これが痛みを持つのだ、と言うことができるだろうか? 心や痛みは石と何の関係を持っているのか?
人は、人間のように振舞うものについてのみ、それが痛みを持つと言うことができる。
というのも、人は身体について、あるいは身体が持っている心について、痛みを持つと言わねばならないからである。だがすると、身体はいかにして心を持ちうるのか?
284. 石を見つめ、それが感覚を持っていると考えよ! ―― 人はこう自問する。一体いかにして人は、物に感覚を帰属させるという考えにすら到達することができたのだろう、と。それなら、全く同様にして、数に感覚を帰属させることさえ可能だろう! ―― いま、もがいているハエを見よ。そうすればすぐにこの困難は消え去り、これまで、いわば滑らかでとりつくしまのなかった痛みという概念について、取っ掛かりを掴むことができるように思われる。
そして私たちには、死体にも痛みは全くないと思われる。生者に対する私たちの態度は、死者に対するそれとは異なる。両者に対する私たちの反応は全て異なる。 ―― もし誰かが「それは単に、生者がしかじかに動き、死者は動かないせいではない」と言うなら ―― 私は彼に、ここには「質から量への」移行の一事例があるのだということを示唆したい。
285. 表情を認識すること、あるいは表情の記述について考えよ。 ―― 表情の記述とは、顔の大きさを述べることによって成り立つものではない! また、どうすれば鏡を見ずに他人の表情を真似できるのか、ということについても考えよ。
286. しかし身体について、それが痛みを持つと言うのは馬鹿げていないか? ―― ではなぜそれを馬鹿げていると感じるのか? 私の手が痛みを感じるのではなく、私が手に痛みを感じるというのはいかなる意味においてか?
「痛みを感じるのは身体か?」という問いの争点はどこにあるか? ―― どうすればこの問いに答えられるのか? どうすれば痛みを感じるのは身体ではないということが認められるのか? ―― それは例えばこういう場合である。人が手に痛みを持つとき、その手が「痛い」と訴えるわけではない(手が「痛い」と書くのでなければ)。そして人は手に慰めの言葉をかけるのではなく、痛がっている人を慰めるのであり、[彼の手ではなく] 彼の顔を見るのである。
287. いいかにして私はこの人に対して同情で一杯になるのだろう? その同情の対象が何であるかは、いかにして示されるのだろう? (同情とは他人が痛みを持っていることを確信する形式の一つだと言える。)
288. 私は固まって石になり、痛みは持続する。 ―― もしこのとき、私が間違っていて、もはや痛みがないのだとしたらどうか! ―― だがこの場合、私は間違えることができない、すなわち、自分が痛みを持っているか否か疑うことには何の意味もない! ―― つまり、誰かが「私は、私の持っているものが痛みなのか、あるいは別の何かなのかを知らない」と言うのなら、私たちは、その人は「痛み」という日本語の意味を知らないのだと考え、彼にその意味を説明するであろう。 ―― ではいかにして説明するか? おそらくは身振りや、あるいは彼を針で刺して「ごらん、これが痛みだよ」と言うことによって。彼はこの説明を、他の人々と同様、正しく理解するかもしれないし、あるいは間違って理解したり、全く理解しないこともあるだろう。そして彼が三つのうちどれを行うかは ―― 他の場合でもそうであるが ―― 彼の言語使用において示されることになろう。
ここで例えば彼が「ああ、『痛み』という語が何を意味するかは知っている。しかし、今ここで私が持っているこれが痛みであるかどうか、それが分からない」と言ったのなら ―― 私たちとしてはただ頭を振り、彼の言葉を理解不能な奇妙な反応と見なさざるをえない。(それは例えば、誰かが真剣に「私は、自分が生まれる少し前、・・・・・・ということを信じていたことをはっきり憶えている」と言うのを聞いたときと同じようなものである。)彼の使った疑惑の表現は、「痛み」という語の言語ゲームに属していない。しかし今、感覚の表現、つまり人間的な振舞いを除外するなら、彼のような疑いを持つことも許されると思われる。私がここで、感覚は、実際そうであるのとは異なる何かとして受け取ることができる、と言いたくなるのは、感覚の表現を使う通常の言語ゲームが破棄されたと考えるとき、私は感覚の同一性の規準を必要とし、ゆえにまた間違いの可能性も存立するからだ、と考えることに由来している。
289. [ある人が言う。] 「私が『私は痛みを持っている』と言うとき、[他人に対してはさておき] とにかく自分自身に対しては正当化される。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] それはどういうことか? それは「私が『痛み』と呼ぶものを他人が知ることができるならば、その人は、私がこの語を正しく使用していることを認めるだろう」ということを意味しているのか?
ある語を正当化せずに使うということは、その語を不当に用いるということではない。
290. 私が自分の感覚を同定するのは、もちろん規準によってではなく、私が同じ表現を使うことによってである。しかしそれによって言語ゲームが終わるのではない。逆に始まるのである。
しかしその言語ゲームは、私が記述する感覚とともに始まるのではないか? ―― 恐らく私たちは、「記述する」という語によってばかされているのだ。私は「私は自分の心的状態を記述する」と言い、また「私は自分の部屋を記述する」とも言う。言語ゲームの多様さを記憶に呼び起こさなければならない。
291. 私たちが「記述」と呼ぶものは、特別な使用のための道具である。エンジニアが目の前に広げている、寸法入りの機械の平面図、断面図、立面図を考えよ。記述ということで事実の言語像を考えるなら、それはミスリーディングな考えである。というのも、像というと、壁に掛かっているような画像しか考えられないからだ。そういう像はただ、物がどういう風に見え、どういう状態にあるのか、ということを模写するだけだと思われるからである。(こういう像はいわば何の機能も果たしていない。)
292. 事実から言葉を読み取る、とか、事実を規則に従って言葉に模写するなどと、いつもいつも考えてはならない! なぜなら、特殊な場合 [=規則の解釈のない場合] においては、君はいかなる導きもなしに規則を適用しなければならないのだから。
293. 私が、自分についての場合からのみ「痛み」という語が何を意味するのかを知る、と言うとき、 ―― 私は他人についても同じことを言ってはならないのか? もし言ってもよいのだとすれば、どうすれば一つの場合をそんな無責任に一般化することができるのか?
さて、人は誰でも、自分の痛みからのみ痛みが何であるかを知る、と語る! ―― 各人が一つの箱を持っていて、その中には私たちが「カブト虫」と呼ぶものが入っている、と仮定しよう。誰も他人の箱の中を覗くことはできない。そして誰もが「私は自分のカブト虫を見ることによってのみ、カブト虫が何であるかを知る」と言う。 ―― しかし、各人が持っている箱の中にはそれぞれ異なる物が入っていることだってありうるのだ。それどころか、箱の中の物が絶えず変化しつづけるということさえ想像可能であろう。 ―― さてしかし、この人々の「カブト虫」という語がそれでも一つの使用を持っているとしたら? ―― その場合、その使用は一つの物に対する記号の使用ではないだろう。箱の中の物は、そもそも言語ゲームに属していない。のみならず、それはある何かですらない。というのも、箱は空っぽでもありうるからである。いや、言語ゲームはこの箱の中の物を通して「短絡させる」ことも可能なのである。箱の中の物が何であろうと、それは消え失せてしまう。
つまりこういうことである。人が「対象と記号」という見本に従って感覚の表現の文法を構築するとき、対象は当の考察から無関係なものとして抜け落ちてしまうのである。
294. 君が「彼はある私的像を眼前に見て、それを記述する」と言うとき、君は、彼が見ているものについて、常にある一つの仮定を行っていたのである。それは、その物を君はもっと詳細に記述できるとか、あるいは実際に記述している、という仮定である。彼が見ているものがどんな種類のものでありうるかについて、いかなる漠とした観念も持っていないということを認めるならば、 ―― それにも関わらず「彼は何かを眼前に見ている」と君に言わせたくするものは何なのか? これはまるで、私が誰かについて「彼は何かを持っている。しかしそれが金なのか、借金なのか、それとも空の金庫なのか、私は知らない」と言うようなものではないか?
295. ならば「私は自分の場合からのみ・・・・・・を知る」という命題は、そもそもいかなる種類の命題なのか? 経験的命題だろうか? ―― 違う。 ―― では文法的命題だろうか?
そこで、各人が自身について「私は自分の痛みからのみ、痛みが何であるかを知る」と言うと想像しよう。 ―― 人々が本当にそう言うとか、そう言おうとしているだけだ、というわけではない。しかし、もし誰もがそう言ったなら ―― それは一種の叫び声でありえよう。そしてその叫びが情報伝達としては何も述べていないとしても、やはりそれは一つの像なのである。このとき、私たちはなぜそのような像を心に呼び起こそうとしてはならないのか? 言葉の代わりに寓意的な画像を考えてみよ。
哲学する際に心のうちを覗くならば、しばしばまさにそのような寓意像と出くわすことになる。それは紛れもなく、私たちの文法を絵で表したものである。それは事実ではなく、いわば絵で表現された語法なのである。
296. [ある人が言う。] 「その通りである。しかしやはり、私が痛みを叫ぶときに随伴するものがそこにあるのだ! それゆえに私は叫び声を上げる。そしてこの随伴するものこそ重要なものであり ―― かつ恐ろしいものだ。」 [ウィトゲンシュタインが言う。] ―― 私たちは誰にそのことを伝えるのか? そしてどのような機会に?
297. やかんの水が沸騰するとき、もちろん蒸気が立ち昇る。そしてまた、やかんの像から蒸気の像も立ち昇る。しかし、「やかんの像の中でも何かが沸騰しているはずだ」と言おうとしたら、どうであろう?
298. 私たちは「重要なのはこれだ」と ―― 自分自身に対して感覚を指しながら ―― 実に好んで言いたがる。 ―― このことからして既に、私たちには、何の情報も伝えないことを言う強い傾向があることを示している。
299. 哲学的思考にふけるとき、これこれと言わずにはいられなくて、そのように言う傾向に抵抗できないということは、ある仮定をせざるを得ないとか、ある事態を直接理解している、あるいは知っている、ということを意味しない。
300. 「彼は痛みを持っている」という語を用いる言語ゲームには、振る舞いの像だけなく、痛みの像もまた属している ―― 人はそう言いたがる。あるいは、振る舞いの範例だけでなく、痛みの範例も属している、と。「痛みの像は『痛み』という言葉によって言語ゲームに入り込む」と言うことは誤解である。痛みの表象は像ではない。ゆえにこの表象は、言語ゲームにおいて、私たちが像と呼ぶであろう何ものによっても置換できない。 ―― 確かに、ある意味において痛みの表象は言語ゲームに入り込むのである。だがそれは像としてではない。
301. 表象は像ではない。だが像は表象に対応しうる。
302. もし自分の痛みを見本として他人の痛みを想像しなければならないとしたら、それはそう簡単なことではない。なぜなら、私は私が感じる痛みに基づいて、私が感じない痛みを想像せねばならないのだから。つまり私は、単に想像の中で、ある痛みの場所から別の場所へ ―― 例えば手の痛みから腕の痛みへ ―― 移さなくてはならない、というわけではないのである。というのも、私が彼の体のある箇所に痛みを感じているということ(それもまた可能ではあろうが)を想像してはならないからである。
痛みの振る舞いは痛む箇所を指示することができる ―― しかし、痛みに苦しんでいる人間とは、痛みを表明する人間なのである。
303. [ある人が言う。] 「私にできるのは、他人が痛みを持っていると信じることだけである。しかし私は、自分が痛みを持っていることは知っている。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに。人が「彼は痛みを持っている」と言う代わりに「私は彼が痛みを持っていると信じる」と言うよう決心することは可能である。だがただそれだけである。 ―― ここで心的過程についての説明や言明のように見えるものは、実は、ある言い方を、哲学する際にはより適切と思われる言い方に取り替えたものである。
一度、 ―― 現実の場合に ―― 他人の不安や痛みを疑ってみよ!
304. [ある人が言う。] 「しかし君はそれでも、痛みを伴った痛みの振る舞いと、痛みを伴わない痛みの振る舞いの間に違いがあることは認めるだろう。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 認める? もちろんだ! これほど大きな違いは他にない! [ある人が言う。] 「なのに君は繰り返し、感覚それ自体は何物でもない、という結論に達している。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] いや、そうではない。感覚は何かではないが、しかし何物でもないわけでもない! 結論はただ、何物でもないものが、それ自身については語ることのできない何かと同じ働きをする、ということだったのである。私たちはただ、私たちにつきまとう文法を退けただけなのだ。
言語は常に一通りの仕方で機能し、常に同じ目的 ―― 家や痛み、善悪、その他何についてであれ、その思想を伝達するという ―― に寄与するという観念を打破することによってのみ、パラドックスは消え去る。
305. [ある人が言う。] 「しかし君も、記憶を呼び起こす際には、ある内的過程が生起していることは否定できまい。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 私たちが何かを否定しようとしているかのような印象を与えてしまうのはなぜだろう? 誰かが「思い出す際には内的過程が生起する」と言うとき、彼は続けてこう言おうとする。「確かに君はそのことが分かる。」 そして、人が「思い出す」という語で考えているのが、この内的過程なのである。 ―― 私たちが何かを否定しようとしているという印象は、私たちが「内的過程」の像に反発していることに由来している。私たちが否定しているのは、内的過程の像は「思い出す」という語の使用の正しい観念を与えてくれる、ということである。そこで私たちはこう言おう。内的過程の像は、それに纏わりつく諸々と一緒になって、私たちが語の使用をあるがままに見ることを妨げるのだ、と。
306. なぜ私は心的過程がそこにあることを否定せねばならないのか?! 「今私の中で・・・を思い出すという心的過程が起きた」ということは、ただ「今私は・・・を思い出した」という以外の何物でもない。心的過程を否定することは、思い出すということを否定することであり、誰かが何かを思い出すということを否定することなのである。
307. [ある人が言う。] 「君は偽装した行動主義者ではないのか? 君は、根本的には、人間の振舞い以外は全て虚構であると言うのではないか? 」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] もし私が虚構について語るとすれば、それは文法的虚構についてである。
308. どのようにして心的過程や心的状態、あるいは行動主義についての哲学的問題が生じるのか? ―― その第一歩は全く目立たないものである。私たちは過程や状態について語り、その本性を未決定のままにしておく! 恐らく、いずれはそれらについてもっと知るようになるだろう ―― 私たちはそう考える。しかしまさにそれによって、私たちは特定の思考方法に縛り付けられてしまっている。というのも、私たちは、過程をより良く知るようになるということについて特定の観念を抱くからである。(手品師は奇術において決定的な一手を指したのだが、まさにその一手は私たちにとって無害なものに見えたのだ。) ―― そして今や、私たちの思想を理解可能にするはずだった比較が崩壊する。それゆえ私たちは、まだ未探究の媒体における理解不可能な過程を否定しなくてはならない。そのようなわけで、私たちがまるで心的過程を否定したかのように見えるのである。だがもちろん、それを否定するつもりなどないのだ!
309. 哲学における君の目的は何か? ―― 蝿に蝿取り壺からの出口を示してやること。
310. 私がある人に「私は痛みを持っている」と言う。それに対する彼の態度は、私の言ったことを信じる、または信じない、疑いを持つ、等々であろう。
彼が「それほど酷い痛みではないだろう」と言うと仮定しよう。 ―― これは、彼が私の痛みの表現の背後にある何かを信じていることの証拠ではないのか? ―― 彼の態度は、彼の態度の証拠である。「私は痛みを持っている」という文だけを考えるのではなく、「それほど酷い痛みではないだろう」という答えもまた、自然な音声と身振りで置き換えられていると考えよ!
311. [ウィトゲンシュタインが言う。] 「痛みを伴う痛みの振舞いと痛みを伴わない痛みの振舞い、これほど大きな違いは他にない!」 ―― [ある人が言う。] 痛みの場合、私は、その違いを自分に対して私的に提示することができると信じている。しかし折れた歯と折れていない歯の違いならば、誰にでも提示することができる。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし私的に提示するためには、痛みを引き起こす必要など全くない。痛みを想像するだけで十分である ―― 例えば顔を少し歪めてみたりして。そしてそのとき、君は、そうやって自分に提示したものが痛みであって、例えば顔の表情ではないということを知っているのか? また、何を自分に提示すべきかを、いかにして提示する前に知るというのか? この私的な提示というのは幻想である。
312. [ある人が言う。] しかし歯の場合と痛みの場合はそれでもやはり似ていないか? というのも、歯の場合における視覚が痛みの場合における痛覚に対応しているのだから。私は視覚を痛覚と同じぐらい拙く、あるいは同じぐらい上手に、自分に提示できる。
[ウィトゲンシュタインが言う。] 次のような場合を想像せよ。私たちの身の回りの物(石、植物、等々)の表面に、触ると私たちの皮膚に痛みを引き起こすような斑点や部位があるとする。(例えば、その表面の化学的な性質によって。しかし今はそこまで知る必要はない。) この場合私たちは、特定の植物の赤い斑点を持つ葉について語るように、この痛みの斑点を持つ葉についても語るであろう。私が思うに、この斑点とその形についての知覚は私たちにとって有用であり、その結果、事物についての重要な性質を導くことができるであろう。
313. 私は赤を提示するように痛みを提示することができる。そしてまた直線や曲線、木や石を提示するように。 ―― まさにこれを私たちは「提示する」と呼ぶのである。
314. もし感覚の哲学的問題について明らかにするために、私が現在の自分の頭痛の状態を考察したくなっているとすれば、それはある根本的な誤解を示している。
315. 痛みを全く感じたことのない人が、「痛み」という語を理解できるだろうか? ―― それが可能か否かは、経験が教えるべきことなのか? ―― そしてもし私たちが「痛みを一度も感じたことがなければ、痛みを想像することはできない」と言うとき ―― 私たちはそれをどうやって知るのか? どうすればそれが真であることを判断できるのか?
316. 「考える」という語の意味を明らかにするために、私たちは考える際に自己を見つめる。そのとき私たちが観察するものこそ、この語が意味するものであろう! ―― しかし、この概念はまさにそのように使われてはいない。(それはちょうど、チェスを知らないのに、ゲームの最後の一手を厳密に観察することによって「チェックメイト」という語が何を意味するかを見出そうとしているのに似ている。)
317. 誤解を招きやすい対照。悲鳴は痛みの表現 ―― 命題は思想の表現!
あたかも、誰かに他人の胃の中の様子ではなく、頭の中の様子を知らせることが命題の目的であるかのように。
318. 考えながら、あるいは書きながら話すとき ―― 普段私たちがするように、という意味だが ―― 私たちは一般に、話すよりも速く考えている、とは言わない。この場合、思想は表現から引き離されてはいないと思われる。しかし一方、人は思想の速さについても語る。思想がいかに稲妻のように脳裏に閃くか、問題がいかに一瞬のうちに明らかになるか、等々。すると当然、次のような疑問が生じる。すなわち、稲妻のような思想の際にも、思想の欠如していない話をするときと同じことが起きているのか ―― 単にそれが著しく加速されているだけなのか? 前者の場合、いわば時計の仕掛けが一瞬で回りきってしまうのに対し、後者の場合、言葉に妨げられて一歩一歩進んでいくのである。
319. 私は、二、三の語や線を書き付けることができるのと同じ意味において、ある思想を稲妻のごとく自分の前に見る、あるいは理解することができる。
何がこの書き込みをこの思想の要約たらしめているのか?
320. 稲妻のように現れる思想は、代数式がそこから展開される数列に関係するのと同じように、話された言葉に対して関係しうる。
例えば、私にある代数的関数が与えられれば、私は、1,2,3から10までの項について計算することができることを確信している。このような確信は「十分に根拠付けられている」と言われるだろう。私がそのような関数を計算する教育を受けてきたから、等々の理由で。そうでない場合は、この確信は根拠付けられていない ―― だがそれでも、成功することによって正当化はされる。
321. 「ある人間が突然理解するとき、何が起こっているのか?」 ―― この問いは立て方を間違えている。これが「突然理解する」という表現の意味を問うものなら、答えは、私たちがそう呼ぶ過程を指示することによっては与えられない。 ―― この問いは、ある人が突然理解することの徴候は何か、突然理解することに特徴的な心的随伴現象はいかなるものか、という意味に解しうる。
(人が、例えば彼の表情の動き、あるいは心の動きに特徴的な呼吸の変化を感じると仮定する根拠はない。たとえ人がそれらに注意を向けた途端、それらを感じるとしても。) ((心構え))
322. この表現の意味についての問いに対する答えが、上記のような記述によって与えられないということは、理解とはまさに特殊で定義不可能な体験であるという [誤った] 結論へ私たちを導く。しかし、私たちが関心を持つべきは以下の問いであることが忘れられている。すなわち、私たちはいかにしてこれらの体験を比較するのか? 私たちは何をこれらの出来事の同一性の規準として確立するのか?
323. 「今や私は続きを知っている!」は一つの叫びである。これはある自然音、ある歓喜の痙攣に対応している。もちろん、私のこの感覚から、先を続けようとするときに私が立ち往生しないことなどが帰結するわけではない。「続きを知っていると言ったときは、私は確かに知っていたのだ」と言うこともあるだろう。例えば突然の物忘れに襲われたときなど。しかしこの突発的な障害は、私がつまづいたという単純なことではありえない。
また次のようなことも考えられる。ある人が繰り返し見せかけの閃きを得て ―― 「今や私はそれが分かった!」と叫ぶのだが、決して行為によって正当化することができない。 ―― 彼にとっては、あたかも、念頭に浮かんだ像の意味を再び一瞬にして忘れ去ってしまうかのように思われるのだ。
324. 次のように言うことは正しいだろうか? 「ここで問題となっているのは帰納であり、私の持っている本が手を離せば地面へ落下することを確信しているように、私が数列を続けられることも確信している。そしてある日突然、明らかな原因もなしに数列の展開につまづくことがあったとしても、手を離しても本が空中に浮いているのを見たときと同様、驚くことはない。」 ―― これに対して私はこう答えよう。まさにこの確信について、私たちはいかなる根拠も必要としない。何が成功以上にこの確信を正当化できるというのか?
325. [ある人が言う。] 「私がこのような体験 ―― 例えばこの数式を見るなど ―― をした後に、私が先を続けられることの確実性は、単に帰納に基づくものである」 [ウィトゲンシュタインが言う。] それはどういうことか? ―― [ある人が言う。] 「火に触れば火傷するだろうということは、帰納に基づいている。」 [ウィトゲンシュタインが言う。] それはつまり、「これまで私は火に触れると常に火傷した。ゆえに今度もそうなるだろう」と推論する、ということか? それとも、過去の経験は私の確実性の根拠ではなく、原因であるということか? ―― これは、私たちが確実性という現象を観察する仮説の体系、自然法則の体系の問題である。
将来への確信は正当化されるか? ―― 人が何をもって正当化とみなすかが ―― その人の思考と生活のあり方を示している。
326. 私たちはこれを期待し、あれに驚かされる。しかし根拠の連鎖には終わりがある。
327. 「話さずに考えることはできるか?」 ―― さて、考えるとは何だろう? ―― 君は考えないないか? その際に起きていることを観察することができないか? それは実に簡単なことのはずだ。君は、考える際に起こることを観察するときは、天体現象の観察の場合のように、現象が起こるのを待ち、起きたら大急ぎで観察する、という必要はないのである。
328. さて、何がなおも「考える」と呼ばれるのか? 何のためにこの語を使用することを学んだのか? ―― 「私は考えた」と言うとき ―― 私は常に正しくなくてはならないのか? ―― そこにはどのような種類の誤りがあるのか? 私たちが「私がしたことは、本当に思考であるか? 私は間違っていないか?」と問うような状況があるだろうか? もし誰かが思考する過程で測量を行ったとしたらどうだろう。その測量の間、自分に対して何も話さなければ、彼は思考を中断したことになるだろうか?
329. 私が言語を使って考えるとき、「意味」は、言語表現と一緒に私の念頭に浮かぶのではない。そうではなく、言語そのものが思考の乗り物である。
330. 思考は一種の語りであろうか? 人は、それこそが考えながら話すことを考えずに話すことから区別するものだが、と言いたいであろう。 ―― その場合、思考は語りに随伴する過程であるように思われる。恐らくは他の何かにも随伴することができ、また独立して持続しうるような過程である。
「この筆は先が丸まってしまっているが、まだ使える」という一行を言ってみよ。まずは考えながら、次に考えずに、そして最後に、言葉なしに思想だけを考えてみよ。 ―― さて、私は、ある行為の途中で筆先を試し、顔をしかめて ―― 諦めの身振りをしながら書きつづける、ということができよう。 ―― あるいはまた、私は何かの測量を行っていて、そばで見ていた人が「彼は二つの大きさが三つ目の大きさと等しく、ゆえにどれも互いに等しいと ―― 言葉なしに ―― 考えた」と言うであろうような振舞いをすることもできるだろう。 ―― しかし、ここで思考を形成しているのは、もし言葉が思考を伴わずに発せられるべきではないとしたら、言葉に随伴せねばならない過程ではない。
331. 声を出してしか思考できない人間を想像せよ! (声に出してしか読むことのできない人間がいるように。)
332. 私たちは時として、心的過程を伴う文のことを「思考」と呼ぶが、しかしその随伴過程を「思考」とは呼ばない。ある文を言い、それを考えよ! それを理解しながら言ってみよ! ―― そして今度は、それを声に出さずに、君が理解しながら言ったときに随伴させたものだけをやってみよ! (表情をつけて歌を歌い、次に歌わずに表情だけを繰り返せ! ―― この場合も、人は何かを繰り返すことができよう。例えば、体を揺すり、呼吸をゆっくりにしたり速くしたりする、等々。)
333. 「それを確信している人だけが、それを言うことができる。」 ―― それを言うとき、確信はどのような助けになるのか? 確信は、発された表現と並んでそこにあるのか? (あるいは、低い音が高い音に覆い隠されるように、表現によって覆い隠されているため、いわば、確信を大声で表現するときにはもはや聞こえなくなっているのか?) 誰かが「記憶を頼りにあるメロディを歌えるためには、そのメロディを心の中で聞き、それに倣って歌わなくてはならない」と言ったとしたらどうか?
334. 「それゆえ君は、本当は・・・・・・と言いたかったのだ。」 ―― この言い方によって、私たちは人をある表現形式から別の表現形式へ導く。人は、自分が本当に「言いたかった」こと、自分が「思っていた」ことは、それを口に出す前に心の中に存在していたのだという像を使おうとする。私たちにある表現を放棄させ、代わりに別の表現を採用させるよう突き動かすものは、多種多様でありうる。このことを理解するためには、数学の諸問題の解決が、その問題提起のきっかけや根源に対して持つ関係を考察することが役に立つ。ある人が三等分を試みているのに、他方、それが不可能なことが証明されているときの「定規とコンパスを使った角の三等分」という概念。
335. 私たちが ―― 例えば手紙を書く際に ―― 自分の思想にふさわしい表現を見つけようと努力するとき、何が起きているのか? この言い方は、この過程を翻訳や記述といった過程と比較している。すなわち、思想はそこに(例えば既に前もって)存在しており、私たちはただその表現を探しているだけである、と。この像は、程度に差はあれ、多くの場合について適切である。 ―― しかしこの場合、以下に挙げることも全て起こりえないか? ―― ある気分になると、その表現が現れる。あるいは、私が記述しようと努力している像が念頭に浮かぶ。あるいは、ある英語の表現を思いつき、それに対応するドイツ語の表現を思い出そうとする。あるいは、ある身振りをして、「この身振りに対応する語はどれか?」と自問する、等々。
人から「君は表現をする前に思想を持っているか?」と訊かれたとしたら ―― そこで何と答えねばならないだろうか? さらに「表現以前に存在していた思想は、何によって存立していたのか?」という問いに対しては?
336. ここに提示されている事例は、奇妙な語順で並べられたドイツ語やラテン語の文を考えることは、まともな語順の文を考えることほど簡単ではない、と誰かが想像している事態と似ている。この場合、まず最初に [まともな語順の] 命題を考え、それから語の順番を並び替えなければならない。(あるフランスの政治家が言っていた。考える順番に従って語が並ぶのがフランス語の特性である、と。)
337. [ある人が言う。] だが私は、命題の全形態を、例えば最初から既に意図していたのではないか? もしそうなら、命題は発せられる以前に、既に私の心の中にあったのである! ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] もし命題が心の中にあったのなら、一般に、命題はそれ以外の語順で並んでいたのではない。しかし私たちは、ここで再び、「意図すること」について、すなわちこの語の使用について、ミスリーディングな像を作ってしまっている。意図は状況や人間の慣習、制度の中に埋め込まれている。チェスの技術が存在しなければ、私はチェスをすることを意図できなかっただろう。私が命題形式を前もって意図している限り、それは私がドイツ語を話せることによって可能になったのである。
338. 人は、話すことを学んだなら、とにかく何かを言うことができるだけである。だから、何かを言おうとする人は、そのために、ある言語をマスターすることをも学んでいなくてはならない。それでも、明らかなことだが、彼は話そうとするときに話さねばならないわけではない。踊ろうとするときに踊らなくてもよいように。
このことについてよく考えるとき、心が踊りや語りなどの表象を把握するのである。
339. 考えるということは、語りに生命や意義を付与したり、悪魔がシュレミールの影を地面から引き剥がしたように[28]、語りから引き離すことができるような、そういう非身体的な過程ではない。 ―― だがどのような意味で「非身体的な過程」ではないのか? もし私が非身体的な過程を知っていれば、思考はそのうちの一つではないのか? そうではない。「考える」という語の意味を原初的な仕方で説明したかったので、この「非身体的な過程」という言葉を、当惑しながらも採用したのである。
しかし、「考える」という語の文法を、例えば「食べる」という語の文法から区別しようと思うなら、「考えることは非身体的な過程である」と言うことができよう。しかしそれだけでは、 [双方の] 意味の違いは極めて僅かであるように思われる。(それは、数は非実体的な対象だが、数記号は実体的な対象だと言う場合に似ている。) 不適当な表現方法は、間違いに嵌まり込むための確実な手段である。いわばそれは、私たちが抜け出すための出口を閉ざしてしまうのである。
340. 語がどのように機能するかを推測することはできない。その適用を見つめ、そこから学ばなくてはならない。
しかし、この学習を妨げる先入見を取り除くことは容易なことではない。それは生半可な先入見ではない。
341. 思考を欠いた語りと、思考を欠いていない語りは、ある楽曲を、思考を欠いたまま演奏することと、思考を欠かずに演奏することに比せられる。
342. ウィリアム・ジェームスは、語りを欠いた思考が可能であることを示すために、聾唖者バラード氏の思い出を引用している。そこでバラード氏は、まだ幼年期で話せなかった頃に、神と世界について思考したと書いている。 ―― これはどういうことだろうか? バラード氏は言う。「それはあの楽しい遠出の間だった。私が言葉を書くようになる2、3年前のことだ。私は、世界はどのようにして存在を始めたのかを自問し始めたのだった。」 ―― あなたは、これがあなたの言葉を伴わない思考を言葉へ正確に翻訳したものだという自信がありますか ―― 人はバラード氏にそう問いたくなるだろう。だがなぜこのような問いが ―― こんな場合でもなければおよそ存在するとは思えない問いだ ―― 生じてくるのか? 私は、彼の記憶が彼を欺いていると言いたいのか? ―― 私は、自分がそう言うかどうかすら知らない。この思い出は奇妙な現象なのであり ―― その思い出から、語り手の過去についていかなる結論を導くことができるか、私は知らないのである。
343. 私が自分の思い出を表現する言葉は、私の思い出の反応である。
344. 人間が音声言語を全く話さず、心の中で、表象の中で、自分に対して話しかける、ということは思考可能だろうか?
「人間が常に心の中でのみ自分に対して話しかけているとしても、それは結局のところ、彼らが今も時として行なっていることを恒常的に行なっているに過ぎない。」 ―― それゆえ、このような想像を行うことは簡単である。ただ、若干から全てへの簡単な移行をするだけでよいのだ。(類似の例:「無限に長い並木とは、単に終わりのない並木に過ぎない。」) ある人が自分に対して話していることについての規準は、彼が私たちに話すことと、その他の彼の振舞いである。そして私たちは、普通の意味で話すことのできる者についてのみ、「彼は自分に対して話している」と言うことができるのである。私たちは、オウムや蓄音機についてはそのように言わない。
345. 「時として起こることは、常に起こりうる。」 ―― これはどのような種類の命題だろう? 似たような命題として、もし「F(a)」が意義を持つなら、「(x).F(x)」は意義を持つ、というものがある。
「ある人がゲームで悪い一手を指すことがありうるなら、全ての人間が全てのゲームにおいて悪手以外の手を指さないこともありうるであろう。」 ―― それゆえ私たちは、ここにおいて、私たちの表現の論理を誤解し、言葉の使用を間違って記述したくなる誘惑に駆られるのである。
命令は時として守られない。しかし、命令が決して守られないとしたら、どのように見えるだろう? 「命令」の概念はその目的を失ってしまうだろう。
346. だが、神がオウムに突然理性を与え、オウムが自身に対して語りかけるようになる、ということは想像できないか? ―― しかしその場合に重要なことは、それを想像するために、私はある神性の想像を援用した、ということである。
347. [ある人が言う。] 「しかし私はそれでも、自分については、『自分に対して話し掛ける』がどういうことか知っている。もし音声言語を話すための器官を失ったとしても、なお私は自分の中で独話をすることができるだろう。」
[ウィトゲンシュタインが言う。] もし私がそのことを自分についてのみ知っているとしたら、それゆえ、私が知っているのはただ、私がそう呼ぶことだけであって、他人がそう呼ぶことまで知っているのではない。
348. [ある人が言う。] 「これらの聾唖者は手話だけを習う。しかし誰でも内面においては、自分に対しては音声言語を話している。」 ―― さて、君はこの文を理解できないか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] いかにして私は、私がそれを理解しているか否かを知るのだろう?! この情報(これが情報だったとしてだが)を受けたことで、私は何をすることができるだろう? ここでは、理解という観念全体が怪しげな匂いを放っている。私は、自分がそれを理解していると言うべきか、理解していないと言うべきかを知らない。私は次のように答えたい。「これはドイツ語の文である。見かけ上は全く問題ない ―― つまり、実際にそれを使おうとするまでは。この文は他の様々な文とある関係にあり、その関係のゆえに、この文が私たちに何を知らせてくれるか本当は知らないのだと、言いがたくなっているのだ。哲学をすることで無感覚になっていない人ならば、ここでは何かがうまく行っていないことに気付く。」
349. [ある人が言う。] 「しかしこの仮定はそれでも確かにまともな意義を持っている!」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 確かに。この言葉と像は、日常の状況においては、良く知られた使われ方をする。しかしそういう使われ方をしない場合を想像することで、私たちは初めて、いわばこの言葉と像の剥き出しの姿を自覚することになる。
350. 「だが、誰かが痛みを持つと仮定するとき、私は単に、私がしばしば感じるのと同じものを彼も感じると仮定しているのだ。」 ―― このように言ってみたところで、それ以上の進展はない。これではまるで、「でも君は『ここでは5時だ』がどういうことかは知っている。それなら、『太陽では5時だ』がどういうことかも知っている。それはまさに、ここで5時ならば太陽でも同時刻である、ということだ」と言うようなものだ。 ―― 同一性を媒介とした説明は、ここでは機能しない。なぜなら、私は確かに、ここでの5時があそこでの5時と「同時刻」だと呼びうることぐらい知っているけど、まさにどのような場合に時刻の同一性について語るべきかを知らないからである。
全く同様に、彼が痛みを持っているという仮定は、彼が私と同じものを持っているという仮定と同じである、と語ることも説明になっていない。なぜなら、私は文法の以下の部分、すなわち「ストーブが私と同じ体験を持っている」と人が言うのは、「ストーブと私の両方が痛みを持っている」と言う場合に限られることを、十分承知しているからである。
351. それでも私たちは常に言いたくなる。「痛覚は痛覚である ―― 彼がそれを持っているにせよ、私がそれをもっているにせよ、彼が痛みを持っているか否かを、私がどのように知るにせよ。」 ―― それについては私も同意できよう。 ―― さて君が私に向かって「私が『そのストーブは痛みを持っている』と言うときに私が意味していることが、君は分からないのか?」と訊ねるとしたら ―― 私はこう答えることができる。「君の言葉は私をあらゆる表象に導くだろう。しかしそれ以上の役には立たない。」 あるいは「太陽ではちょうど午後5時だった」という言葉を聞いたとしても、私は何かを表象することができる ―― 例えば5時を指している振り子時計を。 ―― もっと良い例は、地球上における「上」とか「下」という語の応用例である。この場合、私は「上」や「下」が意味するものについて、全く明確な表象を持っている。私は当然、自分が上で、地球が下にあることを理解している! (この例を笑わないでほしい。確かに学校ではこういう言葉遣いはおかしいと習ったが、問題を解決することよりも問題を塞ぐことの方が遥かに簡単なのだ。) よく考えればまず分かるのは、この例では「上」と「下」が普通の使われ方をしていないということである。(例えば、地球の裏側にいる人々を、地面の「下」にいる人々と言うことはできるが、それなら、彼らが私たちについて同じ表現を適用することも認めてやらなくてはならない、ということ。)
352. いま、私たちの思考は妙ないたずらをしているようだ。つまり、私たちは排中律を引用して「そのような像が彼の年頭に浮かんでいるかいないかのどちらかであり、第三の場合はない!」と言う。哲学の他の領域でも、この奇妙な議論に出くわすことがある。つまり、「πの無限展開の中には、いつか『7777』が現れるか現れないかのどちらかであり、第三の場合はない」という場合である[29]。神は知りたもう ―― だが私たちは知らない、というわけだ。しかしこれはどういう意味なのか? ―― [このように言うとき、] 私たちはある像を使っている。それは目に見える数列であり、ある者はそれを遥か先まで見通し、ある者は見通していない、という像である。排中律の命題はこの場合、このように見えるかあのように見えるかのどちらかだ、ということを述べている。従ってこの命題は本当は ―― まさに自明のことなのだが ―― 何も述べておらず、私たちに一つの像を与えているのである。それゆえ問題は今や、現実が像と一致するかしないか、ということでなくてはならない。さて、この像は一見すると、私たちが何をなし、何をどのように探すべきかを規定しているように見える ―― しかし実は何のはたらきもしていない。なぜなら、私たちはまさに像の応用の仕方を知らないからである。もしここで「第三の場合は存在しない」とか「第三の場合など存在するものか!」と言うのなら ―― それは、私たちがこの像から目を逸らすことができないということのうちに表現されている。本当はそうではないと感じているにも関わらず、この言葉の中に既に問題とその解決が存在しているように見えてしまうのだ。
全く同様に、誰かが「彼はこの感覚を持っているか持っていないかのどちらかだ」と言うとき ―― それを聞いた私たちの念頭には、とりわけある一つの像が浮かぶ。そしてその像が既にこの言明の意義を間違いなく規定しているように思われるのだ。「今や君は、何が問題になっているかを知っている」 ―― 人はそう言いたいだろう。だがまさにその点こそを知らないのである。
353. 命題の検証の種類とその可能性についての問いは[30]、「君はそれをいかにして意味しているか?」という問いの一つの特殊形に過ぎない。これに対する答えは、命題の文法に寄与する。
354. 文法において規準と徴候の間を揺れ動くと、そもそも徴候しか存在しないかのように思えてくる。例えば私たちは「経験は、気圧計が下がると雨が降るということを教える。しかし経験はまた、私たちが湿気や寒気といった特定の感覚を持つとき、あるいはこれこれの視覚印象を持つときに雨が降るということも教える」と言う。このように言うことの論拠として、このような感覚印象は私たちを欺くことがある、ということが持ち出される。しかしそのとき見落とされているのは、感覚印象が私たちに雨が降っているように見せかけるという事実は、ある定義に基づいているという点である。
355. 重要なのは、感覚印象が私たちを欺きうるということではなく、私たちが感覚印象の言語を理解しているということである。(そしてこの言語は、他の全ての言語と同様、合意に基づいている。)
356. 人はこう言いたくなる。「雨が降っているか、雨が降っていないか、どちらかである ―― いかにしてその知識を得たかを、私がどのように知るかは、別問題である。」 だがそれなら私たちは、何をもって「雨が降っていることについての知識」と呼ぶのか、という問いを立てよう。(あるいは、私はこの知識についての知識しか持っていないのか、という問いも立てよう。) さて、この「知識」を何かについての知識として特徴付けているのは何か? ここでは、私たちの表現形式が私たちを惑わしているのではないか? 「私の目が、そこに椅子があることについての知識を与えてくれる」という表現は、まさに誤解を招きやすいメタファーではないか?
357. 私たちは、犬はもしかしたら自分に語りかけるかもしれない、とは言わない。しかしその理由は、私たちが犬の心をそれほど正確に知っているから、であろうか? 人は「生き物の振る舞いを見れば、その心も見ているのだ」と言うかもしれない。 ―― しかし私は、自分についても、私が自分に語りかけているのは私がしかじかに振舞うからだ、と言うだろうか? ―― 私は、自分の振る舞いの観察に基づいてそのように言うわけではない。しかし、私が自分に対して行う語りが意義を持つのは、私がそのように振舞っているからに過ぎない。 ―― すると、その語りは、私が思うから意義を持つわけではないのか?
358. しかし命題に意義を与えるのは、私たちの思念ではないのか? (これはもちろん、無意義な語の羅列を思うことはできない、ということも含意する。) そしてこの思念は心の領域に存在する何かであるが、また私的な何かでもある! それは把握不可能な何かであり、ただ意識自身にのみ比せられる。
どうしてこれを馬鹿らしいと一蹴できよう! いわばそれは、私たちの言語が見る夢なのだ。
359. 機械は考えることができるか? ―― 機械は痛みを持つことができるか? ―― 人間の体はそのような機械であると言うべきだろうか? 確かに、人間の体はそのような機械に限界まで近づく。
360. だが、やはり機械は考えることはできない! ―― これは経験命題か? 違う。私たちは人間、およびそれに類似したものについてのみ、それは考えると言う。例えば、人形や精霊である。「考える」という語を道具と見なせ!
361. 椅子は自分で・・・・・・と考える。
どこで考えるのか? その一部分でか? あるいは体の外で? 椅子を取り巻く空気の中で? それともどこでもないのか? だがもしそうなら、この椅子の内的言語と、傍にある別の椅子の内的言語の違いは何なのか? ―― では人間の場合はどうか? 人間はどこで自分に語りかけるか? この問いが無意義に思え、まさにこの人間が自分に語りかけるということ以外、いかなる場所の特定も必要でないのはどうしてか? 一方、椅子はどこで自分に語りかけるのか、という問いは、答えを要求するように思われる。 ―― その理由は、その場合、椅子がどのようにして人間に似るのかを、私たちが知りたいと思うからである。例えば、頭が背もたれのてっぺんであるかどうか、などを。
人が心の中で自分に語りかけるとは、どういうことなのか? そこで何が起きているのか? ―― 私はいかにしてそれを説明するべきだろう? そう、君が誰かに「自分に語りかける」という表現の意味を教えられるようにしか、説明することはできない。そして子供のとき、私たちは確かにこの表現の意味を習う。 ―― ただ、そのとき私たちに教える人が「そこで起きていること」を言ってくれるなどとは、誰も言わないだろう。
362. むしろ、この場合、教師は生徒にその意味を直接言うことなしに意味を伝えているかのように見える。それでも生徒は最終的には自分自身に対して正しい直示的説明を与えられるようになるのだ、と。そしてここに私たちの幻想がある。
363. 「私が何かを想像するとき、確かに何かが起きている!」 そう、何かが起きている ―― そのとき私は、何のために大騒ぎをするのか? きっと、起きていることを伝えるため、である。しかし人はそもそもいかにして何かを伝えるのだろう? 人はいつ、何かが伝えられた、と言うのだろう? ―― 伝達という言語ゲームとは何なのだろうか?
私は次のように言いたい。君は誰かに何かを伝えられることをあまりに自明なことと見なしている。つまり私たちは、会話において言語を使った伝達にとても慣れてしまっているので、伝達において重要なことの全ては他人が私の言葉の意味 ―― 心的な何か ―― を把握する、いわば彼の心のうちに受け入れることの中にある、と思っている。もし他人が言葉を受け入れる際にあることを行なったとしても、そのあることは言語の直接的な目的には属さないかのように思われるのだ。
人はこう言いたいだろう。「伝達は、私が痛みを持っていることを他人が知ることを引き起こす。つまり伝達は、この知るという心的現象を引き起こすのだ。その他のことは伝達にとって非本質的である。」 知るというこの奇妙な現象が何であるか ―― この問題はいずれゆっくり時間をかけて考えよう。心的出来事というのは本当に奇妙なものだ。(これはちょうど次のように言うようなものだ。「時計は時間を知らせる。だが時間が何であるかは、未だ決定できていない。そして人が何のために時間を読み取るのかということは、ここでは問題にならない。」)
364. 誰かが頭の中で計算をする。彼はその結果を、例えば橋や機械の構築に使うとしよう。 ―― 君は、彼は本当はその数を計算によって発見したのではない、と言うだろうか? 例えば、ある種の恍惚状態の中で突如念頭に浮かんだのだ、と。しかし、たとえ頭の中であっても、その数値は計算されねばならないし、実際に計算されたものである。なぜなら彼は、自分が実際に計算したこと、そしていかに計算したかを知っており、正しい結果は計算なくして説明不可能だからである。 ―― [ある人が言う。] しかしもし私がこう言ったらどうか? 「彼は自分が計算したと思っているだけなのだ。さらに、なぜ正しい結果は説明可能でなくてはならないのか? 一語も発さず、記号を書かずに計算できた、などということは、全く理解不可能なことだ。」
[ウィトゲンシュタインが言う。] 想像の中の計算は、ある意味において、紙上の計算よりも非現実的なのだろうか? それは現実的な ―― 脳内の計算である。 ―― [ある人が言う。] 脳内の計算は紙上の計算と似ていると言うのか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 両者を似ていると呼ぶべきか否か、私は知らない。黒い線が書かれた一切れの紙が、人間の体 [頭] に似ているということか?
365. [ある人が言う。] アーデルハイトと司教は本当のチェスをしているのか?[31] ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] もちろんそうだ。二人は単にチェスをする振りをしているわけではない ―― そういう脚本であれば、振りをすることもできたであろうが。 ―― [ある人が言う。] しかしこのチェスには例えば始まりがないではないか! ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] そうではない。 [脚本には書かれていないが] 始まりはちゃんとある。そうでないと、二人のしていることは確かにチェスでなくなってしまう。
366. 頭の中でやる計算は紙上の計算よりも非現実的なのか? ―― 恐らく人はそのように言いたいだろう。しかしまた反対の見解へ傾いて、紙やインクは私たちの感覚与件から成る論理的構成物に過ぎない、と自らに言い聞かせることもある。「私は頭の中で……という掛け算を行った。」 ―― 例えばこのような言明を、私は信じないか? ―― しかしそれは本当に掛け算だったのか? それは単に「一つの」掛け算ではなく、この ―― 頭の中の ―― 掛け算だったのである。ここが、私が過ちを犯す点である。なぜなら私は今や、それは紙上の掛け算に対応する、心的な過程であった、と言いたくなるからである。その結果、「心の中のこの過程は、紙上のこの過程と対応する」と言うことが意義を持つことになってしまう。すると、記号の表象によって記号自身を描写するような写像の方法について語ることが意義を持つことになってしまう。
367. 表象像とは、人が自分の想像を記述するときに記述される像のことである。
368. 私がある人に部屋の様子を記述する。それから、その人が私の記述を理解したしるしに、私の記述に基づいた印象派的な絵を描かせてみる。 ―― すると彼は、私の記述においては緑色であった椅子を暗い赤に塗った。私が「黄色」と言ったものについては青色で塗っている ―― それが、彼がこの部屋から受けた印象なのである。そして私は言う。「全く正しい。この部屋はそう見えるのだ。」
369. 人はこう問いたくなる。「人が頭の中で計算を行うとき、それはどのように起こっているのか ―― 何が起こっているのか?」 ―― 個別的な場合においては、その答えは「まず最初に17と18を足し、次に39を引いて……」といったものになるだろう。しかしこれは私たちの問いに対する答えにはなっていない。頭の中で計算するということは、そのような仕方では説明されない。
370. 人が何かを想像しているときに、表象とは何か、そこで何が起こっているのか、などと問うてはならない。代わりに、「表象」という語がいかに用いられているかを問わなくてはならない。しかしこれは、私が言葉についてのみ語りたがっている、ということではない。なぜなら、私の問いの中で「表象」という語が問題になっている限り、その問いは表象の本質についても問題にしているからである。だから私が言っていることは、単に、この問いは何かを指示することによっては ―― 想像している当人にとっても、他の人にとっても ―― 解明することはできないし、何らかの出来事の記述によっても解明しえない、ということなのである。最初の問いも言葉の説明を求めているが、しかしその問いは、私たちの期待を誤った種類の答えへ向けてしまうのである。
371. 本質は文法において表明される。
372. 次の言葉についてよく考えよ。「ある本性の必然性に対して言語において相関している唯一のものは、恣意的な規則である。この本性の必然性について命題の中へ抽出することのできるものは、この規則だけである。」
373. あるものがいかなる種類の対象であるかは、文法が述べる。(文法としての神学)
374. この場合の大きな困難は、この事象を、人が何かを描写できないかのようには描写しない、ということである。つまり、あたかもそこに記述を引き出せる対象があるにも関わらず、私はその対象を他の人に指示することができないかのようには描写しない、ということである。 ―― そして私に提案できることは、せいぜい、そのような像を使うという誘惑に逆らわないことだけである。しかしまた、そのときこの像がどのように適用されているかを探究することである。
375. 誰かに、小さな声で自分に対して読むということを教えるとき、どのようにするだろう? 彼がそれをできていると、どのようにして分かるだろう? 彼自身は、いかにして自分が要求されたことを行っていることを知るのだろう?
376. 私が心の中でABCと呟くとき、それを黙ってしている人と同じことをしているということの規準は何か? もしかしたら、私の喉頭と彼の喉頭において同じことが起きていることが確認されるかもしれない。(同様に、私たち二人が同じことを考えたり、同じことを願ったりするときにも。) しかしそれなら私たちは、「これこれを黙って言う」という言葉の使用を、喉頭や脳内で起こる過程を指示することによって学んだのか? 私の a という音の表象と彼の同じ音の表象とでは、異なる心理的過程が対応することもありえるのではないか? 問題はこうである ―― いかにして二つの表象を比較するか?
377. ある論理学者は恐らくこう考える。同じは同じである ―― 人が同一性についてどのようにして確信しているかは、心理学的問題である。(高さは高さである ―― 人がときには高さを見て、ときには高さを聞くということは心理学に属することである。) [ウィトゲンシュタインが言う。] 二つの表象の同一性の規準は何か? ―― ある表象が赤いことの規準は何か? 私にとって、他人がその表象を持っているときの規準は、彼の言葉と行動である。私にとって、私がその表象を持っているときの規準は、何もない。そして「赤い」に当てはまることは、「同じ」にも当てはまる。
378. [ある人が言う。] 「私は、二つの自分の表象が同じだと判断する前に、それらを同じものとして認識しなければならない。」 そしてその認識が生じるとき、「同じ」という語が私の認識を [正しく] 記述するものだということを、私はいかにして知るのか? [ウィトゲンシュタインが言う。] それはただ、私がその認識を別の仕方で表現でき、かつ、他の人が、この場合は「同じ」という語を使うのが正しいと教えられるときだけである。
なぜなら、私がある語を使うことに正当化を必要とするなら、その正当化は他の人にとってもそうでなくてはならないからである。
379. [ある人が言う。] 最初、私はそれをこれとして認識し、次に、これが何と呼ばれるのかを思い出す。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 次の問いをよく考えよ。人がそのように言うことが正当であるのは、いかなる場合なのか?
380. いかにして私は、これが赤いと認識するのか? ―― [ある人が言う。] 「私はそれがこれであるということを見て、それから、これが赤いと呼ばれることを知る。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] これ? ―― いったい何のことか?! この問いに対するどういう答えが意義を持つのだろう?
(君は、毎度毎度、内的な直示的説明の方へ傾いて行く。)
見られたものから語への私的な移行について、私はいかなる規則も適用できないだろう。この場合、規則は実のところ、宙に浮いてしまっている。適用の制度が欠けているからだ。
381. いかにして私は、この色が赤いと認識するのか? ―― 一つの答えはこうであろう。「私はドイツ語を習ったから。」
382. 私がこの語に対してこの表象を作るということを、どうすれば正当化できるか?
誰かが私に青色の表象を指示し、これが青色の表象であると言ったのか?
「この表象」という言葉は何を意味するのか? いかにしてある表象を指示するのか? いかにして同じ表象を二度指示するのか?
383. 私たちは現象(例えば思考)ではなく概念(例えば思考の概念)を分析するのであり、ゆえに、語の使用を分析するのである。そのため、あたかも私たちの仕事は唯名論のように見えることもある。唯名論者の誤りは、全ての語を名前として解釈し、その使用を実際には記述せず、いわば記述についての紙上の指示だけを与えているところである。
384. 「痛み」という概念を、君は言語を学ぶとともに学んだ。
385. [ウィトゲンシュタインが言う。] 次の問いを自問せよ。ある人が、紙に書いたり呟いたりせずに、頭の中で計算することを習ったということは考えられるか? ―― [ある人が言う。] 「それを習う」ということは、きっと、それができるよう育てられる、ということである。すると問題はただ、それをできることの規準として妥当なものは何か、ということである。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかしまた、ある種族は暗算だけを知っていて、それ以外の計算方法は知らない、ということも可能だろうか? こう訊ねると、人は、「それは一体どういう事態なのか?」と自問せざるを得ない。 ―― そのため、これを一つの例外的ケースとして想像するほかないだろう。こうなると、なおも「暗算」という概念を適用してよいものかどうか、疑わしくなってくる。 ―― あるいは、このような状況では「暗算」の概念はその目的を失ってしまったのではないか? というのも、この種族の場合に起きる現象は、今や [計算とは] 別の範例へと引き寄せられるからである。
386. [ある人が言う。] 「しかし何だって君は自分をそんなに信じないのかね? 君も普段はいつだって「計算する」がどういうことか知っているじゃないか。君が想像の中で計算したと言うなら、実際そうなのだろう。もし計算しなかったのなら、そうは言わないだろう。同様に、君が想像の中で赤いものを見ていると言うのなら、それはまさに赤いのだろう。そう、君は普段は『赤』とは何か知っているのだ。 ―― そしてさらに言うなら、君はいつでも他人との一致に頼るわけではない。なぜなら、自分の見たものを報告しても、他の誰もそれを見なかったということは、往々にして起こるからだ。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] いや、私も自分を信頼してはいるのだ ―― 頭の中でこういう計算をしたとか、こういう色を想像した、とういことを何の疑念も持たずに言っている。この場合の困難は、私が自分が本当に赤いものを想像したかどうかを疑っている、ということではない。そうではなく、私たちは、どのような色が念頭に浮かんだかを、何のた躊躇もなく指示し、あるいは記述することができるため、表象を現実に写像することに何の困難もないということが問題なのである。すると、表象とその現実における写像とは、見間違えるほどよく似て見えるだろうか? ―― [ある人が言う。] しかし私は、ある人物のデッサン画からその人物を何の躊躇もなく認識することができる。 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし私はこう問うことができる。「この色の正しい表象はどう見えるのか?」あるいは「その正しい表象はどういう性質ものなのか?」 私はそれを習うことができるのか?
(私は、何かの正しい表象について述べる人の証言を受け入れることはできない。なぜならそれは証言ではなく、彼が言いたいことを語っているに過ぎないからである。)
387. [表象の] 深い相は簡単に私たちの手から逃げてしまう。
388. 「確かに私はこの場合、何もスミレ色のものを見ていないが、しかし君が私に絵の具箱を見せてくれれば、私はその中からスミレ色を指し示すことができる。」 人はいかにして、もし・・・・・・ならばそれを指し示すことができる、すなわち、それを見れば認識することができる、ということを知り得るのか?
いかにして私は、私の表象から、現実の色がどのように見えるかを知るのか?
いかにして私は、私が何かを為し得るだろうということを、つまり、私が今いる状態はその何かを為し得る状態であるということを、知るのか?
389. 「表象は他のいかなる像よりも、その対象に似ていなくてはならない。なぜなら、私がどれほど像が描写すべきものに似せて像を作ろうとも、それは常に別のものの像でありうるからである。」 しかし表象には、それがこれの表象であって、他の何物の表象でもないということが含まれる。」 このようにして表象は、像を超えた特別なものとみなされるようになるのかもしれない。
390. 小石が意識を持つことを想像できるだろうか? もしできるなら ―― なぜそのことは、私たちはその想像癖に何の関心もないということを証明するだけに違いないのか?
391. 私はまた恐らく、道ですれ違う人はみな耐え難い苦痛を持っているが、彼らはそれを完璧に隠蔽しているのだと想像することも(簡単ではないが)できる。この場合、重要なことは、私が完璧な隠蔽を想像せねばならないことである。つまり、簡単に見破って「彼の心は痛みを持っているが、そのことは彼の体とは無関係なのだ!」とか「体には全く痛いような兆候は見えないに違いない!」と言ってはならないのだ。 ―― さて、そのような想像をしたとき、私は何を行ない、何を語り、それらの人々をどのように見なすだろう? 例えばある人を見て、私は、「それほど耐え難い苦痛を持っているのに笑うことは大変に違いない」とか、そんなたぐいのことを考える。いわば私は、他人が痛みを持っているかのように振舞う役割を演じているのだ。
392. [ある人が言う。] 「彼が痛みを持っていると想像すとき、本当は私の中で・・・・・・ということが起こっているだけである。」 すると別の人が言う。「私は・・・・・・をする際、考えずに想像することができると信じている」 (「私は語らずに考えることができると信じている。」) この考えはすぐ行き詰まる。この分析は自然科学的分析と文法的分析の間を揺れ動いている。
393. [ある人が言う。] 「笑っている人が、実は痛みを持っているのだと想像するとき、私はいかなる痛みの振舞いも想像しない。というのも、私はまさに正反対の振舞いを見ているからである。すると私は何を想像しているのか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 既に言ったとおりである。私はそのために、必ずしも自分が痛みを感じると想像する必要はないのだ。 ―― [ある人が言う。] 「しかしすると、それを想像するということは、どのようにして起こるのか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] (哲学以外の)どういう場合に、私たちは「私は、彼が痛みを持っていると想像できる」や「私は・・・・・・であると想像する」、あるいは「・・・・・・であると想像せよ!」という言葉を使うのか?
例えば、劇である役を演じなければならない人間に対して「君はここでは、この人物は痛みを持っているが、それを隠していると想像しなければならない」と言う ―― しかし私たちは、彼に何の指示も与えず、本当はどうするべきなのかも言ってやらない。それゆえ、上記の分析も役に立たない。 ―― 私たちは今や、その状況を想像している役者に視線を向ける。
394. 私たちが「君がこれを想像したとき、君の中では実際何が起こっていたのか?」と訊ねるのは、どのような状況下においてか? ―― そのとき、どのような答えを、私たちは期待するのか?
395. 表象可能性が私たちの探究でどのような役割を演ずるのか、つまり、命題の意義をどの程度保証してくれるのか、という点については、不明瞭さが存在する。
396. 命題を理解する際に何かを想像することは、命題に従ってスケッチを描くことと同様、命題の理解にとって本質的なことではない。
397. 「表象可能性」の代わりに、特定の描写方法による描写可能性という語を使うことができる。そしてもちろん、そのような描写から、それ以上の使用への確実な道が続いていることもありうる。一方、どうしても頭から離れない像が、何の役にも立たないこともある。
398. [ある人が言う。] 「何かを想像したり、あるいは実際に何らかの対象を見るとき、私は確かに、隣の人が持たないものを持っている。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 君の言いたいことは分かる。君は周囲を見回して、「私だけがこれを持っている」と言う。 ―― だが、この言葉は何のために使われるのか? 何の役にも立たない。 ―― 従ってまたこのように言うことも可能ではないか? 「この場合、『見る』ということも ―― それゆえまた『持つ』ということも ―― 主観や自我も、話題にはなっていないのだ。」 私はこう問うことができるのではないか、君が「自分だけが持っている」と言うもの、それを君はどのような意味で持っているのか?。君はそれを所有しているのか? 君はそれを見ることすらない。そう、それは誰も持っていないと言うべきものではないか? 他人が何かを持っているということを君が論理的に排除するなら、君がそれを持っていると言うことも、また意義を失う。これは明らかなことである。
しかしそれなら、君は何について語っているのだろう? 確かにさっき私は、君が何を考えているのか、内心では分かっていると言った。しかしその意味は、人がこの対象を把握したり、見たりすることをどう考えているのか、いわば、その対象を視線と身振りによって言い表すことをどう考えているのかを知っている、ということであった。この場合、人がどのような仕方で前を見たり、周囲を見渡したり ―― その他諸々のことをするのか、私は知っている。私が信じるところでは、君は(例えば部屋の中に座っているとして)「視覚上の部屋」について語っている、と言うことができる。所有者がいないものとは、この「視覚上の部屋」のことである。私はそれを所有することができない。入ることも、見つめることも、指し示すこともできない。この部屋は、他の誰にも属すことができない限り、私にも属さない。換言すれば、私が現に座っている物質的な部屋に対して使うのと同じ表現形式を適用しようとする限り、この部屋は私に属さない。物質的な部屋を記述するときは、所有者に言及する必要はないし、また確かに所有者を持つ必要もない。一方、視覚上の部屋は所有者を持つことができない。その理由は、こう言うことができよう ―― 「なぜなら、部屋の中にも外にも主人はいないから。」
ある風景画、幻想の風景画を考えよ。そこには一つの家が描かれている。 ―― 誰かがこう訊ねた。「この家は誰のものですか?」 ―― あるいは「家の前のベンチに座っている農夫のものだ」と答えられるかもしれない。しかし農夫は、家に入ることができない。
399. こうも言えるかもしれない。視覚上の部屋の所有者は、それがどのような性質のものであれ、視覚上の部屋と本質を同じくせねばならない。しかしその当人は、部屋の中には見当たらないし、この部屋には外部も存在しない。
400. いわば、この「視覚上の部屋」を発見したかに見える人は、実際何を発見したかと言えば、新しい言い回しであり、新しい比喩なのである。あるいはまた、新しい感覚とも言えるかもしれない。
401. 君はこの新しい把握を新しい対象を見ることだと解釈している。君は自分が行った文法的な動きを、さながら自分が観察する物理現象であると解釈している。(例えば、「感覚与件は万物の構成要素であるか?」という問いを考えてみよ。)
しかし、次のような私の表現は、反論を免れまい。君はある『文法的な』動きを行った。とりわけ、新たな把握を発見したのだ。それは言うなら、新しい画法、あるいは新しい韻律や新しい種類の歌を発見したようなものである。 ――
402. [ある人が言う。] 「私は確かに『私はいまこれこれの表象を持っている』と言う。しかしこの「私は持っている」という言葉は他人に向けた記号であるに過ぎない。 表象の世界は表象の記述において完全に表現されているのだ。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 君の考えは、「私は持っている」は「さあ気をつけろ!」のようなものだ、ということである。君は、この言葉が本当は別の仕方で表現されるべきだと言いたいのだ。例えば簡単に、手で合図をしてから [表象を] 記述する、という具合に。 ―― もしこの場合のように、私たちの日常言語の表現(それがきちんと役割を果たしていたとしても)に賛同しない人がいる場合、その人は、普通の表現方法とは矛盾する、ある像を頭の中に持っているのである。一方で私たちは、私たちの表現方法は事実をありのままには記述していないと言いたい誘惑に駆られる。あたかも、(例えば)「彼は痛みを持っている」という命題は、当人が痛みを持っていないというのとは別の意味で偽でありうるかのように。あるいは、たとえこの命題が何とか正しいことを主張していたとしても、その表現形式は何か偽なことを語っている、というのかのように。
なぜなら、観念論者、独我論者、実在論者の間の論争がまさにこのような様相を呈するからである。ある人々はこの「彼は痛みを持っている」という通常の表現形式に対し、ある主張に対して仕掛けるような攻撃を行ない、またある人々は、この形式に対して、理性的な人間なら誰もが認める事実を断言するかのごとく擁護するのである。
403. もし私が「痛み」という語を、私がこれまで「私の痛み」と呼んできたもの、および他人が「L.W.の痛み」と呼んできたものに限定して使うよう要求した場合、それで他の語との結合において「痛み」という語が欠落したとしても、それを何らかの方法で補完する表記法さえ用意されていれば、他人について何か不当なことが起こることはない。その場合でも他人はなお同情され、医者から治療されるなどするだろう。「しかし、他人はまさに君が持っているものと全く同じもの持っているのだ!」と言ったとしても、無論、この表現方法に対する反論にはならないだろう。
しかしそれなら、私はこの新しい表現方法から何を得るのだろう? 何も得ない。だが独我論者だって、自分の見解を主張するとき、やはりいかなる実際的な利益も欲さないではないか!
404. 「私が『私は痛みを持っている』と言うとき、私は痛みを持っている人物を指示しない。なぜなら私は、誰が痛みを持っているかを、ある意味では全く知らないから。」 このことは正当化されうる。なぜなら、何と言っても私は、これこれの人が痛みを持っていると言ったのではなく、「私は・・・を持っている」と言ったのだから。それによって私は、誰も名指していないのである。それは、私が痛みのために呻くことが、誰も名指さないのと同じことである。それでも、他人はその呻き声によって、誰が痛みを持っているかを見て取るのだが。
ではいったい、誰が痛みを持っているかを知るとは、どういうことか? それは例えば、この部屋の中のどの人間が痛みを持っているかを知るということ、つまり、そこに座っている人、この角に立っている人、あそこにいる金髪で背の高い人、などなどの誰が痛みを持っているかを知るということである。 ―― 私はここで何を言いたいのか? それは、人の「同一性」には非常に様々な規準があるということである。
さて、そうした規準のうちどれが、「私」が痛みを持っていると言うことを規定するのか?
405. [ある人が言う。] 「しかし君が『私は痛みを持っている』と言うとき、君はいずれにせよ他人の注意をある特定の人物に向けようとしている。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] それに対する答えはこうなるだろう。そうではない。私はただ私に注意を向けようとしているのだ。
406. [ある人が言う。] 「しかし君はそれでも、『私は・・・を持っている』という言葉によって君と他人を区別しようとしている。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] いかなる場合でもそんなことを言えるだろうか? 例えば、私がただ呻くときでも [私は自分と他人を区別しようとしているのか] ? そして私が私と他人を「区別しよう」とするときでも ―― 私がそれによって、L.W. という人物と N.N. という人物を区別しようとしているというのか?
407. 誰かが呻き声を上げている。しかし私は言う。「誰かが痛みを持っている ―― だが私には、それが誰だか分からない!」 ―― これを聞いて、人がその呻いている人物を急いで助けに行く。こういうことも、想像できるだろう。
408. [ある人が言う。] 「しかしその場合でも君は、痛みを持っているのが自分であるか他人であるかは、疑っていない!」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 「私は私が痛みを持っているか、他人が痛みを持っているかを知らない」という命題は論理積である。そしてその構成要素 [=連言肢] の一つは「私は、私が痛みを持っているか否かを知らない」である。 ―― そしてこれは有意義な命題ではない。
409. たくさんの人が輪になって立っていると想像せよ。その輪の中には私も入っている。私たちの誰か、あるときはこの人、またあるときは別の人が、見えないところにある発電機に繋がった電極を持っている。私は他の人たちの顔を観察して、誰が感電しているのか見極めようとする。 ―― ある場合には、私は「いま私は誰に電流が流れているか知っている。つまり私だ」と言う。この意味において、私はまた「いま私は誰が電気ショックを受けているか知っている。つまり私だ」とも言うことができよう。これはどこか奇妙な表現方法かもしれない。 ―― しかし他人に電流が流れているときに、私も電気ショックを感じると仮定すれば、「いま私は誰が・・・であるか知っている」という表現方法は全く不適切なものになる。それはこのゲームに属していない。
410. 「私」は誰も名指さず、「ここ」はいかなる場所も名指さず、「これ」はいかなる名前も名指さない。しかしこれらは名前と関連を持っている。名前はこれらを使って説明される。これらの言葉が使われないことが物理学の特徴であるということも、また真実である。
411. 次に挙げる問いはどのような使い方が可能で、どのように決着がつくか、よく考えよ。
1) 「これらの本は私の本か?」
2) 「この足は私の足か?」
3) 「この体は私の体か?」
4) 「この感覚は私の感覚か?」
いずれの問いにも、実際的な(哲学的ではない)使い方がある。
2)については、私の足に麻酔がかけられていたり、足が麻痺した場合を考えればよい。そういう状況では、私がこの足に痛みを感じるか否かを確定することによって、この問いに決着をつけられるだろう。
3)については、鏡に映る像を指差す場合が該当する。しかしある場合には、体に手を触れながらこの問いを立てることもあるかもしれない。また、別の場合には、この問いは「私の体はこんな風に見えるのか?」と同義である。
4)については、そもそもこの感覚とはどの感覚のことだろう? つまり、人はこの問いを使うとき、どのようにしてこの代名詞を使うのだろう? まず1)と同じ使い方ではない! ここでもまた、感覚に注意を向けることでそれを指示しているのだという思い込みが、誤りを引き起こしている。
412. 意識と脳内の過程の間の間隙を架橋できないという感覚。この感覚は日常生活の考察には入り込まない。それはなぜか? この異種性の観念は軽い眩暈 ―― 論理的な手品をするときに感じるような ―― に結びついている(私たちは、集合論のある種の定理に触れる際にも、この眩暈に襲われる。) 私たちの場合、この感覚はいつ生じるのか? それは例えば、私が自分の意識に特定の仕方で注意を向け、驚いて、「これは脳内の過程によって引き起こされているに違いない!」と、額に手を当てて自分に言い聞かせているときである。 ―― しかし「私の注意を私の意識に向ける」とは何を意味しうるのか? だがこんなものが存在するということほど奇妙なことはない! 私がこのように名づけたものは(というのも、日常生活ではこんな言葉は使われないから)、見るという一つの行為であった。私は自分の前を凝視したのだが ―― しかし何か特定の点や対象を見たのではない。私の眼は大きく見開かれ、私の眉は(特定の対象に興味が惹かれた場合、たいてい寄るのだが)寄っていなかった。そのような興味関心が、この見るという行為に先行していたのではない。私の視線は「空虚」で、あるいは、空の明るさに驚き、その光を受け止めている人に似ていた。
さて、さきほど私がパラドックスとして語った命題(これこそ脳内の過程によって引き起こされている!)に、全く逆説的な点はなかったということを考えよ。この命題は、ある実験の最中に言うことがありえよう。例えば、私の見る明るさの効果が脳の特定の部位の興奮によって引き起こされることを確かめるような実験において。 ―― しかし私は、この命題をごく普通の、逆説的ではない意義を持っているような環境で使うことはなかった。私の注意は、実験で測定されるような種類のものではなかった。 ―― (もしそうだったら、私の視線は「空虚」ではなく「集中」したものであったろう。)
413. ここに内観の一例がある。それは、ウィリアム・ジェームスが「自己」は主に「頭の中にあり、かつ頭と喉の間にある奇妙な運動」から成ると考え出したものと似ていなくもない。ジェームスの内観が示したのは、(「人物」、「人間」、「彼自身」、「私自身」などと似たり寄ったりのものを意味する限りでの)「自己」という語の意味ではないし、そのような存在の分析でもなく、「自己」という語を発し、その意味を分析しようとする一哲学者の注意の状態であった。(そしてここから学べることは多かったであろう。)
414. 君は、それでも自分が織物を織っているに違いないと考えている。なぜなら、君は一台の ―― からではあっても ―― 織り機の前に座って、織る動作をしているからである。
415. 私たちが提供するのは、実は人間の自然史に対する考察である。しかしそれは、人の好奇心をそそる貢献ではなく、誰も疑わなかったことの確認であり、常に私たちの目の前にあるため注意を惹かなかったことの確認である。
416. [ある人が言う。] 「人々は声をそろえて、自分たちは見、聞き、感じる、と言う(たとえ少なからぬ人が盲目だったり、聾だったりしても)。つまり人々は、自分は意識を持っていると、自分について証言する」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし何と奇妙なことか! 「私は意識を持っている」と言うとき、私は実際、誰にそれを報告しているのか? 自分に向かってそのように言うことの目的は何で、他人はいかにして私を理解できるのか? ―― 「私は見る」、「私は聞く」、「私には意識がある」などの命題は、実際にそれぞれの使用を持つ。私は医者にむかって「いま私は再びこっちの耳で聞いている」と言うし、私が気絶していると思っている人には、「私は再び意識が戻っている」と言う。
417. すると私は、自分を観察して、自分が見ていること、あるいは自分に意識があることを知覚するのか? そもそも何のために観察について語るのか! なぜ単純に「私は自分に意識があることを知覚する」と言わないのか? ―― しかしここで「私は知覚する」という言葉を使うのは何のためか ―― なぜ「私には意識がある」と言わないのか? ――
しかしここでの「私は知覚する」という言葉は、私が自分の意識に注意を向けているということを示唆してはいないか? ―― だが普通はそうではない。 ―― もしそうなら、「私は・・・を知覚する」という命題は、私に意識があることではなく、私の注意がこれこれに向けられているということを語ることになる。
しかしそもそも、私に「私は再び意識が戻っている」と言うよう仕向けるのは、ある特定の経験ではないのか? ―― それはどのような経験か? どのような状況で、私たちはそう言うのか?
418. 私に意識があるということは経験的事実だろうか? しかし人は、人間については意識があると言い、木や石については意識がないと言うのではないか? ―― もしそうでなかったとしたら、どうなるだろう? ―― 人間がみな意識を持っていないとしたら? ―― 違う、この語の普通の意味では、そうではない。しかし、例えば私には ―― 実際そうであるようには ―― 意識がなかったかもしれない。
419. いかなる状況下で私は、ある部族に酋長がいる、と言うだろう? そしてその酋長には意識がないといけない。酋長は意識なしでは許されない!
420. しかし、自分の周りの人々が自動機械であり、今までと同じ振舞い方をしているとしても、意識は持っていないと想像することはできないか? ―― もし私がいま ―― 部屋に一人でいて ―― そういう想像をするなら、人々が(トランス状態にあるかのように)硬直した目つきで自分の仕事を果たすのを見ることになる。 ―― これは恐らく、少し不気味な考えだ。しかし例えば、路上での普通の往来の中で、もう一度この考えに固執しようとしてみよ! 例えばこう言うのだ。「あそこにいる子供たちはただの自動機械に過ぎない。あの生き生きとした様子も全て機械的なものに過ぎない。」 そうすると、この言葉は全く何も言っていないか、あるいは、君の中に一種の不気味な感情、あるいはそれに類するものを喚起するだろう。
生きた人間を自動機械と見なすことは、ある図形を別の図形の極限状態または変種として見なすことに喩えられる。例えば、窓枠の十字をまんじ(卍)として見なすように。
421. 「彼は激痛に苛まれ、七転八倒していた」という一つの報告の中で、体と意識の状態が互いに混在しているということは、パラドックスのように思われる。こういう報告はごく普通にあることである。それがなぜパラドックスと思うのか? 私たちが、この命ダイアは手で触れられるものと触れられないものを扱っている、と言いたいからである。 ―― しかし、私が「この三つの柱が建物に安定性を与えている」と言うとき、君はそこに何かパラドックスを見つけるだろうか? 三と安定性は手で触れられるか? この命題を道具と見なせ、そしてその意義をその使用とみなせ! ――
422. 私が人間の心の存在を信じるとき、私は何を信じているのだろう? 私が、この物質は二つの炭素原子環を含むと信じるとき、私は何を信じているのだろう? どちらの場合も、像が前景にあるが、意義は遥か彼方の遠景にある。つまり、像の適用を簡単に見通すことができないのだ。
423. 確かに君の中ではこれら全てのことが起こっている。 ―― そして今はただ、私たちが使う表現だけを私に理解させてほしい。 ―― 像はそこにある。そして私は、個別の場合における像の妥当性に異議を唱えるつもりはない。 ―― ただそれでもなお、その像の適用を私に理解させてほしい。
424. 像はそこにある。私はその正当性に異議は唱えない。しかしその適用はいかなるものか? 盲目の像を盲人の心または頭の中の暗黒として考えよ。
425. すなわち、一方では、像を見つけようと努力し、それが見つかると自ずから像の適用も行われるという場合が無数にあり、他方では、私たちは既に像を持っており、いたるところでそれが私たちの心に浮かんでくる ―― しかし、その像は私たちを困難から助けてはくれない。逆に、そこで初めて困難が始まる。
例えば私が「この装置がこの容器に入れられるのをどう想像すればよいのか?」と問うなら ―― 縮小版の図面などが答えとして役に立ちうる。人は私に向かって「見なさい、こういう風に入るんだ」とか、あるいは恐らく「なぜそんなことを不思議がるのか? 君がここに見るように、それはあそこでもこうなっているんだ」などと答えることができる。 ―― 後者の説明は、もちろん、それ以上のことを明らかにしておらず、与えられた像を適用するよう、私に要求しているだけである。
426. ある像が呼び起こされる。それが一義的に意義を確定するように見える。像の本当の使用は、像が私たちに描いてみせる使用に比べ、不純なものに見える。ここでもまた、集合論のときと同様のことが起きている。表現形式が、神のためにあつらえられているように思われるのだ。私たちの知りえないことを知り、無限系列の全体や人間の奥底の意識を見通す存在のために。もちろん、そういう表現形式は、私たちにとってはいわば法衣のようなものである。私たちは確かにそれを着るが、大したことはできない。私たちには、この服に意義と目的を与えるであろう真の力が欠けているからだ。
表現を実際に使うとき、私たちはいわば回り道をし、脇道を抜けていく。たしかに、目の前にはまっすぐで広い大通りが見えている。しかしもちろん、その通りは永久に封鎖されていて、使うことができない。
427. 「私が彼に話している間、私は彼の頭の中で何が起きているか知らなかった。」 このように言うとき、人が考えているのは脳内の過程ではなく思考の過程である。この像は真剣に取り上げられるべきである。私たちは実際、彼の頭の中を見たいと思う。だが、こう言うことで私たちが意味しているのは、他の言い方をすれば「私たちは彼が何を考えているか知りたい」ということに過ぎない。私はこう言いたい。私たちはこの生き生きとした像を持ち、それを使っている。 ―― しかしその使用は、当の像と矛盾し、 [思考の過程という] 精神的なものを表してしまっているのだ。
428. 「思考、この奇妙な存在」 ―― しかし私たちが思考するときには、思考は奇妙なものとは思われない。それが不可思議なものに思われるのは、思考している間ではなく、いわば回顧的に「いかにして思考は可能か?」と言うときだけである。思考がその対象そのものを扱うことがいかにして可能だったのか? 私たちには、あたかも思考によって現実を捕らえたかのように思われるのである。
429. 思考と現実との一致ないし調和は、これが決して赤くないのに、これは赤であると、私が誤って言うことにある。そして私が誰かに「これは赤くない」という命題における「赤い」という語を説明しようとするとき、私はそのために赤いものを指し示す。
430. 「この物体に物差しをあてても、物差しは物体がどれだけの長さかを語りはしない。むしろ物差しはそれ自体 ―― 私はそう言いたいのだが ―― 死んでいる。それは思考が成し遂げることを何も成し遂げない。」 ―― あたかもこれは、私たちが生きた人間にとって本質的なことは外的な姿であると思い込み、そういう形の木偶を作り上げ、生物とは似ても似つかない、その死んだ木像を恥じ入りつつ見た、というようなものである。
431. 「命令と遂行の間には間隙がある。その間隙は理解によって埋められなくてはならない。」
「命令は理解において初めて、私たちはこれをしなければならないという意味になる。命令は ―― それだけでは、ただの音声やインクの線に過ぎない。 ―― 」
432. あらゆる記号はそれだけでは死んでいるように見える。何が記号に生命を与えるのか? ―― 記号はその使用の中に生きる。記号は自らの中に生命の息吹を持っているのだろうか? ―― それとも使用が記号の息吹なのか?
433. 私たちが命令を与えるとき、あたかも、その命令が望んだ最後のものは、表現されないまま留まるかのように思われることがある。なぜなら、命令と服従の間には常に間隙が存在するからである。例えば私が、ある人に、腕を上げるような特定の動きをするよう望むとする。私は、その動きが彼に明確になるように、手本を見せてやる。この像に曖昧なところはないと思われる。だがそれも、彼はいかにしてその動きをしなければならないということを知るのか、と問うまでのことである。 ―― そもそも彼は、私が常に彼に与える記号をいかにして使用するべきかを、どうやって知るのか? ―― そこで私は、他人を指差したり、激励の振舞いをするなどすることで、さらに記号を追加して命令を補完しようと考える。このとき、あたかも命令は口ごもり始めるかのように見える。
まるで記号が、私たちの中にある不確実な方法を使って、理解を呼び起こそうと努めているかのごとく、である。 ―― しかし、いざ記号を理解するとき、私たちはどの記号において理解をするのだろう?
434. 振舞いは手本を示そうと試みる ―― 人はそう言いたいかもしれない ―― しかしそれは不可能である。
435. 「いかにして命題は描写するということを行うのか?」 ―― このように問うとき、答えは次のようになるだろう。「そんなことも知らないのか? 君が命題を使うとき、君はそれを見ているじゃないか。」 そう、何も隠されてはいないのだ。
いかにして命題はそれを行う? ―― そんなことも知らないのか? 何も隠されてはいないのだ。
しかし「そう、君は命題がいかにしてそれを行うかを知っている。何も隠されてはいない」という答えに対して、人はこう反論したいかもしれない。「確かに。だが全てがあまりに速く流れ去るので、私はそれを、いわばもっと広く別々にされているのを見たいのだ。」
436. ここにおいて人は、簡単に哲学の袋小路に迷い込んでしまう。その袋小路とは、この課題が難しいのは、捕らえがたい現象、素早く逃げてしまう現在の経験とか、そういうものこそ、私たちが記述すべきものだからだ、と信じることである。そこでは、日常言語が粗雑に見え、私たちは、日常語っている現象ではなく、「簡単に消え去ってしまう現象、その出現と消滅によって、私たちが日常語る現象を生み出すような現象」に関わらなくてはならないかのように思われる。 (アウグスティヌス曰く、それらは最も明白かつ身近なものなのですが、その同じものが他方ではあまりにも匿されていて、その発見が新奇なことになるのです。)
437. 願望は、自らを充足するもの、あるいは充足するであろうものを既に知っているように思われるし、命題や思考は、自らを真たらしめるものを、たとえそれが全く存在しないとしても、知っているように思われる! まだそこに存在しないものをこのように規定するということは、何に由来するのか? この専制的な要求は [何に由来するのか] ? (「論理的必然の厳しさ」)
438. 「計画は、計画として充足されていない何かである。」 (願望、期待、推測などと同様に。)
そこで私はこう思う。期待は充足されていない、なぜなら期待は何かについての期待であるから。信念、または思念は充足されていない。なぜなら思念とは、何かが事実であるという思念、何か現実的なことが思念という過程の外側で起きているという思念であるから。
439. 人はどのような意味で、願望、期待、信念などを「充足されていない」と呼ぶことができるのか? 未充足についての私たちの原像はどのようなものか? それは空洞なのか? そして人は、空洞のようなものを充足されていない、と言うだろうか? これもまたメタファーではないのか? ―― 私たちが未充足と呼ぶものは、一つの感覚ではないのか ―― 例えば空腹のような。
私たちは特定の表現体系において、ある対象を「充足されている」とか「充足されていない」という言葉で記述することができる。例えば空洞のシリンダーを「充足されていないシリンダー」と呼び、それを一杯にしたシリンダーを「その充足」と呼ぶことにすれば。
440. 「私はリンゴが食べたい」と言うことは、私はリンゴが私の未充足の感覚を静めてくれると信じている、ということを意味しない。この命題は、願望の表出ではなく、未充足の表出である。
441. 私たちは生来そうであるし、特定の訓練や教育によってもそうなるのだが、特定の状況下で願望の表出を行うよう順応させられている。(もちろん、そういう「状況」が願望なのではない。) 私は願望が満たされる前に先立って、何を自分が望んでいるか知っているか、という問いは、このゲームには全く現れない。そしてある出来事が私の願望に沈黙をもたらすということは、それが願望を満たすということを意味しない。もしかしたら私は、自分の願望が満たされたとしても、自分は満たされないかもしれない。
他方また、「望む」という語は「私は自分でも私が何を望んでいるか知らない」のようにも使われる。(「なぜなら願望は望まれたものを私たちから隠蔽するから。」)
もし人が「私は、それを手に入れる前に、自分が何を求めているのか知っているか?」と問うたらどうであろう? もし私が話すことを学んでいれば、私はその答えを知っている。
442. 私は、あるひとが銃の狙いを定めるのを見て、「私は銃声を期待している」と言う。銃声がする。 ―― 何と、それは君の期待していたことである。するとこの銃声は既に何らかの仕方で期待の中にあったのだろうか? それとも君の期待はただ別の観点において銃声がしたことと一致するのか? この轟音は君の期待の中に含まれていたのではなく、期待が満たされたときに偶然の出来事として付け加わったのか? ―― いやそうではない。もし轟音が起きなかったら、私の期待は満たされなかったであろう。轟音が期待を満たしたのだ。それは、私が期待していた客に一緒にくっついてきた2番目の客なのではない。 ―― この出来事のとき、私の期待の中にも無かったものは、偶然の出来事、いわば運命のおまけだったのだろうか? だがそうすると、おまけでないものは何だったのか? そもそも、この発砲に関する何かが既に私の期待の中に生じていたのか? ―― そして何がおまけだったのか ―― というのも、私は完全な発砲を期待していたのではなかったのか?
「銃声は私が期待したほど大きくなかった」 ―― 「すると君の期待の中ではもっと大きな銃声が響いていたのか?」
443. 「君の想像するこの赤は、しかし確かに君が眼前に見るものと同じではない(同じ物ではない)。そうすると君は、どうして君が見る赤が想像した赤と同じだったと言うことができるのか?」 ―― しかしそれは、「ここに赤い染みがある」という命題と「ここに赤い染みはない」という命題の場合と類似したことではないのか? どちらの命題にも「赤い」という語が現れる。それゆえこの語は赤い何物かの現存(Vorhandensein)を指示することはできない。
444. 人は恐らく、「私は彼が来ることを期待する」という命題における「彼が来る」という言葉は、「彼が来る」という主張における場合とは異なる意味において使われていると感じている。だがもしそうなら、いかにして私は自分の期待が満たされたということについて語れるというのか? 私が「彼」と「来る」という二つの語を、例えば直示的説明によって説明しようとすれば、この二つの命題における「彼」と「来る」についても同じ説明が適用されるだろう。
しかし次のように問われるかもしれない。彼が来るとき、その様子はどう見えるのか? ―― ドアが開いて、誰かが入ってくる、等々。 ―― 私が彼が来ると期待するとき、その様子はどう見えるのか? ―― 私は部屋の中を行ったり来たりして、時おり時計を見る、等々。 ―― しかし前者と後者は似ても似つかない! そうすると、どうすればこの「彼が来る」という同じ言葉を記述のために使うことができるのか? ―― だが私は恐らく、あっちへ行ったりこっちへ行ったりしながら「私は彼が入ってくることを期待している」と言うであろう。 ―― すると今や、ある類似性が現れている。だが一体いかなる種類の類似性なのか?!
445. 期待と充足は言語において接点を持つ。
446. 「出来事は、それが起きるときと起きないときとでは、異なって見える」と言うのは滑稽であろう。あるいは「赤い染みは、それがそこにあるときとないときとでは、異なって見える ―― だが言語はこの違いを無視する。なぜなら言語は赤い染みについて、それがそこにあるか否かを語るのだから」と言うことも滑稽ではないか。
447. この感覚は、あたかも否定命題は命題を否定するために、まずある意味で命題を真にしなければならないかのような、そういう感覚である。
(否定命題の主張は否定される[肯定]命題を含むが、その [肯定命題の] 主張を含むのではない。)
448. [ある人が言う] 「私が今夜は夢を見なかったと言うとき、私はそれでもどこに夢を求めるべきかを知っていなくてはならない。つまり、『私は夢を見た』という命題は、現実の状況で適用される場合、偽ではあるがナンセンスではない。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] するとそれはつまり、君はそれでも何かを、いわば夢が生じる場所を君に意識させる夢の暗示を感じたということなのか?
あるいは、私が「私は腕に痛みを持っていない」と言うとき、それは私が、いわば痛みが起こりえる場所を暗示する痛覚の影を持っている、ということなのか?
現在の痛みのない状態は、どの程度痛みの可能性を含んでいるのか?
ある人が「『痛み』という語が意味を持つためには、痛みが生じたときにそれを痛みとして認識することが必要である」と言ったとする。それに対してはこう答えられる。「そのことは、痛みの欠如を認識することほど必要なわけではない。」
449. [ある人が言う] 「しかし私は、痛みを持ったときには、それがいかなるものか知らなくてはならないのではないか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 人はまだ、命題の使用は各語について何かを想像することにおいて成立するという考えから脱却していない。
人は、言葉によって計算し、操作し、言葉を時とともにあれやこれやの像の中に持ち込んでいるということを、良く考えていない。 ―― それはあたかも、例えば、誰かが私に引き渡すべき雌牛の取り扱い説明書には、その説明書が意義を失わないために常にその雌牛の表象が随伴していなくてはならない、と信じているようなものである。
450. 誰かがどのように見えるかを知っていること、すなわちそれを想像できるということ ―― 他方また、それを真似できるということ。真似するためにはその対象を想像せねばならないのか? そして真似することは、想像するのと同じぐらい強力ではないのか?
451. 私がある人に「ここに赤い円を想像せよ!」という命令を与え ―― さらに、命令を理解するということは、それが遂行されたときどうなるかを知ることであり ―― あるいはそれどころか、それがどういうことであるかを想像できることである、と言うとしたら、どうであろう?
452. 私はこう言いたい。「期待という心的過程を見ることができたなら、何が期待されているかも見えなくてはならない。」 ―― しかしこれはまた、期待の表現を見る人は期待されているものを見る、ということでもある。すると、人はいかにしてそれを、別の仕方、別の意味において見ることができようか?
453. 私の期待を知覚する人は、期待されているものを直接に知覚するのでなくてはならない。すなわち彼は、知覚された出来事から推論されるのではない! ―― しかし、人が期待を知覚すると言うことは意義を持たない。期待について、彼は期待すると言う代わりに彼は期待を知覚すると言うことは、表現のばかげた歪曲であろう。
454. 「全ては既に・・・・・・にある。」
このような指示は、心だけが唱えられる魔法ではないのだ。
455. 「私たちが何かを思うとき、そこにあるのは死んだ像(いかなる種類のものであれ)ではない。思うとは、誰かに近づいて行くようなものなのである。」 私たちはそのように言いたがる。私たちは、その思われたものに向かっていく。
456. 「人は何かを思うとき、自分で思うのである。」 すなわち人は、自分で動く。自分で突進するので、その突進を観察することができない。決してできない。
457. そう、思うということは、誰かに近づいていくようなものなのだ。
458. 「命令はそれに服従することを命じる。」 すると命令は、服従が存在する前にそれを知っているのか? だがこれは文法的命題だったのであり、それが言うところは、もし「これこれをしろ!」という命令が発されたら、「これこれをする」はその命令に対する服従と呼ばれる、ということなのである。
459. 私たちは「命令はこれを命ずる ―― 」と言い、それを行う。しかしまた私たちは「命令はこれを命ずる。私は・・・・・・を行わなくてはならない」とも言う。私たちはこれを、ある時は命題へ、ある時は実演へ、ある時は行動へと翻訳する。
460. ある行為が命令に従っていることの正当化は、次のように言うことでなしうるだろうか? 「君は『黄色の花を持ってこい』と言った。それゆえここにある花が私に満足感を与えた。そのようなわけで、私はこの花を持ってきたのだ。」 そのとき人は、こう答える必要があるのではないか? 「私は君にむかって、私の言葉のために君にそのような感情を与える花を持ってこいと言ったのではない!」
461. 命令はどういう意味において遂行を予期しているのだろう? ―― 命令がこれを命じ、後にそれが遂行されることによってか? ―― しかしそれは「後に遂行されるか、または遂行されないこと」でなくてはなるまい。そしてこれは何も言っていない。
「しかし、たとえ私の願望が、後に事実となることを決定しないとしても、いわば、事実が私の願望を満たすか否かという事実のテーマを決定しているのである。」 私たちは ―― いわば ―― 人が未来を知っていることに対して驚いているのではない。そもそも人が(正しくにせよ間違ってにせよ)予言できるということに驚いているのである。
まるで、その正誤の別に関わらず、ただの予言が未来の影を先取りしているかのようである。一方で、予言は未来について何も知らないし、何一つ知りえない。
462. 彼がそこにいないとき、私は彼を探すことができる。しかし彼がそこにいないとき、私は彼を吊るし首にすることはできない。だが、人はこう言いたいかもしれない。「それでも、私が彼を探すとき、彼はどこかにいなくてはならない。」 ―― すると、私が彼を見つけられないとき、そしてまた彼が全く存在しないときにも、彼はやはりどこかにいなくてはならないことになる。
463. 「君はその人を探していたのか? 彼がそこにいるか否か、それすら知りえなかったというのに!」 ―― しかしこの問題は、数学における探求において実際に生じるのである。例えば、角の3等分の方法を探すことがどうして可能だったのか、という問いを立てることは可能である。
464. 私が教えようとしていることは、明白でないナンセンスから明白なナンセンスへ移行することである。
465. 「期待というのは、何が起こるにせよ、それが期待と一致するかしないかのどちらかでなくてはならない、というように行なわれる。」
では、次のように問う人がいたらどうであろう。「すると、事実は期待によって、肯定ないし否定が決定されているのか、それともそうではないのか? ―― すなわち、いかなる意味において、期待がある出来事 ―― どんな出来事にせよ ―― によって応じられることが決定されているのか?」 この問いに対しては次のように答えなくてはならない。「その通りである。ただし、期待の表現が未決定であったり、その表現が、例えば様々な可能性の選言を含んでない限りにおいて。」
466. 人間は何のために考えるのか? 考えることは何の役に立つのか? 人間は何のためにボイラーの強度を計算し、その内壁の強度を偶然に任せないのか? しかし、そのように計算されたボイラーがそう頻繁に爆発しないということは、単なる経験的事実である! そうはいっても、以前、火の中に手を入れて火傷した人は、もう一度それをやるぐらいなら他の何でもやるだろう。それと同様に、ボイラーの強度を計算しないぐらいなら、やはり人は何でもするであろう。 ―― しかし私たちは原因に興味はない ―― そこで私たちはこう言う。実際、人間は考える。例えばボイラーを製作するとき、人間は考えて作る。 ―― さて、そのように作られたボイラーが爆発することはありえないのか? もちろん、ありえる。
467. すると人間は、思考がその有用性を実証するから考えるのか? ―― 考えることは有利に働くから、考えるのだろうか? (子供を教育するのは、教育が有用性を実証しているからなのか?)
468. なぜ人は考えるのか、ということを、いかにして議論の俎上にあげるべきだろう?
469. だが人は、思考はその有用性を実証する、と言うことができる。例えば、以前は感覚に基づいて内壁の強度を決めていたが、今ではこれこれの仕方で計算して決めているので、ボイラーの爆発回数が前より減ったのだ、と。あるいは、技術者が計算する度にもう一人別の技術者に計算をチェックさせるようになって以来、と。
470. それゆえ人は、計算がその有用性を実証したので、時には考えるのである。
471. 「なぜ」という疑問を抑えこんで、初めて重要な諸事実に気付く、ということがしばしばある。そのとき、その諸事実が私たちの探求におけるある答えへと通じていく。
472. 現象の同質性についての信念の本性は、恐らく、私たちが予期される事柄にたいする恐怖を感じる場合に、最も明確に現れる。ただ過去に火傷をしただけであろうとも、私の手を火の中に入れるよう動かしえるものは存在しないであろう。
473. 火に触ると火傷するという信念は、火が私に火傷を負わせるという恐怖と同種のものである。
474. 火の中に手を突っ込めば火傷するだろうということ、これは確実である。
すなわち、私たちはここに、確実性の意味することを見ているのである。(「確実性」という語の意味することだけではなく、確実性についての大切なことをも。)
475. 仮定の根拠を問われると、人はその根拠を想起する。この場合に起きていることは、出来事の原因が何だったのかを考え込んでいるときに起こることと同じではないか?
476. 恐怖の対象と恐怖の原因は区別されなくてはならない。
私たちに恐怖や恍惚を引き起こす顔(それらの対象)は、それゆえ原因ではなく ―― いわば ―― 恐怖や恍惚の向かうものなのである。
477. 「なぜ君は熱い鉄板に触ると火傷すると信じているのか?」 ―― 君はこの信念の根拠を持っているか? また、この信念に根拠は必要なのか?
478. 机を指で押すと反発力を感じるということを想定するために、私はどのような根拠を持っているか? この鉛筆を手に突き立てると痛みを感じると信じるために、どのような根拠を持っているか? ―― このように問うと、数百もの根拠が候補に名乗りをあげるが、それらが互いに発言を許すことはほとんどない。「私はそれを数え切れないぐらい経験した。それに似たような経験の話も何度も聞いた。もしそうでなかったら・・・・・・。等々」
479. 「いかなる根拠によって君はそれを信じるか?」という問いは、「いま君はいかなる根拠からそれを導き出すのか(いま導き出したのか)?」ということを意味しえるだろう。しかしまた「君はこの想定に対していかなる根拠を後から挙げることができるか?」を意味することもできるだろう。
480. それゆえ、ある見解に対する「根拠」ということで実際に理解できるのは、ある人がその見解に到達する前に自らに言いきかせたことだけであろう。 [例えば] 彼が実際に行なった計算。さて、「しかし以前の経験はいかにして、後にこれこれが起きるだろうという想定の根拠となりうるのか?」と問う人がいたら ―― 答えは、私たちは一体、そのような想定の根拠についていかなる一般概念を持っているのか、というものである。過去についてのこの種の陳述を、まさに私たちは、それが未来に起こるだろうという想定の根拠と呼ぶのである。 ―― もし私たちがこのようなゲームを行なっていることを不思議がる人がいたら、私は過去の経験が持つ効果を引き合いに出そう(火傷をしたことのある子供は火を怖がる、というような)。
481. 過去についての陳述によって、未来に何かが起こるとが確信されるわけではない ―― このように言う人を、私は理解しないだろう。このような人には、一体君は何を聞きたいのか、と問うことができよう。君はいかなる陳述をもって、そのことを信じる根拠と呼ぶのか、何をもって「確信する」と呼ぶのか、いかなる種類の確信を期待しているのか、と。 ―― もし過去についての陳述が根拠ではないのなら、一体何が根拠であるのか? ―― もし君が、それは根拠ではないと言うのなら、私たちの想定には根拠があると正当に言いうる場合がどういう場合でなくてはならないかを、述べることができなくてはいけいない。
注意せよ、この場合、根拠とは、それから信念の対象が論理的に導かれるような命題ではない。
ただし、信じるために必要なことは、知るために必要なことよりも少ない、と言えるわけではない。 ―― なぜなら、ここでは、論理的推論への近似は重要ではないのだから。
482. 「この根拠は良い根拠である。なぜならこれは出来事の生起を確からしくするから」という表現が、私たちを誤った方向へ導く。このように言うとき、私たちはあたかも、それ以上の何か、それを根拠として正当化している何かを言ったかのようである。だが他方、この根拠は出来事の生起を確からしいものにする、という命題は、良い根拠の特定の尺度に当てはまるということを語るのでなければ、何も語っていない。 ―― しかも、当の尺度は根拠づけられていない!
483. 良い根拠とは、そのように見える根拠である。
484. 人はこう言いたがる。「ある根拠が良い根拠であるのは、ただ、それが生起を実際に確からしくするからである。」 いわば、それが実際に出来事に対してある影響 ―― いわば経験的な影響 ―― を持つからである、というわけだ。
485. 経験による正当化には終わりがある。終わりがなければ、正当化ではない。
486. そこに椅子があるということは、私の感じる感覚印象から導かれるのか? 一体、いかにして感覚印象から命題を導くことができるのか? できるならば、感覚印象が記述する諸命題から導かれるのか? そうではない。 ―― しかし、そもそも私は、感覚、すなわち感覚与件から、椅子がそこにあるということを推論しているのではないか? ―― 私は推論などしていない! ―― だが時には、例えば次のような推論をする。私はある写真を見て、「ゆえにそこに椅子があるに違いない」と言う。あるいはまた「そこに見えるものから、椅子がそこにあると推論する」と言う。これは推論であるが、しかし論理学の推論ではない。推論とは、主張への移行である。ゆえにまた、主張に対応する振舞いへの移行でもある。「私が結論を引き出す」のは、言葉においてだけではなく、行為においてもそうなのである。
私がこうした結論を引き出したのは、正当なことだったろうか? このとき人は、何を正当化と呼ぶのか? ―― 「正当化」という語はどのように使われるのか? 言語ゲームを記述してみよ! そこから、正当化されていることの重要性も読み取れるであろう。
487. 「私が部屋を出るのは、君が命令したからである。」 「私が部屋を出るのは、君が命令したからではない。」 後者の命題は、私の行為と彼の命令の関連を記述しているのか、それとも、この命題が関連を作っているのか?
人はこう問うことができる。「君がそれをするのはこのせいだとか、このせいではないとか、どこから分かるのか?」 これに対する答えは、まさか、「私はそれを感じるのだ」というものだろうか?
488. それをするのはこのせいであるとか、このせいではないとか、私はいかにして判断するのか? 徴候によってか?
489. どのような状況で、どのような目的のために、私たちはこのようなことを言うのか、自問せよ。
この言葉にはいかなる行為の仕方が随伴しているか? (挨拶について考えよ!) この言葉はいかなる場面で用いられるか? そして何のために用いられるか?
490. この思考過程が私をこの行為へ導いたと、私はいかにして知るのか? ―― さて、このように言うとき、それは特定の像である。例えば、ある実験的な探究において、計算 [という思考過程] がさらなる実験へと私を導く、というような。この像はそのように見える ―― そして今や、私はその一例を記述することができるだろう。
491. 「私たちは言語がなければ意思疎通することができない」わけではない。 ―― だが確かに、私たちは言語がなければ他人にしかじかの影響を及ぼすことはできない。街路や機械を作る等々のこともできない。そしてまた、語ることや書くことなしには、人間は意思疎通することはできないだろう。
492. 一つの言語を発明するということは、自然法則に基づいて(あるいは自然法則と一致するように)、特定の目的のための装置を発明することだと言えよう。しかしそれには別の意味もある。それは、私たちがゲームの発明について語るときの意味と類似している。
私はここで、「発明する」という語の文法と結びつけることで、「言語」という語の文法について語っているのだ。
493. 「雄鶏は鳴き声で雌鶏を呼ぶ」と言われる ―― しかしこの発言の根底にすでに、私たちの言語との比較が潜んでいるのではないか? 雄鶏は、何らかの物理的作用によって雌鶏を行動させると想像してみれば、その相は一変してしまうのではないか?
するとしかし、「こっちへ来い!」という語が言われた人にどういう仕方で作用するかが示され、その結果、最終的にはある種の条件下で脚の筋肉に神経伝達が行なわれる、等々ということであるとすれば、 ―― 「こっちへ来い!」という文は、私たちにとって文としての特性を失うのだろうか?
494. 私はこう言いたい。私たちの日常言語、すなわち私たちの語言語の装置こそ、何よりも私たちが「言語」と呼ぶものであり、それから、それとの類比または比較によって別のものになるのである。
495. 明らかなことだが、ある人間(または動物)がある記号に対して私が望むように反応し、他の記号に対してはそうしないということを確認できるのは、経験によってである。例えばある人が「―→」という記号に対しては右に、「←―」という記号に対しては左に進むが、「o―|」という記号に対しては「―→」という記号と同じようには反応しない、等々。
そう、私はどんな事例も考え出す必要は無く、ドイツ語だけを学んだ人間は、ドイツ語を使うことでしか操れないという現実を考察すれば足りるのである。(なぜならいま私は、ドイツ語の習得者であるということを、ある種の影響に対するメカニズムの調節と見なしているからである。だから、他の人がドイツ語を学んだのか、あるいは生まれつきドイツ語の文に対して、普通の人間がドイツ語を習得した場合と同じように反応するのかどうかということは、気にしなくてよいからである。)
496. 文法は、言語がその目的を果たし、人間にしかじかの影響を与えるためにはいかに構築されるべきかを語らない。文法はただ、記号の使用を記述するのみである。しかしまた、文法はいかなる仕方でもこれを説明しない。
497. 文法の目的が言語の目的であるという意味においては、文法規則は「恣意的」であると言えよう。
もしある人が「私たちの言語にこの文法規則がなかったとしたら、この事実を表現することはできなかっただろう」と言うのなら ―― ここにおける「できる」が何を意味するのか、自問してみよ。
498. 「私に砂糖を持ってきてくれ!」や「私に牛乳を持ってきてくれ!」は意義を持つが、「砂糖 私に 牛乳」という語結合は意義を持たないと私が言うとき、それは、この語結合の発言が何の作用も及ぼさないという意味ではない。いま、これが作用を及ぼし、他人が私の顔を凝視して口をポカンと開けたとしても、それによって、これは「私を凝視しろ」という命令なのだとは言わない。たとえ私が、まさにこの作用を引き起こそうとして発言したのだとしても。
499. 「この語結合は意義を持たない」ということは、この語結合を言語の領域から締め出し、それによって言語の領域を確定することである。この境界線を引くとき、そこには様々な根拠がありうる。ある場所を、柵や線や他の手段で囲えば、ある人間を外に出さないとか、中に入れないという目的がありうる。だがそうた語結合もあるゲームに属することはできるし、その境界はゲームを行なう人間によって飛び越えられるべきものであったりする。あるいはそれはまた、ある人間の所有地がどこで終わり、他の人の所有地がどこで始まるかを示すこともありうる、等々。それゆえ、私がある境界線を引いたとしても、そのことはなぜ引いたかを語るものではない。
500. ある命題が無意義だと言うことは、いわばその意義が無意義だということではない。そうではなく、そのような語結合はその言語から締め出されている、流通から排除されている、ということである。
501. [ある人が言う。] 「言語の目的は思考を表現することである[32]。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] それなら、各命題の目的は一つの思考を表現することになる。すると例えば「雨が降る」という命題は、いかなる思考を表現しているのか? ――
502. 意義についての問い。次のやりとりを比較せよ。
「この命題は意義を持つ」 ―― 「どのような意義か?」
「この語列は命題である」 ―― 「どのような命題か?」
503. 私が誰かに命令を与えるとき、記号を与えればそれで全く十分である。そのとき、私は決して「記号はただの言葉に過ぎない。だから私はその背後へ回らなくてはならない」とは言わない。同様に、私が誰かに何かを訊ね、そして彼が答えを(つまり記号を)返したとき、私はそれで満足する ―― それが私が期待したものであるから ―― そして「それはただの返答に過ぎない」といって異議を唱えることはない。
504. だがこう言う人がいるかもしれない。「彼の思っていることを、私はいかにして知るというのか。私が見ているのはただ彼の記号だけなのに。」 これに対して私はこう言おう。「彼の思っていることを、彼はいかにして知るというのか。彼が見ているのはただ彼の記号だけなのに。」
505. 私は命令に従って行為できる前に、命令を理解している必要があるのか? ―― 確かに! さもなければ、君は何をすべきか分からないであろう。 ―― しかし一方、知っていることから行為へは飛躍があるのだ! ――
506. 「右を向け!」という命令を受けて左を向き、それから頭をたたいて「ああ、そうだった。右を向くんだった」と言って右を向くような、ぼんやりした男。 ―― このとき、彼の念頭には何が浮かんでいるのか? ある解釈か?
507. [ある人が言う] 「私はそれを言っているだけではない。言うことで何かを意味しているのだ」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 私たちが言葉を(ただ言うだけではなく)意味しているとき、心の中で何が起こっているか深く考えると、あたかも何かがその言葉と結びついており、その結合がなければ言葉が空転してしまうかのように思われるのだ。 ―― まるでその言葉が私たちに食い込んでいるかのように。
508. 例えば「天気がいい」という命題の場合、これに含まれる語は恣意的な記号である。そこで代わりに「あ い う」で置き換えよう。しかし私は、これを読むことで即座に「天気がいい」という命題の意義と結びつけることができるわけではない。 ―― 私は、いわば、「天気」に「あ」を、「が」に「い」を、「いい」を「う」で置き換えて言うことに慣れていないのだ。しかしそれは、私は「あ」を即座に「天気」に結びつけることに慣れていない、ということではない。そうではなく、私は「天気」の場所に「あ」を使うことに慣れていないのであり ―― つまり「天気」の意味で用いることに慣れていないのである。(私はそのような言語をマスターしていない。)
(私は華氏で温度を計ることに慣れていない。ゆえに華氏の温度計は私に何も「語らない」のである。)
509. 誰かに「この言葉はいかなる点で、君が見るものの記述であるのか?」と訊ね、彼が「私はその言葉によってそれを意味しているのだ」と答えたとする(彼は例えばある光景を見ていた)。そのとき、なぜこの「私は……でこれを意味している」という答えは答えになっていないのか?
人はいかにして眼前に見るものを言葉によって意味するのだろう?
私が「あいう」と言って、それによって、天気がいいということを意味したと考えよ。すなわち私は、これらの記号を発することで、いつもいつも「天気」の意味で「あ」を、「が」の意味で「い」を使う人間だけが普通なら持つ体験を持ったのである。 ―― この場合、「あいう」と言うことは、天気がいいと言うことなのか?
私がこの体験を持ったということの規準は、どのようなものであるべきなのか?
510. 「ここは寒い」と言って、ここは暖かいと思う、ということをしてみよ。できるだろうか? ―― できたなら、そのとき君は何をしたのか? そのやり方は一通りだけなのか?
511. 「ある言明が意義を持たないことを発見する」とは一体どういうことなのか? ―― そして「私が言明によって何かを意味するとき、その言明は意義を持たなくてはならない」とはどういうことなのか? ―― 私が言明によって何かを意味するとき? ―― 私はそれで何を意味しているのだろう?! 人はこう言うだろう。有意義な命題とは、人が語ることのできる命題であるだけでなく、また考えることのできる命題である、と。
512. あたかも「語言語は無意義な語の配列を許すが、表象言語は無意義な表象を許さない」と言うことができるかに思われる。 ―― すると、図面言語もまた、無意義な図面を許さないのだろうか? それに従って物体が形作られるような図面を考えてみよ。すると、ある図面は意義を持ち、ある図面は持たないということになる。 ―― 私が無意義な語の配列を想像する場合はどうか?
513. 「私の本のページ数は、x3 + 2x - 3 = 0 の解の一つと同じである」とか「私の友人の数は n である、かつ、n2 + 2n +2 = 0 である」のような表現形式について考えよ。これらの命題は意義を持つか? すぐにはわからない。ここにおいて、私たちが理解する命題のように見えるものが、実は何の意義も生み出さないということがいかにして起きるか、その実例を見ることができる。
(このことは、「理解する」と「意味する」という概念に光を投げかける。)
514. ある哲学者はこう言う。私は「私はここにいる」という命題を理解し、それによって何かを意味し、何かを考える ―― たとえこの命題が、いかなる状況で、どのように使用されるかを全く思い出さないとしても。それなら私が「バラは暗闇の中でも赤い」と言えば、君は文字通り、暗闇の中でバラの赤を眼前に見るのだ。
515. 暗闇の中のバラの二つの像。一つは真っ黒である。なぜならバラは見えないから。一方の像は、バラが細部まで描かれ、その周りを黒が取り囲んでいる。この二つのうち、一方が正しく、他方が間違っているのか? 私たちは、暗闇における白いバラと赤いバラについて語らないか? しかも、暗闇では両者は区別できないと言うのではないか?
516. 「π の展開において、7777という数字の連続は現れるか?」という問いが何を意味するか、私たちは理解していることは明らかのように思われる。これは日本語の命題であり、415が π の展開において現れるということ、あるいはそれに類似したことがどういうことであるかを、人は示すことができる。すると、このような説明が通用する限り、その限りにおいて、先の問いも理解していると言うことができる。
517. こうして次のような問いが生じる。私たちはそもそも、ある問いを理解するということについて、誤ることがあるのではないか? なぜなら、数学の証明のあるものはまさに、「私たちが想像できると信じていたものは、実は想像できないものだった」と言わせるようなものだからである。(例えば正7角形の作図。) こういう証明は、私たちが表象可能なものの領域と思っていたものの再点検を促す。
518. ソクラテスがテアイテトスに言う。「すると想像する人は、何かを想像するのではないかね?」 ―― テアイテトス「そうでなければなりません。」 ―― ソクラテス「すると何かを想像する人は、現実的なものを想像するのではないか?」 ―― テアイテトス「ええ、私もそう思います。」 [『テアイテトス』189a]
すると、描く人は、何かを描くのでなければならない ―― すると、何かを描く人は、現実的なものを想像するのではないか? ―― では、描く対象は何か? (例えば)人物像、あるいは、像が描写する人間なのか?
519. 人は言うだろう。命令はそれに従って為される行為の像である、しかしまた、命令はそれに従って為されるべき行為の像である、と。
520. [ある人が言う。] 「もし人が、命題をも可能的事態の像と見なし、命題は事態の可能性を示すと言うならば、その命題がなしうることは、せいぜい平面像や立体像、あるいは動画のなすことでしかない。それゆえ、命題は事実でないものを提示することはできないのである。それゆえ、何を(論理的に)可能と見なし、何をそうでないと見なすか ―― すなわち、まさに文法が何を許すのか ―― は、私たちの文法に完全に依存しているのではないか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] しかし文法は恣意的である! ―― [ある人が言う。] 文法は恣意的なのか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 命題のような構成物を与えられても、私たちはそれによって何をなすべきか知っているわけではない。いかなる技術も、私たちの生活の中にその使用があるわけではないのだ。もし哲学において、全く無用のものを命題に含めたいという誘惑に駆られるなら、私たちがその適用について十分に考えなかったからそう感じるという場合が、しばしば見受けられる。
521. 「論理的に可能」と「化学的に可能」を比較せよ。例えば、正しい原子価によって与えられる構造式(H-O-O-O-Hなど)は、化学的に可能な結合であると言えよう。もちろん、こういう結合が実在せねばならないわけではない。しかし他方、HO2という式は、現実のいかなる結合とも対応しえない。
522. 命題を像と比べるとき、私たちは、それを肖像画(ある歴史上の人物の絵)と比べるのか、風俗画と比較するのかを考えなければならない。どちらの比較にも意味がある。
私が風俗画を見るとき、私がその絵の中の人物が本当にいたのか、本当にそういう状況にあったのか、一瞬たりとも信じることが(思い込むことが)なかったとしても、その絵は何かを私に「語る」。それでは、私が「一体その絵は何を私に語っているのか?」と問うたとしたら、どうであろう。
523. 「その絵は自らを私に語る」 ―― 私はそう言いたい。つまり、絵が何かを私に語るということは、それ自身の形と色において成立するのである。(ある人が「この音楽のテーマは私に自らを語る」と言うとき、それはどういうことなのか?)
524. 絵画や創作話が私たちを楽しませ、私たちの心を奪うことを、自明なことと思わず、奇妙なことだと見なせ。
(「自明なことと思わない」 ―― これはつまり、君を不安にさせる他のことに驚くように、それについても驚くことである。すると、君がその事実を他の事実と同じように受け取ることによって、厄介な問題は消え去る。)
((明白なナンセンスから明白でないナンセンスへの移行。))
525. 「彼はそう言うと、前日と同じように彼女のもとを去った。」 ―― 私はこの命題を理解するか? 私はこの命題を、ある話の文脈の中で聞いたときと同じように理解するか? もしこの命題が孤立していれば、私はこれが何を扱った命題か知っているとは言わないだろう。しかし私は、この命題がどのように使われうるかは知っている。つまり、この命題が使われる文脈を。(一つの命題から、よく知られた幾つもの道があらゆる方向へ向かって伸びている。)
526. ある像、ある図面を理解するとはいかなることか? ここにもまた、理解と無理解が存在する。そしてまた、理解と無理解という表現は様々なことを意味しうる。例えば、ある像が静物画であるとしよう。私はその一部を理解できない。私には、そこにある物を見ることができず、ただカンバス上の色斑点しか見ていない。 ―― または、私は全体を物として見ているのだが、それが私の見知らぬ対象なのである(それらは器具のように見えるが、使い方を知らない)。 ―― もしかしたら私は、それらの対象を知っているのだが、しかし別の意味で ―― それらの配列を理解していないのである。
527. 言語の命題を理解することは、人が信じている以上に、音楽の主題を理解することによく似ている。ただし私が言いたいのは、言語命題の理解は、人が考える以上に、一般に音楽的主題の理解と言われるものに近いということである。なぜこの楽譜の中で音の強弱やテンポが変化せねばならないのか? 人はこう答えるだろう、「なぜなら、それら全てがどういうことなのか、私は知っているから」と。だがそれはどういうことか? それをどういってよいか、私には分からないだろう。「説明」のために、何か別のものと比較することはできるかもしれない。例えば、同じリズム(つまり、同じ楽譜)を持つものと比較するのである。(人は言う。「分からないのか、それはある結論を導出しているようなものなのだ」 あるいは「それはいわば挿入句なのだ」、等々。このような比較をどう根拠づけるのか? ―― それには多様な根拠づけが存在する。)
528. ある言語に全く似ていなくもない何かを持つ人々を考えることができよう。語彙や文法を持たない音声の身振り。(「舌で語る」)
529. [ある人が言う。] 「その場合、音声の意味は何か?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] では音楽における意味は何か? もっとも、この音声身振りの言語が音楽と比較されなければならないと言うつもりは、毛頭ないが。
530. 「心」という語が何の役割も果たさない言語もありうるかもしれない。その言語においては、例えば、ある語を、新しく発明した任意の語によって置き換えることは、私たちにはどうでもよいことである。
531. 私たちが命題の理解について語るのは、その命題を同じことを言う別の命題で置き換えられるという意味である。しかしまた、別のいかなる命題でも置き換えられないという意味でもある。
(ある音楽のテーマを他のテーマで置き換えられないように。)
ある場合には、命題の思想は色々な命題に共通のものであるが、別の場合には、その言葉がその配置にあることによってのみ表現されるのである。(詩の理解。)
532. [ある人が言う。] すると、「理解する」は二つの異なる意味を持っているのか? ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 私はむしろ、「理解する」の複数の使用方法がこの後の意味、つまり理解についての私の概念を形成するのだと言いたい。
なぜなら私は、「理解する」をそうした全ての場合に適用したいのだから。
533. [ある人が言う。] しかし先の第二の場合、人はいかにして「理解する」という表現を説明し、理解を伝えられるのか? [ウィトゲンシュタインが言う。] 次のように問え。いかにして人は、誰か他人を詩やテーマの理解へ導くのか? この問いに対する答えが、人がそこでどのように意義を説明するかを示すものだ。
534. ある語をこの意味で聞くということ。そうしたことがあるということは、何と奇妙なことか!
そのように区切り、そのように強調し、そのように聞かれることで、命題はこれらの命題、像、行為へ移行を始めることになる。
(これらの言葉からは、多くのよく知られた小道があらゆる方向に伸びている。)
535. 私たちが教会音楽の終わりを終わりとして感じることを学ぶとき、何が起こっているのか?
536. 私は言う。「この顔(臆病な印象を受ける)を、私は勇敢な顔として考えることもできる。」 こう言うことで、私は、この顔をした誰かが他人の命を助けることができる、などと言うつもりはない(無論、どのような顔についてもそういうことを想像することはできるが)。むしろ私は、その顔自身のある相について語っているのである。私はまた、この顔を普通の意味で勇敢な顔に変えることができると想像することができる、と言うつもりもない。もっとも、それが特定の仕方で勇敢な顔に移行することはあるかもしれない。表情を再解釈することは、楽曲の和音を、あるときはある旋律への移行として、またあるときは別の旋律への移行として和音を再解釈することと比較することができる。
537. 私は「この顔に臆病さを読み取る」と言うことができる。しかしいずれにせよ、臆病というのはその顔に単に外的に結びついているのではなく、恐怖というのは表情の中に住んでいるものである。表情が少し変われば、それに対応する恐怖の変化について語ることができる。「この顔を勇気の表れとしても考えることができるか?」 ―― このように問われたなら、私たちは、いわば、勇気をその表情の中にどう組み入れてよいかを知らない。そうして例えば次のように答える。「私は、この顔が勇敢な顔であるなら、それがどういうことであるかを知らない。」 しかしそれなら、この問いに対する解答はいかなるものか? あるいは「ああ、私はいまそれを理解した。勇敢な顔とは、いわば外的なことに動じない顔のことなのだ」と答える人がいるかもしれない。私たちはこのようにして勇気を読み込む。ここで人は、勇気はその顔に適合している、と言うかもしれない。しかし、いったいこのとき、何が何に適合しているのだろう?
538. 例えば、私たちがフランス語では述語として使われる形容詞は、その主語と性が一致することに驚き、それは「この人はいい人だ」という意味であると自分に説明する場合などは、これの類似例である(そうは見えないかもしれないが)[33]。
539. 私は、ある人の笑顔を描いた絵を見ている。その微笑を、あるときは好意的なものとして捉え、あるときには敵意のあるものとして捉えるとき、私は何をしているのだろう? 私はしばしば、好意的または敵対的な空間的・時間的環境において想像しているのではないか? そうすると私は、この絵に相対して、遊んでいる子供を見下ろして笑っている人や、反対に、敵が苦しむ様を見下ろして笑う人を想像しているのかもしれない。このことは、私が、一見すると好ましい状況をそれ以上の環境によって異なる解釈をすることができるという事実によっても、何ら変化しない。特殊な事情が私の解釈を転換させないのなら、私はある種の微笑を好意的なものとして解釈し、「好意的」な微笑と呼び、それ相応に反応するだろう。
((確率、頻度))
540. [ある人が言う。] 「もし言語の機構とそれを取り巻く全環境がなかったとしたら ―― もうすぐ雨は止むだろうなどと考えられるはずがない、ということは、本質的なことではないか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] 君は、環境がなければ、その言葉を自らに向かって言っても、それが意味を持つことなどできるはずがない、と言いたいのか?
誰かが天を指差して、何か理解不能な語の羅列を叫んだとせよ。私たちが彼に、いったい何を言ったのかと訊ねると、彼は「ありがたい、もうすぐ雨がやむだろう」という意味だ、と答えた。しかも、彼は個々の語の意味も教えてくれた。―― そしてさらに、彼が突然、いわば正気に戻って、いやさっきの言葉は全くのナンセンスだった。口にしたときは良く知ってる言語の文(それどころか良く知っている成句)のように思われたのだけれど、と言ったと仮定せよ。 ―― こんなとき、私たちは何と言うべきだろう? 彼は、その命題を口にしたとき、理解していなかったのだろうか? 命題はその完全な意味を自らのうちに有していたのではないのか?
541. しかし、先の命題の理解と意味はどこにあったのか。まだ雨は降っていたがすでに小降りになっていたときに、彼は天を指差しながら、「モウスグアメガヤムダロウ」という音列を嬉しそうに発した。その後に彼は、自らの言葉を日本語の言葉に結びつけたのである。
542. [ある人が言う。] 「だが彼は、自分の言葉をよく知っている言語であるかのように感じたのである。」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う。] その通り。そう判断する規準は、かれが後でそう言った、ということである。だから今や、「聞きなれた言語は、まさに完全に確定的な仕方で感じられる」などと言ってはならない。(この感情の表現は何か?)
543. 叫びや笑いは意味に満ちていると言うことはできないか?
「意味に満ちている」というのは、だいたい、そこから多くのことが読み取れるという程度のことである。
544. 「彼が来さえしてくれたら!」という渇望が私の口から出るとき、その感情はこの言葉に「意味」を与える。しかし、個々の語にまで意味を与えるだろうか?
だがここで、次のように言うこともできよう。その感情はこの言葉に真実を与える。そして君はそこに、諸概念がいかに互いに融合しているかを見ることになる。(このことは、数学的命題の意義は何かという問いを思い出させる。)
545. 誰かが「私は彼が来ることを期待する」と言うとき、―― この感情は「期待する」という語にその意味を与えるだろうか? (そして「私は彼が来ることをもはや期待していない」という命題の場合はどうか?) この感情は、「期待する」という語に特別な響きを与える。すなわち、この語は響きの中にその表現を持っている。もし感情がこの語に意味を与えるのなら、ここでの「意味」とは問題になっている当のもののことである。しかしなぜ感情が問題になっているのか?
期待は感情か? (指標)
546. だから私は言いたい。「彼に来てほしい!」という言葉は、私の願望に満ちている、と。それに、言葉は私たちから搾り出されることもある ― 叫び声のように ―。言葉は口に出すのが難しいこともある。例えば、何かを断念したり、弱点を認める場合など。(言葉はまた行為でもある。)
547. 否定、それは一つの「心的行為」である。何かを否定し、そのとき自分が何をしたか観察してみよ! ―― 例えば、心の中で頭を振っているか? もしそうであるなら、その過程は、命題の中に否定記号を書くことよりも私たちの関心に相応しいことであるのか? 今や、君は否定の本質を知っているというのか?
548. 何かが起こることを願うこと ―― そして、何かが起こらないことを願うこと。この二つの過程の違いは何か?
その何かを絵で描写しようとするとき、人はその絵で様々なことをしようとするだろう。例えば、取り消し線を引いたり、区切ってみたり、等々。しかし、そうしたことは私たちにはがさつな表現方法であるように見えるのだ。語言語では、私たちは「でない」という記号を使いさえする。これは下手糞な方便のようなものである。人はこう思っている。それは思考の中で、既に別の仕方で起こっているのだ、と。
549. 「『でない』という語は、いかにして否定しうるのか?!」 ―― 「この『でない』という記号は、後に続くものを、君が否定的に把握すべきだ、ということを暗示しているのだ。」 否定記号は何か ―― もしかしたら非常に複雑な何か ―― を行なうための一つの契機なのだ、と言いたい人もいるだろう。あたかも、否定記号が私たちを何かに誘惑するかのように。しかし一体何に? それは語られていない。それは、ただ暗示されればよいのだと言わんばかりに、また、私たちは既にそれを知っているのだと言わんばかりに。私たちはどのみちそのことを知っているのだから、説明など不要なのだと言わんばかりに。
550. 否定とは、排除し、拒絶する身振りだと言うことができよう。しかし、私たちはそのような身振りをなんと様々な場合に使っていることか!
551. 「『鉄は摂氏100度では溶けない』と『2 × 2 は5ではない』における否定は同じ否定か?」 この問いは内省によって判断するべきだろうか、つまり、私たちがこの二つの命題によって考えることを見ようと努めることによって判断するべきだろうか?
552. 私たちが「この棒は 1m の長さだ」と「ここに一人の兵士が立っている」という命題を言うとき、私たちは「1」という語で異なることを思い浮かべているということ、「1」という語が異なる意味を持っているということが明らかになるだろうか、と問うたとしたら、どうだろうか? ―― そんなことは全く明らかにならない。―― 例えば、「1m ごとに兵士が立っている、2m ごとに兵士が立っている」のような命題を言ってみよ。そして「君はこの命題中の二つの1で同じことを考えているか?」と訊かれたら、例えばこんな風に答えるのではないだろうか。「確かに私は同じことを考えている。それは1 だ!」(こう言いながら一本の指で天を指す。)
553. さて、「1」が、あるときは測定値を表し、またあるときは基数を表すとしたら、「1」は異なる意味を持つのだろうか? こういう問いを立てるのなら、人は肯定的に答えるだろう。
554. 特定の命題、例えば否定を含まない命題にしか否定が適用されないという、私たちよりも「原始的」な論理を持つ人々を想像することは容易である。そういう論理においては、「彼は家へ向かっている」を否定することはできるが、否定命題の否定は無意義になるか、または否定を反復したものとして見なされるであろう。私たちとは異なる否定の表現手段について考えよ。例えば、命題を話す声の高さで表現するような場合、二重否定はどう表されるだろうか?
555. こうした原始的な論理を持つ人々にとって、否定は私たちと同じ意味を持つだろうか。この問いは、5 で終わる数列持つ人々にとって、「5」は私たちと同じ意味を持つだろうか、という問いと類比的であろう。
556. 否定のために「X」と「Y」という異なる二つの語を持っている言語を考えよ。二度「X」を使うと肯定になり、二度「Y」を使うと強い否定になる。それ以外の点では、二つの語は同じように使われる。―― さて、この二つが命題の中で繰り返されていないとき、同じ意味を持つだろうか? ―― この問いには、幾つか異なる答えが可能であろう。
- 二つの語はそれぞれ異なる使用を持つのだから、異なる意味を持つ。しかし、これらの語が繰り返さずに使われ、かつそれ以外の文言が同じである場合は、二つの命題は同じ意義を持つ。
- 二つの語は、ちょっとした慣習上の違いを除けば、言語ゲームにおいて同じ機能を持っている。どちらの使用も、同じ行為、しぐさ、像などを通して同じように習得される。そして両者の用法の違いは、副次的なこと、言語の気紛れな性質の一つとして、語の説明に追加されることになる。それゆえ私たちは、「X」と「Y」は同じ意味を持っていると言うだろう。
- 私たちは、二つの否定に異なる表象を結びつける。「X」は、いわば語の意義を180度反転させる。それゆえ、二重否定は元の意義と同じ向きになる。一方、「Y」は頭を振るようなものである。だから、二回頭を振ることによって、一回目に頭を振ったことが帳消しになることがないように、「Y」を二度使用したときにも、二度目の「Y」が最初の「Y」を打ち消すわけではない。それゆえ、両方の否定を使う命題が実際には同一のものになってしまうとしても、「X」と「Y」は異なる観念を表しているのだ。
557. 私が二重否定を口にしたとき、私がそれを肯定ではなく否定の強調として使っていた、ということは、どのようなことにおいて成り立つのだろう? 「それは・・・・・・のうちに成り立っていた」という答えは存在しない。私は、「この二重否定は強調を意味していた」と言う代わりに、私はそれをある状況の下では強調として用いると表明することができる。また、「二重否定は否定の打消しを意味する」と言う代わりに、例えば括弧でくくることでも表せる。 ―― [ある人が言う] 「それはそうだが、しかし括弧そのものは、それでも様々な役割を果たしうるのではないか。一体、否定が括弧として理解されるべきだなどと、誰が言うだろうか?」 ―― [ウィトゲンシュタインが言う] 誰もそんなことは言っていない。君は、まさに君の理解を言葉によって説明したのだ。括弧が何を意味するかは、その適用の技術のうちにある。問題は、「私は・・・・・・と思った」と言うことが意義を持つのはいかなる状況においてか、そして「彼は・・・・・・と思っていた」と言うことを正当化するのは、いかなる状況か、ということである。
558. 「このバラは赤色である」という命題における「である」は、「2掛ける2は4である」という命題における「である」と意味が異なるだろうか? この問いに対して、これらの語には異なる規則が適用されるのだと答えるとしたら、私たちはここで、語は一つだけで規則が異なるだけだ、と言わねばならない。 ―― そして私が文法的規則のみに注目する場合、その規則がまさにそれぞれの文脈における「である」という語の使用を可能にするのである。 ―― しかし、「である」という語が二つの命題において異なる意味を持つことを示す規則というのは、二つ目の命題における「である」という語を等号(=)で置き換えることを許容するのに対して、最初の命題においてはそのような置換を禁止する規則なのだ。
559. たとえば人は、「2掛ける2は4である」という命題における「である」という語の機能について語るかもしれない。 あたかもこの命題が一つのメカニズムであって、語はその中で特定の機能を持つというような。しかしその機能はどのようにして成り立つのか? それはどのように明らかになるのか? というのも、何も隠されたものなどなく、私たちは完全な命題を見ているからである! その機能は計算の過程において示されなければならない。((意味体))[34]
560. 「語の意味とは、意味の説明によって説明されるものだ。」 つまり、君が「意味」という語の使用を理解しようとするならば、人が「意味の説明」と呼ぶものを見なくてはいけない。
561. そうすると、私が、「である」という語が二つの異なる意味(繋辞と等号)で使用されると言う一方で、その意味は語の使用である、すなわち繋辞と等号としての使用であるとは言わないことは、奇妙なことではないか?
人はこう言いたいかもしれない。これら二種類の使用が一つの意味を与えるのではなく、同じ語による同君連合(Personalunion)など、非本質的な偶然に過ぎないのだ、と[35]。
562. しかし、私はどのようにして、表記法(Notation)の本質的特性と、非本質的で偶然的な特性を判別するのだろう? 表記法の背後には実在が存在しており、それが文法に正当性を与えるのだろうか?
ゲームにおける類似例を考えてみよう。チェッカー(西洋碁)では、キングに「成る」と、二つの石を重ねることで表す。そのとき人は、一つのキングが二つの石から構成されることは、ゲームにとって非本質的なことだとは言わないのではないか?
563. 石(駒)の意味は、ゲームにおけるそれの役割であると言おう。 -- いま、個々の対局の前に、どちらのプレイヤーが白の石を使うことになるかは、くじによって決まるとする。 そのために、一人が両方の手を握って、片方の手にキングの駒を隠し、もう一人が運任せにどちらか一方の手を選ぶ。そのとき、この抽選に使われることを、人はキングの駒のゲームにおける役割に含めるだろうか?
564. それゆえ私は、このゲームにおける本質的な規則と非本質的な規則を区別したいと思う。人は、このゲームには規則だけでなく、ねらい(Witz)もあるのだ、と言いたくなるだろう。
565. なぜ「このバラは赤色である」という命題と「2掛ける2は4である」という命題において、「である」という同じ語が用いられるのだろう? 私たちは計算においては、「である」という語の色に関する同一性を全く用いていない! ―― チェスにおいて、駒がキングを表すためにも、対局者の石の色を決めるためにも使われるのはなぜか? ―― しかし、ここでいう「同一性を用いる」とはどういうことだろうか? 私たちがまさに異なる命題において同じ語を使うとき、一つの使用が存在するのではいか?
566. このとき、同じ語、同じ石の使用に一つの目的があるように見える ―― もし同一性が偶然的で非本質的ではないとすればだが。そして、その目的は、人が石を認識し、どのようにすればそれでゲームをするのかを知ることができる、ということであるように見える。 ―― それは物理的、あるいは論理的な可能性について話しているのか? もし後者だとすれば、まさに石の同一性がゲームに属しているということだ。
567. それでも、ゲームは規則によって規定されなければならない! それゆえ、ゲームの規則が、チェスの対局の前の抽選のためにキングの駒を使うことを規定しているとすれば、その規則は本質的にゲームに属しているということだ。これに対して反論がありえるだろうか? この規則にはねらい(Witz)が見えないという反論はどうか。たとえば、駒を動かす前にその駒を三回ひっくり返すこと、という規則のねらいが理解できないように。 もしこのような規則をあるボードゲームに見つけたとしたら、私たちは驚いて、この規則の目的について憶測を行うだろう。(「この規則は、プレイヤーが考えなしに駒を動かすのを防止するためにあるはずではないか?」)
568. もし私がゲームの特性を正しく理解しているならば ―― 私はこのように言うだろう ―― そのことはゲームの特性に本質的に属しているわけではない、と。((意味は相貌(Physiognomie)))
569. 言語は一つの道具である。言語の諸概念も道具である。すると人は、たとえばこう考えるだろう。「私たちがどの概念を使うかは、大きな違いではありえない。フィートとインチを使っても物理学をやれるように、メートルとセンチメートルを使っても、結局のところ、物理学をやれる。こうした違いは、単なる便宜上のものにすぎない。」 しかし、ある測量体系における計算が、私たちが費やしうる時間と労力を超えるような場合には、この考えは正しいとは言えない。
570. 概念は私たちを探究へと向かわせる。表現が私たちの関心であり、また私たちの関心を支配する。
571. ミスリーディングな類比:心理学は物理学が物理的領域における事象を扱うように、精神的領域における事象を扱う。
視覚、聴覚、思考、感情、意志は、物体の運動や電気的な現象などが物理学の対象であるのと同じ意味では、心理学の対象ではない。このことは、物理学者はこれらの現象を見て、聞いて、考えて、報告を行うの対して、心理学者は、主体の発言(行動)を観察することから分かる。
訳注
[1] ここでの「意味」は、BedeutungとSinnのBedeutung、つまり語の指示対象のことです。ウィトゲンシュタインは『論考』で、BedeutungとSinnの区別に基づく対応説的な意味論を展開しましたが、『探究』ではこの方向からのアプローチは採用されません(一貫して二つの用語は頻出しますが)。代わりに提示されるのが、一種行動主義的な「語の使用を見る」アプローチです。
行動主義については第307節と第308節も参照。
[2] 以下の文章も参照。
「クレタの嘘つき。」「私は嘘をついている」と言う代わりに、「この命題は偽である」とも書くことができよう。それに対する答えはこうなろう。「よろしい、だがあなたはどの命題を意味しているのか。」 ―― 「この命題である。」 ―― 「なるほど、しかしそのうちのどの命題が問題なのか。」 ―― 「これである。」 ―― 「なるほど、それでこれとはどの命題を指しているのか。」等々。彼は完全な命題に到達するまで、自分が何を意味しているのかを私たちに説明できまい。 ―― また次のように言うことができる。つまり、その根本的な誤りは、ある言葉、例えば「この命題」という言葉がそれの対象を表さないで、その対象をいわば暗示する(遠くから指し示す)ことができる、と考えていることにある、と。
(『断片』第691節)
[3] 微分幾何学では直線や点は曲線の「退化した」形と見なされます。
[4] フレーゲは、命題の書き手が当の命題が真であることを主張するかしないかによって、主張力を持つ命題と、ただイメージを喚起するだけの記号結合を区別しました。前者が「判断」、後者が「表象結合」または「内容」(ウィトゲンシュタインがここで言う「想定」のこと)と呼ばれます。この結果、字面は同じに見える命題も、判断か表象結合のどちらかに分類されることになります。以下にフレーゲ自身の言葉を引用します。
判断は、常に、記号|―を用いて表現するものとする。そしてこれは、判断の内容を示す記号または記号結合の左に書かれる。水平な線の左端にある小さな垂直な線を省くと、この判断は単なる表象結合に変わり、[判断の]書き手は、それを真と認めるか否かについては何も表現しないことになる。たとえば、|―Aが、「反対の磁極は互いに引き合う」という判断を意味するものとしよう。すると、―Aは、この判断を表現するのではなく、反対の磁極は互いに引き合うという表象を単に読み手のうちに呼び起こすにすぎないのであるが、それは、たとえば、そこから帰結を導き、そして、これによって思想の正しさを吟味するためである。われわれは、このような場合には、「―ということ」あるいは「―という命題」という語で書き換える。
(『概念記法』pp.10-11)
フレーゲの「内容」と「主張」の区別は、日本語の文法形式に慣れている人間にとって、決して自明とはいいがたいものですが、ドイツ語や英語を母語とする場合は自然な発想です。というのも、「内容」とか「想定」というのは、文法単位として見れば、ドイツ語のdass節、または英語のthat節に対応するからです。
「that he is kind」というthat節は、これだけでは真偽を主張する力を持たない、これが主張力を持つためには、「I think」、「It is not the case」などの句を付け加える必要がある、フレーゲはそう考えたのでしょう。
[5] この段落においてウィトゲンシュタインが表明しているのは、フレーゲの文脈原理 ―― 語の意味は文全体の中で問うべきであり、語の意味を孤立させて問うてはならない ―― の支持です。最初の段落にも、「これこれであること」は言語ゲームにおける指し手ではない、という言葉があります。これも、言語ゲームにおいて有効な指し手は必ず文でなくてはならず、文節や句ではないという、ウィトゲンシュタイン流の文脈原理の表明です。ただし、フレーゲが数字、図形の形態、直線の方向など限定された表現にのみ文脈原理を適用したのに対し、ウィトゲンシュタインは適用範囲を最大限に一般化し、任意の語に対して文脈原理を適用します。
ウィトゲンシュタインはかつて『論考』において文脈原理の支持を表明しましたが、この節は『論考』以後それが現れる最初の箇所です。第41節と第49節も参照。
[6] ラッセルが「論理的原子論の哲学」で述べた考えです。ラッセルは、固有名もまた「省略された確定記述句」であり、本来の固有名(論理的固有名)は「これ」とか「あれ」だけである、と考えました。ラッセルがこのような思想に到達した理由を理解するには、『数学の原理』の存在論と、「表示について」におけるその修正を理解せねばなりません。一言で言えば、「現在のフランス国王」のような空な確定記述句に対応する存在者の存在が否定されたことを受けて、「ペガサス」のような空な固有名に対応する存在者も承認されなくなったためです。詳しくは、「論理的固有名を求めて」『言語哲学大全』第I巻を参照。
[7] Satzzusammenhang は、フレーゲが『算術の基礎』の序文で文脈原理を主張するときに使った造語です。従ってこれを「文脈」と訳してもいいのですが(実際、黒崎訳ではそうなっている)、日本語で文脈と言うと通常は「複数の文の間の関係」や「発話状況」の意味になってしまうので、「文という関連」と訳しました。
[8] ここで批判されている「語が指示する対象を語の意味とみなす」ことは、一般に「意味の物化(hypostatization, reification)」と呼ばれます。この方向を突き詰めると、初期ラッセルのように「あらゆる語の意味はそれが指示する存在者である」という極端な実在論へ傾くことにもなります。しかし、この方針を採用する意味論には大きな困難がつきまとうため、いくら直観的に理解しやすくとも、採用するべきではありません。
後にクワインも、「名指すこと(naming)と意味すること(meaning)を混同している」として意味の物化を批判しました。「何があるのかについて」『論理学的観点から』(岩波書店 1972)を参照。
[9] 「命題の分析」とは、複合命題をより単純な命題の真理関数によって表現しなおすことです。この分析を究極まで推し進めた結果得られる命題が要素命題です。前期のテキストである『草稿』1914年9月20日も参照。
[10] 家族的類似性は可能無限を支持する構成主義の立場から生まれたものだと、個人的には考えています。ウィトゲンシュタインはここで「全てのゲームに共通のもの」、伝統的な哲学の用語を使うなら「イデア」と呼ばれる概念を批判しますが、それはイデアが実無限を前提しているからです。現実に存在するゲームの数は常に有限で、常に新しいゲームが生まれる余地があるのに、どうして「全てのゲーム」という飛躍した観念の存在を許容することが正当化できるでしょう? それゆえ、人間に許されることはただ、現実に存在するゲーム同士の間の共通項を数え上げることだけです。その共通項は、ひょっとすると現存のゲームの全てについて”偶然”当てはまるかもしれません。しかし、明日新しいゲームが考案されたときには、それが当てはまらないこともありえます。人間の持ち駒を現実のゲームの集合という有限集合だけに限る立場では、イデアという実無限的な概念が許容される余地はありません。
[11] 例えばフレーゲの以下の文章を参照。
我々は、次のようなことを要求します。つまり、概念はどの項に対しても値として一つの真理値をもつこと、どの対象に対しても、それが当の概念に帰属するか否かが確定されているということです。換言すると、我々は、概念に関してはその明確な境界づけを要求しているのであり、この要求が充足されないならば、概念に関する論理法則を定めることが不可能となるでありましょう。
(G.フレーゲ「関数と概念」[1891]『フレーゲ著作集 第4巻』p.32)
[12] ウィトゲンシュタインがここでイメージしている立方体の見取り図は下図のようなものです。
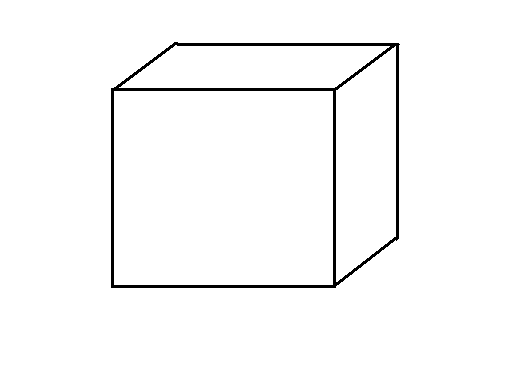
「これを持ってこい!」と言われたとき、この図を立方体として解釈した人はサイコロを持ってくるでしょうし、平面図として解釈した人は、こういう形の紙の切抜きをもってくるでしょう。
[13] 「異なる分野の表現形式の間の類比」とは、例えば、「川が流れる」という表現から、「時が流れる」という表現を作り出すことです。日常言語にはこのような類比的表現が多くありますが、そのほとんどは類比に正当な理由があって使われるのではなく、慣用としてほとんど無自覚に使われます。(時を川のように流れるものとイメージすることに正当な理由があるかどうか、日常生活の中で気にする人は少ないでしょう。)
[14] 「ある表現形式を別の表現形式で置き換えること」で念頭におかれているのは、恐らくラッセルの記述理論です。記述理論については、79節およびラッセルの「表示について」を参照。
[15] 第93節-第95節には、興味深い見解が示されています。まず注意しなくてはならないのは、命題(Satz)と命題記号(Satzzeichen)が区別されて使われていることです。命題がタイプ、命題記号がトークンに当たりますが、ラムゼイも指摘するように、ウィトゲンシュタインは既に『論考』のときから一貫して、命題をトークンとして捉えています。
これと同じ見解が、『青色本』でも述べらています。ただし、こちらではキマイラの代わりに「影」という語が使われています。
[16] 以下を参照。
私たちの日常言語の全ての命題は、事実そのあるがままの姿で、論理的に完全に秩序づけられている。 ―― 私たちがここで述べるべきかの最も単純なものは、真理の似姿ではなく、真理そのものである。[17] 第95節と第114節も参照。
(私たちの問題は抽象的ではなく、おそらくは存在するもののうちで最も具体的な問題である。)
(『論考』5.5563)
[18] 命題変項は命題関数のことです。『論考』3.313、3.314、3.316などを参照。
[19] ここでウィトゲンシュタインは、フレーゲとラッセルによる数の定義を念頭に置いていると思われます。二人は、自然数を定義する際、0から始めて順次帰納的に定めるという方法を採用しました。そのため自然数は「帰納的数」(ラッセル)とも呼ばれます。この節の「命題の帰納的系列」という表現は、そうした自然数の定義と比較させるためのものでしょう。フレーゲとラッセルの数の定義方法の詳細については、ラッセルの「無限公理」および、私の解説「世界には何個のものがあるのか」を参照。
[20] 以下141節までが、有名な心理主義批判の議論です。この議論ををまとめた文章がありますのでそちらも参照。
[21] 傾向性は、潜性、傾性とも訳され、物や人間の持つ潜在的性質を意味します。例えば、「ゴムは茶色である」と言われるときの「茶色」という色が顕在的性質であるのに対し、「ゴムは絶縁体である」というときの絶縁性は潜在的性質です。つまり、物がある特定の状態にあることではなく、ある特定の条件下に置かれるならばある特定の状態になることを意味するのが、この傾向性という概念です。
しかし、顕在的性質と潜在的性質の区別は明確につけられるのか、その有無を感覚によって判断できないのに存在を認めるべきか、など色々と問題含みの概念のため、ライル、カルナップ、グッドマンら多くの哲学者(特に現象主義的な哲学者)が分析の対象としました。
[22] なぜ理解が心的過程ではなく、痛覚の増減や音を聴くことが心的過程であるのか。ウィトゲンシュタインはその違いを、持続時間の有無を基準として判断しています。第151節で、「理解は一瞬のうちに起こる」と述べられています。つまり理解は時間の長短という性質を持ちません。一方、痛覚の増減や音を聴くことは、明らかに、必ず一定の持続時間を必要とします。
[23] ここでは、像の適用方法(解釈方法)には多用な種類がありえるのであり、ただ一つの適用方法だけが像にあらかじめ結びついているのではない、という事実に読者の注意を向けさせています。機械の像には、普通、ある一つの動作が結びついていると考えられています。しかし、それだけが可能な動作の全てだと言うことは、誰にもできません。
像とその適用方法の多様性という主題については、第85節と第139節も参照。
[24] もし意図するという行為(A)の後に意図された行為(B)が続くことが経験的な関係であるとすれば、「AならばB」という命題は経験的命題です。そして経験的命題は、それを偽にする可能的状況を記述することができます。例えば、「私はチェスをしようと意図した。そして実際には将棋をした」という状況が可能である、ということです。しかし現実にこんなことが起こるとは考えられません。(「心変わりをして急に将棋をしたくなったらそういう状況も起こりうるのではないか?」という反論は、認められません。その場合でも将棋をする直前には「将棋をしよう」という意図が存在するはずだからです。) ゆえに、AとBの関係は経験的関係ではありえない、ということになります。
[25] クリプキがその独自の解釈を展開する始点として注意を喚起したことで知られる一文です。ここでウィトゲンシュタインは「懐疑論的パラドクス」を提出し、なおかつそれを受け入れているのだ、というのがクリプキの解釈です。彼の解釈が誤解であることは既に常識とされていますが、その議論の持つ影響力は大きなものでした。『ウィトゲンシュタインのパラドクス』を参照。
[26] 計算の芸術家(Kunstrechner)は、第233節の授業に登場する生徒たちと同じ種類の人間です。彼らは芸術家のようにインスピレーションに従い、作曲するように計算を行います。そして正しい結果に到達しても、その方法を他人に説明することができません。インスピレーションに従うことは伝達可能な技術ではないからです。
しかし、もし計算がこのような仕方で行われるものだとしたら、その方法もまた伝達不可能であり、日々小学校で行われている算術の授業は全くの無駄であることになります。ところが私たちは、算術を教え、教わることが可能であることを、経験的に知っています。ゆえに「インスピレーションに従うことと規則に従うことは同じではない」(第232節)ということになります。
[27] この命題は、ア・プリオリな命題の例としてカントがよく使ったものです。
-
私は分析的判断を作るために、その判断において私のもっている主語概念のそとへ出ていく必要はない。それだからまた経験の証言を必要とするものでない。「物体は拡がりをもつ」という命題はア・プリオリに確立されている。従ってこの命題は、経験判断ではない。
(『プロレゴメナ』(岩波書店 2003)p.36)
[28] シュレミールは、シャミッソーの『影をなくした男』(1814)の主人公です。彼は無尽蔵に金貨を生む「幸運の金袋」と引き換えに、悪魔に影を売り渡します。
[29] ブラウワーが決定不能問題の例としてよく引用したものの変形です。井関清志・近藤基吉『現代数学 ―― 成立と課題』(日本評論社 1977) p.163も参照。
[30] 1920年代後半から30年代前半にかけてのテキストである『考察』やその当時の講義で頻繁に登場していた「検証」の概念は、『探究』ではほとんど姿を消します。この節は数少ない例外です。検証主義についてはシュリックの「意味と検証」が分かりやすいでしょう。
[31] 司教とアーデルハイトは、ゲーテの戯曲『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』の登場人物です。この戯曲の第ニ幕第一場は、二人の勝負が終盤に差し掛かったところから始まります。
[32] 「思考は命題において知覚可能な形で表現される」(『論考』3.1)
[33] 日本語だと何を言っているのか分かりませんが、ドイツ語では「der Mensch ist ein guter(この人はいい人だ)」のように、名詞にかかる形容詞 gut が名詞の性に引っ張られて変化します(この例だと、一見、述語的用法に見えますが、冠詞 ein が付いているので、Mensch が省略されていると考えてください)。これと同様の変化が、フランス語では形容詞が述語として使われるときにも起こる、という意味です。
[34] 原語ではBedeutungskörper。英語ではmeaning-bodyと訳されるようです。個々の語には非言語的な実体が対応するという、実在論的な考え方を表した言葉です。 この考え方に従えば、語の使用規則(語の可能な組みあわせ)は、実体同士の関係によって規定されることになります。 前期ウィトゲンシュタインにもこうした傾向は見られましたが、文における語の使用が語の意味を決めると考えるこの頃のウィトゲンシュタインは、こうした意味の実在論には批判的です。
[35] 同君連合は文字通り同一人物が複数の独立した君主国の君主になるケースで、英連邦王国におけるイギリス女王、オーストラリア女王などが一例です。ウィトゲンシュタインの祖国であるオーストリアも、1918年までオーストリア=ハンガリー二重帝国という形の同君連合でした。 そのため、この統治形態は彼にとって馴染み深いものだったのでしょう。
著:L.ウィトゲンシュタイン
訳:ミック
作成日:2003/12/25
最終更新日:2017/06/22

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

 Tweet
Tweet